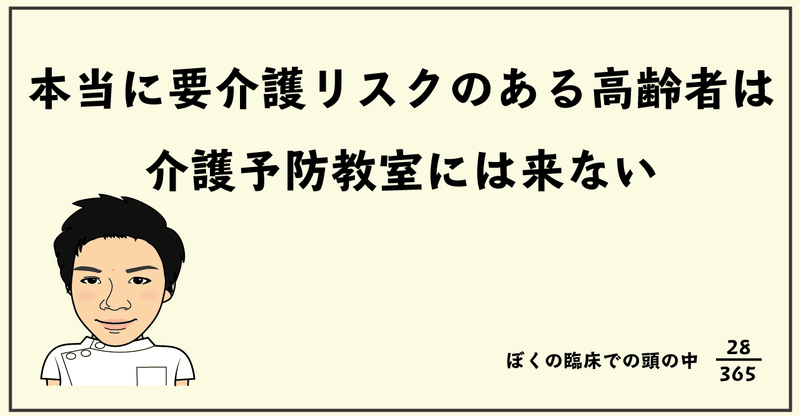
本当に要介護リスクのある高齢者は介護予防教室にはこない
今回は、高齢者の介護予防に関するお話です。
ここ数年、高齢者の介護予防に関わる取り組みに参加させて頂く機会が多く、特に、今年度(R2年度)からは神戸市の介護保険課地域包括支援係という、在宅高齢者の自立支援をする仕事に就かせて貰っています。
神戸市は高齢化率が30%、要介護認定率が20%を上回っており、介護予防にとても力を入れています。
神戸市が実施している介護予防事業は多岐にわたり、介護保険のサービスはもちろん、介護保険認定を受けられていない方に対しても、各地域で介護予防教室を定期的に開催したり、フレイルチェック(元気度チェック)を薬局で実施できるようにしたりと、様々な方面からアプローチしています。
そんな中で、最近僕が強く感じることがあります。
それは、本当に要介護状態になるリスクの高い高齢者には、これらの介護予防の手がなかなか届かないということです。
ここでいう、「本当に要介護状態になるリスクが高い方」というのは、まず、家から出られない方です。
身体機能が低下し、外出が困難になると、家に閉じこもりきりになってしまいます。
すると、活動量が減り、さらに身体機能が低下していくという悪循環に陥ります。
さらに、外出しないことで、人との交流が減り、心も弱っていきます。
なので、外出が出来なくなってきていることは、要介護への入り口に立っているということです。
ですので、こういった方達にこそ介護予防が必要なのですが、外出が出来ないからこそ、地域で開催される介護予防教室やその他のイベントに参加できず、要介護リスクが高まっていることを誰からも気づかれないというジレンマがあります。
(逆にいうと、地域の介護予防教室に参加出来ている人たちは、その時点でそこそこ元気。)
こういった外出出来なくなってきている方の中で、介護認定を申請されている方であれば、訪問サービスや送迎ありのデイサービスを利用することで介護予防を図ることが出来るのですが、外出は出来なくなってきていても、自分の身の回りのことは自分で出来るし、(買い物は宅配サービスを利用したりして何とかなっているし)生活にはまだそれほど困ってないという人は、介護認定も申請されないと思ってます。
なので、行政や周囲の人たちが気づかないところで、着々と要介護に向かって進んでいる人たちが結構多いんじゃないかと思っています。
もう1種類、「本当に要介護状態になるリスクが高い方」に自身の健康に関心がない方が当てはまると思っています。
健康状態が不安定な高齢者にとって、いくつになっても元気で自立した生活が続けられるか、年齢とともに心身が衰え要介護状態になるかの境目は、日々の生活習慣以外にありません。
自身の健康に関心を持ち、栄養バランスの良い食生活と運動習慣のある生活を送っているのと、自身の健康に関心がなく、若いころの生活習慣をそのまま続けているのとの差はとてつもなく大きく、高齢であればあるほどその影響は大きいです。
ですので、こういった自身の健康に関心がない方にこそ、介護予防に関する知識を与え、生活習慣を改めるための働きかけをしていく必要があるのですが、ここでもジレンマがあり、健康に関心がないからこそ、地域で開催される介護予防教室やその他のイベントに参加せず、介護予防に取り組むきっかけが与えられないのです。
このように、「外出が出来なくなってきているが、介護認定は受けていない方」と「自身の健康に関心がない方」こそが、本当に介護予防が必要な方達だと思っています。
しかし、今のところこの方たちにまで、介護予防の手を伸ばす仕組みはないように思います。(全部悪くなってから気づかれて対処する後追い状態です)
これらに対するアプローチとしては、いくつか僕なりにも考えがあるんですが、それもいつか書きます。
▽自主トレばんく|セルフリハビリ指導用イラスト資料集
自主トレ、ホームエクササイス、セルフリハビリ指導用のイラスト資料が無料でダウンロード出来ます。
https://jishu-tre.online/
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
