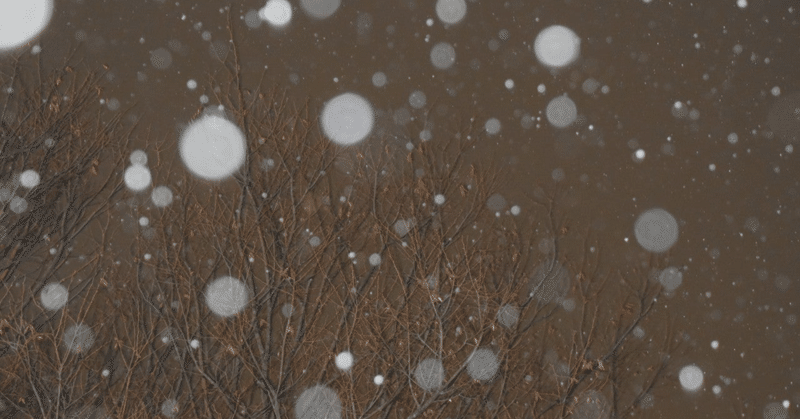
紫がたり 令和源氏物語 第二百七十七話 真木柱(八)
真木柱(八)
やがて陽が暮れて、空からは雪がちらほらと舞い降りると右大将ははや玉鬘姫の元を訪れたくてじっとしておられません。
夫のそわそわした素振りが北の方には辛きこと。
そのような姿を見るよりは、と声をかけます。
「あなた、雪が降ってまいりましたわ。早くお出掛けになりませんと」
そのように大人しい様子は昔愛した姿そのままなので、右大将は却って罪悪感に苛まれます。
しかし玉鬘姫のことを考えると、会いたくて心が逸るのです。
「こう雪が降ってはとも思うのだが、源氏の大臣に夜離れと疑われるのも辛いのでやはり出かけることにしよう」
北の方はさびしそうに笑うと自ら右大将の新しい直衣に香を焚き染め始めました。
こうしているとまったくよくできた北の方で、非の打ちどころもないものよ、と右大将はしみじみとこの人が愛しくなります。
他の女に愛を移した己の心こそ恥じられて身の置き所がなくなりますが、鬢(びん)を整え、装束を身につけると威厳が滲み出て男盛りの貴人らしい佇まいで堂々としておられます。
「では、行ってくる」
右大将が北の方に背を向けたその刹那、一体何が起こったのやら、右大将の視界は真っ白に塞がれました。
辺りが煙って粉のようなものが鼻から入り込んで息もできません。
「な、なんと」
右大将が咳き込んでいると甲高い声で北の方が喚きました。
「おほほ。灰まみれの右大将、いい気味だ。そのみすぼらしい姿で女に逢いにいくがいい」
どうやら北の方が香を焚き染める時に使う火取り(小さな火鉢のようなもの)を右大将の後ろから浴びせかけたようです。
灰が撒き上がり、小さな炭の燃えかすが直衣をぶすぶすと焦がす嫌な匂いが立ち上りました。
「北の方さま、落ち着いてくださいませ」
「どうか、お静まりください」
「ええい。お放し、あの非情な男を懲らしめてやる」
女房たちが北の方の袖を押さえておりますが、次から次へとなぎはらわれてしまいます。
鬢まで真白くなった右大将はあまりのことに驚き呆れましたが、北の方の目は血走り、口からは呪詛の言葉が漏れるばかり、よほど性質の悪い物の怪がとり憑いているとしか思えません。
「殺してやる~」
右大将に掴みかかるその姿は鬼そのものの形相で、先程までの憐憫の情などは欠片も残らず消え失せるのでした。
右大将は暴れる北の方を取り押さえ、「早く僧を呼べ!!」と叫びました。
北の方は恐ろしい力で引っ掻いたり噛みついたり、じたばたと暴れています。
右大将の腕は傷だらけでは血がだらだらと滴り落ち、北の方の口は鮮血にまみれて、なんともこの世のものとは思えぬ恐ろしい光景なのでした。
「なぜだ、どうしてこのようなことになってしまったのだ」
右大将はただ泣いていました。
僧侶たちが大勢邸に呼ばれ、北の方にとり憑いた物の怪を調伏しようと声高に読経を始めました。時には数珠でその体を打ち、護符を貼りつけて、明け方にようやく沈静化したのでした。
この騒動で玉鬘姫の所へ行けなかった右大将は、せめて手紙だけでもとしたためました。
その手紙を書いている間は心が玉鬘姫に寄り添っているようで、ほっと幸せな気持ちになれるのです。
心さへ空に乱れし雪もよに
ひとり冴えつる片敷きの袖
(あなたに逢えない寂しさに心乱れ、雪降りしきる中でただ一人温もりもなく私の袖が冷たいのをおわかりいただけますでしょうか)
右大将は玉鬘姫の返事が待ち遠しくて、しばし現実から離れられる心地でしたが、姫の方では右大将が来ないことなどむしろ気が楽であるとばかりに手紙は開かれもせずに打ち捨てられたままなのでした。
右大将は訪れなかったことを恨んでいるのであろうかと胸を痛めますが、まったく心の通じ合っていないことにお気づきではない。
温度差と深い溝が横たわる夫婦仲ゆえは玉鬘姫の心情を思えばさもあらん、というところでしょうか。
次のお話はこちら・・・
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
