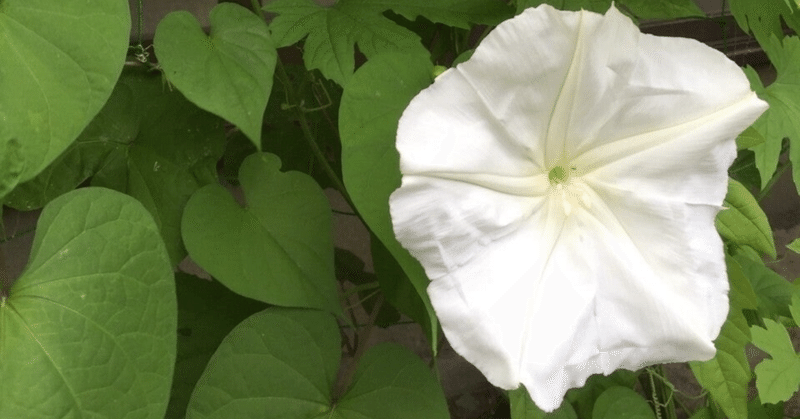
紫がたり 令和源氏物語 第二百十話 玉鬘(三)
玉鬘(三)
それでは当の姫君の心裡はどうなのでしょうか。
物心つく前に乳母たちとこの田舎にやってきた姫には母の記憶がぼんやりとしかありませんでした。
いつでも優しく微笑んでいるような静かな人だったと思い浮かびます。
突然に姿を消してしまった、と乳母やその娘たちからも聞かされておりましたが、もはやこの世にはいないのではないか、そう身内特有の縁によって感じられるのです。
姫は一度だけ母の夢を見たことがありました。
訴えるような瞳が印象的で、どこか悲しげな様子でした。
即座に母に間違いないと直感しましたが、その背後には闇にまぎれる影のようにゆらりと沿う美しい女おり、どうやら母の黒々とした長い髪を握りしめて自由を奪っているようです。
美しく整った顔は陰惨な笑みを浮かべ、まるで人ではないようで、母を心底憎んでいるらしく、背筋がぞっと冷たくなりました。
いったい母はどのような恨みを買ってあのように苦しんでいるのだろうか、目が覚めても恐ろしさのあまりに震え、母が憐れで涙が零れたのでした。
実の父という人の話も乳母たちから聞きました。
代々大臣を輩出している尊い血筋の御方だと。
母は身分高い正妻に疎まれて逃げ、庶民の暮らす町に身を潜めたということです。
なぜ父は母を守ろうとしてはくれなかったのか。
それを考えると姫にとっては実の父といわれても会ったこともない、まったく見知らぬ御方と大差はないのです。そこに思慕の情も涌いてはきません。
乳母たちは自分を尊い姫、と呼ぶけれども、この頼りない身の上では生まれなど何ほどのものか。今際の際にまでこの身を気にかけてくれた少弐には、自分の存在は重荷なだけではなかったか。
聡い姫はそのように苦しんでおりました。
次のお話はこちら・・・
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
