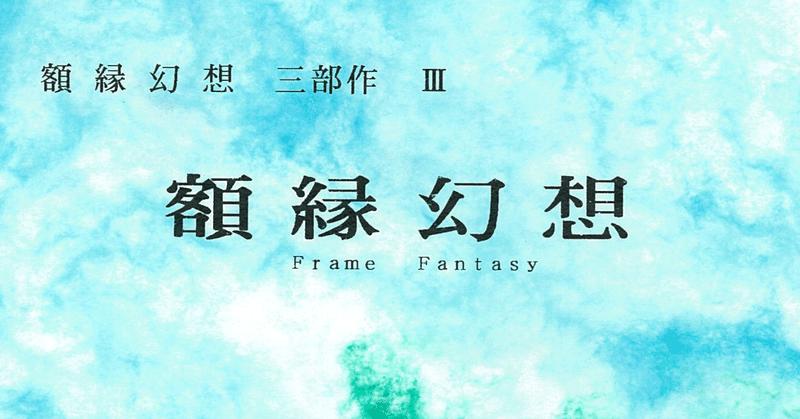
「額縁幻想」 ② 偽の配達員
「額縁幻想」 ② 偽の配達員
「じゃあ、ママもやっぱり知らないのね」
それが鏡であるということは伏せておいて、翌日、絵里香はハプスブルク家由来の品物の存在について、日本の母親に一応確かめてみた。
「大丈夫。今日はこれからホームパーティーがあって、お客さんの出入りもあるから。その人が来たら、わざとみんなに紹介しちゃうから。うん。大丈夫。お休みなさい」
母の心配をよそに、絵里香はさっと電話を切った。聞くべきではなかったか。あちらではもう夜。異国の地で一人暮らしを始めた娘の近辺に、ハイデンベルク家の財宝を狙う怪しげな男が出没しているとなると、親としては気になって眠るどころではなくなるだろう。
ザルツブルクの伯母も同様に、「知らない」と言った。長年ここで暮らしていた家族にさえ秘密にされていたとは、どういうことなんだろう。やはりあの額縁は理由を知る者の手によって隠されていたわけか。危険なものだけど、ハプスブルクから受け継いだ貴重な品だから、処分できなかったのか。
そうなると、ますますホフマンの話を聞きたくなる。だけど、ただ彼を待っているなんて嫌。迷ってないで、さっさと出かけてしまおう。いつもタイミングを逃してしまうプラネタリウムを、今日こそは観に行くんだものね。
夕方からのホームパーティーの面々は、自分たちで自由に準備したいだろうから、こちらは消えていたほうが良いのだと、絵里香は割り切っていた。
ここウィーンでピアノ教師をしていた絵里香の祖母は、自宅の広間を開放して、しばしばサロンコンサートやホームパーティーを開いていた。その頃から音楽は日常にしっかり溶け込み、日本からたまに訪れる絵里香は、そうした環境に慣れ親しんできた。
祖母の亡き後も、弟子たちによってその習慣はずっと続けられている。つい先日も、ウィーン滞在を決意してはるばるやって来た絵里香の歓迎も兼ねて、楽しいサロンコンサートが催されたばかりであった。
午前中から焼きあげ、カラフルなアイシングで丁寧に飾りつけをしたクッキーを、絵里香はキッチンに用意した。音楽仲間は身内同然で、鍵も渡してあるから大丈夫。そろそろ急がないと、また見損なう羽目になる。
前回は勇んで天文台に行ったのに、なぜか映画館に入ってしまった。
入口を間違えたのだ。
謎の言語にドイツ語字幕のついたファンタジー調の内容に、随分と凝ったプラネタリウムだなと感心しつつ、画面が天井ではなく、正面にあることに気づいた時は既に遅し。プラネタリウムの上映時刻はとっくに過ぎていた。ドイツ語の会話はかなり習得しつつあるものの、町中の表示などの文字系は、まだまだ苦手な絵里香であった。
そして今日は町外れのプラターにある、天文台とは別のプラネタリウムを目指していた。
ウィーンっ子の憩いの場、プラターに、絵里香は幼い頃からよく祖父母に連れられて来ていた。「第三の男」にも登場した大観覧車に、本物のお馬さんのメリーゴーランド。あるときは車で、あるときは地下鉄で。しかし今回は、市電に挑戦。それが間違いの元とは露も知らずに……。
路面電車の終点「プラター」で下りると、そこは四方にただの並木道が果てしなく続くばかりであった。え? ここはどこ? 巨大観覧車は? 絵里香は慌てて乗務員に尋ねた。
「ここはどこですか!?」
「あなたはどこに行きたいのですか?」
「プラターです!」
「ここがそのプラターですよ」
「でも、大観覧車は? プラネタリウムは!?」
乗務員は笑った。そしてこの広い空間全体が市民の公園、プラターであると、説明した。遊園地はあちらのほうですよ。と、彼は遙か彼方を指し示した。
これでは上映時刻に間に合うわけがない。
── わたしって永遠に、プラネタリウムを見れない運命なんだろうか ──。
絵里香は途方に暮れ、それでも大観覧車のふもとにあるプラネタリウムを目指して、並木道を黙々と突き進んで行った。
表の門も、屋敷のドアも、すっかり開け放たれていた。中からは楽しげな笑い声。おそらく遅れて参加の客人の為に扉を開けたままにしてあるのだろう。
チャンス、とばかりにクラウス・ホフマンは遠慮なく敷地内に足を踏み入れた。
と、ケータリングサービスのバイクが停車し、何やら運び込もうとしているではないか。
さらなるチャンス! クラウスはアルバイト風の青年に歩み寄った。オープンサンドの宅配か。
「お疲れさま。おいくらですか」
「2パックで、40ユーロ。配達料はサービスですよ」
「では」と、クラウスは配達員の頭から、黒いらくだマークのついた制帽を取り上げた。
「これも含めて百ユーロでは? ちょっとしたジョークに使いたいんだ」
バイト青年は嬉しそうな困ったような、複雑な表情を浮かべた。
「何て言い訳したら……。無くしたなんて、店長に叱られるなあ」
「風に飛ばされたと」
商談成立。二人はにこやかに握手を交わす。
風に飛ばされたんだ。風に……。とつぶやきながら、青年は走り去った。
「どうも〜」と、帽子を目深にかぶり、クラウスは大広間に正々堂々と侵入した。
格式張った催しではなさそうで、上品そうな、比較的年配の紳士淑女の内輪の集まりのようだった。辺りをすばやく見渡してみる。幸いなことに、あのおっかないお嬢さんは席を外しているようだ。クラウスはメインテーブルのご馳走を少しばかりずらし、持参の品を広げる空間を手際良くこしらえた。
「わあ、美味しそう!」
箱の中から現れた色とりどりのオープンサンドに、周囲の女性陣から歓声があがる。卵やツナ、クリームチーズ、サーモンマリネに、オリーブやピクルス、ケッパーなどがトッピングされた定番ものから、生ハムとラディッシュ、赤キャベツのマヨネーズ和えといった、ベートーヴェンが通っていた頃からの、昔ながらのレシピも美しく再現されている。
「お代は頂いてますので」
多少の出費は致し方ない。クラウスは観念した。ここで彼女を呼ばれたりしたら、元も子もないのだ。
「絵里香も早く帰ってくればいいのに」
ご馳走をパクつきながら、誰かが言った。
「どうしても観たいプログラムが今日までだって、プラターのプラネタリウムに張り切って出かけたそうよ」
そんな声も聞かれる。
彼女のことだな。ははあ、これは邸内を探る絶好のチャンスだぞ。クラウスは頭をフル回転させた。
「では失礼します」と出て行きかけながら、広間の中央に鎮座するグランドピアノに目を止めるふり。
「やあ、ベーゼンドルファーかあ」
懐かしい仲間に出会ったかのように、鍵盤の上に手を滑らせる。彼が片手でさらりと弾いた下降音階と、続く軽い和音の絶妙なハーモニー、その一瞬の手際があまりにも鮮やかで、一同は、おや? と、ケータリングサービスの青年に注目した。
「いい音だなあ。年代物なんですね」
彼はピアノの椅子を引きながら、遠慮がちに首を傾げた。
「いいですか? ちょっとだけ」
うんうんと、一同がうなずく間もなく、青年の指先から思いもよらぬ美しい音楽があふれ出た。
優美なアルペジオに続く、しっとりと哀愁に満ちたメロディーは、往年の名曲〈恋はフェニックス〉の、軽めのジャズアレンジであった。少々気だるく、何とも粋なオスカー・ピーターソン版に、意図せずとも自然に加わってしまうウィーン訛りによる、ゆきずりの配達員が奏でるジャズは、実に新鮮で魅力的。洗練されたお洒落感に、その場の空気は一転し、中庭にいた連中までがピアノの周囲に集まってくる。
予想以上の周囲の反応に、クラウスは少々とまどった。調子に乗り過ぎてはいけない。派手にひけらかすこともできたが、あくまでも控え目に、上品にラストをまとめあげた。
やんやの拍手喝采と、アンコールの要請。彼らの心をつかんで味方に引き入れるには、もう一曲くらい必要か。クラウスは、こういう場にもっとも効果を発揮すると思われる、即興的に駆け巡る鮮やかな序盤に、しっとり胸に染み入る主題が魅力の、モリコーネの映画音楽を選択した。
〈愛を奏でて〉という曲名も、元の映画も、哀愁漂うメインテーマも、知るものはあまりいなかったが、殆どの女性、どころか年配の男性までが胸を打たれて涙していた。
「仕事に戻らなきゃ」
クラウスはいさぎよく立ち上がった。
「店長に叱られる」
とりあえず、この広間には例のものはなさそうだ。
「手を洗いたいな。汗かいちゃった」
そばにいた女性が、広間の脇のリビングの、さらに奥のキッチンに彼を導こうとした。クラウスはリビングを一瞥し、鏡がないことを確認してから、
「ああ、顔も洗いたいから、洗面所がいいな」
廊下の突き当たりの右手、と洗面所の在処を教わったら、あとはこっちのものだった。
クラウスは廊下を進みながら、他の部屋の状況を見渡した。突き当たりの左手に、間違えたふりをして侵入する。そこは広々としたアトリエだった。
壁から床に渡り、所狭しと飾られている大小様々な絵。風景画、人物画、殆どがわかりやすい写実的なものであったが、その色使いは彼特有のエネルギッシュなロマン性に満ちあふれていた。
これがシュテファン・ハイデンベルクの絵か。すごいな。クラウスはため息をついた。
画集でしか見たことがなかった、憧れの世界。いつか本人に会おう、いや、会わなければ。祖父の遺言を実行するために。そんな使命感を抱きつつも、自分の心の準備ができず一日伸ばしにしているうちに、彼は亡くなってしまった。
部屋の一角のイーゼルに、描きかけの絵があった。画風が違う? その周囲にも、同様のタイプの絵が何枚か無造作に立てかけられている。色合いはハイデンベルクのものと似ているが、さらにロマンティックで幻想風。
彼女の作品か。
こちらもまた、格別の才能ではないか。夜空のモティーフが好きなのか。それに音楽も。
おっと、見とれていてはいけない。鏡が外され、絵が入っている可能性がなきにしもあらずなのだ。等身大の額縁捜しに集中するが、それらしきものは見つからなかった。
次に洗面所にこもり、ネットでプラネタリウムの上映時間を確認する。ん? 本日のプログラムは既に終了しているではないか。地下鉄を乗り継いだとして、30分。彼女がまっすぐ帰って来たとしても……、あと15分は猶予があるわけか。
ピアノを弾いていた時、一カ所気になる空間があった。こんなチャンスは二度とないんだ。彼らから何らかの情報を引き出せるかも知れない。クラウスは自分を奮い立たせ、再び大広間に戻った。
「ひとつだけ、気になって」
言い訳をしながら、広間の中庭に通じるガラス戸付近の壁に触れる。
「以前ここに大きな鏡がありましたよねえ」
とんだはったりだったが、等身大の何かが掛けられていた形跡が、かすかにあるのだった。
「30年以上ここに出入りしているけど、鏡などなかったわよ」
誰もが知らないという中、一人だけ目撃者が現れた。
「うん。こないだは確かに掛かってたわね」
ヴァイオリンを弾く、年配の女性がそう言った。
数日前のサロンコンサート当日を含めた、僅か二日間だけ、鏡は掛けられていたのだった。コンサートと今日のパーティー、共に参加しているのは彼女一人だった。
「絵里香が嬉しそうに見惚れてたもの。屋根裏にあった額縁に、鏡を入れたんだって」
屋根裏か! これで鏡の足取りがつかめたぞ。クラウスは苦心してポーカーフェイスを保ち続けた。鏡はわずかな間、確かにここに掛けられていた。そして何らかの事情で、外された。
「でもどうして絵里香はまた外しちゃったのかしら。素敵な、大きな鏡だったのに」
さあ、それ以上追求されると、今度はこちらの立場が危ういぞ。いつ、そんな鏡を見たのかと。クラウスはさりげなく玄関ホール側に移動した。きびすを返して出ていくつもりだったが、女性陣に捕まり、再びピアノの前に引きずられていった。
「あと一曲だけ!」と。
仕方ない。時間はまだ充分あるはずだ。さりげない曲をさらりと弾いて退散しよう。
あれは〈ワルツ・フォー・デビー〉。
ふさぎ込んで帰宅した絵里香の心に、ビル・エヴァンスのしっとりしたメロディーが優しく入り込んできた。じわっと涙ぐんでしまう。落ち込んでいるだけに、なおさら心に響く、きれいな音色。
『大航海時代における星座の道しるべ』だとか『ガリレオが見た星の輝き』といった、ヨーロッパならではの、ロマンあふれたプラネタリウムのプログラムに憧れていた。なのに、今日も観れなかった。
ようやくたどり着いた遊園地は、平日の午後のせいか人気はまったくなく、半ばゴーストタウンと化していた。道を訪ねようにも唯一出合った生命体といえば、リアルメリーゴーランドで待機していたお馬さん方のみ。
大観覧車のふもとにひなびたプラネタリウム館を見つけた時は、既に時間切れ。係のお兄さんは、もう後半だから無料で入っていいよと言ってくれたが、周囲が星空の静寂のロマンに浸っているさ中、ガサゴソ途中から入るのは気が引けたので、遠慮した。
ウラニア天文台に行くといいよ、とプログラムを見せながら、お兄さんは慰めてくれた。ここよりずっと設備もいいしね、と。
前回はそのウラニアに行ったのに、わけのわからない映画を観る羽目に。
異国の地での一人暮らしは、まだまだ難しい。だけど、今日は家に帰れば仲間がいる。
それにしても……。
ジャズを弾く人なんて、いたっけ? しかもあんなにお洒落に弾ける人が。
そのピアニストの正体を知ったときの、絵里香の驚きといったら……!
予定外の家主の帰宅に仰天した、クラウスの慌てぶりといったら……!
謎の訪問者、クラウス・ホフマンがハイデンベルク家に現れて、三日目のことであった。
「額縁幻想」③ へ続く……。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
