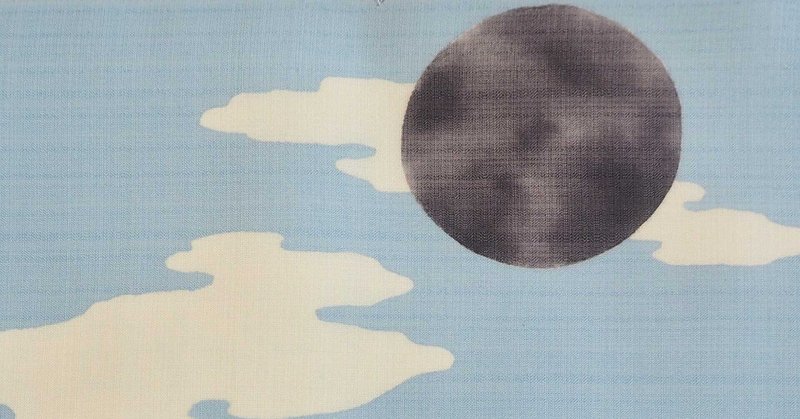
強みでは無いところを押し出しても・・・
今回は、キモノの良さを伝えるのは難しいですな、という話題であります。
例えば
キモノ姿でスポーツをして動画を撮り「キモノでもこんなに動けるよ!みんなも気軽にキモノを着ようよ!」という主張の動画を観ると、わたくし、その人のキモノ愛には心打たれるも、
「いや、スポーツするには、動きやすい衣類の方がいいと思うぞ。洋服でもより動きやすいモノをチョイスするんだから。ついでに言うと履き物もそうだな。安全面からいってもそうだろ?」
と、単純に思うのであります。
「キモノでも工夫次第でスポーツは出来なくはない」というのと「キモノはスポーツに向いている衣類だ」というのは内容が全然違うわけですから「出来なくはない部分」を主張してキモノの良さを広めようとしても無理があるように思うのです。
キモノは、夏は暑いですしね。浴衣だって、風が体の内側を通り抜けるワンピースに比べれば全然暑いです。そういう面でもスポーツに向いていません。
・・・特に優れた部分でもないところを魅力として押し出しても、キモノが一般社会に広まるわけがないですよね。
逆に「法衣を着て自動車を運転していたお坊さんが、運転に相応しくない衣類で運転しているという事で違反キップを切られた」というのもありましたね。その話が本当だとしたら、それもおかしな話です。
どちらも「キモノに対する誤解からそのような事が起こっている」と私は思うのです。
キモノに限らず色々選択肢がある現代に、事実を無視して偏った価値観で何かしらの文化を広げようとしても無理だと私は考えます。
確かに昔はキモノを着て、ある程度の労働はしておりましたが、単純に「昔はそれしか無かった」「それしか知らなかった」から、それを使ってやっていた、というだけの話です。
長着を仕事で着る際は(長着=現在一般に着物と認識されているもの)軽作業をする場合と、ほぼ知的労働のみしかしない場合とでは、素材も仕立て方も着付け方も違いますし・・・
昔から激しい労働をする場合は筒袖と股引だったり、その他運動に向くものを着用しています。郷土資料館などにそういう見本があります。
しかし、それも洋服系の作業に向く衣類よりも実用性が悪かったから淘汰されたわけです。
本来、着物業界の人たちが「今、キモノというと、ほぼ運動に向かない長着の形式のものだけですが、実は和装にはいろいろな種類があり、運動に向くものもありました・・・云々」という事を、社会に向けてキチンと説明しなければなりません。しかし、殆ど無理のあるキモノ擁護論しか見かけません・・・
私は何もキモノを貶めようとして、こんな事を言うのではありません。
「昔はそれしか無かった、それしか知らなかったから、それで間に合わせていた」というのは、キモノに限らず人間生活のあらゆる事においてそうなのだからキモノを特別視するべきではない、そういう面において何かを語るなら、キチンとした解説が必要、という事を言いたいのです。
それと、キモノを語る際に、キモノ業界人が業界の内側から都合の良い事ばかり語るのは問題アリです。単に衣類のひとつとして、そして日本文化全体から考え、社会の人々の利益を考え発言するのが良心的で未来志向な姿勢だと私は思います。
ここ数年で(2021年時)キモノ界隈も、洋服のようにカテゴリーごとの境界線が可視化されて来た気がします。
例えば、高級ファッションや工芸美術品としてのキモノをスタンダードに着るのを楽しむ方々、形式に囚われず着る人の感性で自由に楽しむ方々、古着系をメインに楽しむ方々、キモノは着ないけども夏に浴衣は着る若い方々など・・・
もちろん、以前からそういうカテゴリーはありましたが、もっとあいまいな感じでした。今もハッキリとまでは行きませんが・・・
それは「新品の美術工芸的なキモノを着る人口は大幅に減っているけども、カジュアルなキモノや古着、浴衣、レンタル着物を楽しむ人口は増えている」という事と「キモノに関わる業者さんたちの、いろいろな技術の進化」によって起こったのかな、と個人的には考えています。
そのように、キチンとカテゴリーが認識されれば、キモノ愛好者同士の「あんなのおかしい」とか「決まりばっかりで面白くない」とか(その他その他)不毛な争いも減りますしね。それぞれのカテゴリーで楽しんで、その美意識や価値観がお互いに影響を与え合い、文化的に進化すればさらにヨシ、です。もちろん、その全てをシームレスに楽しむ方もいらっしゃいますし。
上記のようにいろいろな和装の分野があるわけですが、全てに共通しているのは、キモノ特有の審美的美しさと、キモノの着用による動きの制限から生まれる独自の所作の美しさ、と言えるのではないでしょうか。
それと、素材フェチ、布大好き民族の日本人の「自分の好きな布を大量に身にまとう喜び」かと思います。
キモノは文様や色を、そして着用方法を、時に洋服以上に過激に楽しめるというところが、キモノを尖ったファッションとして楽しむ人たちに受け入れられたというのもあるかと思います。
それらの要素から、洋服を着た時とは別種の、まるで新しい皮膚を得たかのような高揚感が沸き起こります。
その精神的な喜びに、着る人も、着姿を観る人も、出来ればキモノが消えないで欲しいと思うのではないかと思います。
キモノは、昔とほぼ同じ形式の伝統的衣類が、現代ファッションとしても扱われており、関わる人が減ったとはいえ産業としての規模を未だ維持している珍しい衣類です。(もちろん、キモノだけがそうだという事はありませんが)
しかし、それは「審美性」の部分が進化して残ったので「不便な面も多い」のではないかと私は考えております。
どの国の、どの地域の衣類でも、伝統的なものは、あまり実用的では無いものが多いですよね。洋服でも昔のものは、現代のものに比べれば実用性には欠けます。フォーマル系では古今東西みなそうです。そういう面ではキモノも普通の衣類の一種であって特別なものではありません。
実用的衣類としては、洋服系から発生したものの方が優れていたから、和装系の労働服は淘汰されたけども、長着は審美的に特に優れていた、そしてその面で発展性があったから残った、という事です。
(ちなみに、和装系の労働着として認識されている作務衣が現在の形式になったのは昭和40年ぐらいからだそうです。それも実用性というよりはファッション寄りのものとして残っています)
キモノはパターンと着る形式がほぼ決まっているので認識されにくいのですが、昔より進化している部分が沢山あります。
仕立てや着付けの精度も以前よりも格段に上がっています。それによって、着姿が以前よりもキレイになって来ています。
以前は、キモノはある程度ゆったりと着るものでしたが、今はもっとオーダースーツのように体に沿ったシルエットにする事が増えています。以前のような、寸法的にアバウトな感じがキモノの良さだった、という意見がありますし、確かにそれはその通りなのですが、見栄えは体にしっかり沿い、かつ体型的欠点を補正してくれるものの方が良いですから、それは審美性から言って仕立て・着付けの進化として良いと思います。
特にハイファッション・美術工芸としてのキモノの場合はその傾向が強くあります。
そのような方向性は、高級オーダースーツに凝る人たちと楽しみ方が似ているように思います。
どちらも「制約があるところに知的・美的な部分を見い出して行く衣類」です。
基本的に、キモノは伝統的衣類ですから恒常性が高く、そのような変化・進化は短期間に大きく起こりません。
変化→元に戻る→(繰り返し)→その時に本当に必要なものが伝統に取り込まれる
というサイクルが繰り返されて、少しずつ変化して行くわけです。
伝統系のものは「保守的 = 新しいものを取り入れるかどうかを慎重に見極め、本当に必要となれば取り入れる」という特徴があるからです。保守的という言葉の真意は「変えない」という事ではなく「変化に慎重である」という事です。
それは悪い事ではなく、元々、どの国、地域でも伝統に根ざしたものは、どの分野でもそういう保守性があるのではないでしょうか。
伝統系の文化が持つ特徴的な「縛り(ルール)」の全てが悪いわけではありません。それは、その文化をより際立たせるため、そしてそれを楽しむために欠かせないのです。何でもアリは、逆に力が分散してしまい、面白く無くなるものです。伝統的な文化は、時代の変化で簡単に変わってはいけないのです。
しかし、キモノはアバンギャルドな創作性についても広く許容する特徴も同時に持っています。
保守への反動として、キモノをそのような伝統的形式から切り離して自由に着る方向もあります。それも、今盛んです。素晴らしい事だと思います。それもまた和装なのです。そのようなものの一部が伝統に取り込まれる事によって伝統は腐らずにいられるわけです。
事実を丁寧に観察すると、私にはキモノは変わっていないのではなく、進化して今の形式に落ち着いてるように観えます。
そのような進化によって残っている和装を、見当違いの方向から広めようとしても、無理なのではないかと私は考えております。
何にしても「今までキモノ界隈でやって来た事、そしてその延長線上の事」を繰り返しても効果は無いと思います。
今まで通りの事を繰り返すのが伝統ではありません。伝統文化に生命を与えるのは人間の新しい創作的エネルギーです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
