
【北欧読書6】 読書施設としての図書館は滅びるのか?
魅力的なプログラムが目白押しのマルチカルチュラルな文化空間となった公共図書館で、読書に没頭する利用者は「古き良き時代の図書館にこだわる時代に取り残された人びと」なのだろうか。
文化と情報の総合センターになった図書館
北欧の公共図書館が伝統的な本の館であったのは、1960年代までである。その後、図書館は徐々に変化し、21世紀の今、そこは文化と情報の総合センターである。さまざまなサービスが展開される中で、「3Dプリンタの使えるラボ」「コワーキングスペース」「起業支援」「フィットネスプログラム」等のキーワードを前面に押し出して来館を誘う。
司書にとって、図書館が社会の変化に合わせて変わっていくことは当然のことなので、常に時代の先端の知的動向に鋭敏である。自らを「文化仲介者」と称し、新しいメディアや情報テクノロジーを利用者に提供することに全く躊躇はない。
このような状況の中で、図書館は古いイメージを取り払い進化し続けてきた。それは必然的な流れでもあった。もし図書館が社会の流れと隔絶された状態で、資料提供を中心とした伝統的な機能にしがみつきそこに留まっていたら、おそらく社会施設として淘汰され図書館自体がなくなっていたかもしれないからだ。

エンパワーメントのための場所
公共図書館は柔軟性が高い生涯学習施設として、利用者が自分のやりたいことを主体的に実現していく、エンパワーメントのための場所である。
学校がフォーマルな学習空間だとすると、図書館はインフォーマルな学習空間であり、学びの対象も方法もぐっと広がる。ひとりひとりが持つ異なる学びのニーズを叶えるために、図書館には多様な学習支援システムが用意されている。そして利用者の学びを支えるために、必要な専門技術を身につけた司書が必ず配置されている。
公共図書館への来館は自由意志に任されている
公共図書館はすべての人に開かれているが、来館は完全に自主的な意志に任されている。だから図書館に行かない人がいるのは、当然のことだ。実際に、図書館の利用率が世界的にみて間違いなくトップクラスのデンマークでも、一年に一度も図書館に行かない人はたくさんいる。
しかし自分の意志で図書館に行かないことを選んだ人以外に、情報アクセスの必要がありながらも図書館を利用できない人、図書館という選択肢が選べない人がいる。たとえば基本的リテラシーを獲得していない人びとは社会から排除され、情報アクセスへの道が阻まれることが多い。
来館を自由意志に任せないのはどんな場合か
公共図書館は、このようなグループに所属する人びとを社会に包み込む役割を担っている。だから社会的に排除され、情報アクセスができずにいる人に関して、図書館側は来館を黙って待つことはしない。図書館側から働きかけて図書館に来てもらって、図書館は何ができるのかを示すのだ。
図書館では無料の語学教室を開催していること、子どもは宿題を無料で見てもらえること、困ったことがあれば無料で法律家に相談できること等々を伝え、利用できそうなプログラムを推薦して、実際に参加してもらう。
だけどこの場合も、継続して図書館を使うかどうかは、やはりその人に委ねられることになる。ずっと図書館に通い続ける人もいれば、図書館のサービスを通して情報リテラシーを獲得し、図書館をいったん卒業する人もいる。

「読書施設としての図書館は滅びる」
公共図書館の来館がそうであるように、利用方法もまた利用者に全面的に任されている。図書館はただ提供可能なサービスのメニューを提示し、利用者に主体的にそれらを選んでもらうのが原則である。
とはいえ、図書館側としては資料コレクションを生かした伝統的なサービスだけでなく、新しいメディアとサービスが利用されることを、大いに期待していることは間違いない。
オンラインデータベースの探索や電子資料の閲覧、新しい電子機器を使った創作活動や図書館でのワークショップなどが、これからの図書館のスタンダードとなることを想定して、図書館サービスをデザインしている。そして、そこには「読書施設としての図書館は滅びる」という強い危機意識が働いているのだ。
伝統的な図書館にこだわる利用者
実はこうした図書館の変化の流れにうまく乗れていないのは、むしろ利用者の方かもしれない。多くの人はいまだに「古い図書館のイメージ」をかたくなに持ち続け、何でもできるようになった図書館でただひたすら黙って一人で本を探したり本を読んだりしている。
図書館がこんなに変わっているのに、なぜ来館者の多くは変わらないのだろう。もちろん図書館側のPR不足はあるだろう。でもそれ以上に「図書館は本を貸し出す場所」という利用者自身による思い込みが、図書館での行動の幅を狭めているようにもみえる。

利用者は図書館に読書空間を求めている
つまり現時点で、サービス提供者である図書館側の思惑と、利用者の行動は必ずしも一致していない。結論を最初に言ってしまうと「多くの利用者は図書館に読書空間を求めている」のだ。図書館がどのような変化を遂げようとも、利用者は図書館を読書のための場所だと信じて疑わない。
北欧各国で刊行されている図書館統計は、そんな「変わらない利用者」をはっきり描き出している。どこの国でも、図書を借りたり読書したりすることを、図書館訪問の目的としてあげる人が最も多いのだ。
図書館で読書することは時代遅れなのか?
COVID-19の存在の片鱗も見えなかった2017年夏、夕暮れのフィンランド公共図書館。ティーンエイジャーの女の子2人が、半分にカットしたスイカを無邪気に食べながら大声でおしゃべりしている。その傍らで、別な世界にいるかのように読書に打ち込んでいる人びとがいる。
図書館愛好者の多くは、レファレンス質問もせず、文化プログラムにも参加せず、3Dプリンタを利用することもなく、ただひたすら図書館で読書に打ち込むことに喜びを見出す人たちなのである。
読書施設としての図書館は滅びない
魅力的なプログラムが目白押しのマルチカルチュラルな文化空間となった図書館で、読書に没頭する利用者は「古き良き時代の図書館にこだわり、時代に取り残された人びと」なのだろうか?
そうした人びとの振る舞いから、読書空間として図書館が持つ存在感の圧倒的な強さを示すことによって、「読書施設としての図書館は滅びる」という主張に対し反論することは、十分可能性があることではないだろうか。
21世紀の多目的文化施設となった図書館の世界に、「ただひたすら読書をする利用者」をきちんと位置づけること、それは読書というたぐいまれな営みを支える公共図書館の存在意義の再構築につながるに違いない。
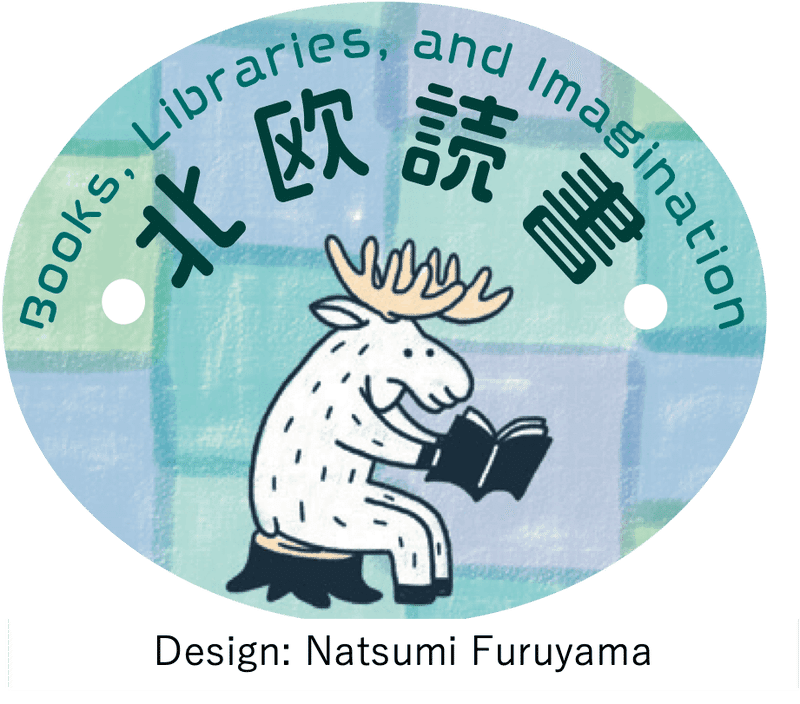
見出し画像 吉田右子・小泉公乃・坂田ヘントネン亜希『フィンランド公共図書館:躍進の秘密』新評論, 2019, 口絵
写真1 吉田右子『デンマークのにぎやかな公共図書館』新評論, 2010, p. 159
写真2 吉田右子・小泉公乃・坂田ヘントネン亜希『フィンランド公共図書館:躍進の秘密』新評論, 2019, p. 113
写真3 同上, p. 189
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
