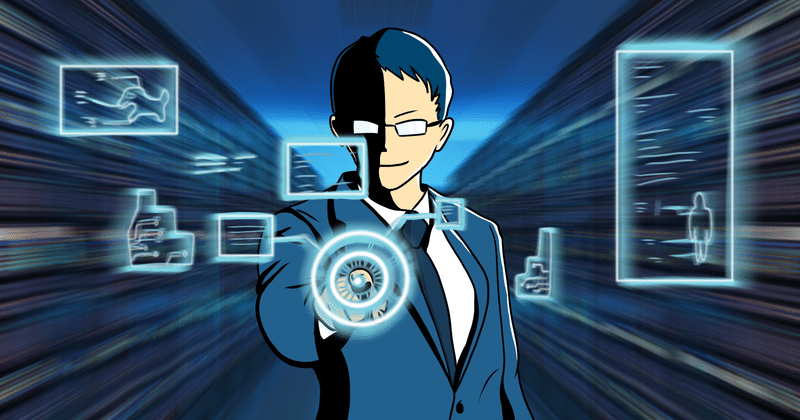
【映画所感】 マトリックス レザレクションズ ※ネタバレ注意
1999年に公開され、その斬新な映像手法と世界観で、後世に多大なる影響を与えた傑作『マトリックス』。2003年には続編となる2作が相次いで発表され、“マトリックス3部作”として一応の完結をみた。
古今東西、人気シリーズの宿命というべきか。どうしてもパート2、パート3と回を重ねるごとに、竜頭蛇尾の印象は否めなくなってくる。
“マトリックス3部作”もその例外ではなく、やはり第1作目が特別な輝きを放っていることは間違いない。それでも2作目の『マトリックス リローデッド』の、高速道路をわざわざ建設して撮影した圧巻のカーチェイスや、新キャラクターたちの躍動など、既存のアクション映画を軽く一蹴するくらいのポテンシャルはつねに備えていた。
とにかく、1作目の革新性が突き抜け過ぎたが故に、こと『マトリックス』の映像に関しては、鑑定眼のハードルがとてつもなく高くなってしまった。
名作の次回作のみに課せられる、全方向からのプレッシャー。大ヒットを記録したのち、一人歩きを始めた『マトリックス』関連のビジネスは、ウォシャウスキー姉妹のコントロールの及ばない範疇まで増殖していく。
当初から3部作になる構想だったというが、1作目の成功以降、純粋に創作だけに傾けられた時間は如何ほどのものだったのだろう。そんな状況の中、『マトリックス リローデッド』と『マトリックス レボリューションズ』をまとめ上げ、シリーズを完結に導いたウォシャウスキー姉妹には、最大級の労いと賛辞を贈ることしかできないはずだ。
「極東の島国で何をほざいてやがる」と罵られたとしても、その気持ちは揺るがない。
で、本作『マトリックス レザレクションズ』。公開直後から賛否両論吹き荒れ、本国アメリカでは、否定派の勢いが日に日に増していると伝え聞く。
「片腹痛いっ!」
確かに少々トリッキーな構成で、前半部分は“救世主ネオ”を探すという第1作目のストーリーをなぞったかたちで進行する。映画内設定では、前作の戦争終結から60年後の世界。トーマス・アンダーソン(ネオ)は、大人気ゲーム『マトリックス』の開発者として、ゲーム会社に勤めるクリエイターになっている。
このゲーム会社でのターン、いわゆる“仮想現実”の世界が楽しい。ラナ・ウォシャウスキー監督の自虐ネタとも取れるセリフが、ゲームクリエイターたちの口を借りて、次々と語られる。
この20年、毎年のように繰り返される続編の要請。さまざまな媒体への無断転用。預かり知らぬところで、ワーナー・ブラザースが勝手に企画を立ち上げ、『マトリックス』の新シリーズを作ろうとしているといった動き。監督の信条を無視した、イデオロギーへの『マトリックス』の曲解と引用など。
経済の動向によって左右されるアートの価値を、監督自らの経験を通して“ゴン攻め”してくれている。
この部分を「面白い、サイコー!」と肯定的に捉えるか、「超クールなサイバーパンクの世界はどこへ行ったんだ?」と嘆くかによって、評価は真逆のベクトルを進み、別々の終点を示す。
ギリシャ神話や聖書、哲学やSFといったジャンルからの影響を多分に受けて構築された『マトリックス』。新作では、確かにそうした一見小難しく思える要素は、後退しているかのように映る。ただ、内容が薄まったと言われれば決してそうではない。
前作の公開から20年余り、ウォシャウスキー姉妹を取り巻く環境は、公私ともに激変しているのだ。当時からトランスジェンダーの要素、考え方を巧みに作品へと昇華させていたが、今回のトリニティーの扱い方を見れば、一目瞭然。前作より明らかに色濃く反映されている。兄弟から姉妹へ、アンディからラナへ、そしてラリーからリリー(今作は不参加)へとすべてがアップグレード。
後半は、ネオと同じく生存していた、トリニティーの覚醒がストーリーの核心となって、物語を牽引する。今回の主役は、トリニティーといってもいい。子どもたちに囲まれ、虚構の世界で幸せに暮らすトリニティー。彼女が真実に目覚めるとき、『マトリックス』の世界はまた一つ次のステージへと移行する。
『マトリックス レボリューションズ』のエンディングからつづく、トリニティーのキラーワード「きれいね……」が、本作でも炸裂。次にくるネオのつぶやき「君なのか……」で、さらにトドメを刺された。
年齢を重ねたトリニティーは、なお一層美しい。ドゥカティをこよなく愛する姿も決まっている。1971年にテレビアニメ化された『ルパン三世』の衝撃は、皮のつなぎでバイクに跨る峰不二子の容姿と直結する。峰不二子の原体験はトリニティーの他、『ドラゴン・タトゥーの女』のリスベット、『ダークナイト ライジング』に登場するキャットウーマンと 、つつがなく受け継がれていく。
“バイク愛”もそうだが、個人的にトリニティーを語る上で欠かせないアクションの復活もうれしい。正対する相手に向け、片足を後方に振り上げ、背面から足裏やかかとを顔面に打ち付ける蹴り技。スクリーンで久しぶりにお目にかかれたことだけで、感涙した。「背面逆かかと落とし」とでも命名して、後世まで語り継ぎたい。現在のネオによる“バレットタイム”が見られなかったことを、帳消しにしてくれたとさえ思える。
自分のノスタルジーを掻き立ててくれたのは、救世主ネオではなくトリニティーのほうだった。ラナ・ウォシャウスキーの思うツボ。彼女の仕掛けた目論見が、あらわになった上での大団円。すこぶる気持ちがいい。
機械と人間の対立から機械と人間の和解による平和、そして今作はその先を見据えている。機械と人間の協調によって共生していく未来。
その未来に、“女”と“男”といった些末な違いは、もはや存在すらしていないのだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
