
固定観念の破り方
農学研究者&教育研究者の篠原信さんの新著『世界をアップデートする方法 哲学・思想の学び方』を読んだ。
篠原さんはSNSの長文投稿で人気の方だが、実は、数冊本も出版されている。これまで、『ひらめかない人のためのイノベーションの技法』や『子どもの地頭とやる気が育つおもしろい方法』 の2冊を読んだことがある。
どちらの本も、いわゆる常識や固定観念を覆されるような彼独自の世界の見え方がおもしろく、気に入っている。
今回読んだ『世界をアップデートする方法 哲学・思想の学び方』は、古代から現代までの社会思想史である。あとがきによると、哲学・思想の「びじゅチューン!」(Eテレで放送されている型破りな美術番組)を目指したそうだ。そのコンセプト自体がすでにおもしろい。
具体的には、西洋哲学・思想と東洋思想に分けて、哲学者や思想家、思想自体を時間軸で取り上げながら、独自の解釈・切り口で論評している。篠原さんの中で一度消化し、発酵させた結果の産物ともいえる感じで、取り上げる人物、思想がどんな固定観念をどのように打ち破り、どんな新常識を打ち立てたのか、短く的確にまとめてあるのが特徴である。
私的には一番最初のソクラテスだけでも読んでよかったと思えるぐらいの発見があった。
ソクラテスといえば「無知の知(不知の自覚)」で有名だが、ソクラテスのすごさはそこにはなく、天才だけが「知」を独占していたのを、凡人でも生み出せるものに変えたことにあるように思うと述べている。
その方法が「産婆術」である。「産婆術」とは、助産術のことではなく、凡人でも問いを重ね、考えを深めていけば新たな知を発見できる方法のことを指す。「弁証法」といわれることのほうが多いが、その違いを本の中では、
ソクラテスの産婆術は、無知を自覚する若者に対しては知を創造する技術となるのに、自分のことを天才だと思っている人に向けると「弁証法」に姿を変え、その人物の無知ぶりを暴き出す武器となってしまう。
心が開いている者に対してなら、知を作り出す「産婆術」となり、閉じている者に対してはその知識の窮屈さ、融通の利かなさを暴き出す「弁証法」になってしまうのだろう。
と表現し、最後に、この産婆術は、現在ではコーチングとして活かされていると言及している。
ほかにも数多くの人物・思想が取り上げられているが、ここでは私的に気になったあと2人を取り上げたいと思う。
まず取り上げたいのがルソー。
もともと教育に対して強い関心を持っており、つい先日、哲学者で教育学者でもある苫野一徳さんの『「エミール」を読む』を読んだばかりなのも、気になった要因の1つである。
『社会契約論』によって、君主制というそれまでの常識を覆し、民主主義をいう新たな常識を生み出し、『エミール』によって、ムチで叩く教育から、子ども自身の学ぶ力を最大限引き出す教育へとシフトさせた天才ルソー。
ルソーの教育論は、のちのモンテッソーリやジョン・デューイの教育論にもつながっている。
そして、ルソーの話とは逸れるという注釈付きで、興味深い話が共有されている。『逝きし世の面影(渡辺京二)』という本で、幕末・明治初期の日本の子育てについて、日本人は子どもをとてもかわいがり、ムチで指導するような乱暴なことをしないのに立派に育つ様子を見て、西洋人たちが驚いている例が多数紹介されているという。ルソーが提案した西洋では新しいといわれる教育法を、日本ではごく自然に実践していたことに西洋人が驚嘆したというエピソード。しかしながら、その後日本では、日露戦争あたりから、逆に西洋のそれまでのムチで叩いて厳しく子どもを育てることを良しとする方法を逆輸入し、その「信念」が現在でもまだ消えていないと指摘してる。
確かに、ムチで指導するようなことは”ほぼ”なくなっているが、心理的虐待という形で、今なお、呪いのように引き継がれていると思う。
教育虐待やエデュケーショナル・マルトリートメントにもつながってると思えてならない。
そして、最後に、取り上げるのはレイチェル・カーソン。
この本に登場する唯一の女性。海洋生物学者で、哲学者・思想家という枠では通常では取り上げられない人物だと思う。
ほかにも常識を覆いしただろう人物が多数いる中で、あえてカーソンを取り上げた真意はなんだろう?それだけでも興味がそそられる。ただ、篠原さんのSNSなどに投稿されているテキストをいくつか読んだことのある方なら、納得な人選だと感じるかもしれない。
本文では、
科学万能主義というそれまでの常識を覆し、科学も過ちをおかすことがある、という新常識を生み出したといえるだろう。
とまとめている。
篠原さんはもともとが農業研究者というのもあり、カーソンの代表作『沈黙の春』には心動かされただろうし、教育研究者でもあるので、『センス・オブ・ワンダー』にもひかれるところがあるのだろうと思う。
この本では6ページを割いて紹介されているが、篠原さんのnoteで、レイチェル・カーソンについて書かれたnoteがあったので、紹介しておく。
こちらの記事では、「カーソンは、科学に慎重さを与え、教育において「教えない教え方」を提案するという、二つの画期的なイノベーションを起こした。世界の常識をアップデートした人物として数えられてしかるべきだろう。」と締めくくっている。
実は、私にとってレイチェル・カーソンの『沈黙の春』も『センス・オブ・ワンダー』も思い入れの強い本である。『沈黙の春』は、学生時代に読んで、生物学に興味を持つきっかけを与えてくれた本であり、科学万能主義に懐疑的な価値観をはぐくんでくれた本でもある。また、観察する目の大切さとシステム思考的な考え方を最初に教えてくれた本でもある。『センス・オブ・ワンダー』の世界観はは、子育てするにあたり、ずっと土台の価値観として持ち続けている。
話は逸れるが、『センス・オブ・ワンダー』の新訳本がこの3月に出版された。独立研究者である森田真生さんが訳され、未完のこの本の新訳とともに、「その続き」として森田さんが描く「僕たちの『センス・オブ・ワンダー』」というテキストの2部構成になっている。カーソンが残した問いかけに応答しつつ、新しい読み解き、新しい人間像の模索を行っていて、なかなか魅力的な本である。挿絵のテイストもその世界観にマッチしている。GWに読了したが、今や10代後半になった子どもたちが小さい頃に、もっと一人の大人として、できたことがあったかもしれないと、少し感傷的な気持ちになった。
なお、この本がきっかけで、森田真生さんのことを知り、いろいろググって、以下のインタビューにたどり着いた。中でも、「共感」について語っている部分が新しく、目からうろこがポロポロおちたので、ぜひ読んでみてほしい。
さて、ここまで、特に関心が高かった3人を取り上げたが、残りは、実際に本を手に取って読んでいただきたい。
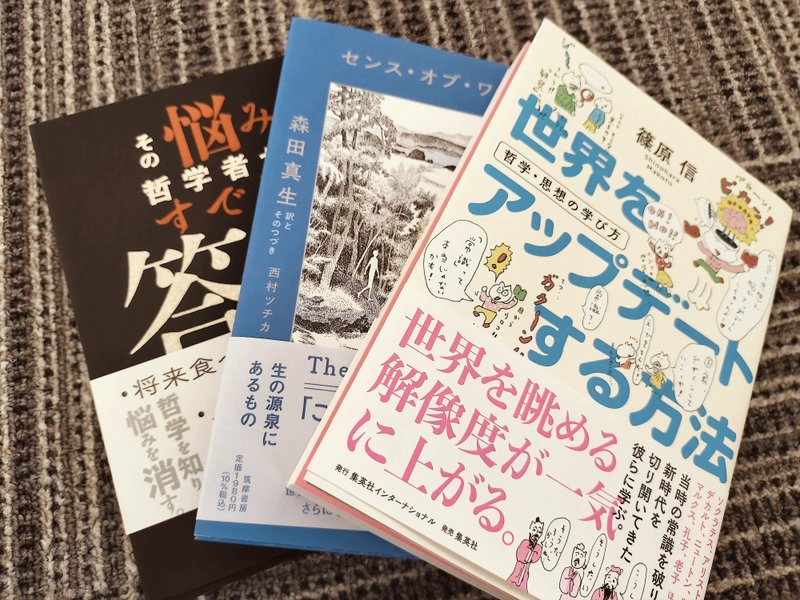
まとめ
この本も含め、これまで、哲学の本(といっても専門書や古典的書物ではなく、一般書)を興味の赴くままにあれこれ読んできて思うのは、古代から今現在まで、人間の本質的な部分は変わらないのかもしれないということ。
もちろん、当時の常識を破り、新常識にアップデートしながら脈々と思想が受け継がれてきのは間違いない。尊敬する哲学者・教育学者の苫野一徳さんが、哲学の歴史を「長い思考のリレー」と表現されていたが、まさにそうだと思う。とはいえ、巷にあまたある自己啓発本の類は、これまで紡がれてきた哲学的思考のエッセンスを形を変えて表現しなおしているだけかもしれないとも思う。
本棚にあって時折読み返す本に、『その悩み、哲学者がすでに答えを出しています(小林昌平)』があるが、この本なんかはストレートにそれを伝えている。こういう本を読むと、悩みなんて悩みではなくなってしまう。私は、何らかの課題について考えることがあっても、悩むとことがほとんどない。それはきっと、哲学に触れているおかげである。
学者でも研究者でも知識人でもなく、一般の単なる自由気ままな探究者でしかないので、哲学を小難しく考える必要なんてなく、これからも、ただただ哲学的思考を幸せに生きるために活用していきたいと改めて思う。
そして、いわゆる固定観念に懐疑的であるという点では、今までもこれからも変わらぬ私の世界の見方であるが、知の巨人たちのように世界をアップデートすることがなくても、一般の民が小さくこつこつ固定観念を破る行動をするだけでも、世界は少しずつ変わるのではないかと信じている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
