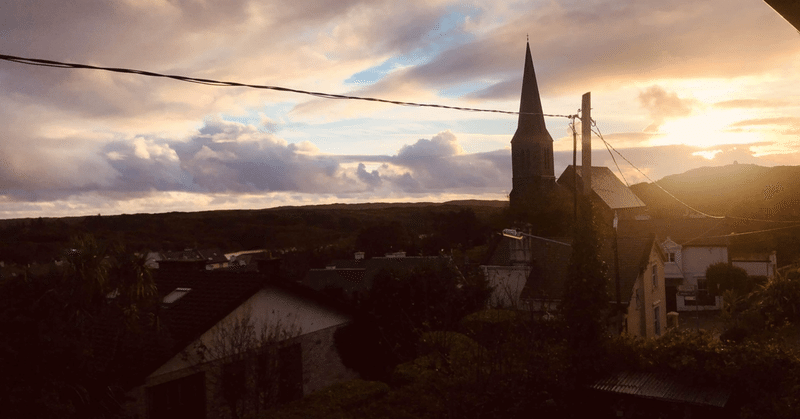
20世紀の巨匠に挑んでみる ジェイムズ・ジョイス『若い芸術家の肖像』
活字中毒と名乗っているだけあって(noteのプロフィール欄など)、小説に退屈or冗長な部分があっても、「これも修行の一つだ」程度に受けとめて、淡々と読み進める方です。なので、今まで途中で挫折した小説は四冊だけ。一つは、島崎藤村の『夜明け前』。これは中学生の時とKindle端末を購入した時、二回挫折しています。幕末を舞台にした小説なので、とても興味があったのですが、数ページで目が霞んできて。最近、藤村の別の作品を読んで、体質的に合わない作家だと確信しました。それから、ゲーテの『ファウスト』(小説ではなく戯曲だけど)。これは訳が古かったのかな。
挫折した小説、残りの二つはジェイムズ・ジョイスの作品です。『フィネガンズ・ウェイク』の方は、挫折というか…
川走、イヴとアダム礼盃亭を過ぎ、く寝る岸辺から輪ん曲する湾へ、今も度失せぬ巡り路を媚行し、巡り戻るは栄地四囲委蛇たるホウス城とその周円
丸善で最初のページを見た瞬間に、これは無理だとあきらめました。日本語なのだろうか?
それに比べると、『ユリシーズ』の方は普通のモダニズム小説でした。冒頭も、
押し出しのいい、ふとっちょのバック・マリガンが、シャボンの泡のはいっている椀を持って、階段のいちばん上から現れた。椀の上には手鏡と剃刀が交叉して置かれ、十字架の形になっていた。
理解できる文章です。ただし、この後は、説明的な文章はあまりなく、アイルランド・ダブリンの1904年6月16日という一日が、主人公であるレオポルド・ブルームやスティーブン・ディーダラス、その他の人びとの「意識の流れ」によって描かれます。同じように「意識の流れ」を描いていても、『ユリシーズ』では、前に感想文を書いたヴァージニア・ウルフの『ダロウェイ夫人』よりも、外界と人の意識の境目が曖昧です。人びとの意識が散漫で、絶えず外界の影響を受けているんですね。広告の文字や他人の雑談などを自分の中に取り込み、意識を形作る。一方では分散し、一方ではどこまでも拡張していく私という存在。ーー多分、『ユリシーズ』の方がより現実に近い形で人の意識を描いていると言えそうですが、あまりにも捉えどころがないために、読み進めるのに苦労しました。結果、四巻中一巻を読み終えた時点で続きを諦めた、と。
*
ところが、『ダロウェイ夫人』の感想文を書いている最中に、「今ならジョイスも読めるかも?」という何の根拠もない自信がわいてきて…といっても、積読本を多数抱えている身で文庫本四巻になる『ユリシーズ』に挑戦するのは無謀なので、電子化されていた『若い芸術家の肖像』を読むことにしました。
この小説は、ジョイスの自伝的小説で、『ユリシーズ』の準主役であるスティーブン・ディーダラスの成長を描く教養小説でもあります(教養小説=主人公がさまざまな体験を通して内面的に成長していく過程を描く小説のこと。宮崎監督の新作『君たちはどう生きるか』の原作も、戦前の代表的な教養小説です)。『ユリシーズ』の六年前に書かれた作品なのですが、意識の流れ手法は一部にしか使われていません。といって、伝統的な手法で書かれているわけでもなく、主人公の成長につれて文体が変わったり、状況を説明する文章がほぼなかったりと、モダニズム文学らしさが感じられる作品となっています。
もっとも、同じジョイスの小説でも、『フィネガンズ・ウェイク』や『ユリシーズ』とは比べものにならないぐらいに読みやすく、普通に楽しめる小説でした。百年以上も前のアイルランドの少年の成長物語なのに、まわりの友達への違和感…別に孤立しているわけではなく、一緒に遊んだりもするけど、ふとしたことで周囲への違和感が湧き出て、苛立ちと怒りで自分を持て余してしまう…といった描写が、自分のことのように感じられました。
逆に、政治や宗教が子どもに影響を及ぼす様は、自分には縁遠いことなので、非常に興味深く読むことができました。
いつだったか、マーティン・スコセッシ監督が「同じカトリックでも、イタリアのカトリックとアイリッシュのカトリックは別物」とおっしゃっていました。この本に書かれているのがアイリッシュ・カトリックの教えなのか、あるいはイエズス会の教義なのかわかりませんが(主人公はイエズス会が経営する学校に通っています)、罪の意識と地獄落ちの恐怖で子どもを追い込んでいくんですね。特に、性に対して非常に厳しくて、スティーブンが女性に愛憎相半ばする面倒な感情を抱いたり、十代の少年にしては過剰なほどにリビドーを発散させたりしてしまうのも、精神を縛るカトリックの教えゆえだと感じました。神が人を縛り、人を追い込んでいく…という状況は、日本人にはなかなか理解しにくいですが、ジョイスの描写力のおかげで、少し理解が進みました。
この小説を読んだからといって、『ユリシーズ』や『フィネガンズ・ウェイク』に近づけたとは全く思えませんが、ジョイスという険しい山の登山口にはたどり着けた気がします。
読んでくださってありがとうございます。コメントや感想をいただけると嬉しいです。
