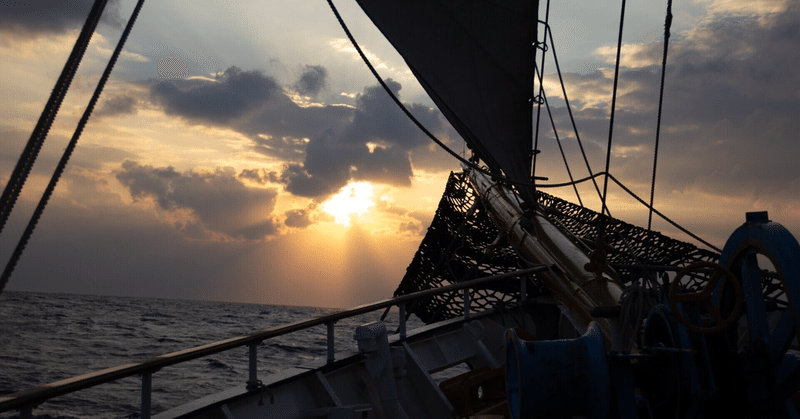
「トライアングル」その6
連載ファンタジー小説
わたしはだれ?
第十五章 洞窟の中
「おい、おまえら、な・・・」
「静かにしろ!」
ハメドが、トンデンじいさんの口を押さえた。
黒頭巾の男たちは、じっと耳をそばだてている。
やがてばぁばたちの耳にも、ギャァァーと体の芯まで凍りそうな不気味な声がきこえてきた。
まっ暗な中、ばぁばの耳にダフネのおびえた息づかいがきこえる。
ばぁばは右手でダフネを、そして左手でサラダッテを抱き、洞窟の外でうなっているものが去ってくれるのをじっと待った。
どれくらい時間がたったのだろう?
無気味なうなり声が遠ざかっていくと、洞窟の中で、ふぅーと安堵のため息がひびいた。
「もう大丈夫だ。ハメド、あかりをつけてくれ」
カチッと火柱がたち、ランプの光が洞窟の中を照らした。
「一体あれはなんだよ?」
カンタンがきいたが、アルドは答えず
「このばあさんがいったように、おれたちにも、おまえたちにも秘蔵のカードをあるようだな。すぐにでも見せ合いたいところだが、じきに陽もくれる。そうなったら、もう外には出られないから、扉はこのまま閉めて、まず飯だ。
おいブレンド、支度をしてくれ」
といって、洞窟の中に作られた炉に火をおこし始めた。
炉にそなえつけられた鉄の三脚の上で、ヤカンがしゅんしゅんと音をたて始めると、ブレンドは香りのよい葉をその中に入れた。そして奥から干し肉と固い丸パンを出してきた。
カップに熱いお茶が入れられ、それぞれが無言で肉やパンを食べ始めた。
ダフネは何も食べたくなかったけれど、香りのよい茶だけはうれしく、ゆっくりと味わいながら飲んだ。
やがて大皿に盛られた食べ物がなくなり、カップにふたたびお茶が注がれると、まずサラダッテが口を開いた。
「このお茶、ほんとうに香りがよくっておいしいわ。こんなお茶始めて。なんの葉を乾燥させたのかしら?」
「ブルーフェアリーの葉だ」
「ブルーフェアリー?」
思わず口走ったダフネを、アルドをじっと見つめている。
男たちは、洞窟の中でも、黒頭巾をとろうとはしない。
「さて、そろそろカードを見せ合おうじゃないか。おれたちから始めるか?それともおまえたちからか?」
「どっちからでもいいよ」
ばぁばが答えると、アルドはちらっとダフネを見てからいった。
「じゃあ、まずおれから話そう。おれの名はアルド。こっちのでっかい奴はハメド、あとの二人は双子で右が兄のブレンド、左が弟のシラードだ」
「あんたたち、若く見えるときもあるし、その反対にずいぶん年をとったようにも見えるけど、本当の年はいくつなんだい?」
ばぁばがきくと、炉を囲んで座っていた四人はお互いの顔を見合って、にやりと笑った。
「おれは二十四で、ハメドは一つ下の二十三、この二人は十八になる」
「ヒュー」
カンタンが口笛を鳴らした。
「おれよりずっと若いじゃないか」
(はっきり顔は見えないが、年よりずっと老けてみえる。ここ子たちは、よっぽど苦労してきたみたいだね。さっきのうなり声といい、ここではなにか恐ろしいことがあったことは確かだ。まぁ、その話もおいおいでてくるだろうから、ゆっくり話をきこうかね)
ばぁばは、チロチロと燃える炎を見つめながら心の中でつぶやいた。
「まず、どこから話そう・・」
アルドが、ふたたび話し始めた。
「フラリアは・・・、フラリアは、本当はとてもきれいな国なんだ」
「知ってますよ」
アルドのことばに、サラダッテはうなずいた。
「知ってる?緑の国、風の国だったフラリアをか?」
「ええ。私は三十年前に、植物学者のリーフ教授の助手として、この国に来たことがあるのよ。
その頃、ここはブルーフェアリーの花が咲き乱れ、やさしい風がいつも吹いていたし、それに見渡す限り緑の大地が広がって、子どもたちの笑い声がいたるところで響いていたわ」
アルドは、ぎゅっと唇をかんだ。
「そうだ、フラリア人は風の民。風の声をきき、風とともに歌ってきた。
風は教えてくれた、いつ種を蒔き、いつ収穫すればいいかを。そして船を浮かせることのできる石がどこに埋まっているかを。
フラリアの民は、みな豊かだった。長はいつもいっていた、風は知恵をわけてくれる。その風に感謝し、使う分以上にほしがって大地を傷つけてはいけないとな。もちろん風の声をきく豊かなフラリアの力を欲しがる外の者はたくさんいた。だからフラリアを囲むオオカベ山と海には、侵入者を防ぐために、強い風をいつも吹かせていたんだ」
「でも私がリーフ教授とここに来たときは、その風が割れて中に入ることができたんですよ」
「風はとても賢い。そいつが悪をもたらすときは強い風を吹かせ国に入るのを妨いだ。その逆に善をもたらす者には何もしない。
ここの風はな、想いを読み、それを汲み取ることができるんだ」
「そんなにすごい能力を持ちながら、どうしてこの国は滅んだんだ?やっぱり十二年前にの戦争が引き金だったのか?」
「えっ?」
トンデンじいさんのことばにアルドは耳を疑った。
「十二年前?なにいってるんだ、戦いが始まったのは三年前だぞ」
今度はトンデンじいさんのほうが驚いた。
「おいおい、なんだよ、フラリアは二度も戦争があったのか?」
「ここで戦いがあったのは、一度だけだ」
眉をひそめ、アルドがいった。
「戦いは一度だけなら、どうして三年前と十二年前に別れるんだ?」
「絶対に十二年前ですよ」
「そうだよな、おれたちが飛行船で飛んでた時に、内戦のニュースをきいたんだぞ」
カンタン、サラダッテ、トンデンじいさんが口々にしゃべり始めたそのとき
「おれは・・・」
黒頭巾の男の一人、ハメドが低い声で口をはさんだ。
「おれは、さっきアルドがいったように、今年で二十三になる。十二年前、おれが十一の時、この国は平和だった」
「ああーっ、くそっー、いったいどうなってるんだよ。おい、フラリアって国は二つあるんじゃないか?」
カンタンが、髪の毛をむしりながら叫んでいると、ばぁばがふと思いついたかのようにつぶやいた。
「ちょっとききたいんだけどねぇ、今年は何年になるんだっけ?」
「デイフル暦五百十年だろ」
怪訝な顔をしながらもアルドが答えたのをきいて、ダフネは身震いをした。
「デイフル暦五百十年?なに寝ぼけたこといってるんだ。今年はデイフル暦五百十九年だぞ。なぁカンタン?」
「おう、そうだとも。五百十九年、百年ぶりにほうき星が近づく年だ」
ダフネがそっと男たちを見ると、四人が四人ともまっ青な顔をしていた。
「どういうことだ?どうしておれたちとおまえたちの年が違うんだ?」
アルドの声は震えている。どちらが正しいのかわからない。
しゅんしゅんと湯が沸く音だけが響く洞窟の中で、ばぁばが静かにいった。
「もしよかったら、この国でなにがあったのか話してくれるかい?」
炉の炎が影をつくり、それがアルドの顔を、長い間苦汁をなめた年寄りのように見せた。
これを見て、ダフネは恐ろしくなり、ばぁばの腕の中に自分の手をすべりこませると、ばぁばは心配ないよ、というかのようにうなずいてくれた。
第十六章 風の街フラリア
「風の街フラリア」
アルドの顔から影が消え、幸せな時を思い出したかのようにほほえんでいた。
「風で回る風車の音、子供たちの笑い声、市場のざわめき、時々起きる小競り合いの怒鳴り声さえ今はなつかしい。
ブルーフェアリーの香りが町中に漂い、誰もがこの幸せがいつまでもつづくものだと思っていた。だが違った」
アルドは、炎をはさんで向かい側に座っていたカンタンを見た。
「おい、おまえ。おまえはここで何が起こったと思う?」
そうきいた声には、はかりしれないほどの怒りがかくれていた。
「あー、えーっと、風の力が弱くなって、外から敵が攻めてきたんじゃないのか?」
フフフッと笑うアルドの声をきいて、ダフネはぞっとした。
「敵が攻めてきた、そう、それだったらどんなによかったか・・。
この国を滅ぼしたのが他の国のやつだったら、おれたちはこんなにも苦しまなかった。
だが・・・、だがちがう。フラリアをこんなふうにしたのは、自分達フラリア人なんだ。
そうだ、おまえたちがいう十二年前としよう。あの時からフラリアは変わった。さっきいったように、フラリアの民はみな豊かだった。だれもが平和で、自分たちの持っている物に十分満足していた。そう、そう思っていた、長も、おれも、そしてほとんどの民がな。
だが、ちがっていた。フラリアが風の声をきき豊かだということは外の世界の奴らも知っていた。
その中に、この力を利用したいと思う腹黒い奴らがいたとしてもおかしくないだろ?だけど、そういう奴は、フラリアの風がじゃまをして国の中には入れない。ずっと長い間、そうやって国は守られてきた。
だがな、今まで考えなかったような卑劣な手を使うやつがあらわれたんだ。そいつらは考えたんだ、自分たちがフラリアに入れないのだったら、フラリアから外に出てきた者を利用すればいいってな。
フラリアでは、ほとんどのものを自国でまかなっていたけれど、どうしても外から仕入れないといけない物もあった。この他国と取引をする交易人にやつらは目をつけたんだ。
どんな手を使ったかは、おれは知らない。だがな、問題はそそのかされた交易人が欲を持つようになり、腹黒い奴らの側についたということ。そして裏切ったその交易人の長は国で一、二を競うほどの風使いだったということだったんだ」
「交易人の長?国で一、二番の風使い?それはどういうことなんだい?」
アルドは、身を乗り出してきいてきたばぁばのカップにお茶を注いだ。
「フラリアには三人の長がいた。国のさまざまな法の取り決めを司る長タッカード、精神的な長であるフォラード、そして他国との交易を司る長オリド。
この三人の長たちはな、だれよりも風の声をよくきくことができた。
風の教えと風がなにを伝たがっているかをな。そして、それだけじゃない、風を操ることもできたんだ」
「風を操る?どうやったらそんなことができるんだ?」
カンタンが口をはさんだ。
「風に自分の意志、想いを吹き込む。
意思を持った風は、吹き込んだ者の思い通りに操られる。そうなった風は、風のことばをきくことのできるフラリアの民をも主人の思いのままに操ることができるんだ」
「なんて恐ろしい。そんな能力を持った人に悪の心が宿ったら・・・」
サラダッテが、両手で口をおおっている。
「そうだ、その恐ろしいことが現実になった。
外の悪人と手を結んだオルドは、まず交易人を味方につけ、交易人たちは、自分の妻を友を巻き込んで、さらに多くの民をオルド側にした。
人間なんて弱いものだぜ、ほんのちょっとの誘惑ですぐに折れるからな。今の今まで自分に満足していたやつが、他人と比較し始めると不足分が不満になる。
オルドは風を使って、足りない、足りないっていう気持ちを国中にばらまき、いろんなところで反乱をおこした。だから長フォラードはブルーフェアリーを使ってこの反乱をしずめようしたんだ」
「ブルーフェアリーには、そんな効用があるの?」
サラダッテが驚いている。
「ブルーフェアリーの香りは、風を浄化する。
ブルーフェアリーの香りが風にのって流れていれば、怒りや不満の気持ちは収まるはずだったんだ。だがな、オリドは賢かったよ。その動きをいち早く察して、あの花を一本残らず根こそぎ焼くつくしたんだからな」
アルドは、サラダッテが咲かせたブルーフェアリーの花を見てつぶやいた。
「もう一度この花を見られるとは思わなかった」
「おい、それからフラリアはどうなったんだ?話を止めるなよ」
カンタンがせかした。
「そのあと?そのあとはどうなったと思う?教えてやろうか?そう、まるで地獄そのものだった」
ハメド、シラード、ブレンドは唇をかみしめ、涙がにじんだ顔を見られまいとするかのようにうつむいていた。
「二人の長、タッカードとフォラードも風に意思を持たせ、オリドの巨大な負のエネルギーを持つ風を押さえ込もうとした。
だがな、いったん火がついた邪悪な風は二人の力をもってさえ止めることはできなかったんだ。
負のエネルギーを持った風は、フラリアの民の不安、怒りの心をさらなる糧として、ますます巨大になり、ついにはその主人であるはずのオリドの命令さえきかなくなってしまったのさ。
自分が蒔いた恐怖の種は芽をだし育った。だがな、その芽は大きく育ちすぎ、もはや制御することもできなくなった。そして最後はオルドをも飲み込んでしまった。
おまえたちもきいた悲しみ、苦しみ、怒り、すべてを持つあの風のうなり声が国中で吹きまくった。略奪、ケンカがおこり、気が狂った奴だっている。なあばあさん、フラリアの地形は知ってるか?」
アルドが、ばぁばにきいた。
「たしか北から見ると、砂漠、フラリアの市街地、海の順にあっただろ?
砂漠から海に向かって急傾斜していて。この砂漠の侵入を防いでいるのが、国の背後を囲むようにそびえ立つオオカベ山。違うかい?」
「そうだ、そのとおりだ。壁になっているオオカベ山には、一箇所だけ低い所があってな、ここには砂の浸入を防ぐために堰が造られていたんだ。
この堰を、狂った風が人の心を操って破壊させたから、砂が街の中に濁流のようになだれ込んできた。
逃げまどう人の恐怖の声、赤ん坊や子どもの泣き声・・・。もう止してくれっとどれだけ願ったことか・・・、だがこれで終わりじゃなかった」
ことばが止まった。
両手をかたく握りしめうつむくアルドをせかす者は、だれもいなかった。
しばらくすると大きく息を吸い込み、アルドはふたたび話し始めた。
「逃げまどう人の上をうなり声をあげた風が通ると、今度はみんな海に向かって歩き始めたんだ。ハルーメンの笛吹きが笛を吹いて子供を連れて行ったように、巨大な負のエネルギーを持った風が、フラリアの民を海に連れ込んでいった。
赤ん坊を抱いた母親が、年よりが、男が、女が、みんな次々と海に入っていって、そのあとはだれも帰ってこなかった」
ダフネの目が恐怖で大きく見開いていた。
ばぁばも、サラダッテも、カンタンも、そしてトンデンじいさんさえもなにもいえなかった。
やがて、炉の中でパチンと火がはぜたとき、カンタンが顔をあげた。
「なあ、おれ、今気がついたんだけど、フラリアの国民はみんな死んだんだよな?だったら、こいつらはだれなんだ?」
「そういわれればそうだな。おまえら、こんなだれもいなくなった所にいるなんて、なんかやましいことでもしたんじゃないか?」
トンデンじいさんがこういうやいなや、ハメドがさっと立ち上がった。
「きさまぁ、勝手なことをいいやがって」
「おっ、やるか?おれは強いぜ」
「よせっ」
アルドは、トンデンじいさんに飛びかかろうとしたハメドを止めた。
「ことばには気をつけてほしいなぁ、じいさん。こう見えてもおれらは繊細なんだからさ」
アルドの口元は笑っていたが、その目は冷たく光っていた。
ばぁばは首を小さくふって、トンデンじいさんをおしとどめた。
「さあて、おれは最初のカードを見せたぜ。次は、あんたたちの番だな」
第十六章 ダフネの耳
「まず、自己紹介から始めようかね。わたしの名は、サスーラ。今は物書き稼業をしている。こっちはサラダッテ、植物学者。トンデンじいさんにその甥のカンタン、二人は修理工で機械のことならピカ一の腕前だよ。そしてこの子はダフネ、今の名前だけどね」
「今の名前?どういう意味だ?」
アルドがきき直した。
「この子の本当の名はわからないんだよ。じつはね・・・」
それからばぁばは、十二年前、木の船から赤ん坊を助けたけれど、そこには身元を知るなんの手がかりもなく、ただ種が入った紙箱だけがあったこと。今年サラダッテの温室で、その種から芽が出たこと。そしてその花がブルーフェアリーであったことを話した。
「バカなことに私は、この子に三月はダフネっていうように月ごとにかわる名前をつけていたんだ。
ころころと名前が変わるなんて、まるで根無し草だよ。その根無し草を断ち切るきっかけが今まではなかった。
けどね、ようやくそれが見つかったんだ。船の中にあったのはブルーフェアリーの種だったから、この子はフラリアで生まれたのかもしれない、そこにいけば何かわかるかもしれない、そう思ったから私らはここに来たのさ。それなのに・・」
「木の船って、どんな形だった?」
ばぁばが話し終えるのを待ちきれずに、双子の兄ブレンドが口をはさんだ。
「どんな形って・・・、赤ん坊一人がやっと入れるような小さな木の船さ。後にプロペラがついていたけど、それがどうして飛べるのかなんて、私らにはちっともわからなかったよ。
ブレンド、だったっけ、どうしてそんなことをきくんだい?」
ブレンドが答える前に、アルドはダフネの腕をぐいっと引き寄せ、すばやくの長い髪をかきあげた。
「おおっ!」
ハメド、ブレンド、シラードが、大きく息を吸い込んだ。
「てめえ、なにしやがる」
カンタンはアルドに飛びかかったが、するりとかわされ、大きな音をたてて洞窟の壁に激突した。
「おっと失礼」
アルドが頭を下げると、三人の男たちは大笑いをした。
「いいかげんにしておくれっ!これはいったいなんのまねだい?」
ばぁばはアルドの腕からダフネをひきもどすと、アルドが答えた。
「希望だ」
「希望?なにが希望なんだい?」
「その子の耳だ」
「ダフネの耳だって?」
「生まれたときからその形だったのか?」
ばぁばは、さぐるような目でアルドを見た。
「十を過ぎた頃から少しずつ変わってきて、十二の時、この形になったんだよ。けど、この耳がどうしたっていうんだい?」
「見ろ」
まずアルドが、それに続いて他の三人も黒い頭巾を後ろにおろした。
弱い光の下だったが、四人の顔ははっきりと見える。浅黒い肌をして鷹のようにするどい黒い目を持つアルドは黒い髪をうしろに束ねていた。いかつく張ったアゴをもつハメドは、アルドと同じように黒い髪をしていたが、まだ少年の面影が残るブレンドとシラードの双子の顔は、アルドたちとちがって白い肌をしていた。二人はそっくりな顔をしていたが、瞳の色だけがブレンドは青、そしてシラードが茶色と違っていたのだった。
「お、おまえら、その耳・・」
トンデンじいさんがあえぎながら、アルドの左耳を指さしている。
ダフネは、ばぁばの手をぎゅっと握った。
「気がついたか?」
四人の左耳は、ダフネの耳と同じ形をしていたのだ。
「シラード、話してやれ」
「ぼくが?ぼくでいいの」
アルドはうなずいた。
「ぼくたちはヘブンスなんだ」
「ヘブンスって?」
サラダッテとトンデンじいさんが同時にきいた。
「ヘブンス、半分っていう意味さ。アルドやハメド、それにぼくらの母さんはフラリア人だけど、とうさんは外の人なんだ。
ぼくらの母さんはみんな交易人でね、外にでていたときに父親と出会ったんだと思う。
ふふ、思うってどういうことだってききたそうな顔だね」
トンデンじいさんは、あわててうつむいた。
「父親がだれかなんて、みんな知らないさ。そんなことはどうでもいい。母さんは、ぼくたちを生んでから少しの間フラリアにいたけど、三歳になったとき船大工のダッフルドじいさんにぼくらを預けて、また交易人を始めたたのさ。そこには同じヘブンスのアルドやハメドがいたんだ」
「それがその耳とどういう関係があるんだ?」
こうきいたのはカンタンだ。
「フラリア人はね、みんなこの子みたいに両耳が蝶の羽みたいな形をしてるんだ。でもぼくたちの耳は、左耳はそうだけど右耳はあなたたちと同じ形。だからぼくたちは、純粋なフラリア人ほどうまく風の声をきくことができなかった。小さいころは、半フラリア人ってバカにされたけど、でも、この半耳のおかげで助かったんだよね」
「半分しかきこえないから、恐ろしい風に操られなかったの?死なずにすんだの?じゃあ、じゃあ、もしかしてあなたたちは、ずっとフラリアに住んでいたの?」
どれだけさびしかっただろう?そう考えただけで、ダフネのほほに大粒の涙がこぼれていった。
そんなダフネを、シラードは愛おしそうに見つめている。
「あんたたちがフラリアの生き残りなら、この子が乗っていた木の船のことをなにか知らないかい?」
ばぁばの問いにアルドが答えた。
「あの船はおれたちが作った」
「おまえたちが作っただって?」
カンタンとトンデンじいさんが飛び上がった。
「お、おまえ、あれは帆もないのに飛んでいたんだぞ。動力源はなんだ?どういう仕組みになっているんだ?」
「おい、じいさんちがうだろ。今きくことは、こいつらがダフネのことを知っていたかどうかなんだって」
ダフネも、サラダッテも、ばぁばもアルドを見ていた。
「おれたちは、この子が生まれたときから知ってるさ」
「ああ、ばぁば」
ダフネは、ぎゅうとばぁばの手をにぎった。
「おれたちは、船大工のタッフルドじいさんにガキの頃からみっちりと修行させられたんだ。あの舟はな、おれたちが初めて仕上げまで全部まかされて造ったやつだ」
「その船に、どうしてダフネが乗っていたの?」
サラダッテがきくと、ばぁばとダフネは、まばたきもせずアルドのことばを待った。
「タッフルドじいさんのとなりには、ブルーフェアリー畑の世話をしていたサテルドとその奥さんのイマルダが住んでいたんだ。
イマルダは、おれたちの服を繕ってくれたり、腹をすかせているとパンを焼いたりしてくれた。
ヘブンスのおれたちをかわいがってくれたのは、長フォラードのほかにはあの人たちだけだった。だからイマルダに子どもが生まれた時、おれたちはなにかお祝いをしたかったんだ。けどな、金を持ってないおれたちができることといえば、たった一つ・・・」
「わかった。船を造ること。あの船を造ることだったんだな」
トンデンじいさんが叫んだ。
「赤ん坊はかわいくってね、ブルーフェアリーの花を見せるとうれしそうに笑うし、それにつぼみにさわると、そのつぼみが次々に開くから、長フォラードはこの子が大きくなったら、すばらしい花の世話人になるだろうっていってたんだ」
シラードのことばをきくと、サラダッテはわっと泣き出してしまった。
「おいおい、まだ肝心な事をきく前に泣くなよ。しょうがねえなあ、ばあさんになると涙もろくなってよぉ」
こういったトンデンじいさんの声もかすれていた。ダフネの胸がはげしく鼓動している。
「その赤ん坊の名前は・・」
ばぁばがダフネの手をにぎりしめた。
「その赤ん坊の名前は、フレイ・サテルド」
十七章 空白の時間
「ばぁば、名前、私の名前よね?」
「ああ、ああ、わかってるよ」
ばぁばはダフネを見てうなずいたが、その顔を険しかった。
「おいおいサスーラなんだよ、そんなに難しい顔しやがってよぉ。ダフネの素性がわかったんだぜ、もっとうれしそうにしろよ」
「あらやだ、トンデンじいさんったら。ダフネじゃなくって、フレイですよ」
泣きすぎて鼻の頭がまっ赤になったサラダッテは、ぶっーと鼻をかんでから抗議した。
「十二年と三年」
ばぁばがいった。
「この問題がまだ残っているよ」
「おっとそうだった。おい見てみろよ」
カンタンが、ダフネ、いやフレイを指さしている。
「今まできいた話からすると、その木の船に乗っていたのはダフネ、あっ、ちがうフレイなんだよな。じゃあきくけど、フレイはいつ生まれたんだ?」
「この国がおかしくなるほんの少し前だ」
アルドが答えると、カンタンはすぐにまた質問した。
「ということは、おまえらの説からすると三年前っていうことだよな?けど、こいつはどう見ても三つには見えないぞ。なあ、これをどう説明するんだ?」
この問いにアルドは何も答えなかった。いや、答えられなかったのだ。
アルドだけではない、この中にいるだれひとりとして、どうして時間のずれがあるのかわからなかった。
「まるでここだけ時間が止まっていたみたい」
フレイが、ぽつりとつぶやいた。
これをきいてハメドは、何かを思い出したかのようにつぶやいた。
「時間が・・・止まった?ああ、そうか。これは・・・もしかしたら・・・」
「なにか思い当たることがあるのか?」
アルドがいうと、ハメドは小さくうなずいた。
「あの時、長フォラードが・・・」
「しっ、だまって」
ハメドの話をフレイがさえぎった。
目を閉じ、髪をかきあげて、一心に何かをきいていたフレイの体が震え始めた。
「来る、また来るわ!」
アルドは、すぐに洞窟の入り口に走りよって、木の扉から外をうかがった。
「くそっ、もどってきた」
ブレンドがすかさず火を消したので、洞窟の中はまっくらになった。
暗闇の中では、風のうなり声が、さらに恐ろしさを増すようだ。
ハメドは、このいまいましい風の声をききながら、長フォラードのことばを思い出していた。
一時間ほどすぎると、木の扉のすぐ後ろに立っていたアルドがいった。
「もうだいじょうぶだ」
「クソッ、あいつは一度通り過ぎれば次の日まで来なかったのに、どうしてもどってきたんだ?こんなこと一度もなかったんだぞ」
ハメドはこういったあと、フレイを見た。
「この子がいるからか・・。
あいつは感じてるんだ。自分の敵が来たことをな。
あの混乱の時、アルド、おまえとシラードたちは狂って外に飛び出したタッフルドじいさんを追いかけていき、おれはフレイの船を守るために仕事場に残っていただろ?そこに突然長フォラードが来たんだ。
ひどく疲れているみたいだったから、おれは薬草茶を出した。けど、長フォラードはこれには手をつけず、おれの顔をじっと見てこういった。
万が一、この国があの風に屈したとしても、それはいっときのことだ。新しい風は必ずやってくる。ただそれには時間が必要だ。
フラリアを滅ぼさないために、わしは空白の時間を用意しておく。これがあれば、おまえたちはきっと新しい風に出会えるだろうとな」
「それって、どういうことだ。おれには全然わからないぞ」
わからないのはカンタンだけじゃない、ばぁばたちも同じだ。そんなばぁばたちを見ながら、アルドがいった。
「フラリアの子は十二になると、大人と同じようにどんな風の声もきくことができる。長フォラードは、おれたちとフレイが再び出会うことを願った。けれど、そのためには十二年待つ必要があったんだ」
「そら、やっぱり三年じゃなくって十二年だったな」
カンタンがいった。
「ちがうっ、長フォラードはおれたちが生き延びるために、ここの時間の流れを変えてくれたんだ」
「十二年を三年にか?どうしてそんなことをする必要があるんだ?」
「おまえはっ・・・おまえは、ここで・・あの風におびえ、砂だらけの廃墟になり希望が見えないこの街で生きていく辛さを知らないだろ?
おれたちは、国の外に出ることもできず、ただここで生きてる、いいや生きてるなんていえない、息をしているだけだったんだ」
「四人でいられたから、おかしくならずにすんだんだ。もし、一人で残されたら、とっくに狂っていた」
アルドとハメドが、しぼりだすような声でいった。
「どうしたらそんなことができたのか私には想像もつかないけど、長フォラードという人は、あんたたちが背負うものを、少しでも軽くしようと時間の流れを変えたんだろうね。
待つ時間をもっと短くしてやりたかったのだろうけど、きっと三年が精一杯だったんだよ」
いつのまにか炉の火も消え、洞窟内にひんやりとした隙間風が吹き込んできた。
「アルド、みんな疲れているようだから、話はひとまずここで終わりにして、休もうじゃないか?」
「そうだな。夜は冷える。体にかける物が奥にあるから、それを使ってくれ」
ばぁばはざっくりと編まれた布をダフネ、いや今はもうフレイにかけてやった。
「頭をわたしの膝にのせて横になってごらん」
ばぁばのことばどおり横になったフレイの横で、サラダッテが、小さな声であのダフネの子守唄をハミングしていた。
3
この記事が気に入ったら、サポートをしてみませんか?
気軽にクリエイターの支援と、記事のオススメができます!
気に入ったらサポート

30年前に標高700mに位置しまわりを山々に囲まれた過疎の町に移住しました。植
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
