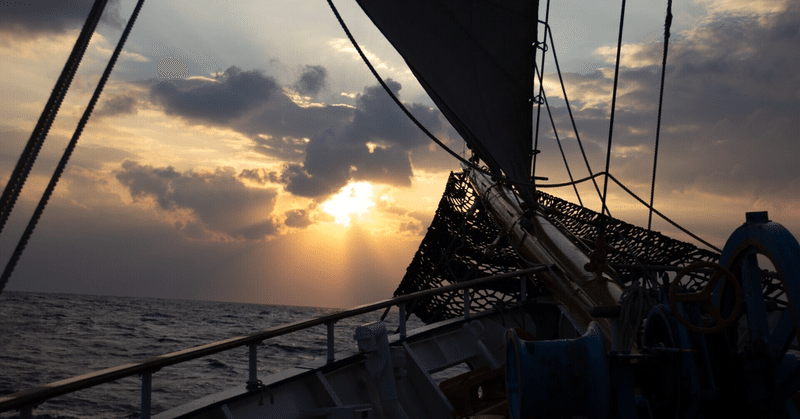
「トライアングル」その5
連載ファンタジー小説
わたしはだれ?
第十三章 廃墟の街
ばぁばが少し傾いた飛行船から飛び降りると、ずぶっと足が地面にのめりこんでしまった。
「どうなってるんだい?」
足元を見てみると、ばぁばの編み上げ靴がすっぽりと砂に埋まっていた。
「砂?」
「ああ、どこもかしこも砂だらけだ」
「この砂が、着地のショックをやわらげてくれたんだね」
飛行船は、砂が厚く積もった小高い丘に半分埋もれる形で着地していたのだ。
丘の下には、砂をかぶった灰色の街が広がっている。この街の周りには、羽がずたずたにもぎとられ、壊れたたくさんの風車が、要塞のように建っていた。
「街があるね」
「あれがなかったら、砂漠に墜落したと思うとところだったな」
ばぁばも、トンデンじいさんも、ここがどこなのかわからない。
「ねぇ、なにが見えるの?」
砂に何度も足をとられながら、サラダッテが少し遅れてやってきた。
「えっ?」
サラダッテガ、驚きの声をあげた。
「あの風車。それにあの塔・・・。まさか・・、でも、・・・。ああ、よく見えない。カンタン、ほらあそこに建っている塔の壁に模様があるでしょ?あなた、それがどんな形をしているかわかる?」
カンタンは、サラダッテが指さした塔を見てみた。
「三角形?ああそうだ、角の一角が重なり合った三つの三角形の模様だな」
「三角、トライアングル・・・やっぱり・・・。ああサスーラ、私、あの塔を覚えているわ」
「覚えてるだった?サスーラ、あんた、ここがどこかわかるのかい?」
「ええ、あそこ・・あそこに見えるのは、フラリアの街よ」
サラダッテがあえぎながらいった。
「ここがフラリア?うそよ。だってサラダッテは、フラリアは緑あふれる国だっていったじゃない。でも・・、でもここには、緑なんてどこにもない。
ねぇブルーフェアリーの花は、どこに咲いてるの?」
山も丘も街もすべてが砂におおわれていた。
芽吹きの季節が始まっているのに、木々は立ち枯れ、地面には草の一本も生えていない。ここは、まるですべてのものが死に絶えたようだった。
ばぁばも、サラダッテも、そしてトンデンじいさんさえも、この灰色の街がフラリアと知って、ことばもなく立ち尽くしていた。
そんな中で、カンタンが大きく鼻をならしながら吠えるようにいった。
「おいおい、みんなしてどうしたんだ?なに辛気臭い顔してるんだ?こんなところに突っ立っていたって何もわからないだろ?ほら、街に行くぞ」
カンタンにこういわれても、ダフネは返事もせず、じっと砂の上にしゃがみこんでいた。
「おいダフネ、おれたちは、まだなにもわかってないだろ?それなのに、もうあきらめたのか?
おまえがいってた本当の事を知りたいっていう気持ちは、そんな中途半端なものだったのか?えっ?」
カンタンにぐいっと右手を持ち上げられたダフネは、涙声でいった。
「ちがう、ちがうわ。中途半端な気持ちなんかじゃない!私、知りたい。本当のこと知りたい。でも・・・でも、こんな砂だらけの所で何がわかるの?」
「なにがわかるか、わからないかなんて、それこそ行ってみないとわかんないだろ?
いいか、サラダッテのところで十二年間眠っていたあの青い花が咲いた。あんな竜巻があっても、船が落っこちても、おれたちは無事だった。これって、あの猫の名前どおりミラクル、奇跡だろ?だったら、これからだって奇跡がおきるんじゃないのか?」
これをきいて、トンデンじいさんは、自分の膝をピシャリと思いっきりたたいた。
「こいつのいうとおりだ。こんなことでめげるなんて、おれもどうかしてたな。うん、もう大丈夫、目がさめたぞ」
「ほんとにそうね。さあさ、元気をだしてみんなで街がどうなってるか調べてみましょ」
ダフネの手をとってトンデンじいさんとサラダッテが歩き始めると、ばぁばはカンタンの肩をトンとたたき
「ありがとうよ」
といってから、サラダッテたちの後を追った。
砂におおわれた街の中は、しーんとして物音ひとつきこえてこない。まるで砂がすべての音を飲み込んでしまったかのようだ。
どの家も、どの建物も窓ガラスが割られ、ドアが開け放しになっていた。
ばぁばたちは、手分けして一軒一軒、家の中を調べてみたけれども、人の姿はもちろんのこと、ネズミ一匹さえ見つけることができなかった。
「気にいらないねえ」
ばぁばは眉をひそめ、じっとまわりをうかがっていた。
「なにがだ?サスーラ」
そうききながら、トンデンじいさんは、戸棚を開けて飛行船の修理に役に立つものはないか探していた。
「ほら、きいてごらん」
そういわれ、トンデンじいさんは手を止めて耳をすましてみた。
「何もきこえないじゃないか」
「そう、何もきこえない。だからおかしいのさ。サラダッテは、フラリアではいつも心地よい風が吹いていたっていってたんだよ」
「風?」
「そう風」
「そういえば・・・、ここは全然吹いてないな」
「フラリアは風の国だよ。ところがどうだい?今は小鳥の羽一枚飛ばせる風もない。どうしてなんだい?だれが風を止めたんだい?この国の人はどこに消えちゃったんだい?
せっかくフラリアについたというのに、これじゃあ何もわからないじゃないか。かわいそうにダフネは・・・、あの子は・・・」
ばぁばは、砂まみれのテーブルクロスを引っ張り、その上にあった皿やコップを床に叩き落した。
どんなに苦しいときでも、どんなに悲しいときでも、決して泣き顔を見せたことがないばぁばの頬に涙が流れていく。
「サスーラ」
トンデンじいさんが、小刻みに震えるばあばの肩に手をかけようとしたそのとき、サラダッテの悲鳴が聞えた。
第十四章 男たち
ばぁばとトンデンじいさんが外に出るやいなや、後ろから腕をつかまれた。
「なにをするんだい?」
手をふりほどこうともがいたばぁばの前に、ダフネとサラダッテが両手をあげて立っていた。そして二人の足元には、両手を後で縛られたカンタンがうずくまっていたのだ。
「ダフネ!」
「おっと、それ以上動くと命の保証はないぜ」
黒い頭巾で顔を覆い隠していた二人の男が、ばぁばに銃をむけている。
「おめえらカンタンになにをしやがった?」
つかまれていた手をふりほどき飛びかかろうとしたトンデンじいさんの頭に、背の低い方の男が銃口を突きつけた。
「およしっ!」
銃口を突きつけた男は、ばぁばの鋭い口調に一瞬ひるみ、自分の後ろに立つ背の高い男を見た。
すると、その男はにやりと笑っていった。
「ブレンド、銃を降ろせ。ばあさん、なかなか威勢がいいじゃないか。だがな、おれたちに逆らないほうが利口だぜ」
「おまえたち、私らをどうするつもりだい?」
銃をつきつけられても、ばぁばはひるむことなくその男をにらんでいる。
「ふふん、肝がすわったばあさんじゃないか。だがな、今きくことができるのは、おれたちの方なんだぜ」
「なにをがきたいんだい?」
「なあばあさん、おまえたちはどこから来た?」
「ここよりずっと北の国からだよ」
「北の国?」
男は、まじまじとばぁばを見た。
「どうやってだ?」
「歩いてきたとでもいおうか?」
皮肉のまじった口調でいったばぁばの胸元を、男はぐいっとつかんだ。
「ふざけるなっ!今度そんな口のききかたをしたら、仲間の頭に穴があくぜ」
「ばぁば、手が痛い」
ダフネは、ずっと上げている両手がしびれていた。
「私らは何にもしないよ。もう銃を向けるのは止めておくれ」
背の高い男が右手を上げると、二人の男は銃をおろした。どうやら背の高い男が、リーダーのようだ。
「わかっているだろうが、ちょっとでもおかしな態度をみせたら、すぐに撃つからな」
ばぁばは持っていた小さな折りたたみナイフでカンタンを縛っていた縄を切って、口から流れている血をハンカチでふいてやった。
「で、もう一度きくがどうやってここまで来た?」
リーダー格の背の高い男がきいた。
「飛行船できたんだよ」
「飛行船で?じゃあ丘の上に落ちた船は、おまえたちのだったのか?風は?風はどうしたんだ?吹いていなかったのか?」
ばぁばのことばが信じられないかのように、男の目は大きく見開かれている。
「吹いていたさ。まるで竜巻のようなやつがね」
「そうだ、この国の周りには、どんなに頑丈な飛行船でも近づけないほどの風が吹いているんだ。だからもう誰もここに入ることができないはずだ。それなのにおまえたちは来た。どうやってだ?」
男は、まるで自分自身に問いかけているかのようにいった。
「私の方こそききたいね。こんなに砂に埋もれているなんて、この国はどうなってしまったんだい?ここには、あんたたちのほかに誰もいないのかい?」
「きいてるのは、おれのほうだっていったよな?」
男がばぁばの手をねじ上げようとしたその時、バババババッと爆音をたてて、不思議な乗り物が空を飛んできた。
「なんだ、あれ?あれって飛行船だよな。帆もないのにどうやって飛べるんだ?」
細い木のボートのようなものに舵がついただけの飛ぶ船を、カンタンとトンデンじいさんは腰をうかせて見ていた。
やがてエンジンが止み、その船が地面に着地すると、ここから同じように黒い布で顔をおおった男が降りてきた。
「おい、アルド。飛行船の中で、これを見つけたぞ」
アルドと呼ばれるリーダー格の男が、ブルーフェアリーの鉢を受け取った。
「その花をかえしなさい!」
植木蜂を取り返そうとアルドに飛びかかったサラダッテの額に、アルドが銃をつきつけた。
「どうしておまえたちがこの花を持っているんだ?どこで手に入れた?」
「銃を撃ったら、話せなくなるわよ。いいの?」
サラダッテが、アルドをぐっとにらんでいると、ばぁばが二人の間にわってはいった。
「どうやら私らは、お互いききたいことがあるようだねえ、アルドさん。ここは銃なしで、仲良く手札を見せあおうじゃないか」
アルドは、ばぁば、サラダッテ、トンデンじいさん、カンタン、ダフネの顔を順々に値踏みするかのように見て回り、それから空を見上げていった。
「もうすぐあいつらがやってくる頃だ。とりあえずこいつらは連れていくからブレンドはじいさん、ハメドはこのでっかい方のばあさん、それからシラードはこの男を乗せろ。おれはこっちのばあさんと子どもをランダムに乗せる。いいか?おまえら、わかっているだろうが変なまねをするんじゃないぞ」
「早く乗れ」
黒い頭巾で顔を覆った男たちは、ランダムと呼ぶ空を飛ぶボートを発進させ、南に向かって飛び始めた。
アルドは自分の前にダフネを、そして後ろにばぁばを乗せた。
「しっかりつかまっていないと落ちるぞ」
ランダムが風をきって飛び始めると、ダフネの長い髪が風の中を泳ぐように後ろに流れ、いつもはしっかりと隠されている耳が現れた。
これは・・・?アルドは自分の目をうたがった。
「おまえ、その耳・・・」
ダフネはあわてて髪の毛をおさえ耳を隠したけれど、もう遅かった。
アルドは、ダフネの耳をしっかりと見てしまったのだ。
「その耳は・・・」
このアルドの声は、「きゃぁーーっー」というダフネの悲鳴でかき消された。
「ダフネ、どうしたんだい?」
「ばぁば、ばぁば、くる、恐ろしい声がくるわ。ああ、はやく逃げないと捕まっちゃう」
「えっ、なんだって?なにがくるんだい?」
「おまえ、あいつらの声がきこえるのか?」
「ああだめっ、もう近くまできてる」
「くそっー、おいシラード、追いつかれるぞ。もっとスピードをあげろ」
爆音をたてて猛スピードで街の上を通り過ぎ、山に向かって飛んでいた四台のランダムの前に岩山が迫ってきた。
もう目の前が岩肌だ。
「ぶつかるぞっ!」
カンタンが大声で叫んだけれど、黒頭巾の男たちはスピードを落とそうとはしない。
「あぶないっ!」
サラダッテが悲鳴をあげた。ぶつかる寸前、ランダムは左下方に急旋回し、細い岩穴に入っていった。
上からは見えなかったが、ここは岩と岩の間に隠された洞窟のようだ。
「扉を閉めろ!」
ギギギッーと鈍い音をたてて、厚い木の扉が洞窟の入り口をふさいだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
