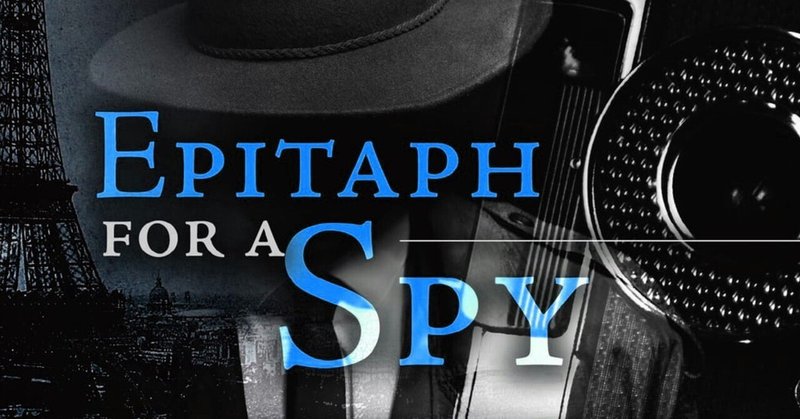
古典ミステリー初読再読終読:エリック・アンブラー『あるスパイの墓碑銘』+『シルマー家の遺産』 その2
(承前)
主人公ヴァダシーはフランス海軍情報部の手先にされ、スパイを見つけるためにホテルに戻る。こうなれば、当然、狭い場所を共有した集団のひとりひとりの人生を輪切りにする、いわゆる『グランド・ホテル』タイプの展開にならざるを得ない。




ヴァダシーがベガンから渡された容疑者リストには国籍が記されていた。支配人夫妻はともにスイス国籍、男のフランス人滞在者がふたり、若いアメリカ人兄妹、イギリスから来た退役軍人夫妻、スイス人実業家夫妻、上述の若いフランス人の連れと思われるフランス人女性、スイス人実業家夫婦、変名を使っている正体不明のドイツ人、〆て独仏伊英米瑞という六か国の容疑者たちに対し、「探偵」はハンガリー人の無国籍者という構図が提示される。
これで、ああ、『シルマー家の遺産』のエンディングはそういう意味だったのかと、膝を叩いた。どちらの長編でも、アンブラーは国家/民族を擬人化して、国際関係を人間関係として暗示していたのだ。

◎国境の「にじみ」
『あるスパイの墓碑銘』が第二次大戦直前に書かれたのに対し、『シルマー家の遺産』は戦後に書かれた。しかし、同じように、バルカン半島から黒海周辺の複雑な国際関係と、そこに生きる人々について語るいっぽうで、同時に、ドイツについても語っている。
エリック・アンブラーという作家が、日本ではそれほど注目されなかった理由はこれだと思う。いろいろな国が、複数の国と国境を接し、モザイクのように組み合わされ、何世紀ものあいだ、離合集散を繰り返してきたために、「分離」と「融合」という、本来、まったく正反対で取り違えようのないはずのふたつの異なった概念が、長い時間の中で流体化し、状況に応じてどちらにも変化する、不可解な合金のようなものになってしまった世界、とでも云おうか……。
われわれの国境はほぼ安定している。民族の違いもかなりはっきりしている。なにしろ、あいだに海があるので、アルザス・ロレーヌ地方に代表されるような、二つの国のあいだでテニス・ボールのように行ったり来たりし、民族が入り混じってしまう土地、などというものもあまり馴染みがない。

しいていうなら、沖縄と北海道が日本にはっきりと組み込まれたのは比較的近年のことだし、朝鮮半島とのあいだには長い往来の歴史があり、国境も書き換えられたことがある点をあげられるが、この「国境のにじみ」は、ヨーロッパのあくどい色の交雑に比較すれば、水墨画のように淡いものにすぎない(いや、半島の人たちは断じてそうは思わないだろうが、あくまでもヨーロッパとの比較でのこと)。
しかし、世界を見渡せば、日本のように海という明解な境界に守られている国、民族のほうが圧倒的少数派であり、地続きの他国、他民族との争いを繰り返してきた歴史を持つほうが多数派なのだ。アンブラーを読んで得るものは、われわれにとっては異質な、そういう観念の現実性、その中に生きるリアリティーである。
◎シルマー家の「遺産」
フィラデルフィアの弁護事務所に勤める若手弁護士ジョージ・ケアリーは、フィラデルフィアで亡くなったスナイダーというドイツ系婦人の巨額の遺産の相続者がヨーロッパにいるかもしれないので、その発見、あるいは、存在しないことの確認を命じられる。
物語の中では、人探しというのはつねに危険な仕事だ。フィリップ・マーロウだって、失踪者を見つけるだけの簡単な仕事を引き受けたばかりに、何度も殺されそうになったではないか。『シルマー家の遺産』の主人公も、相続人の手掛かりを追ってヨーロッパを動きまわっていくうちに、バルカン半島の不安定な政治情勢の中に入りこんでいく。

相続人はひとりもいませんでした、なんていうのでは小説は成立しないので、どこかにいるのは読みはじめた時からわかっている、話はふたつにひとつ、どちらかの筋道をたどると見た。1)難しい捜索に成功するまでの面白さを見せる、2)相続人が困難な状況に置かれていて、その障碍をいかに取り除いて相続を完遂するかを見せる、のふたつだ。
結果は読んでのお愉しみ、なんて云っていたら、これを書いている意味がなくなるので、あっさり書く。未読の方はこの部分を読むと愉しみを失うことになると警告しておく。
結果は、どちらでもなかった、というか、どちらかというと後者かな、というあたり。発見までの困難も当然あったが、眼目は、相続者の正体であり、彼が背負っているもの、ドイツ的な何か、かつて戦争を起こし、また起こしかねない「民族の血」のような何か、である。
相続者は、彼のおかれた状況が許さないので、広大なアメリカの土地の相続を放棄するが、かわりに、ケアリーが相続者を発見するのに利用した、シルマー家の祖先の手記を要求する。彼は祖先のナポレオン戦争での戦いぶり、その後の戦場離脱と負け戦での生き残り方を「相続」した。それが第二次大戦末期に、捕虜となり、はからずもドイツ軍を離脱し、国籍も失い、反政府軍の兵士となって大戦後を生きた彼にとっては、何よりも重要な「遺産」だったのだ。

第二次大戦後、戦争を生き延びた「ドイツ」軍人のなれの果てが、「アメリカ」にある遺産を放棄するという構図であり、やはり、ここでも『あるスパイの墓碑銘』と同じように、国ないしは民族が、ひとりの人間の中に描かれていると感じる。
◎もうひとりのドイツ人、もうひとりの放浪者
『あるスパイの墓碑銘』の登場人物でもっとも力を込めて描かれているのは、ハインバーガーという変名で宿泊しているシムラーなるドイツ人だ。ヴァダシーは、彼が変名を使っていること、ドイツ人であることから、このシムラーがもっとも怪しいとにらみ、接近していき、ついに正体を明らかにする。
ここからもまた未読の方の楽しみを奪うことを書く。
シムラーが語った身の上は、ヴァダシー自身と同じ、政治状況に翻弄された流転の物語だった。シムラーはかつてドイツの社会主義系新聞の主幹だったが、1933年、ヒトラーのナチスが選挙で政権を取ったとたん、彼の新聞は弾圧を受け、シムラーは逮捕されて、取り調べもないまま収容所に送られ、しばらくそこで過ごしたのち、おそらく証拠不十分だったのだろう、ドイツの市民権を放棄するという条件の下、釈放された。


しばらくパリにいて、働きもしたが、言葉の障壁があるので新聞記者としてはうまくいかず、収容所で教えられたプラハのある場所に行くと、そこはドイツ共産党の地下組織の本部で、彼はそこで新聞を発行し、ひそかにドイツ国内に運搬する活動に携わった。
しかし、ゲシュタポに目をつけられ、警察に通報されてしまったので、いったんスイスに逃げ、プラハの組織の紹介で、さらにフランスに入りこみ、このホテルの支配人に居場所を提供してもらった、というのだった。
これがアンブラーの描いた典型的な人物、政治状況に押し流され、みずからの文化から切り離されて、異国を彷徨う寄る辺なき人だ。
◎さらなる漂流者/体現者
『シルマー家の遺産』の相続人は、ちょっとコンラッド『闇の奥』のカーツに似た雰囲気があるのだが、ひょっとしたら、アンブラーはコンラッドを意識していたのではないだろうか。

もうひとり、印象的な人物が登場する。ケアリーは、英語以外にはドイツ語を多少解する程度で、女性通訳を雇う。これがまた『あるスパイの墓碑銘』のヴァダシーと似た境遇で、ユーゴスラヴィアのセルヴィア地区に生まれ、ベオグラード大学を出た。1945年、ヨーロッパ戦線の終結時に、「強制追放者」(強制労働のためにナチスに連れ去られた人)のキャンプにいるところを、イギリスの将校に秘書として雇われ、語学の才能を発揮した。ニュルンベルク裁判では米国弁護団の通訳となって、準備作業に携わり、以後、米国大使館や国際機関の仕事をしてきた。
『あるスパイの墓碑銘』のヴァダシーと、『シルマー家の遺産』のこの女性通訳は、ハンガリー人とセルヴィア人の違いはあるが、ともにユーゴスラヴィア人で、国外に出て、みずからの文化から切り離され、複数の言語を操る語学の能力に頼って、ヨーロッパを漂流している。
彼女は、最後の最後にいたって、決定的な行動をするのだが、それがひどく唐突に見え、なぜこういう結末にしたのかと首を傾げた。しかし、『あるスパイの墓碑銘』の滞在者の国籍を見ているうちに、そうか、彼女はユーゴスラヴィアそのものだったのか、だから、ああいう行動を選んだのだ、とようやく『シルマー家の遺産』の意味が理解できた。

わたしには唐突に見えた結末での彼女の違背は、たぶん、欧州人にはそれほど不可解なものではないのだろう。彼らの頭の中には、バルカン半島から黒海周辺の国々ないしは民族が繰り返してきた反目と同盟は、常識としてどっかり腰を下ろしているのだと思う。だから、アンブラーは「彼女」(英語のsheおよびherという人称代名詞は、人間ばかりでなく、車や船などの乗物にも使われるし、そして、国家にも使われる)にあの不可解な行動をとらせたのだ。
◎ディミトリオスの棺、トプカピ、SOSタイタニック、怒りの海
アンブラーは映画化作品も多いし、自身、第二次大戦中は軍の映画製作に携わったし、原作者ではなく、脚本家としての仕事もある。
つらつら考えてみると、わたしが最初に接したアンブラーの作品は、A Night to Remember (SOSタイタニック)で、小説家ではなく、脚本家アンブラーの仕事だった。小学校の時、テレビで見たのが最初だった。おおいに感銘を受けた。マシュー・フィシャーのThe Band on the Titanicは、この映画にインスピレーションを得たに違いない。わたしらにとっては、タイタニック映画と云えば、例のディカプリオのあれではなく、あくまでもアンブラー脚本の古いほうである。

そのつぎも映画で、『トプカピ』、これは脚本ではなく、原作だが、やはり小学校の終わりか中学の時に見た。どちらも最近、ヴィデオで楽しく再見した。チープではなく、しっかりした造りの映画だ。ディミトリオスの棺も二十年ぐらい前に見たが、原作のほうは半世紀近く前に読んだきりで再読していない。

こうしてあれこれ上げていくと、やはり、トプカピの原作であるThe Light of Day(真昼の翳)と、The Mask of Dimitrios(ディミトリオスの棺)ぐらいは再読しようという気になってくる。
昔、何と何を読んだか、もう明確には覚えていないのだが、ハヤカワ・ポケット・ミステリーを600冊ほど蒐集した関係で、アンブラーもかつては十冊以上持っていて、その半分ぐらいは読み、どれもまっとうな小説と感じたことは覚えている。

『あるスパイの墓碑銘』は、このところの古典ミステリー再検討の一環として読んだのだが、やはり、乱歩の云う「謎と論理の物語」という枠組みの中にすっぽり収まるタイプの小説ではなく、しいてどこかの系統に収めるなら、モーム『アシェンデン』、あるいはコンラッド『闇の奥』の流れを汲む、英国小説の本道を行くものと感じた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
