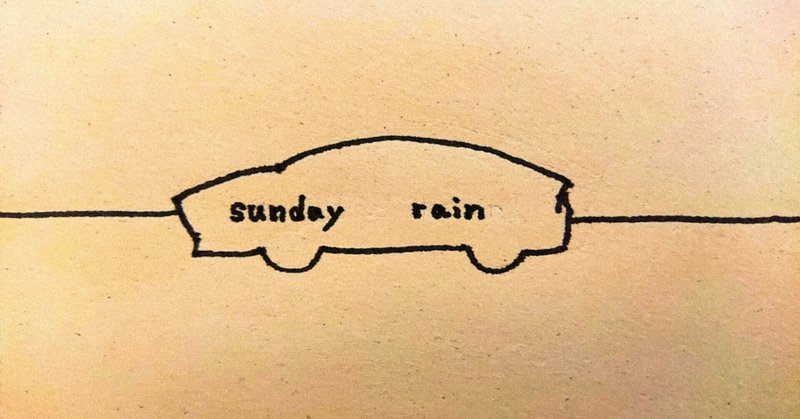
サンデイ・レイン
黄砂が降り始めたのは日曜の昼過ぎからだった。
社会人になり、初めて出た給料でローンを組んだ彼はホンダの旧車を中古で買い、何度もリペアしながら乗っていた。だが今の彼が乗っているのは真っ白なエコカーだ。
ボディに覆いかぶさった黄砂を水で流していると家の中から金切り声が聞こえる。彼がリビングに小走りで向かうと、彼の妻がテレビの前で怒鳴っていた。
彼の妻が指をさしているのはテレビ台で、リモコンがテレビ台の横に置いていないことに対して声を荒げている。
彼の妻が声を荒らげるのは今月に入ってもう三回目で、今月はまだ半分もすぎていなく、先週はテーブルの上に置いていないと怒鳴っていた。
平謝りを繰り返し、なだめすかして彼はやっと会社へ向かう。
多くの現代人は平日を嫌うが、彼は違う。妻から遠ざかれる平日を愛していると言っても過言では無い。そして、彼が同様に憩いを感じるのは、最近アプリで知り合った少女と東京近郊のカフェへ行く時間だった。こちらはまだ愛までとはいかないが、友情以上の仲になっているのは確かだ。
上野駅の近くにあるオープンカフェへ向かうと、少女は既に窓際席でメロンソーダを飲んでいた。窓の向こうは黄砂のせいでくすんでいて、少女はひどく退屈そうに外の景色を眺めている。それは窓のくすみのせいではなく、彼女が見る世界が既に退屈だからだと、彼は知っていた。
少女は不登校生だった。
それは母親が酷い更年期障害を患っていて、面倒を見なければならないからだ。
父親は開業医のため、少女は働きに出ずにすんだ。だが母親のことは全て、彼女が背負わなければならなかった。互いに背負わされるもの同士、どうしたって共通点は生まれ、傷を癒し癒される度に二人は惹かれあっていく。
「ねぇ、殺したいと思ったことない?」
2杯目のコーヒーを本日のブレンドか、それとも違うものにしようかと、迷っていた時、彼はそう問いかけられて答えが口からこぼれた。
「あるよ。何度も」
彼は、店員を呼び本日のブレンドを頼むと、少女も彼と同じものを頼んだ。それから、ふたりは、次はどこの喫茶店へ行こうかと計画を立てるのに夢中になって、次回の日程と目的地が決まると店を出た。
外を出ると目に砂が入り、彼が目を瞑る。
再び彼が瞼を開くと、少女は上を向いている。そして温い舌の上に乗せた砂利を奥歯で噛みしめていた。
「私らの人生ってこんな感じなんだろうね」
少女は視線だけを彼に向ける。エクステをして長くなった少女の睫毛がアゲハのように二度羽搏いた。
「まぁ、でも『悪くない』って思える日も確かにあるんだよ。だから、厄介なんだろう」
同意を示すように少女は笑い、彼の元へ駆け寄り手をとった。
再び少女の笑顔を見るために、彼は明日も生きてみようと思った。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
