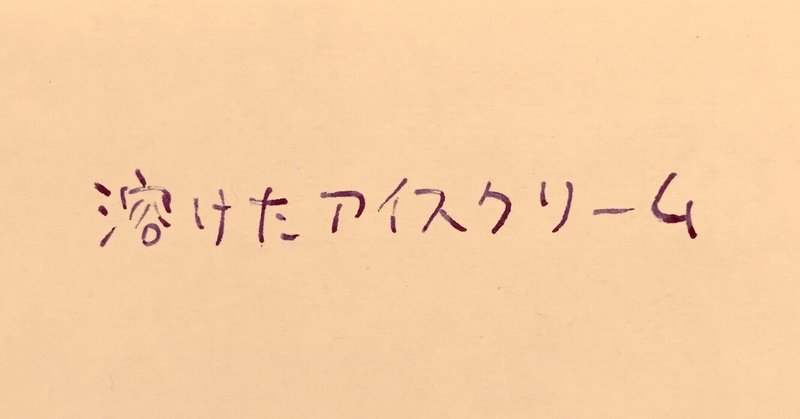
ショートストーリー劇場〜木曜日の恋人〜㊸ 『溶けたアイスクリーム』
八月のある日曜日。午後二時十六分。外気温36℃。
閉めたカーテンの隙間から差し込む光。ベッド脇の壁に葉影を映す。
エアコンの室外機が顫動し、建て付けの悪いベランダの床板がガタガタと立てる音。窓の外を子供たちが何事か叫びながら走って行く音。金槌が木材を打ち付ける音。車の音。もっと耳をすますと、通りを二つ隔てた公園から大勢の蝉たちが歌うラブソングが聞こえてくるのが分かる。それから、ベッドが軋む音。わたしが上げる声。彼の鼻息。
それがいまわたしたちを取り巻くすべての環境。
わたしの上にいる彼の胸をつたる汗が一雫、わたしの胸に落ちる。わたしはそれを、波頭を見つめる葛飾北斎のように、目に焼き付ける。顎を引いて下を見る時の顔が、昔ある人に変な顔だと言われたことを思い出して、視線だけでそれを見る。滴り落ちた汗をわたしは自分の胸をさすってなじませる。荒々しい口づけ。それは、この営みが終わりに向かうことを示している。彼がわたしにしがみついて全てが終わる。そこにはなんの音もない。どんな景色も存在しない。わたしが「生命」をもっとも実感する瞬間。「死」がすこしも入りこむ余地のない、完璧な「命」の時間。今、わたしたちと同じ状態にいる人は、世界中で何組くらいいるのだろう?
そのままわたしたちは少し眠り、シャワーを浴びて、服を着て、カレーの材料を買うためにスーパーマーケットへ向かう。日曜日にカレーを作って食べるのが、わたしたちの習慣になっている。
途中。道で人とすれ違う度にわたしは、この人はわたしたちがさっきまであんなことをしていたなんて知らないんだな、って思う。それは当たり前のことなんだけど、なんだかちょっと不思議な気もする。わたしは、さっきまでしていたあんなことを思い出して、彼の腕に自分の腕を絡める。
住宅街の袋小路になっている所。長く延びた日陰にキラークイーンが佇んでいる。
キラークイーンというのはわたしがその猫に勝手につけた名前で、本当の名前は分からない。そもそも性別も分からない。でも、わたしは雌であってほしいと思う。しかもどんな異性も振り向かせるような雌であってほしいと思う。だからそう名付けた。キラークイーンはいつもその袋小路にいて、通りかかる人が近寄っても決して逃げない。みんなからの写真撮影に気軽に応じている。彼は、キラークイーンに対し少し複雑な感情を抱いている。彼はわたしと同じくらい猫が好きなんだけど、通行人からチヤホヤされるのが大好きで、自分の魅力を自分でよく承知して袋小路に佇んでいる様子が猫らしくないから、可愛くないやつだ、なんて言っている。でも彼女が彼の足元をくるくる回ると、やれやれ参りましたって感じで彼はしゃがんで王女様の言いなりになり、背を撫でてやる。やっぱりこの子はキラークイーンなんだ、ってわたしは思う。
目的のスーパーマーケットの先にあるカフェにレモネードを飲みに行こう、とわたしは提案する。わたしたちはカフェに行き、レモネードとフライドポテトを注文する。
彼は最近読んだという物理学の話をわたしにしてくれる。
物理学の世界では「完璧な美しさは崩れる運命にある」のだという。
完璧な美しさとはなにか、とわたしは問う。
鉛筆を、尖った方を下にして立たせることは、理論上は可能である。しかし、実際に我々は先の尖った鉛筆を立たせることは出来ない。つまり、理論的に完璧で美しいものは、現実世界で存在出来ないということだ、と彼は説明する。
ならばわたしに欠点がたくさんあることをあなたは感謝しなくてはならない、とわたしは言う。彼は笑う。
それからわたしたちは、窓辺の席から通りを眺め、通行人の見た目からその人にどんな苗字が相応しいかを決める、というゲームに興じる。彼はある男の人を指して「野口」と名付ける。その人は本当にどこからどう見ても「野口」にしか見えなくて、私はレモネードを噴き出しそうになる。
飲み物で身体が涼み、カフェを出たあと、今度は彼がもっと先へ行ってみようと提案する。少し進んで坂道を登ると、見晴らしのいい公園に行き着く。こんな公園があるなんて知らなかったね、とわたしたちは口を揃える。
夕暮れが、空にオレンジとピンクと青の見事なグラデーションを描いている。美しい空。
この人は時々、こういう景色にわたしを巡り合わせてくれる。今まで素通りしてきたこういう景色がこの世にあるのだとわたしに教えてくれる。なんてことのない日曜日の午後を美しい一編の詩に変えてくれる。
わたしの心のどこかには、この人の隣にいることでしか刺激されない部分がたしかにあるようだ。ひとたび、そこが刺激されると、わたしは全身を震わせて、この世界に求愛したい気持ちになる。夏の屋外に放り出されたアイスクリームみたいに、みるみる溶けていく。
こうした愛おしい瞬間に、わたしは胸が締め付けられるような切なさも同時に感じる。
それは、この瞬間がいまにも過去になっていき、やがて思い出になってしまうから。
わたしたちの命に限りがあるかぎり、思い出の総量には上限があり、一つ素敵な思い出が出来ると、先にあるものよりも後ろにある思い出の方が多くなっていくから。
わたしは彼にそういった意味のことをなんとか言葉にして話す。
彼は空を見たままなにか考え込んでいる。
この人はいたずらに結論を急がないし、ある種の物事には必ずしも結論が伴わないことを知っている。そこが彼のいい所だ。だからわたしはなんだって彼に話してしまう。
今日のカレーは夏野菜をふんだんに使ったカレーにしよう、とわたしは急に思いついたことを口にする。彼はそれを素晴らしいアイディアだと称揚する。
坂道を下り、わたしたちはスーパーマーケットに向かう。
いくつもの日曜日。わたしはそうやって何度も生まれ変わる。
・曲 SHE IS SUMMER / Darling Darling
SKYWAVE FMで毎週木曜日23時より放送中の番組「Dream Night」内で不定期連載中の「木曜日の恋人」というコーナーで、パーソナリティの東別府夢さんが朗読してくれたおはなしです。
上記は8月24日放送回の朗読原稿です。
なにか特別大きなことがあったわけではないけれど、いつまでも心に残っている日ってありませんか?
そんな一日のような物語を作ってみたいと思って書きました。
小説というより詩を書く感覚ですね。
朗読動画も公開中です。よろしくお願いします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
