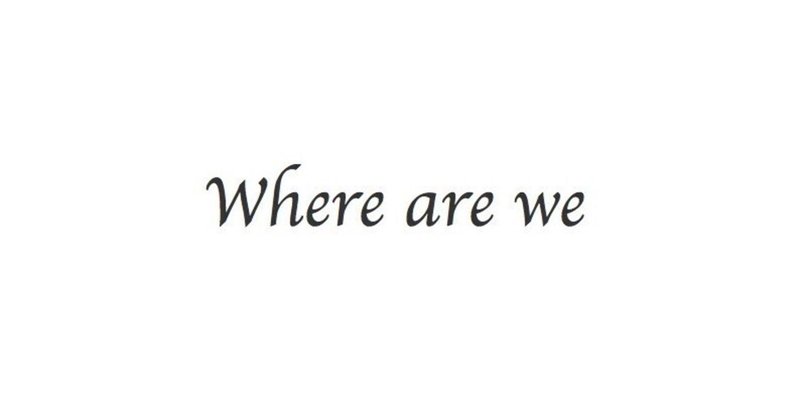
何処へも行けない 3
ほとんど水道水の味しかしないアメリカンコーヒーを飲み干す頃には、今朝から俺の身に起き続けていた様々な出来事が、どうやら、非常識なことであったと、薄っすらであるが気づき始めた。
「気でも狂ったんだ。」
カウンター席、誰にともなく呟いた。店には俺と店員しか居ない。
年齢は俺と同じくらい。二十代後半に見える正気のない男だ。俺が店に来てからずっとひたすらに本を読んでいる。注文を聞く時も、コーヒーを淹れる時も、カップを出す時も。本の表紙には「ヴェルコカンとプランクトン」と書かれている。聞いたことのない本だった。
「大学を出るまでは、自分が選ばれた人間だと思っていた。成績上位でね。学費の免除も受けていた。課題の評価もいつだって最高だ。馬鹿と間抜けしか居ない講義室や研究室で、俺の書いたレポートや論文が晒されるたびに絶頂していた。何度も色んな教授の研究室に足を運んだよ。呼ばれたからね。仕方なくさ。友達は皆大変だなって同情したけど、その瞳にはいつだって羨望があったことを俺は知っている。あれは幻なんかじゃない。」
息継ぐたびに聞こえてくるのは、本のページを捲る音と、片隅で回る、レコードの針が擦れる音。肝心の音楽は俺の耳に入らなかった。
「大学院に行くって選択肢もあったさ。だけど、行ってどうする? 興味のあることは沢山あったよ。統合失調の研究とかね。母方の家系が気狂いで。正月になると、父方の親戚連中から嫌な視線を向けられた。陰湿な奴らなんだ。だけど、そんなものを研究したところで一体何になる? 病なんてものはそう簡単に消せやしないさ。選ばれた人間の中でも階級がある。まさか自分がフロイトやレインになれるとは思っていないし、彼らだって病をこの世から消せたわけじゃない。」
そこで初めて店員が本から顔を上げた。上げたと言っても、俺を見たわけではない。何か考えるように、思い出すように、虚空を見つめた後で、立ち上がり、レコード台の元へ向かった。回転が止まっていたのだ。俺は店員が戻って来るまで話さなかった。そこで初めて自分が、今まで独り言を話していたのではなく、あの店員に向けて語っていたのだと気がついた。店員がレコードをひっくり返して針を落とす。俺は、彼が戻って来た時、何から話そうか、少しだけ考えていた。
「それで、この五年間で三回転勤した。でも、遠くへ行けたわけじゃない。どの職場にも同じ駅から辿り着ける。乗り換える必要すらなかった。何も変わらない。それに何の意味があるのか分からない。転勤に限った話じゃない。形骸化した習慣、無意味な業務連絡、杜撰な管理体制、忖度ばかりの関係性に俺の頭は壊れていった。心じゃない。頭だ。疲弊したとか、鬱になったとか、そういった話じゃないんだ。知性を奪われたんだ。脳のシワにアイロンをかけられて、均一な形に均された。俺はもう人間ではなく人形なんだ。下された指示が適切なのか意味があるのか、そんなことを考える能力すら失って久しい。」
コーヒーが空になると、店員はサーバーを持ち上げて俺のカップに注いだ。
「誰が淹れてくれと頼んだ?」
「これはサービスです。」
「ありがとう、なんて言うとでも? 君の態度は一体全体なんなんだ。失礼だとは思わないのか?」
「どうぞ怒ってください。気に入らないのなら殴ってもらっても構わない。」
「変わった人だ。」
「受け売りですよ。」
「この店は人に紹介されたんだ。小学校低学年くらいの女の子さ。友達がやっている店だと言っていた。今となっては、俺はあの子を白昼夢だったんじゃないかって思っている。あの子は実在するのか?」
「どうでしょう。私に友達は居ないので、何とも。」
「俺もそうさ。友達と呼べるような奴はほとんどいない。一人だけ居たんだが、疎遠になってしまった。夢見がちな奴でね。小説家になると言って大学を辞めたんだ。青臭い男でね。酔うといっつもビートジェネレーションの話をした。俺は日本にビートジェネレーションを起こしたいんだって。具体的には? って俺が突っ込むと、あいつはいつも泣き出した。ハリボテなのさ。知りたての言葉で自分を飾っていただけだ。まあ、実際に行動を起こしたことは評価するけどね。だけど、結果は散々なものだろう。疎遠になってもう七年八年経つけれど、あいつの名前なんてどこでも聞こえない。」
「好きだったんですか?」
「嫌いだよ。負け組の人生だ。でも、最近ふっと思い出すんだ。今何をしているんだろうって。」
「羨ましいんですね。」
「どうなんだろうな。安心したいだけかもしれない。ああ、こいつよりはまだマシだって。嫌な人間になってしまったよ。」
入り口でベルが鳴った。けれど、振り返っても、そこには誰も居やしない。
「今、扉開かなかった?」
「開いてませんよ。」
「病気かな?」
「そう見えます。」
「サンドイッチを作って欲しい。」
「かしこまりました。」
店員は本を片手にサンドイッチを作り始める。器用なもんだ。やがてサンドイッチが完成して、
「これは何サンド?」
と尋ねると、
「BLTサンドです。」
と店員。
「トマト入れるの忘れてない?」
「間違えました。BLサンドです。」
店員は再び読書に戻る。俺はBLサンドに齧りついたが、どうやら、マヨネーズも忘れているらしい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
