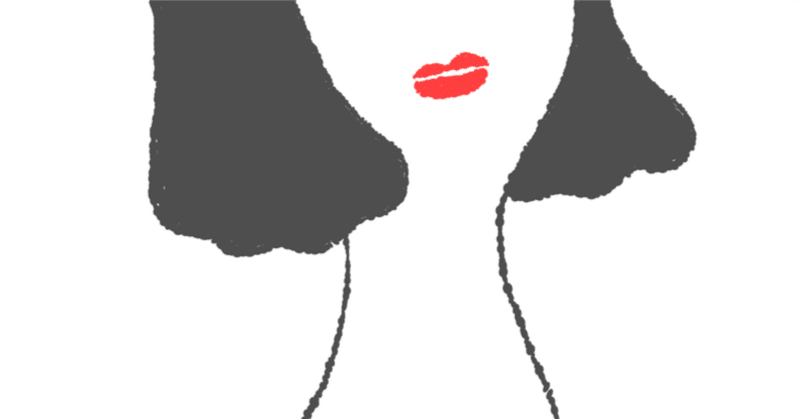
中年ラブ・ストーリー(後編)
「で、キスしちゃったんだ」
三原さんにメッセージを送ると、即日会うことが決まった。
「だからね、三原さん。そこばかり何回確かめるんですか」
三原さんとは仕事終わりに、職場の近くのバルで待ち合わせをした。
三原さんは上機嫌で、私と克也さんがキスしたと何度も言うけれど、あれは事故だ。大事故。現に私の前歯はいまだに痛くて仕方ない。
「ガチって音がしたんですよ。ほんとに痛かったの」
「だけどそれ、周りから見たらキスしてたように見えたでしょう」
「見ようによっては、そうかもしれないですね。かなり滑稽な動きしてましたけど」
三原さんは よっぽど二人の前歯がぶつかりあったシーンが気に入ったのか、何度も手を叩いて笑っている。
「ねぇ、もっと甘い話を期待してたんだけど」
「いや、私だってね。まさか5年ぶりのチューが事故の産物だとは思いませんでしたよ」
突如覆いかぶさって来た克也さんが私を抱きしめたところまでは良かった。お酒とおでんで温まった心と体が油断していて、すんなり受け入れてしまったのだ。そのあと、まさかキスしてこようなどと思わず、驚いて顔を避けようとしたら。思わぬ顔面の事故というのはあるものなのだ。
「ねえ、まだ次の約束はしてないんでしょう?」
「次かぁ、なかったですね。歯がぶつかって直ぐに逃げましたから、私」
あらヤダ、と言ってまた三原さんは笑っている。私は、克也さんにもう会わないのかなと思うと、なんだか残念な気がした。
「あっちゃん、なんだか寂しそうよ」
「ええ。意外と楽しんでいたのかもしれないですね、私も」
「いいじゃない、それなら」
「いい思い出ってことで、いいですかね?」
「違う違う」
三原さんが咳き込んだ。
「寂しく思うんだったら、自分から今度は誘ったらいいじゃない、ってことよ」
三原さんと別れて歩きながら、最後に三原さんからかけられた言葉を思い出していた。
「アラフィフの男はかっこつけてた歴史を持ってるひとが多いから、きっと無様な姿を晒して落ち込んでるわよ。あっちゃんの包容力で癒しておやりなさい」
そんなものかしら。同年代の男のことだけど、どうもよくわからない。
私は考えた末、克也さんにメッセージを送ってみた。「こんばんは」と挨拶のみ。
どう返ってくるのだろう。送った途端にそわそわしている自分がいる。
しばらくして、スマートフォンの震えを感じ、メッセージを確認した。
克也さんからも「こんばんは」とだけ入っている。
「どういうつもり?」
少しイラッとしたが、克也さんにとってはこれが通常で、試すようなことをしたのは私の方だと気がついた。
「素直になろう。人間、いくつになっても素直が一番なんだから」
自分に言い聞かせて、変な駆け引きはやめにした。
「昨日は大丈夫でしたか?だいぶ酔ってらしたみたいですけど」
そうメッセージを送ると、克也さんから電話がかかってきた。
「克也さん?」
「もしもし、あつこさん」
克也さんの声が電話越しに聞こえる。私は何故かそれだけで安心した。
「昨日は、どうもすみません。調子に乗って飲みすぎてしまいました。本当にお恥ずかしい」
「いえいえ、まったく。むしろそのあとの、その、歯……私は歯の方が心配で」
「歯?歯がどうかしました?すみません、本当に記憶が定かでなく……」
「ええっ本当に?」
「本当に」
克也さんが嘘を言っているようには思えなかった。私自身、よくお酒で記憶を無くすタイプだったから、十分に有り得ることだと理解出来る。
「そうなのね。覚えてないのね。私たち、ガッチリぶつかったんですよ。その、歯と歯が」
「は?」
はぁ?と言ったのか、歯?と聞かれたのかわからないけど、もうこの話はよそう。
「まあ、とりあえず。なんともないなら良かったわ。私ももう、大丈夫だし」
「覚えていないとはいえ、何かしてしまったようで申し訳ない。しっかり埋め合わせをさせてください」
「埋め合わせなんて、いいのよ。気にしないで。お酒の失態なんて、私も山ほどしてきたの。本当に数々……」
「あつこさん、クリスマスデートに誘っていいですか?」
克也さんがはっきりした口調で声を張った。
「クリスマス、いいの?私で。私は空いてるけど……」
「クリスマスデートなんて言って大袈裟にしてますけど、いいお店を知っているわけでもないし、そもそももう予約なんて取れないかもしれない。それでも良かったら」
「克也さん」
私は克也さんが気負っているものがわかった気がした。
「克也さん、もしかして。大人だからいい所に、大人だから特別なプランをとか、気負ってない?」
「それはまあ、一応……」
「大人なので?」私は笑った。
克也さんは私と似ている。色々、無駄な気を遣って、大人になってからする恋愛のハードルをあげていたのだ。
10代20代で行くようなところはもとより、30代で経験してしまった場所には新鮮な気持ちで行けないから、どこか“穴場”を探したり、大人しか知りえないような“特別”を探すことに疲れと怯えを感じている。少なくとも私はそうだ。
年齢を重ねた分だけ何か知っていなければ、深みを増していなければいけないような。
大人になった多くの人は、ある地点から大して自分が変わっていないことを実感しているはずなのに、何故か恋愛においては期待する部分があったり、期待されているのではと勝手に思っていたり。
実際は、ただ一緒にいて、近くの居酒屋でもファミレスでも楽しく過ごせればそれでいいのに。
「私ね、日高屋が大好きなんですよ。美味しいじゃない。日によって、店によって出される品のクオリティが変わったり。ファミレスみたいに電気が明るくて雰囲気はないけど、値段気にせずじゃんじゃん頼めるし。ハイボールなんてたまにめちゃくちゃ濃い時があるの。そういう時、私は卓上に置かれている水のボトルで勝手に割って飲むのね。そういうの、すごく楽しい」
「ああ、なんかわかります」
「私、日常を楽しめるタイプだから、クリスマスだからって何も気負わず会ってくれたら嬉しい」
「嬉しいんですか?僕とデートして」
克也さんが何を期待して聞いているのかわからなかったけれど、私は素直に答えた。
「ええ、とっても嬉しい。誘われなかったらすごく落ち込むところだった」
「それを聞いて安心しました」
電話越しでも克也さんの笑顔が見える気がした。
「クリスマスって、もう来週なのね」
「また連絡します。近くなったら」
私たちはまた来週会うことになった。
普通のデートでも、とんでもデートでもなんでも。一緒に過ごす人がいることがとても嬉しい。
クリスマスデートって、どんなだったかしら。気負わずに、と言った私は微かに緊張してきていた。
それはとても幸せな緊張だった。

クリスマス当日。私たちは克也さんの住む駅の商店街にいた。
「こんなに栄えているのね、ここの商店街。今のご時世、なかなかないじゃない?」
「でしょう。本当は大きな街に行く必要もなく、なんでも揃ってしまうからこの商店街で呑むことが多いんだよ」
私たちは、商店街の中で一番クリスマスの雰囲気を感じさせない中華屋に入った。店の中では小さなテレビにバラエティ番組を流している。
「いらっしゃいませ」
バラエティの企画に笑ったついでの笑顔で席に案内してくれる優しそうなおばちゃんは、きっと今日がクリスマスだなんて夢にも思わないのだろう。
私たちは4人がけのテーブルいっぱいに好きなものを頼んだ。大きな餃子。安い紹興酒。ザーサイ、麻婆豆腐、チンジャオロース。どれもこれも日高屋を優に超える美味しさだった。
「克也さん、ビール好きだったのね」
私たちは中ジョッキで何度目かの乾杯をした。
「いやあ、今日は軽いお酒にしてるんだよ」克也さんは照れくさそうに笑う。そんな克也さんが、ビールジョッキを置いて、ガサガサと紙袋から何かを取り出した。
「あつこさん、これ」
「あら、なあに?」
クリスマスプレゼント?私、何も用意していないし、用意しない約束だったのに。
簡単な包みを開けると、そこには不格好なシュトーレンがあった。
「え、どうしたの?」
私が驚いて尋ねると克也さんは恥ずかしそうに言った。
「あつこさん。例のパン教室で、自己紹介代わりに好きなパンを言う時、シュトーレンって言って、みんなに突っ込まれてたから。帰ってから調べてみたら、クリスマスまでに食べるものだったんだね」
「そうそう、よく覚えてたわね。私、毎年食べてるのよ。もちろん今年も」
「僕はね、あの日、初めからあつこさんに一目惚れだったんだよ。だから、クリスマスは一緒に過ごしたいし、タイミングはおかしいけど、シュトーレンもプレゼントしたかった」
私は言葉が出なかった。克也さんから渡された手のひらサイズの無骨なシュトーレンに目を落とす。
「まさかこれ……」
「そう。あのパン教室の通常会員になって作った、僕の手作り」
私は克也さんの照れた笑顔を見て涙が滲んだ。
「あなたって最高ね。克也さん」
私は少し身を乗り出して、テーブルに置かれた克也さんの手をとった。とてもあたたかい手だった。克也さんもまた、私の手に自らの手を重ねた。そして言った。
「不思議だけど、まったく恥ずかしくないね。大人になってからの恋ってこんなにいいものなんだな」
そう言って私の目を見つめた。
「愛してます。あつこさん」
笑顔の克也さんに戸惑うことなく、私は満面の笑みで克也さんを見つめ返す。
見つめ合う私たちの後ろで、テレビの中の知らない芸人が「そんなわけないやろ~」と言ったのが聞こえた。
[完]
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
