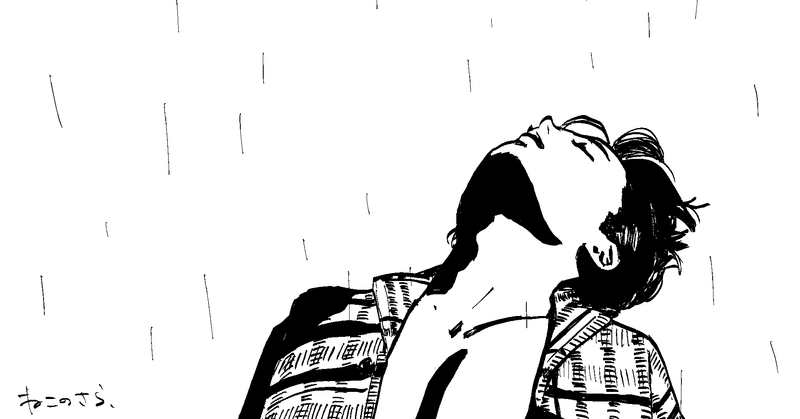
この一日を生き抜け―映画『シングルマン』
1962年、キューバ危機下のアメリカは核攻撃まで秒読み段階とも言われるきわめて緊迫した情勢に置かれ、不安に覆われていた。トム・フォードの初監督作品となった映画『シングルマン』は、その年のロサンゼルスを舞台に、ある男の一日を描いている。
大学教授であるジョージは、8カ月前に最愛の恋人ジムを交通事故で失って以来、喪失感から立ち直れずにいた。たった一人の理解者であり、自分の半身だったジム。彼なしでは生きていく意味も見いだせない。
そんな絶望を知りもせず、世間では政治家が戦争を煽り、核シェルターを買ったと言う同僚は自分と自分の家族だけ生きのびられればいいと言う。近所の子どもは残酷でやかましい。ジョージの孤独と虚無はますます深まっていく。
ジョージはこの日、自分の人生を終わらせるつもりだった。ジムのいない人生にもう未練などない。そう決めて、銃を鞄に入れて職場に出かけた。
大学では、教壇に立って最後の講義をした。その内容は、きっと普段の彼ならば避けるような、ギリギリの話題に迫るものだった。
「少数派の話をしよう。特に”隠れた少数派”。少数派全般は多彩だ。金髪とかソバカスとか。だが問題は、世間から脅威と見なされるタイプだ。たとえ脅威が妄想でも、そこに恐怖が生じる。実体が見えないと、恐怖は増す。それで迫害されるんだ。だから理由はある。恐怖だ。少数派も人間なのに……」
少数派、マイノリティとは、ゲイであることを隠しているジョージ自身のことだ。ジョージは毎朝、「鏡に向かって、世間が期待する"ジョージ”になる」という儀式をしていた。彼はそうして多数派に擬態するのだ。ありのままの自分、ゲイの自分では迫害されてしまうから。
ジムが亡くなったとき、ジョージはパートナーでありながら、葬儀に出席することを断られた。60年代、いまだ同性愛への偏見は強く、ただ好きな人と愛し合っているだけなのに、同性愛者であるというだけで忌避され、差別されなければならないことを、彼はよく知っていた。
ジョージは最愛の人を失くしたことが悲しいだけではない。
マイノリティとして生きる苦しみを、誰にも理解されないまま生きていくことにも疲れていたのだ。
彼は世界のすべてに失望していた。
ちなみに原作小説では、彼のマイノリティに対する考え方が、さらに深く語られているらしい。
「たとえば、そばかすのある人間は、そばかすのない人間にとってマイノリティではない。今、ここで議論しているような意味でのマイノリティではないんだ。では、なぜ、彼らはマイノリティではないのか。マイノリティは、それがマジョリティに対して、現実であれ想像上であれ、ある種の脅威になるときだけ、マイノリティとして意識される。そして、どんな脅威もまったくの想像上のものということはない。それは違う、という人がここにいたら、自問してみるといい――もしもこの特定のマイノリティが、一夜にしてマジョリティになったとしたら、彼らはいったい何をするだろうか、と」
(新藤純子訳)
BLMやフェミニズムへのヘイトを思い出してみれば、恐怖心が人を迫害に駆り立てるということはよくわかる。迫害に「理由がある」という意味も。
けれど、たとえ理由があるからと言って迫害は正当化されない。マジョリティもマイノリティも同じ人間であることを忘れてはいけない。
本当の敵は「自分たちと異なる肌の色や、信念を持つ人間」ではなく、違いを恐れるあまり、過剰に防衛しようとする衝動なのだ。
恐怖こそ真の敵だ。恐怖は世界を支配する。
社会を操作する便利な道具だ……。語りかけても通じない恐怖。
ジョージはそう熱弁して、講義を終えた。
「語りかけても通じない恐怖」とは、当時のアメリカを支配していたものでもあっただろう。そして、私たちを常に支配しているものでもある。脅威になるもの、実体の見えないものへの恐怖は、人を迫害に駆り立てる。それは、コロナ禍でアジア人にヘイトが向けられたことや、今の情勢下でロシア国籍の一般市民が誹謗中傷を受けている事態にも言えるんじゃないだろうか。
恐怖こそ真の敵だ。この言葉は今だからこそ重い。
映画に話を戻すと、授業が終わった後で、ジョージの元には一人の生徒が「圧巻でした」と駆け寄ってくる。彼はジョージともっと話したいと望み、誘いを断られると、近所のバーまでジョージを追いかけてきた。
そのバーで、ジョージと彼は会話を交わす。核の脅威で未来なんて信じられない、というその生徒は、ジョージに孤独を打ち明ける。
「実際、ほとんどいつも、僕は孤独です……。独りだと感じます。つまり人間は、誕生も死ぬ時も一人。生きている間は己の肉体に閉じ込められてる。不安でたまらなくなる。偏った知覚を通してしか、外部を経験できない。相手の真の姿は、違ってる可能性も……」
社会不安によって一歩先も見えなくなった未来は、ナイーブな青年に実存的不安をも投げかけてくるのだろうか。この会話をきっかけに、彼はジョージと打ち解け、二人は夜の海を裸で泳ぐ。
そして海から上がった二人は、ふたたび酒を飲みながら語り合う。なぜ後をつけてきたのか尋ねたジョージに、青年は答えた。
「考え方が人とズレているのがつらかったけれど、先生ならわかってくれると思った」と。
それから、「先生が心配で」とも。
彼は、ジョージが死を決意していることにも気づいていたのだ。
他に理解者もなく、孤独を感じていた者同士だからこそ、わかり合えることがある。救えることもある。会話の後、束の間眠ったジョージは、青年が眠っている姿を見て、死ぬことをやめた。遺書を燃やし、生きることを決意した。
しかしその瞬間、ジョージは心臓発作で倒れ、そのまま命を落とす。あれだけ死のうと思っていてもなかなか銃の引き金を引けなかったのに、皮肉なことに、生きようと思ったとたんにあっさりと死が訪れたのだ。
映画はそこで終わる。見る人によっては、後味が悪いとも言える幕引きだ。
それでも、ジョージにとってこの日は悪い一日ではなかったはずだと思う。少なくとも、目覚めた後に微笑んだジョージの表情は、これまでになく穏やかだった。
ジムを失ってからついぞ感じたことのない、人生の充実感。青年との関わりによって、ジョージはそれを取り戻すことができたのだ。
世界がいつ終わるかわからないと考えると、あらゆることが無意味に思えて、人生の行き先を見失ってしまいそうになることがある。けれど、だからこそ、一日を人生最後の日のように生きること、生き抜くことだけが大事なのだということを、この映画は教えてくれる。
世界の危機とは無関係に、人はそもそもいつ死んだっておかしくない存在なのだ。
過去や未来ではなく、「今」を生きること。それがこの映画のテーマだと、トム・フォードは言う。きっと今この時に必要なのも、そういう精神なのだと思う。
どんなに世界に、人生に失望したとしても、私たちはこの一日を生き抜かなくてはならない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

