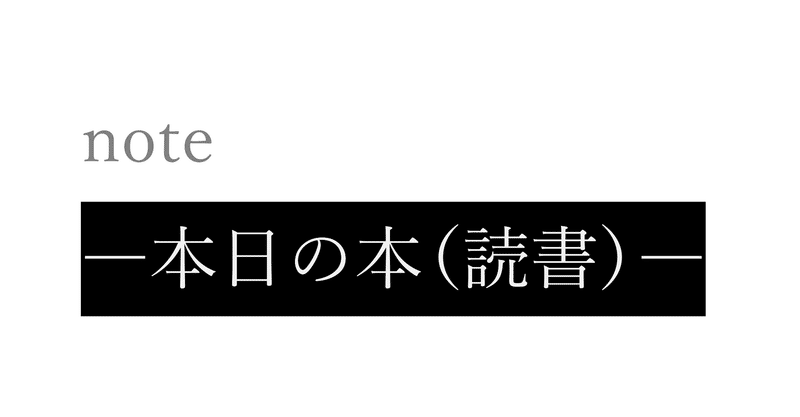
アンリ・バルビュス『地獄』(田辺貞之助、岩波文庫)の感想
戦争小説『砲火』でフランスで圧倒的に支持された小説家で、「モンド誌」を創刊したジャーナリストとしても知られるアンリ・バルビュス。彼の2作目の小説で一躍文壇にその名を知らしめた作品が『地獄』である。このゴスに直球な題名を岩波文庫チェックで眼をひいた人は多いにちがいない。
就職のために上京し、知り合いのだれもいない都会の安ホテルに暮らしはじめたばかりの青年。孤独で鋭敏な感覚でとなりの部屋から音がもれていることに気づく。その出所を探ると、なんと隣室の仕切り壁に穴があいている。このようにして、彼の「地獄ののぞき」生活が開始されるのである。
こう書くと、のぞきの向こう側に地獄のような光景が展開する(『幽遊白書』の仙水がみた「黒の章」のビデオみたいな)とか、主人公がゲスに頽落に落ちていく物語を想像しそうになるが、それはちがう。ここで描かれる「地獄」はもっと観念的でそれだけ切ない性質のものであるのだ。
またしても、ぼくは快楽に心をうばわれた男の顔を見た。ああ! ぼくははっきり見た。彼が孤獨であることを。(p126)
なぜ神は、このすさまじい、しかもお定りの破局に干渉しないのだ。熱愛していたものが、急に、または徐々に、唾棄すべきものとなる、この怖ろしい不思議を、なにか別の不思議によってさえぎらないのだ。なぜ神は人間のあらゆる夢がいつとはなく悲歎にかわるのを救わないのだ。(p86)
恋の絶頂にある人間が次にはそうでないこと。互いに恋を生きるものが結局は孤独なこと。つまり有頂天な希望をいだき現実はそうでない人間のみじめさを指し「地獄」としている。快楽に没頭する人間をみれば快楽が「痰壺のように人間の上に落ちてくる悲哀」(同上)すらただようと言うのだ。
では、この「地獄」から逃れる方法はあるか。それは、不滅の真理、色あせない希望、永遠に変わらぬ心が存在することを意味するだろう。ない。そうこの作品はいう。人間の心は弱く、いつか身体も老いと病にむしばまれ、地球という天体でさえ宇宙のなかで極小の存在である。それが事実なのだ。
しかし、この作品のラストは虚無的でない。この作品の話者がいい意味で普通の人間であることに由来していると思う。「ぼくもご多聞にもれない男だ。欲望もある。人にかくした痴情もある。」(p91)という普通の青年が「地獄」を生きる人間、個室で生をいとなむ人間たちに共感を寄せていく。
ぼくはこんなに輝くばかり美しい女を見たことがない。こんな女を夢みたことすら一度もない。彼女の顔は、最初の日に、ととのった線と明るい輝きとで、ぼくを打った。それに、彼女は背が高く――ぼくよりもずっと高く――肥り肉でありながらすっきりした女のように見えた。(p233)
死病で臨終の床にある老人と形式上の婚姻をかわした女。彼女が夫であるがゆえに「あたしをごらんになる権利」(p220)があると言い、一糸まとわぬ姿になる場面だ。こういう心身のうつくしさ、あるいは、その直後老人が「こうなっては、もう死ぬに死ねないぞ!」(p235)と呟く心に寄りそう。
虚無になれば無に等しい生の短さのなかで、必死になにかをその手につかもうとする人間のいとなみ。とくに、引用の彼女の終局でのふるまいが示唆するのだが、とても崇高とはいえないのにもかかわらず人間の生命力の輝きが目を開かせるものとなる。『地獄』はこんなひねりのきいた人間賛歌だ。
人類とは死の恐怖のうえに立つ新しいものへの欲求だ。そのとおりだ。それをぼくは自分で見たのだ。本能的な動作や拘束されない叫びは、信號のように、いつも同じ方向へ向けられている。(p277)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
