
メディアの威力と、対峙する我々の態度
田端大学の課題図書である『戦争広告代理店』は、多くの方が絶賛する通り、「PR」の持つ威力の凄まじさ、移ろいやすい「世論」への恐怖を、まざまざと感じさせてくれる作品であった。

今回は、そんな作品の読後に抱いた「大きな違和感」をメインに、論を進めていきたいと思う。
【あらすじ】
「情報を制する国が勝つ」とはどういうことか―。
世界中に衝撃を与え、セルビア非難に向かわせた「民族浄化」報道は、実はアメリカの凄腕PRマンの情報操作によるものだった。
国際世論をつくり、誘導する情報戦の実態を圧倒的迫力で描き、講談社ノンフィクション賞・新潮ドキュメント賞をW受賞した傑作。
【プロフェッショナルとしてのPR戦略】
わたしの抱いた「大きな違和感」とは、ルーダー・フィン社(およびジム・ハーフ)のPR戦略は、果たして“道徳的”に正しい戦略だったのだろうか、ということだ。
たしかに、彼らのPR戦略は「プロフェッショナル」として完璧だったと言っていいだろう。
手紙の文面や記者たちへの配慮など、随所に見られる他者への想像力をはじめ、「民族浄化(ethnic cleansing)」、「多民族国家」といった印象的な言葉の適切なタイミングでの使用、世論を動かす上でキーパーソンとなる人物とのコネクションなど、プロとして学ぶべき点は、枚挙にいとまがない。
国益に乏しく、アメリカ国民にとっても興味・関心の薄いボスニア紛争への介入へと、巧みに世論を誘導していった一連の戦略には、恐怖すら覚えてしまう。
しかし、それでもなお、わたしの中にある「大きな違和感」は拭えないままであった。
なぜか。
その理由を説明していこう。
【「損得」と「道徳」の狭間で揺れる「善と悪」】
最大の理由は、「戦争」という、本来どちらにも非があるはずの出来事に「善悪」のラベリングを施し、世界中へと発信したことだ。
彼らのPRには、決して「無から有を生み出すような」情報は無かった。
「強制収容所」という、あわやフェイクニュース確定の言葉も登場するが、最初に使用したのは、あくまで現地の記者であり、彼らは単にそれを世界中に“広めただけ”なのだ。

しかし、そうは言っても
「モスレム人=善良な被害者」
「セルビア人=残忍な加害者」
というラベリングは、あまりに偏向的ではないだろうか。
一方的な侵略などを除けば、戦争において「100-0」の過失など、無いに等しい。
ましてボスニア紛争は、民族同士のトラブルが発端となっているため、比率の差こそあれ、間違いなく双方に非があるはずだ。
現に、セルビア人側にも多数の犠牲者が発生している。
(兵士:20,649人、市民:3,555人)

最終的に、加害者のレッテルを貼られたユーゴスラビア連邦は、国連からの脱退を余儀なくされた。
偏向的な報道を受けて傾いた、国際世論の結果である。
この結果が、即座にバルカン半島の平和へとつながったのであれば、ルーダー・フィン社の戦略に対する見方は、変わっていたかもしれない。
が、紛争はその後、和平合意が成立するまでの約3年間、コソボ紛争まで含めれば、約7年間続いていたのだ。
もちろん、その間にも犠牲者は増え続けていた。
彼らがプロフェッショナルであることに、疑いを挟む余地は一切ない。
「PRなんて虚業だ」などという、的外れな批判をするつもりも毛頭ない。
だが、「社会全体の幸福」という観点から言えば、彼らの持つ強大な力を「善悪二元論」のような単純な図式に帰結させてほしくはなかった。
というのが、わたしの率直な意見である。
【メディアの威力と、対峙する我々の態度】
ここまで、偉そうにルーダー・フィン社の戦略について語ってきたが、そもそも彼らの戦略を批判する資格が自分にあるとは思っていない。
過去の出来事を偉そうに批評することなど、誰にでもできるのだ。
ただ、メディアが発信する情報を鵜呑みにすれば良いのかと言えば、それも正しい態度ではないだろう。
わたしたち一人一人が「本質はなにか」を問い続けていかなければ、正確な情報は、さらに見えにくくなってしまうのだから。
この問題については、W・リップマンが著書『世論』の中で的確に述べているため、やや長文となるが引用する。
報道界の問題が混乱しているのは、その批判者も擁護者もともに、新聞が(略)、民主主義理論の中で予見されなかったものすべての埋め合わせをすることを期待しているからだ。
そして読者も、自身は費用も面倒も負担しないでこの奇跡がなしとげられることを期待している。
民主主義者たちは、新聞こそ自分たちの傷を治療する万能薬だと考えている。
それにもかかわらずニュースの性格やジャーナリズムの経済基盤を分析すると、新聞は世論を組織する手段としては不完全だということを否応なくさらけ出し、多かれ少なかれその事実を強調すらしていることがわかるように思われる。
私は、もし世論が健全に機能すべきだとするなら、世論によって新聞は作られねばならない、と結論する。
今日のように新聞によって組織されるべきではない。
そう。
新聞(=メディア)が世論によって作られるべきであって、世論が新聞によって作られるべきではないのだ。
たしかに我々一般人にとっては、異国の地で起きている紛争など、興味も関心もなく、調べることすら面倒な作業だろう。
ただ、それを言い訳に、正しい情報を得ようとする“責務”から逃れるのは間違っている。
また、最近は「図解」や「動画」など“分かりやすいコンテンツ”の人気が高まっている。
面倒な作業を短縮できるという意味では、大いに納得がいく。
けれども、“分かりやすさ”は諸刃の剣だ。
時にそれは、情報の裏側にある本質を見誤らせる。
ボスニア紛争を例にとれば、「セルビア人=悪玉」という図式は非常に分かりやすく心地のいいものだが、その裏にある歴史や、複雑な民族間の対立などは、見えにくくなってしまった。
今わたしたちがすべきは、漫然と情報を受け入れたり、「テレビや新聞はオワコン」といった、借り物の言葉でお茶を濁したりすることではない。
真にすべきは、メディアを含む“分かりやすいコンテンツ”に流されることなく、「一人一人の主体的な考えこそが世論を作り出していくんだ」という強い意志を持って、情報に接することではないだろうか。
【あとがき】
今回のnoteは、『戦争広告代理店』を読み終えた直後のオンライン質問会が、きっかけとなっている。

田端さんは、この質問に対して「一人一人が、自分の胸に手を当てて考えるしかない」と回答して下さった。
まさに、その通りだと思う。
今回わたしは、ルーダー・フィン社のPR戦略に対して、上記のような考えに至ったわけであるが、必ずしもこれが完璧な正解だとは思っていない。
むしろ、歴史についてもメディアについても知らないことの方が多いため、より詳しい方々に論破してほしいとさえ思っている。
この世界には、簡単に白黒付けられる問題など圧倒的に少ない。
だが、だからこそ前向きな議論が必要なのだ。
メディアに流されることなく、主体的な意見を持つ努力を続けていこう。
このnoteが、1つのきっかけになれば幸いである。
悠仁(@kjm_you)
【参考書籍】
①『世論』
(W・リップマン / 岩波文庫)

②『MEDIA MAKERS ―社会が動く「影響力」の正体―』
(田端信太郎 / 宣伝会議)

③『ユーゴスラヴィア現代史』
(柴宜弘 / 岩波新書)

④『政府は必ず嘘をつく』(堤未果 / 角川新書)

⑤『戦争にチャンスを与えよ』
(エドワード・ルトワック / 文春新書)
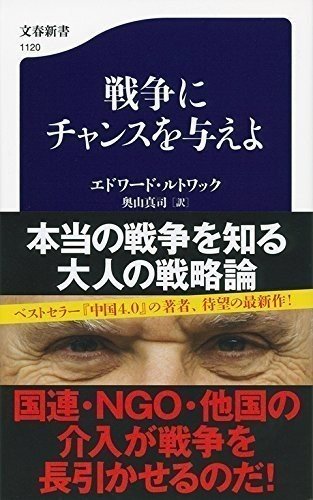
ご覧頂き、ありがとうございます! みなさまから頂いた大切なサポートは、ぼくが責任を持って「カッコよく」使わせて頂きます!
