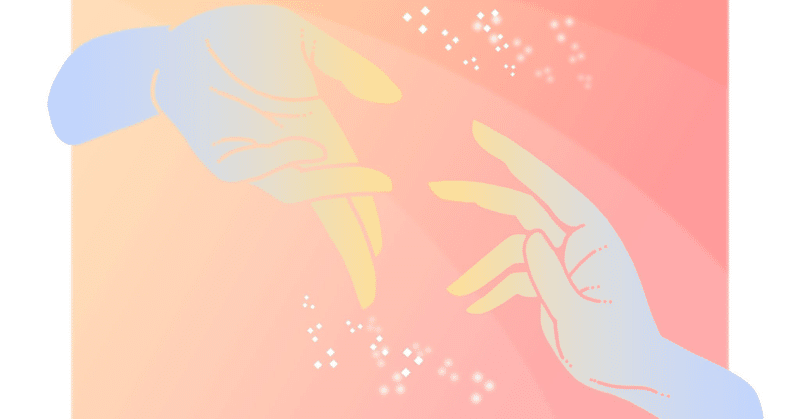
『独り舞』 李琴峰
最初から最後まで、主人公の心がすぐそこに手で触れられそうに近くに感じられた。
ひたむきな主人公を全力で応援したくなる。冷淡な運命に打ちひしがれ、背中を丸める彼女に、大丈夫と励ましたい、上を向けば光があると伝えたい、声が届かないことがもどかしい。そんな気持ちで読み進めた。
*****
台湾の田舎町で生まれた迎梅(インメー)は、子供の頃に、自分の恋の対象が同性であることに気づく。自分が人と違うことを朧げに悟っていた迎梅は、周りと交わらない孤独な少女に成長した。
そして、淡い憧れを抱いていた少女の事故死をきっかけに、独特の死生観を抱くようになる。
生きているうちはできる限り上手く生きようとするけれど、生の辛さが我慢できる範疇を超えてしまったら、彼女は何の躊躇もなく死を選ぶだろう。
周囲に対して心を閉ざした彼女だが、高校時代に、同級生とのはじめての恋愛が奇跡のように訪れた。同じ大学に進み、一緒に講義に出てキャンパスで共に過ごそうと語り合う二人。しかし幸せも束の間、大学進学を目前にしたある日、迎梅は見知らぬ男に襲われ、暴行されてしまう。
「災難」は決定的に迎梅の心に傷を残す。
迎梅は再び心を固く閉ざし、忍耐強く心優しい恋人小雪も、やがて疲れて彼女の元を去って行く。
うつ病を発症し、精神科に通うようになった迎梅だが、「災難」の記憶のある台湾から離れることで人生の転機を見つけようと、名前を「紀恵」という日本読みのできるものに変え、東京で就職をする。
新しい名前と東京でのレズビアンコミュニティ。プライドパレード。職場ではセクシュアリティを隠しつつも、上を向いて生きる彼女には、新しい恋人もできた。
美大出身の薫とは美術館や博物館でデートし、芸術や文学について語り合う。
そして薫に、紀恵は過去を打ち明けることにする。
もし誰かと寄り添い合い、浮世を生き抜くのなら、その人は薫であってほしい、と彼女は思った。互いの抱えている全てを受け入れ合って、こんな生きるのも窮屈に感じるほど狭い、されど見たことの無い風景に溢れるほど広い世界を、春風に吹かれながら、あるいは秋月を眺めながら、歌を口ずさんで共に探検したい。そのためにも、自分の過去を薫に打ち明けなければならない。暗闇の中で孤独な独り舞いを繰り返すのは、そろそろ終わりにしようと思ったのだ。
しかし紀恵の気持ちを現実は裏切る。薫は、なぜ今まで隠していたのかと冷ややかに紀恵を責め、彼女の過去の重荷を「男と経験があった」、「しかもメンヘラ」という言葉で切り捨てたのだ。
あまりにも過酷である。
大学時代、彼女は殻を作り、その殻を小雪に割って欲しいと願った。
しかしその殻は小雪には硬すぎた。
今、彼女は勇気を出して自ら殻を割った。
しかしその中身は薫の受け皿から溢れ出た。
二つの失恋の痛みに読むこちらの心も締め付けられる。
そして、失恋の苦しみを乗り越えたところでさらなる過酷な出来事が襲った時に、紀恵の生の辛さは、「我慢できる範疇を超え」るところまで来るのだ。
物語の最後に、紀恵はある目的を定めて、自分のためだけの旅行を組む。行き先はアメリカ、中国、オーストラリア。
行く先々で出会う人々との束の間のエピソードが、まばゆく胸に響く。そのそれぞれが、彼女に光を見せようと、新たな方角を示そうとするのだが。。。
物語のラストは、お膳立てが出来すぎていると言うこともできる。
だが、もしそれがなかったとしたら、そこにはあまりにも救いがなさすぎる。
綺麗すぎるお膳立てが紀恵を救うことで、今まで彼女の懸命な生を間近で見て、共に心を絞ってきた読者もまた救われるのである。
「迎梅は、自分が考えているより多くの人間に愛されているよ」
小雪のこの優しい言葉は、現実の世界で懸命に生きている全ての人に、作者が伝えたい言葉なのではないだろうか。
*****
作者の李琴峰もまた台湾人で、2013年に来日し、2017年で初めて日本語で本書を書いたというから驚きである。
詩情のある聡明な文章は本当に美しい。
それだけでなく、人間関係の微妙な距離感や古い価値観に対する若い世代の気兼ねなど、とても日本的な感覚を、とってつけたようでも説明的でもない文章で、ごく自然な会話の中に組み込んでいる、その理解と表現の卓越にも驚いた。さぞかしきめの細かい感性と深い洞察力の持ち主なのだろう。
