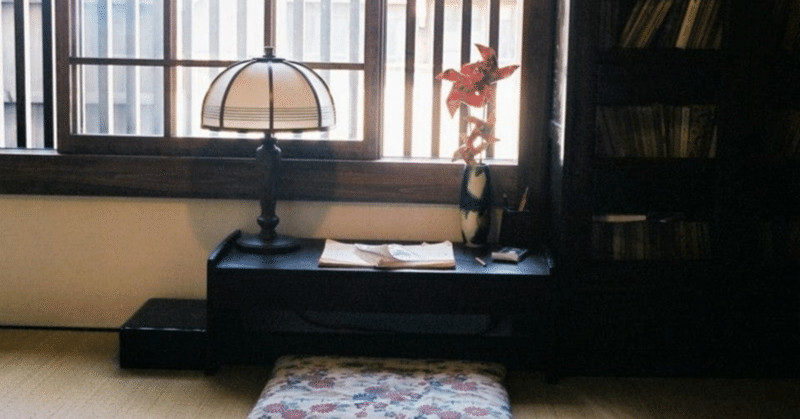
町人学者で生きていく
「小林秀雄の『本居宣長』を読んでたら、『本居宣長は講義中に患者が来ると、たびたび席を中座した』って書いてあるの。本居宣長っていうのは医者で、医者を本業にする町人学者でしょ。だから医者であることの方を、当たり前のように優先するの。患者に医療をほどこすのは世の中に定着している実業だけど、思索という抽象行為の中にいるのは違うからね。学問と正業というのは別なんだよ」
「それで生活を成り立たせるんだとしたら、ヘンな新興宗教みたいに、弟子という信者のみつぎもので食ってくしかない。荻生徂徠みたいに、勉強して学問で出世するっていうことになれば別だけれど、町学者という“フリーの学者”は表向き存在しないんだよね。
好きで勉強して町学者になってる人はたくさんいたけどさ、それは生活費の裏づけが他にあってのことだものね。遊びでそれをやってるっていったら怒られるかもしれないけど、実態としては“趣味に生きてる”っていうのとおんなじなんだよ。
好きで勉強してて、それがご公議の目にとまって、『なるほど感心、これは役に立つ』ってことになったらその人は“学者”だけど、そうでもなかったら、ただの“隠れた知性”ね。全部がなんらかの形で位置づけられてる時代っていうのは、位置づけを持たないものは存在しないも同然なんだから、有名な国学者として評判になって、それで弟子だって大勢おしかけてる本居宣長だってさ、ちゃんと医者としての“本業”を果す為に往診に行ったんだと思うよ。まァ、宣長クラスになったらそんなことしなくたっていい筈なんだけどさ、でもそれやらないでただ“お師匠様”になっちゃったら新興宗教になっちゃうからさ、宣長としてはそれがいやだったんだろうなって思うの。」
仕事が繁忙期で読書の時間が取れなかった先日、「大学院で研究する選択肢もあるか?」と思い立って調べたことがあった。
結論としてあまり現実的ではないことに気づいて諦めた。単純に、家から通える場所に大学院がない。あと学費が払えたとしてもその後の生活費の問題もある。それから、私は夕食を家族と取ることで一日に失ったエネルギーの大部分を回復させているので、その生活スタイルを変えたくない。
そして、私の仕事とライフワークである橋本治の研究は相互補完的関係にあることも事実。仕事を頑張るからこそ研究にも力が入るし、研究することで得た前向きなエネルギーが仕事に発散される循環を生む。仕事に比重がかかりすぎると反動で研究一本に打ち込みたい想いも膨らむが、研究を専業にすると今度は収入や将来が不安で研究がおろそかになるだろう。休みが取りやすくて生活に困らないくらいの安定した収入がある環境で、余暇を研究に充てるのが今の私には合っているようだ。
冒頭で引用した文章で小林秀雄の本の内容に言及されている。私が初めてそのエピソードを知ったのは小林秀雄の講演音源だ。橋本治に出会う前に小林秀雄の講演CDを何百回と聴いていた時期があるのだが、本居宣長の生き方は、まだ社会人として働いていなかった私の“生き方の理想の一つ”として刻まれ、今に繋がっている。
正業と学問という話からは逸れるが、私は「長い時間をかけて一つのことに打ち込む人」が好きだ。結果として完成というゴールに辿り着けなかったとしても。サグラダ・ファミリアのアントニ・ガウディも、本居宣長も、「大河への道」という映画で伊能忠敬について知ったときもそう思った。絶対権力者である将軍様に「よし」と言われることが“いい話”とされる結論には疑問が残ったけれど、一歩一歩歩いて測って日本地図を描いたことはすごいとしか言いようがない(ただし、伊能忠敬は地図完成の三年前に逝去していた)。伊能忠敬が地図作りを始めたのは50代。橋本治が古典の仕事を始めたのは30代。年齢に縛られる考え方は私の悪い癖だが、「今からでも遅くはない、だって…」と思うときに浮かぶ名前は多いほうがいい。
橋本治の著作を全部読むという私の挑戦は、橋本治を知る人であるほど「無理ではないか?」と思われるかもしれない。自分でも時々不安になってそう思うこともある。でもそんなときに背中を押してくれるのは橋本治なのだ。枕草子、源氏物語、平家物語、徒然草、古事記、その膨大な古典の仕事を始めたのがまさに今の私の年齢だったことを考えると、私の挑戦もまた「無理ではない」と思うことができる。橋本治が一文一文を訳し書いたように、私も一文一文を読む日々を積み重ねて行く。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
