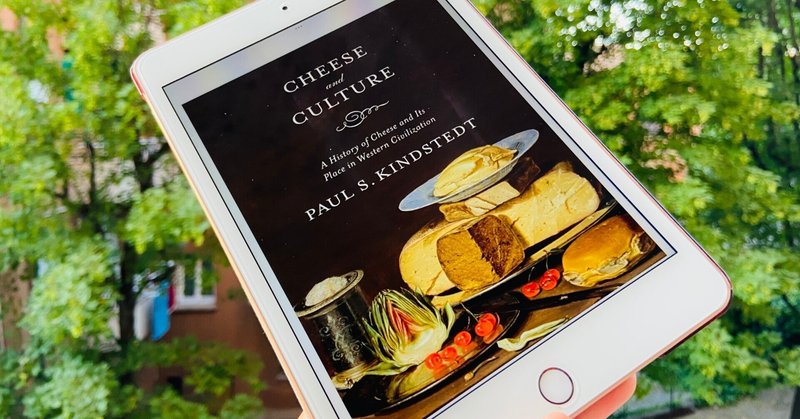
食とグローバリズムと市場主義。アメリカのチーズの歴史から学ぶこと。(文化の読書会:キンステッド『チーズと文明』(8)「伝統製法の消滅 ピューリタンとチーズ工場」)
Cheese and Culture: A History of Cheese and its Place in Western Civilization
By Paul Kindstedt
日本語訳はこちら。
今回は第8章「伝統製法の消滅 ピューリタンとチーズ工場(The Puritans, the Factory, and the Demise of Traditional Cheese Making)」を読んでいきます。
読書メモ
アメリカに移民してきたピューリタンたちは、東海岸の植民地においてもすぐにチーズの需要を見出し、商業的なチーズ作りが始まった。
チーズの商業生産が広がりを見せる中で、先住民や黒人の権利は否定され、辺境に押しやられ、民族間の対立は深まっていった。
ニューイングランドにおけるチーズ・バター生産の繁栄は巨大な大西洋経済圏に組み込まれることで加速し、西インド諸島や南部の奴隷プランテーションやニューイングランドの商人、ラム業者、農家たちとの関係の中で展開していく。
大移民時代の始まり
16世紀 ニューイングランド植民が始まる
1630−40 大移民時代
・イギリス側の社会情勢の悪化や宗教摩擦で、2万人のピューリタンがアメリカ植民地に移住
・ピューリタン植民者と先住民の摩擦が起こる
紛争の結果、先住民が辺境に追いやられる形でヨーロッパ移民の植民が進む
・ラムが先住民の悲劇をもたらしす
アルコールのない文化だったため、ラムにより依存症になる人が続出した
西インド諸島の黒い誘惑
1640年 チャールズ1世の教会改革
・イギリスからのアメリカ移民が途絶える
→植民地の内需不足
・植民地はイギリスからの工業製品を買い続けて、貿易赤字
→植民地の経済は内需依存から貿易による海外市場へシフト
1647年 西インド諸島でペスト流行
→東海岸植民地から農産物を西インド諸島へ輸出開始
→1650年にはチーズやバターも主力輸出品に
17世紀半ば 西インド諸島でヨーロッパ人によるサトウキビ・プランテーションの広まり
・砂糖精製過程の副産物であるモラセスは、発酵させ、蒸留してラムにすると高利益が出る
・ニューイングランドの商人は西インド諸島でラムを買ってアメリカ植民地に売っていたが、その後、西インド諸島でモラセスを買って、アメリカ植民地でラムを生産して販売する販売方式で利益率を上げていく
・奴隷プランテーションとラム貿易によりニューイングランドの乳業者たちは自らのチーズ・バター市場を確保する
→マサチューセッツ、コネチカット、ロードアイランドは乳製品に特化していく
ラムの最も重要な売り先はアフリカで、奴隷とラムが交換された
膨らむ奴隷貿易とチーズ製造
18世紀の奴隷貿易を牽引する、17世紀末の2つの出来事
・2回蒸留・3回蒸留の開発
→高アルコール度数と高品質なラムの生産が可能になった
・1696 イギリス政府によるアフリカ・ロイヤル・カンパニーによるアフリカ奴隷貿易の独占の無効化
→ニューイングランド商人が西アフリカの貿易に参入していく
奴隷がニューイングランドのあらゆる産業で使われるようになっていく
:ロードアイランドとコネチカットでは特に奴隷によるチーズ生産が盛んだった
チーズ産業における男女の役割は
男性奴隷:牧夫
女性奴隷:乳搾り女(イギリスの伝統製法)
☆チーズ・ラム・奴隷の三角貿易
ニューイングランドでアフリカ人奴隷によるチーズ生産
→西インド諸島へ輸出し、チーズとモラセスを交換
→ニューイングランドでモラセスからラム生産
→西アフリカに輸出し、ラムと奴隷を交換
→奴隷は西インド諸島プランテーションへ
「仕上げ塗り」チーズの登場
ニューイングランドにおける初期にチーズ技術はイギリスから移植
:イギリスのCheshireチーズに似ていた
ニューイングランドのチーズ作りにおける最大の発明は「仕上げ塗り」
:プレスの後に木綿を巻いてコーティングをする
→表皮なしの熟成チーズが発展
二つの革命
①アメリカ独立革命→アメリカ合衆国建国
18世紀の後半には北アメリカの市場は西インド諸島の市場より大きくなっていた
奴隷廃止の影響は、イギリスへのチーズ輸出で相殺できる程度だった
19世紀にはニューイングランドのチーズ市場も成長
②産業革命
ニューイングランドは綿産業中心に
:奴隷とラム貿易で資本を蓄えたニューイングランドの商人が綿の機械化に投資し、工業的繊維産業が勃興
→ニューイングランドは綿産業の都市へ=新たなチーズ&バター市場
農家の女性は縫い物に時間をかける必要がなくなった
→成長市場向けにチーズ生産を拡大する
農地を求めて西部へ
18世紀半ばには農地不足
→西部へ農地を拡大していく
食べ物の生産地と消費地の距離が広がっていく
チーズ工場と「規模の経済」
産業革命はチーズ生産にも起こった
;チーズ器具の大量生産によるチーズ作りの効率化、牧畜の大規模化、チーズ生産の大規模化が広まる
女性が持っていたチーズ作りの知見は男性へ
→19世紀初期には家族の「チーズ女」としての女性の地位は失われる
19世紀半ば チーズ工場の登場
;大規模生産施設、大規模牧場、生産プロセスの分化
Jesse & Gerge Williams 初めてチーズ工場のコンセプトを実施
;乳を一箇所に集め、生産と熟成工場の2つに分けて効率生産
→ビジネスは大成功
チェシャーチーズはチェダーチーズに取って代わられる
<2つの発展要素>
・Joseph Hardingsによる科学概念のチーズ作りへの応用;時間、温度、酸度の管理
・イングランドでもチェダーがチェシャーチーズを凌ぐ
1861 アメリカ南北戦争
;男性が戦場へ、女性の負担大→女性がチーズ作りから離れる
イギリス向けのアメリカ産工業生産チーズ輸出が大躍進
&移民の増加や都市化によりアメリカ国内需要も増加
アメリカ産チーズの凋落
繁栄の絶頂に見えたアメリカ産チーズにも影があった。
問題① 生産>需要の状況が慢性的に続く
「生産過剰→価格の低下→コスト削減→質の低下」という負のループ
問題② アメリカ産のチーズの質の評判の低迷
工業生産のチーズは欠陥がなく均質だが、伝統製法の濃くて複雑な味わいを出すことはできない
特に20世紀後半不景気で、経済原理により水分量を増やして熟成期間を短くすると、さらに味わいがなくなった
モッツェレラチーズの躍進
19世紀、20世紀前半のイタリア移民により持ち込まれた
;大量生産を行わず、質を担保
人気が出ると、価格低下の圧力がかかり、工業生産開始
→「モッツァレラ」と名乗れないようなチーズもモッツァレラとして主にピザ用に販売
市場では、アメリカ人は質の違いに気付いていないようだ
他にも様々なチーズが移民によってアメリカに持ち込まれたが、20世紀後半までにスケールアップできないものは淘汰されていった
1970年代以降 近年では、伝統製法による職人のチーズに再び賞賛が集まっている
私見
チーズの近代グローバリゼーションの歴史であるが、世界経済の縮図として、いかにも分かりやすくて好きな章でした。
下記3点について言及したいと思います。
三角貿易と食の歴史
<読書メモより再掲>
☆チーズ・ラム・奴隷の三角貿易
@ニューイングランド アフリカ人奴隷によるチーズ生産
@西インド諸島 チーズとモラセスを交換
@ニューイングランド モラセスからラム生産
@西アフリカ ラムと奴隷を交換
@西インド諸島プランテーション 奴隷による砂糖生産
大西洋三角貿易では、砂糖、コーヒー、タバコなどの商材はよく知られていますが、チーズ・ラムも同様に三角貿易が行われていたことを初めて知りました。
おそらく他の商材でも行われていたことを思うと、三角貿易の合計規模は想像を超えたものなのではないでしょうか。
個人的には、こうした近代グローバリゼーションの中でローカルの料理の文化がどのように変化していったのかに興味があり、いつかこうした大きな歴史と小さな歴史を結びつけるような論文を書いてみたいと思っています。
チーズ作りと女性
もう1点、最近の私の関心に「料理の分野から歴史上’Unvoiced’であった女性史を紐解く」ということがあります。
識字率や記録の必要性の問題で、文献に書かれることが少ない女性は、歴史じ上’Unvoiced’であることが歴史学の課題になっています。
なので、そうした従来歴史学がアプローチ出来ていなかった対象に、違う切り口でアプローチしてみようと思うのです。「料理」はその最たる分野ですよね。私的空間に女性の素晴らしい活躍があったわけですから。
さて、今回の章に出てきた「近代アメリカのチーズ作りにおける女性」を上記要約メモから抜粋してみます。
18世紀 チーズ・ラム・奴隷の三角貿易
@ニューイングランド
男性奴隷:牧夫
女性奴隷:乳搾り女(イギリスの伝統製法)
18ー19世紀 産業革命
農家の女性は縫い物に時間をかける必要がなくなった
→当時成長市場だったチーズ生産を増加
女性が持っていたチーズ作りの知見は男性へ、工業化へ利用
→19世紀初期には家族の「チーズ女」としての女性の地位は失われる
1861 アメリカ南北戦争
男性が戦場へ、女性の負担大→女性がチーズ作りから離れる
女性が媒介役になって、政治と生活史を繋いでいる様子が分かりますよね。
深掘りするなら、例えば、産業革命前夜で、家庭内で女性が代々受け継がれてきた製法で作っていたチーズ作りが、科学的に検証されたりして工業化されていく時などは割と資料などもありそうで、家庭の女性の知見の貢献などは研究できそうですよね。もうあるかもですが。
この調子で、フェミニズムでもなく、経済学でもなく、料理史から女性史の研究するのはまだまだ未開拓で面白いと思います。
市場主義と食
最後の「アメリカ産チーズの凋落」、見応えありましたね。
もう何故そうなっちゃうの。。と思いつつ、結局歴史は繰り返しているのですね。
慢性的な生産過剰で価格圧力で質が下がるという話は、その原理が若干理解ができなかったのですが、
(需要より生産が多いなら生産を抑制するのが普通では?石油や農産物はみんなそうしてるのに。個人の最適解(自分は儲けたい)と全体の最適解(市場全体では供給過剰)のズレ?)
大量生産で質が低下して、評判悪くなって、、という話は、もう分かりきっていること。
「短期的な利益が長期的な利益を毀損する」と原理を言葉にすると簡単だけれども、現在でも世の中のあらゆるところがそうなので、歴史からなぜ学ばないのかという気持ちさえ出てきてしまうくらいです。食品の工業生産化だけでなく、チェーン店の盛衰や、搾取型農業と環境破壊など例を上げればキリがないわけですが、このジレンマの中で世の中回っているのだなと。
時間が経つと巻き返しも大変で、技術も失われて、取り返しつかないのですから、のんきにしてはいられませんね。
特に、食の分野は、市場主義と相性が悪いと思います。
市場主義で本質を誤る話は、先日の大学院の試験でも最大のテーマだったのですが、
(ここで扱ったのは、市場主義と医療。市場原理が医療現場に持ち込まれると命が失われる話)
食も同じで、
飢餓の危機にある国で、食に市場原理を持ち込むのは命を見殺しにするのと同じ(市場原理の値段つけると最貧困層は買えないですので)ですが、
私たち飽食の社会においても市場主義は危険で、食べ手が消費者になった瞬間に、人々の人生の豊かさの追求は合理的で無くなり、そのシンプルな豊かさの積み重ねが作る文化というものが廃れるのです。
生活者側も「美味しいもの食べたい」という欲求が初めにあったはずなのに、いつの間にかそれが鈍るのですよ。
アメリカ人は工業生産のチェダーチーズが入ってきた時に、その質の悪化に気付かなかったと本文にもありましたけれど、日本も程度の差は別として、結構当てはまりそうな例は沢山あります。
この辺、比較的鈍っていないのがイタリア人だと思っていて、「美味しいもの食べたい」と素直に思える彼らはやっぱりすごいなと思うのです。
(ちなみに、これは私だけでなく他の方も言っていました。)
ちなみに、分かりやすくするために〇〇人、と言っていますけれど、過度の一般化をするつもりはありませんが。
でも、やっぱり最後の砦は消費者であると思いますね。
私たちが「良いもの食べたい」という気持ちに素直に従ったら良いと思うのです。
何が言いたかったかというと、このアメリカのチーズの学びはこれからの私たちに生きることが沢山あるということ。
ポスト資本主義の今、これからの50年は急速に次なる豊かさの追求に向かっていくでしょう。
それは、「本当に大切にしたいものを大切にする」時代です。
その中で、お金や効率が物差しになる市場経済の比較重要性が薄れる中で、人々が選ぶ「本当に大切なこと」って何なのでしょう。
きっと食は1つの大きなテーマだと思います。
1日に3回、誰にでも訪れる、豊かさを感じる瞬間ですから。
私はオンライン料理教室や料理家の活動もそのエンパワメントだと思って実施していたりします。
というわけで、お世話になった「文化の読書会」も次回で最終回かしら!
よろしくお願い致します〜
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
