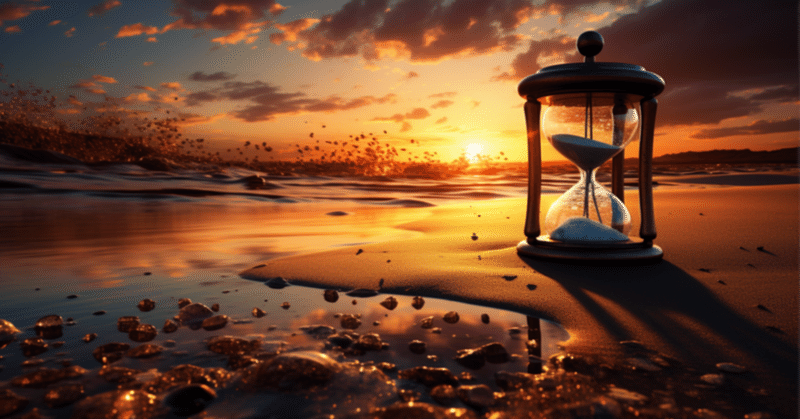
哲学⑤「存在論と死と時間」について思い、考えること
※この文章は、学生時代に哲学の授業レポートで書き記したものとなります。
人はいつの日か必ず死ぬ。それはハイデガーの述べる「究極の可能性」そのものである。その捉えどころのない恐怖心はいつの間にか自分の存在意義について疑念をもたらし、死を起点とした結果、どう死にたいのかどう生きたいのか、という想いへと駆り立てることとなった。
今はなきその人の肉筆を見ると、その人の不存在が胸に込み上げてくる。21歳のときにガンで亡くなった幼馴染みのSちゃんは、9歳の私が親の都合により転校してしまう前にこんな手紙をくれた。
「いままでありがとね!いなくなっちゃうのはさびしいよ でもまたここにかえってきたら1番さいしょにあそぼうね やくそくだよ Sより」
「番」以外、全て平仮名の文体になっているのを見ると、とても懐かしいものを感じる。
単純に「あの頃の自分たちはなんて幼かったんだろう…」と思う一方で、「これが肉筆なんだよな…あのときまだ彼は生きていた」と思わずにはいられない。
文字を書く、とりわけ直筆で書くということは、そこにその人の「生」の時間が流れているように感じる。鉛筆やペンを持って文字を書くという行為は、そこにその人の息遣いがあって、思考があって、指紋があって、その人固有の筆跡があって…成立するものである。そのどれもが欠けては、身体と意思によって握る鉛筆から文字を紡ぎ出すことは不可能である。
その人が、その人としてその「現在」に存在しているからこそなせる行為である(そう考えると、遺書や遺言がその人が死してなお効力を有するのはとても自明の理であると思う)。
文字は時間のつながりである。瞬間・瞬間の連続性が紙面上にビットのように表された、時間の織りなすタイム・トラベル。一つとして同じ文字は存在しない。
不整脈の発作によって死を意識してから、私は自分の終わりを明確にイメージするようになった。何も死ぬ瞬間をイメージしている訳ではなく、単に「いずれやって来る終わり」に想いを馳せるようになっただけなのだが、それを踏まえてから「自分をただの社会における駒や道具」であるという認識は薄れた気がする。勿論、傍から見れば私はただの映画におけるモブかもしれないし、モブ以下の存在で主役でもないかもしれない。けれど、映画のカメラが回っていない社会のどこかで、個々人は個々人の持つ鼓動を動かしている。それは素晴らしいことではないかと考える。死んだら最後、あちらの世界はあるのかないのか。不確定要素が多い命題だが、私が哲学で「死とは何か」という問いから得た暫定的な答えはこれである。
死とは、自己の不存在という大きな痛みを伴った、最高の教訓である。
ハイデガーは死を避けられないものであると見なし(当たり前だが)、自分の死をしっかり見つめることで今を生きる自分のありがたさを認識できるきっかけとなると位置付けたが、ここから先の問いについては述べていない。
つまり、「より善く生きるためにはどうすればいいのか」という問いである。これはおそらくきっと、私や皆それぞれが抱えていく問いであるのだろう。いつか死ぬという大きな自己の喪失と痛みを抱えながらも「どう生きたいのか」を考え続ける。人間は(というか私は)、死を前にするとこんなにも貪欲になれることを初めて知った。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
