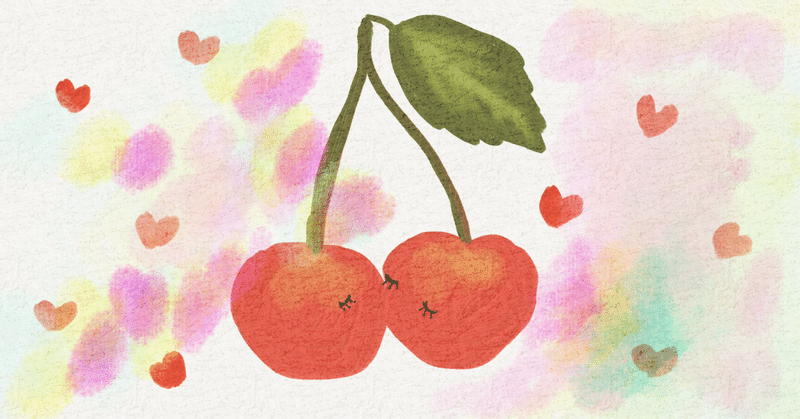
小さな抵抗
小学三年生のころ、二年生まで仲のよかった男の子のことを、三年生のときには「好き」だなと自覚した。きっとこれが初恋なのだろう。
三年生になってはじめての夏休みがもうすぐというころ、わたしは病気になった。自己免疫疾患の病気。
病院で先生にいわれたのは、完治までに一年はかかるとのこと。なので、即入院という診断だった。
わたしは元々臆病気質。病院なんて幽霊がいっぱいで、痛いことしかされないという恐怖しかなく、入院を断固拒否。
子どもの小さな抵抗なんて聞き入れられないという常識なんてその当時のわたしにはないモノだから、なにがなんでも押し通す勢いで大暴れしたようなしなかったような。
ただ、どういう流れになったか記憶にはないが、わたしの小さくて大きな抵抗は受け入れられたのだ。
夏休みを目前に、わたしはその日から投薬と通院という自宅療養がはじまった。
歩くことはままならず、毎日いくどとなく激しい嘔吐と腹痛、足の痛みに襲われる。もちろん学校には行きたくても行けない。
外であそぶことが大好きだったわたしだが、外に出ることすらできなくなったある日、主治医に、
「外に出て太陽を浴びるのも大事。体力が落ちるから散歩もしてみて」といわれ外に出てみるも、太陽の日差しがこんなにも強く、体力が奪われるのかと幼心に感じながら壁を支えに歩くことのしんどさ。
あぁ、わたしこのままずっと、歩くことも走ることもできなくなるのかと絶望さえも感じていた。
その絶望感をあおるかのように、近所に住む同級生の男の子がわたしを見つけ、
「あー!nontaro、学校サボってあそんでるって先生にバラしちゃおう」
なんて皮肉をいってくる。本来のわたしならきっと、「なんだと〜!」といいながら追っかけただろう。
ただそんな気力も体力もない。ヤジるその子を横目に、元気になったらアイツを絶対こらしめてやる!と心の中で誓うことしかできなかった。
治療がはじまって一ヶ月がすぎ、学校は夏休みに入った。わたしはあいも変わらず、激しい嘔吐と腹痛、足の痛みがつづいていた。
毎日毎日、胃の中のモノがなくなって胃液しか出なくなっても吐きつづける苦しさ。
わたしはこのまま好きな男の子に会うこともできず、死んでしまうのだろうか?と、死の恐怖を感じる毎日。
そのときの母も相当大変だったと思う。自宅で小さな商店をしていたため、昼夜問わずわたしの看病はできる。
とはいえ、わたしは食べても食べなくても何度も吐くし、日に何度も激しい腹痛におそわれ母に助けを求める。
薬を飲ませて、激しく痛むお腹には熱々のホットタオルを乗せるため、ヤケドしそうなほど熱いお湯に手を突っ込みタオルをしぼる作業は、そう容易いことではなかったはずだ。
でもホットタオルを乗せられると痛みが和らぐから、わたしは何度もそれを求めた。
足の痛みというのは、ふくらはぎが凍ってると感じるほどの冷たすぎる痛みで、手で触っても実際には冷たいわけではなく、ふくらはぎの中がそういう痛さだったのだ。
ひざ下まである長い靴下を何枚重ねても温かさを感じない。
それはホットタオルやストーブでも温まらなかった。
検査や薬をもらう日、悪化してどうしようもない日の通院は、働く母にとって、地獄の日々だったかもしれない。
きっと何度も、入院してくれないかと頭をかすめたはずだ。だって、これが一年もつづくとなったら、母の体も持たないのだから。
先の見えない闘病生活。
その当時わたしの願いは、元気になって学校に行きたいだった。勉強嫌いだったのにだ。
たぶん、好きな男の子に会いたかったのかもしれない。友だちと外で思いっきりあそびたかったのかもしれない。母の負担を軽くしたかったのかもしれない。
それよりなによりも、生きたいと思ったのかもしれない。
友だちと元気に走りまわってる自分を想像してたのは確かだ。
死の恐怖を感じながらも、きょうだいと騒いでるわたし、美味しいものをたくさん食べてるわたし、学校に行ってるわたし、友だちとあそんでるわたし、いつも元気なわたしを思い描いてた。
夏休みももう終わりに近づいてるころ、あんなに激しかった病状がピタリと治った。
主治医には、奇跡といわれた。一年といわれた病気が二ヶ月でよくなったのだから、驚かれるのも無理はない。
わたしは二学期から、わたしが望んでた通り、元気に学校に登校したのである。
ドキドキワクワクしながらの登校。母から前もって担任の先生に連絡がいってたのだろう。
先生は二学期から席決めを自由にしたことを教えてくれた。
つまり、朝教室に入ったら、好きな席に座っていいというなんとも大胆な席決めだ。
毎日好きな席に座っていいというもの。
わたしが登校した日に先生がわたしにコッソリ耳打ちをする。
「しゅうじ君の隣に座ってね」とウインクする先生。
ドキッとした。その名前を久しぶりに聞いたからってのもあるが、なぜ先生がわたしの好きな男の子を知っているのか?ということ。
まだ子どもなわたしは驚きを隠せず目を見開いた。
親友以外だれにもいってないはず。ということは、わたしが休んでいる間に、先生がわたしになにかできないかと考え、親友に話を聞いていたのかもしれない。
わたしはこの先生の好意を素直に受け取れず、しゅうじ君の隣に座らなかった。というか、あまりにも恥ずかしすぎたのだ。
これまたわたしの小さな抵抗。
あんなに生きたいと思ってたのに、あんなにしゅうじ君に会いたいって思ってたのに。
わたしの担任になってまだあまり関わりがなかったにも関わらず、この先生はなにかとわたしのことを気にかけ、わたしの初恋を応援してくれて、いつもちょっと的外れな気づかいをしてくれたのだ。
一度だけ先生の応援を受け取り、勇気を出してしゅうじ君の隣に座った。
先生はとてもとてもうれしそうな笑顔で、
「やったじゃん!よかったね」とコッソリいってくれた。
ただわたしはあまりの緊張で、隣に座ったことを後悔したことは先生にいえなかった。
今わたしはその先生の顔しか思い出せない。名前すら覚えてない。この先生のことだけは忘れたくないと思っていたのにな。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
