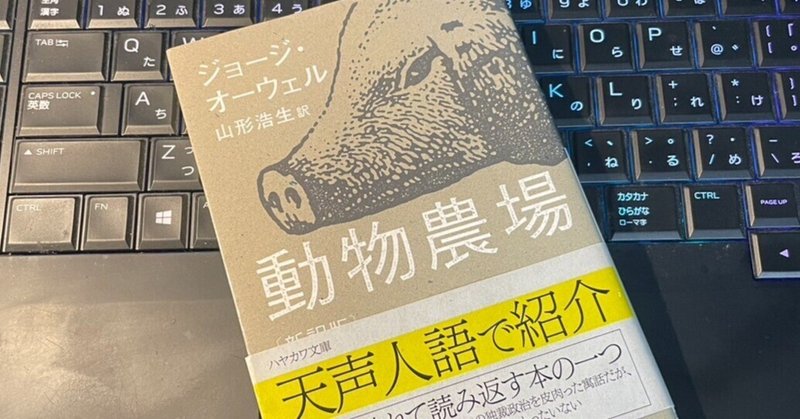
【読書】サラダの歴史 他
サラダの歴史
「食」の図書館シリーズは三冊目です。
ピザの歴史、サンドイッチの歴史を以前読みましたが、普段の食に隠れた歴史を知ることが出来るのでお気に入りのシリーズです。
・ラテン語で「塩をかけたハーブ」を意味する”herba salata”からサラダや英語のSaltができている。
・古代ギリシアでは「四体液説」とサラダの結びつきが強く長らくのあいだ医学的に効果があると考えられていた など
一言に「サラダ」といっても加熱の有無や味付けの種類、さらには野菜だけでなく魚や肉など材料の変化も含めると無数に存在します。
まだまだ知らないサラダがあると思うとワクワクしますね
「おいしさ」の錯覚
ゆる言語学ラジオの水野さんが動画で紹介していたこともあり、図書館で見つけた瞬間に即決で借りました。
ガストロフィジックス(ガストロノミー+フィジックス)という分野で、食に隠れた「おいしさ」の要素を解明していくようなもので、香りや音、環境や手触りなど様々な角度からアプローチしていて、研究者の熱意も伝わってきてとても面白いです。
普段なんとなくで感じている外食での雰囲気や、お店ごとの特徴といったものを興味深く観察するだけでも楽しくなりそうです。
コーヒー好きな私は、
例えば深煎りのコーヒーと浅煎りのコーヒーを同じ色のカップで飲んだときの違いや、コーヒーの甘さや酸味を活かすための工夫には何があるだろうかと考えてみました。
また読みたい一冊です。
とわの庭
「ライオンのおやつ」も書かれた小川糸先生の小説です。
目が不自由で長い間母親意外の人間と会話のしたことのない少女が、様々な苦難や人との出会いを通じて成長していく物語です。
改めて当たり前の幸せを感じることが出来ましたし、現代の生活の辛さというのは自分の幸せの物差しを変えることで免れることが出来るのではないのかなと感じました。
私自身も周りの人の幸せそうな生活を目にして、辛いなと感じることがありますが、考え直してみると決して自分が望んでいるような人生ではないのに何で苦しんでいるんだろうと気付き、はっとすることがあります。
まだまだ自分の感情をコントロールしきれていないですが、この物語も思い出しながら克服していこうと思います。
現代哲学の名著―20世紀の20冊
これは興味本位で借りた本です。
結論から言うとさっぱりわからない。これです(笑)
フッサールやメルロポンティ、西田幾多郎などなど
一人につき10ページ弱で振り返ることが出来る本です。
ここで振り返ると書いたのは、勉強不十分の私には難しく思えたからです。
入門書を読んだことのある人物の箇所は読めますが、そうでない箇所は辛いです。
自分の勉強不足を顧みてモチベーションにします。。。💦
コーヒーと日本人の文化誌
日本へのコーヒーの伝来から、喫茶店文化の系譜やブラジルのコーヒーとの関係性までひも解いてくれる一冊です。
最近ではスぺシャルティコーヒーの普及で純喫茶といわれるようなお店はなかなか出会えないですが、チェーン店やカフェそして喫茶店におけるそれぞれの役割を理解すると、この文化を残していきたいと強く感じます。
愛知県民の私はモーニングのために喫茶店に足を運ぶこともしばしば。
30年後も楽しめるといいなあ
動物農場
友人に貸してもらいついに読めました!
ジョージ・オーウェルは「1984」に続き二作目でしたが、比較的読みやすくて良かったです。
本書はスターリン批判と言われていますが、知識のなかった私は純粋にSFとして楽しみました。(読後すぐに図書館でロシア史を少し勉強しました)
現実の出来事との多少の差異はありますが、うまく物語に昇華していてオーウェルらしく痛快に書かれています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
