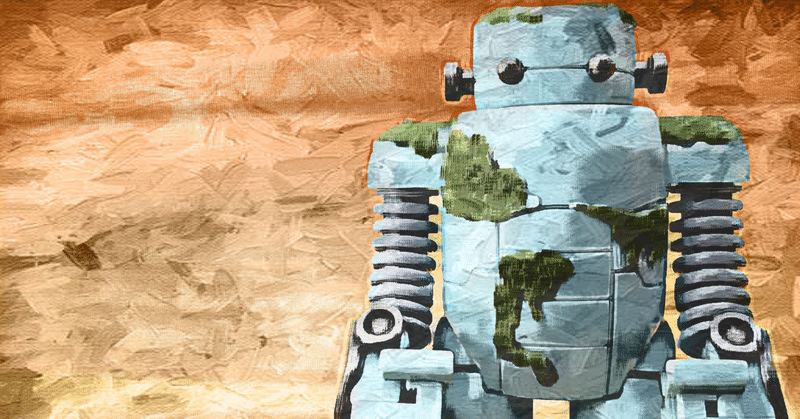
【およそ9000字】ロボット 人間 猫【やさしい世界線】
ロボット 人間 猫
①ボクがスリープから覚めると、目の前には、眠る前には苗木だった木が、大樹に成長していた。また電源が入ってしまったようだ。
ああ。ボクは温かい体に生まれたかった。何が入っているかよくわからないこの体はひどく冷たい。今はもうボクは朽ち果ててしまっていて、森の奥の方。ツタに絡まって、所々がもう錆びてしまっている。自然の力はとてもすごくて、幾重にも絡まったツタや木の根でボクは身動きが取れなくなってしまった。ツタに絡まれたまま木の根っこに体を預けているけど、ボディに無理矢理力を入れて動かせばこの状況から抜け出せるのかもしれない。しかし錆びのおかげで体を動かすのが億劫で仕方ない。それにそもそも動く必要もない。そしてボクはロボットだから人間みたいに足が痺れたり体が凝ったりすることはない。だからボクは動く必要がないからずっとここにいる。ずっと。ずっと。
ただ、バッテリーがいつまで残っているかわからないから、あと何年、何十年、もしかしたら何百年後にはここから本当に動く事ができなくなっているかもしれない。そう思うとボクはこの胸のバッテリーをどうにかして取り出して、壊してしまいたいと思った。太陽が昇り、月がそれを追いかけている。明るくなったり暗くなったり、雨が降ったり風が吹いたり。それをずっと見ているのもそれほど悪くは無いけれど、なんだか言葉にできない苦しさみたいな感覚が、ボクのボディの中枢部分でおかしな響きを起こす。なんだか今日はたくさんの事を考えていたからCPUが焼け付いてしまいそうな気がする。もう寝よう。スリープモードだ。
②ボクが再びスリープから目覚めると、ボクを挟んだ2本の大樹が歪に成長し、途中でぶつかり合ってできたであろう小さな空間にいた。どうやら大樹の成長に巻き込まれてしまったのか、ボクを覆っていたツタは、茶色く枯れてパリパリになってしまっていた。木の幹を背にして、腕や脚を投げ出して座っている姿は変わっていないから、特に大きな転変地異といったものはなかったらしい。今度はどのくらい起きていられるかなあと思っていると、ボクの側に積もった枯れ葉の山が妙にモコモコと動いている。錆び付いた首を無理やり動かすとガリガリという音が鳴った。その瞬間だった。枯れ葉の山から一匹の子猫が勢いよく飛び出してきた。白と黒のハチワレで、ヨチヨチ歩きのくせにグングンと先に進んで行く。そのあとを追うように同じくらいの大きさの真っ白と真っ黒な猫がヨタヨタと先ゆくハチワレの後に続く。ニャーニャーと、その小さい体には似つかわしくないほどのボリュームで2匹は鳴いていた。先に行ってしまったハチワレを呼んでいるのだろうかと思った。しかし木の枝がそこかしこに好き放題伸びてしまっているこの付近は、足元の覚束ない臆病そうな子猫たちにはレベルが高すぎるのかもしれない。黒い方が木の根に足をひっかけころりと転ぶ。それに巻き込まれた白い方も同じように転び、白と黒の毛糸の玉がうごめいているようだった。その2匹の姿を見守っていると、先にどこかへ行ってしまった小さなハチワレを、その親と思わしき白黒のハチワレが首根っこを咥えて戻ってきた。その姿を確認した白と黒は、さっきよりさらにボリュームを上げて鳴き始める。一体その小さな体からどうやってこんなけたたましい鳴き声を発しているのだろうかと不思議な気持ちになった。
親猫は小さなハチワレを咥えたまま近づいてくると、僕の側の枯れ葉の山にその子をポイと放した。続いて同じように白と黒を一匹ずつ丁寧に咥えて枯れ葉の山へと運んでくる。途中にハチワレがまたどこかに行ってしまいそうになっていたが、親猫の一鳴きにより大人しくなったのだった。4匹が枯れ葉の山の上に落ち着くと、親猫が子猫たちをかわるがわる舐めている。その感触が気持ちいいのかハチワレは少し白目を向いている。白はうっとりとしていて、黒は嬉しそうにニャ、ニャと声を上げていた。そのうちに親猫は体を横倒しにした。三匹の子猫たちはどうやら大分腹を空かせていたようで、やっとのことでたどり着いた母猫の乳に必死に吸いついていた。時折母猫のお腹を踏み込んだり、鳴き声ともとれない喜びの声を上げている。そんな子供達の姿を見守る母猫の瞳は、とてもやさしく、少し緑がかった瞳は愛情に満ち溢れている。ときおり目を細めるその姿が微笑ましかった。ボクはそんな猫たちの姿を見ていて、幸せな気持ちになり、眠くなってきてしまった。母猫がボクをジッと見つめている。尻尾がパタパタと動いてはいるものの特段警戒をしているということでは無いらしい。お腹が一杯になったからか、ハチワレと白は、母親の体にピタリと体を寄せ、丸くなって眠っている。すると先ほど木の根で盛大に転んでいた黒が、ボクの背後の木とボディを足場にして、肩へと登ってきた。フンフンと匂いを嗅ぎ、おもむろに爪を立てて、その小さな体を目いっぱい使ってボクの頭で爪とぎを始めた。特に痛むことはない。カリカリ、カチカチという音が頭部の処理機能を刺激する。何故だかわからないけれど、生きている猫の存在を感じると、以前1人でいた時に味わった、言葉にできない苦しみが和らいだ感じがした。どうしてだろう。いつもより優しい気持ちでスリープ状態に入れる気がする。そんなことを考えていると、母猫が小さな陶器に盛られているごはんをカリカリと食べ始めた。ボクはその音を聞きながらとても穏やかにスリープに入っていった。
③次に僕がスリープから目を覚ました時。小さかった3匹の子猫たちは随分大きく成長していた。誰と誰の子かはわからないけれど、子猫たちが数匹増えており、じゃれあったり、毛繕いをしていたり、香箱に座っている姿があった。
ボクは辺りを見渡そうとした時、妙に首の回りが良いことに気づいた。ボクがいる場所は変わってはいないけれど、以前スリープに入った時とは態勢が異なっている。どうした事だろうか。ボディに力を入れると、あれだけギーギーと悲鳴を上げていたボクの関節は、なぜかスムーズに動かすことができる。両腕を枯れ葉が積もった地面につき、脚部に力を込めると、ボクはいとも簡単に立ち上がることができた。そういえば赤茶けて錆びついていたはずの塗装は、決してキレイとは言えないが、爽やかな水色に塗り直されている。詳しい事はわからないけれど、スリープに入っている間に、ボクのことをメンテナンスした誰かがいるのかもしれないと思った。
普段は動かないボクが急に動き出したものだから、周りで寛いでいた猫達が飛び上がった。そして右へ左へと走り去ってしまう。ボクはどうしていいのかわからず、ただ茫然とそこに立ち尽くすしかできなかった。まん丸になったいくつもの瞳がボクのことを見ている。それが興味なのか、恐怖なのかはわからない。しかし、異物に対する警戒の視線であるには変わりなかった。なぜだかわからないけれどボクはひどく悲しくなってしまった。一歩足を踏み出し、枯れ葉を踏みしめる音が響くと、猫達がビクリと体を震わせる。このままここに立ち尽くして、再びスリープモードに入ってしまおうかと思った。しかしその時、以前はやんちゃだったハチワレがゆっくりとボクに近付いてきて、ボクの脚部をフンフンと嗅ぎ始めた。ボクはただその姿を見つめている。するとハチワレは枯れ葉が敷き詰められた地面を踏みしめボクの前を歩いていく。小さい頃、枯れ葉を巻き上げながら走り回っていた子猫は、随分とゆっくりと歩くようになった。わしゃりわしゃりと音を立てる。少し進んだところでくるりとこちらを向き、思ったよりも高い鳴き声で鳴いた。ついてこいということだろうか。ボクはハチワレの後を追う。思ったよりもスムーズに進む脚が嬉しかった。警戒していた他の猫達は、ボクとの距離を縮めようとはせず、一定の距離を保ちながらボクの後ろについてくるのだった。
鬱蒼とした森の木々の隙間から木漏れ日が時折降り注ぐ。そんな光の刺激や温度の変化を感じながら少し急になっている坂を上っていく。木の根っこがそこら中に走っているものだから、後からついてくる猫達の中には、それに躓いてコロコロと転がっている子もいた。そういえば白と黒も小さいときはあんな風にしていたなと思うと、ロボットのくせに少し懐かしい気分になった。そういえば黒と白はどこに行ってしまったのだろうか?あたりを見回してみるけれど、ハチワレと同じくらいの大きさの猫は見当たらない。どこかに散歩でも出かけているのだろうかと思い、そのまま歩を進めていく。時折ボクという存在に慣れてきた猫達は、後ろをついてくるだけではなく、足元をわざとウロチョロしてみたり、ボクの少し先でコロリと寝ころび、グッと伸びをしたりしていた。その内に猫達は思い思いの鳴き声を上げながら、ハチワレがボクを案内するのに合わせてついてくる。騒がしくもかわいらしいピクニックになったなと思った。
どのくらい歩いただろうか?先頭を行くハチワレが急に走り出した。ボクは見失ってはいけないと思い走って追いかけると、足の関節同士がガチガチとぶつかるような音が響いた。木々が途切れて小高い丘に出る。ボクの視界の先には大きな水たまりが広がっていた。ザザ、ザザア。と波が起こっていて、緩い風が吹いている。太陽の光が燦燦と降り注ぐ場所だった。先についていたハチワレは自分の前脚を舐め顔を洗っている。その横には大きくなった白がいた。母猫に舐められてうっとりとしていたのんびりとした性格は変わっていないのだろう。ボクをここに連れてきたハチワレにゆっくりと寄添い横たわった。ボクは辺りを見回すと、崖の少し手前に2つの石が並んで積まれていて、キャットフードの缶と小さな花がそれぞれに置かれているのに気づく。どうやらお墓のようだ。誰がこの墓を建てたのかもわからない。それにここに眠っているのが母猫と黒なのかもわからない。けれどハチワレがボクをここに連れてきて、白がここにいるということはそういうことなのだろう。以前スリープから覚めた際には母猫の子への愛情と、黒の無邪気さが、あるはずのない心が震えた気がしたのを思い出した。近くの野草を摘み、2匹のお墓にそっと供える。胸部の辺りの電気回路でうまく電流が流れていないのだろうか?なぜか少し苦しい気がした。後から追いついてきた子猫達がお墓の周りでじゃれ合っている。ハチワレと白は寄り添いながら、その姿を見守っている。母猫と黒も同じように子猫たちを見守っていたのだろうか。そんな風に思うと2匹にはどうかゆっくりとこの場所で、安らかに眠っていて欲しいと、そう思った。
今日は、スリープから目覚めた日にしては動き過ぎた気がする。バッテリーが切れかかってきたのかもしれない。青空をバックにしていたお墓や、ハチワレや白、小猫達が戯れたりする映像が徐々に白黒へと色褪せていき、視界も狭くなってきた。どうやら本格的に充電切れらしい。元居た場所に戻る元気もなく、目の前が暗くなっていく。ボクは母猫と黒のお墓のそばに転がりそのままスリープモードに入っていく。子猫たちがボクのボディによじ登ってきた。小さな爪を必死に伸ばして上ってくる姿や、所狭しとは香箱に座る温もりを感じる。これまで寂しくスリープモードに入っていたけれど猫達に出会ってからは、なぜかボディの温度が少し上がるといった感覚を知った。目からオイルが零れた気がする。優しい気持ちで意識が遠のいていった。
「ああこんなところいたのか」白髪混じりの作業着を着た男が一人で呟く。たくさんの猫たちに囲まれたロボットはスリープモードに入っているようだった。「ここまで歩けるくらいにメンテナンスができていたようだ」作業着の男はにやりと笑ってロボットの横に仰向けで寝ころんだ。「昔、野良猫を追いかけていったら、ロボットが眠っているなんて思いもしなかったよ」ボディを手のひらでペチペチと叩く。その音を聞いて、ロボットの上で落ち着いていた猫達がおずおずと男に近付いてくる。男は一番近くにいた猫の喉を人差し指でこそぐる。猫はグルグルと喉を鳴らし始めた。「猫達の秘密基地にお前も案内してもらえることができたんだな」ロボットの胸元に軽く拳をぶつけるとコツンという音がなる。男の手の甲にはロボットと同じ水色の塗料が付いていた。「ずっと森の奥にいたから、丘からみえる海は美しかっただろう?」ロボットが応えることは無いのはわかっているが、質問せずにはいられなかった。「また少しの間ここでゆっくりと休んでいるといい」男はそう言うと体を起こす。男の体の上でうとうとしていた猫達はコロコロと転がり落ち、何が起きたのかわからないといった風に目をパチクリとさせた。男が立ち上がり、ポケットからキャットフードを取り出すと、墓の前にそっと供えた。「また来るからみんなと仲良くしているんだぞ」そう言って男はその場から立ち去って行った。
④ひどくボディがギシギシしている気がする。関節がすり減っていたり、パーツが錆びついているというわけではないようだ。それに以前スリープモードから目覚めた時と比べると、電気回路やバッテリーの電力供給も調子が悪い気がする。水色に綺麗に塗装されてはいるが、なんだか旧式の機械に無理やり色を被せたような違和感を覚えた。
そうだ。以前スリープモードに入った時、僕は森を抜け、大きな水たまりが広がる丘にいたはずだ。それなのにここはどこなんだろう?これまでのような土や木々に囲まれた場所ではなく、屋内でどこか殺風景な所だった。辺りには見たことの無い機械が置かれており、頑丈なテーブルみたいな台の上にボクは寝かされている。どこかの実験室だろうか?そうであったとしてもこんな場所には心当たりはなかった。ボディを動かそうとしたが、何か違和感を感じた。何事かと頭を動かしてみると、ボクの体は多くのコードに繋がれていた。そしてボクを照らす明かりは太陽光のように燦燦とはしておらず、人工的な白色の蛍光灯に照らされていた。ここはどこなんだろう。そう考えていると、視界の端で自動ドアが開く。そこには作業服を着て白衣を纏った白髪混じりの老人がいた。何かの実験に失敗したのだろうか?髪の毛は乱れているし、よく見るとメガネのレンズはどうしようもないほどに汚れている。
「目覚めたようだね」優しく、少ししわがれた声だった。
「わしはお前さんの事をよう知ってはおるんだが、どうだい?わしが誰だかわかるかい?」
ボクは意味が分からずキョトンと固まってしまった。「いつの頃だったかな。まだわしが大人にもなっていない時にお前さんと初めて出会った。コロコロとした子猫達が沢山おってお前さんはとても幸せそうに眠っておったよ」そういえば昔スリープから目覚めたとき、母猫のハチワレと、その子猫たちが僕の周りにいたことを思い出した。「お前さんがあそこで眠っておるのはわしだけの秘密だった。それからというもの、時折あの森にお前さんの様子を見に行っていたもんよ。お前さんはわしが様子を見に行くといつもいつも寝ておっての。それでいて以前いた場所とは少しばかり違うところでまた眠っている。その度にまた動いているお前さんに出会えなかった!と嘆いたもんじゃ」カラカラと老人は豪快に笑う。老人の笑い声がボクには気持ちよく響く。不思議な人間だなと思った。「それにな。おまえさんはずっと屋外におるもんだから、ボディやパーツの損傷が激しくてなぁ。特に今回は海風の当たる所にいたもんだから塗装は剥げるし関節には錆が浮く。何でしばらく来れない時に限ってあんな所におるんだね。酷いもんだったんじゃよ?」ギギギと関節を擦り合わせながら両手を合わせて感謝のジェスチャーしてみせた。「言葉が理解できるのか?何と興味深い……」少しの間沈黙が続く。その時この部屋の出入り口をカリカリと引っ掻く音が聞こえてきた。聴覚を凝らせばニャーニャーと鳴き声が聞こえる。「あぁ、そうだそうだ。今回お前さんの状態があまりに酷かったからわしの研究所に運んだんじゃ。そしたらまぁついてくるついてくる。大きいのも小さいのもニャーニャー言いながら。結局みんな連れてきてしまったよ。こんな殺風景な研究所で目が覚めるのも味気ないと思ったしね」ブツブツと説明しながら出入り口を開ける。待ってましたと言わんばかりに猫や子猫達がなだれ込んできた。大きいのも小さいのも、白いのも黒いのもサバや茶トラもいた。そしてある猫は台の上に飛び乗る。ある猫は台の凹凸を使って器用によじ登る。登れずに鳴き声を上げる子猫は、老人がまとめて拾い上げ台の上に乗せた。固くて冷たい台が一瞬にして騒がしく、そして暖かくなった。
あの日目覚めた時に、枯れ葉の山から飛び出してきたハチワレに似た子猫が、鼻をフンフンと鳴らしてボクを嗅いでいる。その後ろには白いのと黒いのが2匹、照れた様に身を寄せ合ってこちらを覗き込んでいた。きっとあの日出会った猫達ではないんだと思う。けれどあの子達とこの子達の姿が重なって見えて、ボクは何だか嬉しくなった。ボンヤリとそんな事を考えているうちに、ボディの上を闊歩するやつもいれば、所々で寄りかかるものもいて、ボクは本当にネコにまみれてしまった。暖かいとはきっとこういう事なんだろう。冷たいはずのボディに熱が生まれる。今までありがとうみんな。
何でボクはこんな事を思っているんだろう。そういえば段々と映像が白黒になってきて、周りにいる猫達がみんな同じ色や柄に見えてくる。ああ。きっとまたスリープモードになっていくんだろうなと思った。しかしいつもの様に視界が狭くなるというわけではなく、ボクは猫達に出会う前のひとりぼっちだった時のことを思い出していた。目の前の映像は点いたり消えたりし始める。そういえば猫達と森の中を歩いて、ハチワレと黒のお墓に行った時に見た海はとてもキラキラしていた。映像の乱れは段々と酷くなってくる。手足のパーツが思うように動かないのはなぜだろうか?スリープから目覚める事が苦痛だった。しかし、今では目を覚ませば沢山の猫達がいる。知らない間に人間の老人とも知り合った。穏やかな気分だ。
「そろそろかもしれんなぁ」老人は呟く。「お前さん。そろそろ本当の眠りにつく時が来たようじゃよ」ボクは何となくその言葉の意味が理解できた。何故かと聞かれたら分からないけれど、何だかそんな気がしていたから。「おまえさんはな、いつ、何故作られたか分からないくらい昔から生きている。正直言ってどういう技術をもってしてお前さんが動いているのかが全くわからんのじゃ。この研究所を作ってからワシも何度も分解して修理しようかと思った。しかし、今日に至るまでワシは、お前さんを動かし続けられるほどの技術を得る事はできなかった」老人は悔しそうに奥歯を噛み締めている。「ダメ元で分解するという事も考えた。でもな。沢山の猫達に囲まれて安らかに眠るお前さんを見ているとそんな事をしてはならないと思った」そう言いながらボディにそっと手を添える。ああ。この老人は優しい暖かい人間なんだ。そう思うと温度が少し上がった気がして急に目の前の映像が鮮明になった。
まん丸のメガネをかけた老人がボクを覗き込む。色んな大きさや柄の猫達も同じ様に覗き込んでいる。ボクはたくさんの瞳に見つめられ、何だか嬉しくなった。そして思う。
生まれた理由や、生きる理由は無かったけれど、生きた理由が今ここにできたなぁと。
「ミンナ…アリガトウ」
ボクの声はボクを見つめてくれているモノ達に届いただろうか?届いていたらいいな。そう思った。
物言わぬはずのロボットが声を発した事、それが感謝の言葉だった事に老人はうっすらと涙をこぼす。そして溢れた涙が頬と顎を伝い、雫となってハチワレの子猫の額にピシャンと落ちる。子猫は何事かと目をまん丸にし顔をブルブルと振るわせると、小さな頭をグルリと老人の方に向け、ニャッと短く泣いた。「すまんかったすまんかった」少し乱暴に子猫を撫でる。ハチワレの子猫は喉を鳴らし始めた。可愛らしい抗議の声も、撫でられる気持ちよさには勝てなかったらしい。老人はメガネをずらして目元の涙を拭いロボットに視線を戻す。そこには電気反応が完全に切れてしまった器だけが、目から液体を流し横たわっていた。
老人は今海の見える丘にいる。ハチワレや黒といった、ここで生きてきた猫達が帰る場所。動かなくなったロボットは、老人の研究所で今も眠っている。もしかしたらいつか目を覚ますかもしれないと老人は思っているが、自分が生きている間にその時が来るかどうかなんて全くわからない。もしかしたら一生起きないかもしれないし、今この瞬間に目を覚ましているかもしれない。果たしてロボットは今何を思って研究所で眠っているのだろうか?
「わしには見当もつかんなぁ」
ボソリと1人呟き、柔らかな地面にバタリと仰向けになると、少しの間、波の音を聞き、海風を感じていた。突然老人の視界にニョキリと茶トラの子猫が現れ、目を丸くして老人の顔をジーッとみつめている。顎に置かれた前足には、柔らかな肉球と、子猫だというのに妙に鋭い爪があって、温もりと、チクリとした痛みが走る。掌に収まるくらい頼りない命なのに、確かに、確かにこの子猫は、今この瞬間を生きている。人差し指でとても小さな額をくすぐると、茶トラはうっとりと目を細めた。
「気持ちいいかい?」
老人が尋ねると、子猫はニャッと短く鳴き、喉を鳴らし始め目を閉じる。ロボットが眠りについた時、たくさんの猫達に囲まれていたのを思い出す。もしかしたらその光景が映像としてロボットのメモリーに焼きついているかもしれない。そんなことを思いながら子猫を撫で老人が呟く。
「いい夢を見てくれよ」
子猫が鳴き声を上げずに鳴いた。
終わり
©︎yasu2023
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
