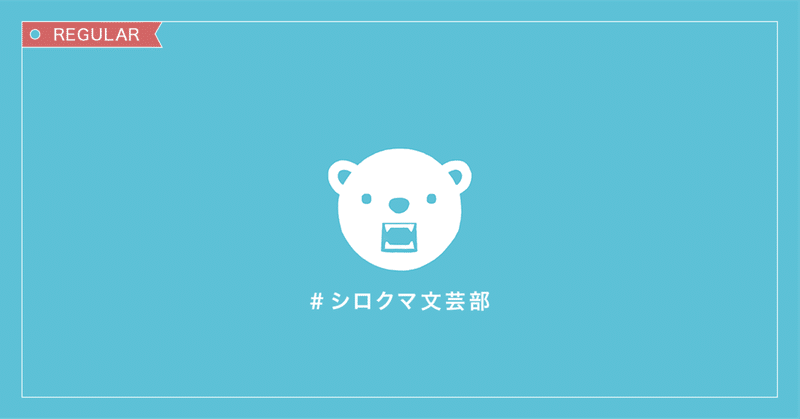
ガトーじい(#シロクマ文芸部)
「ありがとう。いい天気ですな。お達者で」
冬空をかさかさ擦る調子っぱずれの声が、通りの向こうから聞こえた。
「おい、あれ」
ハットがランドセルの上からぼくに寄りかかり、南公園の入り口にたたずむ老人を指さす。ぼくたちは下校途中だった。
よれよれのスーツにトレンチコート、深緑の毛糸の帽子をかぶり、足もとには柴犬が行儀よくお座りしている。老人はブランコを漕いでいる幼稚園児に平坦な声で「ありがとう」というと、またすたすたと歩き出す。左手には黒いかばん、右手はリードを握っている。老人の歩調に合わせ半歩先を行く犬は、冬の夕日に茶色い毛を波立たせていた。
「よし、つけるぞ」
ハットが命令する。ぼくの隣でタコが「げえっ」とささやく。
小学四年生にしてすでに身長が150センチあるハットに逆らえるやつなどいない。ぼくたちのあだ名もハットがつけた。
田口公介(たぐち こうすけ)だからタコ。ぼく浅田凛太朗(あさだ りんたろう)はアリ。ハット流あだ名ルールは、省略だ。それに従うと、本田隼人は「ハト」になると思うんだけど。「隼人だからハットと呼べ」だって。自分だけかっこよくて、ずるいよな。言わないけど。
――「ありがとう」を言って回る変なおじいさんがいる。
二組で誰かが言いだし、あっというまに広まった。「ぼくも見た」「あたしも」なんて声が、ぽつぽつとサイダーの泡みたいに、あとからあとから発生した。こんな一大ニュースに乗り遅れるなんてハットに許せるわけがない。「真相を確かめる」と言い出した。ぼくはタコと顔を見合わせてため息をつく。巻き込まれるのは百パーセント確定だ。
「ランドセルを置いたら公園に集合な」
校門でハットが提案(実質は命令)したけど、その必要はなかったみたいだ。あっさりと噂の人物が見つかるなんて、ラッキーと思った。これでハットも満足だろう。今日は寒いし帰ったら家でプレステをしよう……と胸をなでおろしたのもつかのま、尾行するだって!
ぼくの肩をつかむハットの手に力がこもる。
「いいか。気づかれないよう、姿勢を低くしろよ」
自分が一番目立ってるくせに。ぼくは内心で毒づく。
尾行してすぐにわかったのは、老人は誰かと出会うと、『きをつけ』みたいに両手を脇にぴたりと付け、「ありがとう。いい天気ですな。お達者で」と言う。人だけじゃない。すれ違う犬や猫にまで、ぴしっとアイロンをあてたような姿勢であいさつする。小型犬を連れている人はさっと犬を抱きあげ、大型犬はリードを引っ張られて、そそくさと通り過ぎる。ベビーカーを押しているママは、顔を伏せながら老人の横をすり抜け、すごい勢いでベビーカーを押して去っていった。誰もおじいさんの「ありがとう」に応えない。猫がにゃあと返事したくらいだ。
「なあ、あのじいさん、おれらにも、ありがとうって言うかな」
実験しよう、とハットがいう。いやな予感しかない。こういうことを思いつくのはいつもハットで、犠牲になるのはいつだって、ぼくだ。
「アリ、おまえ、走ってじいさんの前に回れ」
「ほら、早く行けよ」と、ぼくの背中を押す。
ゆるい下り坂をぼくは、はっ、はっ、はっと跳ねるように走る。背中で筆箱がかたかた鳴る。老人の横を駆け抜けるときスピードを落としたけれど、ぼくが通り過ぎるのに気づいていないのか、前を向いてすたすた歩く。正面にしか関心がないみたいだ。
5メートルぐらい先でくるりとUターンした。膝に両手をついて呼吸を整える。まだ息が荒かったけど、老人と柴犬に向かって歩き出す。心臓がぐでんぐでんとうねった。
あと1メートルのところまで近づくと、おじいさんはぴたっと止まった。ぼくもつられて、きをつけの姿勢で立ち止まる。
「ありがとう。いい天気ですな。お達者で」
ぼくに向けられている瞳はおだやかで、それだけ言うと、またすたすたと歩き出した。
ぼくは唇だけで「ありがとう」と返し、きをつけの姿勢のまま立ちつくしていた。耳を擦る北風が冷たくてしかたなかったのに、胸のあたりはふわふわしていた。
「じゃ、次、おれな」
棒立ちのままのぼくの肩をハットは、軽く小突いて走りだした。
「お疲れ」とタコに声をかけられて、ぼくはようやく我に返った。
「どうだった?」と訊かれたけれど、「うん」としか答えられなかった。
「ここで解散だね」
最後に実験をしたタコが戻って来ると、ぼくは当然のように切り出した。もう夕日も力を失いつつある。
「なに言ってんだ。最後までやり遂げなきゃ意味ないだろ」
タコが、しょうがないよ、と首をふる。
2メートルぐらいの距離を保ちながら、ぼくらは老人と犬の後ろを歩く。分かれ道になると犬が「こっち」とでもいうように、先に進む。
「あの犬、道案内してる?」
「今ごろ気づいたのか」
ハットが鼻をふくらませ目を泳がせる。
――気づいてなかったっぽいよ。
タコがぼくに耳打ちする。ぼくもそう思う。ま、いいけどね。
T字路を右に曲がる。『北山』という表札がコンクリートの門についている家の前で、老人は立ち止まった。前から歩いてくる人も犬も猫もいない。門扉に手をかけている。
「よその家に入るよ」
「ちょっとまずくない?」
「止めるか」
ハットが走り出そうとしたときだ。
後から甲高い声と足音が聞こえた。
「あらお父さん、お帰りなさい。早かったのね」
エコバッグを提げたおばさんが駆け寄る。柴犬がその足にじゃれつく。老人はかまうことなく門扉を開け、家に入っていった。
急にランドセルが重くなった。ハットがぼくとタコのランドセルの上にのしかかっている。耳が赤い。
「よしっ。じゃあ、解散」
バンと、ぼくたちのランドセルを叩いて走り去る。高い背に不釣り合いなランドセルが揺れていた。
「今日もガトーじいを尾行するぞ」
校門のところでハットが宣告する。
「なんで、また?」
「ルートは一つとは限らねえじゃん」
これは飽きるまで続くパターンだと観念した。タコも苦笑してる。
「ガトーじいって誰?」
想像はついたけど、たずねてみる。
「昨日のじいさんさ。『ありがとうじいさん』じゃ面倒くせえだろ。略してガトーじいだ」
ガトーじいと犬はまた、南公園の前にいた。
「ありがとう。いい天気ですな。お達者で」
今日は誰にあいさつしてるんだろう。
ガトーじいの尾行が、ぼくらのタスクになって一週間が過ぎたころだ。
前日に降った雪がまだ道路の隅にところどころ残っていた。ぼくらは黒く汚れてぐしゃぐしゃのシャーベットを蹴散らしながら尾行していた。いつものハットなら、とっくに飽きて別のことに興味が移ってもよさそうなのに、なぜか尾行を止めようと言いださない。
公園の先はゆるい下り坂になっている。
あっと思ったときには、遅かった。
どん! と鈍い音を立てて、ガトーじいが滑って倒れた。
ワンワン、ワン、ワン。犬が激しく吠える。
ハットが転がるように走り出す。ぼくとタコが追いかける。
頭から血が流れていた。
「ガトーじい、ガトーじい、ガトーじいぃい」
ハットが涙で顔をぐしゃぐしゃにしながら叫ぶ。
「揺らしちゃだめだ」
ぼくは必死でハットを押さえる。タコがハンカチで傷口を押さえる。
「君たち、ありがとう。救急車を呼んだから」
えっ。ぼくは顔をあげる。
北山のおばさんが立っていた。タコに変わって頭の傷口を押さえる。
「お父さんを見守ってくれて、ありがとう」
膝の上にガトーじいの頭を乗せながら、ぼくらを順に見つめる。
「どうして、知って……」
「ぼくたちの後ろからついて来てましたよね」タコがいう。
あ、だからか。さっき一瞬、タコは後ろを振り返った。おばさんが後ろにいることに気づいてたんだ。
「一人で散歩させるのは危ないし、トラブルになっても困るでしょ。でも、本人は会社に行ってるつもりだったから。離れて見守ってたの。道をまちがえないようハナをお供につけてたけど、それだけじゃね」
柴犬のハナはガトーじいの顔を一生懸命なめている。
うぐっ、ひっく、うぐっ。
「ぼくのじいちゃんも……ぼくのじいちゃんも……」
ハットがしゃくりあげる。こんなに泣いているハットは初めてだ。
「心配かけてごめんね。怖い思いをさせてごめんね。きっと大丈夫だから」
ピーポーピーポー。サイレンの音が近づく。
タコが算数のノートを一枚ちぎって何かを書いていた。
「ぼくんちの電話番号です」
「ありがとう。連絡するから。君たちも気をつけて帰ってね」
その晩遅くに、タコから電話があった。命に別状はなく、頭の傷もたいしたことはなかったらしい。ただし、腰の骨が折れたから、もう歩けないんだって。ガトーじいの「ありがとう」がもう聞けないね。タコは寂しそうにいって電話を切った。
「退院したから」と、北山さんからタコに連絡があった。
「ガトーじいね、明日から施設に入るんだって」
もともと施設の空きを待っていたそうだ。最後に散歩に付きあってほしいと、北山さんに頼まれたという。
南公園の前に車椅子と柴犬がいた。
「心配をかけてごめんなさいね。君たちのおかげで助かったから、最後にお礼が言いたくて。認知症が進んでるんで、わかってないとは思うけど、きっと父もお礼が言いたいと思うの」
北山のおばさんが、「ありがとう」と頭をさげた。
ぼくらは変わりばんこに車椅子を押した。前から誰かが来るたびに車椅子を止めたけれど、ガトーじいが「ありがとう。いい天気ですね。お達者で」と言うことはなかった。ぼくらのことも覚えてないだろう。尾行をしていたときだって、たぶん、ぼくらに気づいていなかったにちがいない。それでもいいと、ぼくは思った。
T字路を右に曲がる。
ぼくたちは車椅子を止めて、北山家の門の前に整列する。
「ありがとう。ガトーじい」
ハットの声がふるえる。ぼくたちは互いに目配せして声を合わせる。
「ありがとう。いい天気ですね。お達者で」
ぼくら三人の声はてんでばらばらにふるえてちぎれる。ぼくはぐいっと左腕で涙をぬぐいながら、最後の「お達者で」で涙がこらえられなくなった。
それまで無表情だったガトーじいが、車椅子の両袖をしわくちゃの手で握って立ち上がろうとする。おばさんが慌てて駆け寄る。背中を支えようとするおばさんの手を払いのけ、両手を脇にぴしっと添わせ背筋を伸ばしてきをつけをする。世界でいちばん美しいきをつけだ。
「ありがとう。諸君。またあした」
<了>
…………………………………………………………………………………………………………………
今回も、またまた、ギリギリに。
小牧部長様、いつもありがとうございます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
サポートをいただけたら、勇気と元気がわいて、 これほどウレシイことはありません♡
