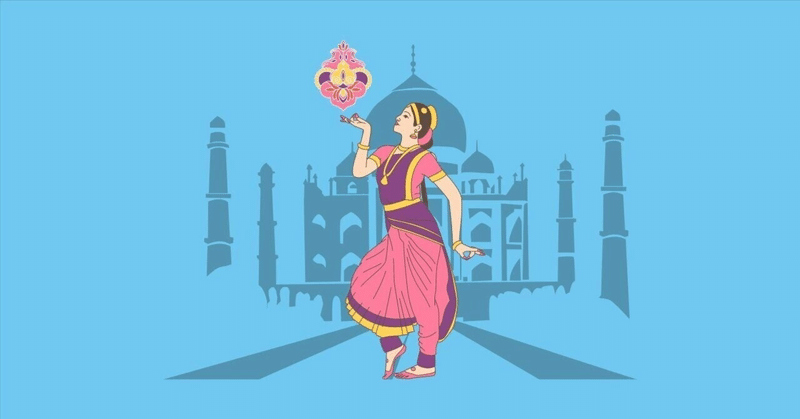
【翻訳】F・W・ベインの印度物語 ~日輪の堕落~ ①
日輪の堕落
The Descent Of The Sun
英訳:フランシス・ウィリアム・ベイン
和訳:弾青娥
註のそれぞれの詳しい内容は以下のnote記事にまとめています。別窓でご覧くだされば幸いです。
邪なる眼
神への祈り
おお、栄光と無限をつかさどられる〈平穏の精神〉よ、〈苦行者たちの王〉よ。踊り狂われる姿をお見せになり、ぐるりと回られれば、まるで蒼穹に色を加えていらっしゃるかのよう。この蒼穹の鏡に反射するのは、御神の喉もとの青色と、御神の黄褐色のもつれた髪のふさを飾る銀色の三日月。御神を、我々はあがめる。そして、絶えず勝利を象徴する〈象たちの象〉の鼻にも我々は帰依する。御神の鋭い怒りの目つきは、燃える森が枯れ草をしなびさせるように、数えきれぬほどに群れをなす煩わしい障害を焼きつくす。
はるか昔のこと。ヒマーラヤの斜面に、うら若い〈空気の精の王〉が暮らしていた。その名はカマラミトラといい、日輪の一部をつかさどっていた。そのようなカマラミトラは、ウマーの夫を崇拝していた。五感で覚える喜びを拒み、カイラーサの氷のごとく冷たい峰と高原に囲まれるなか、独りで生きていた。カマラミトラはそこにとどまると、まずは葉の上に、次に煙の上にのっかり、それからようやく大気を漂い、おぞましく厳しい苦行に励んだ。そうして、百年たってからのこと。〈創造物の主〉は御心を動かされて、カマラミトラを憐れむようになられた。御神は、黄昏時にこの者のもとにご示現なさった。苦行者の姿をとられていたが、高い木を思わせるほどの背丈で、御髪にあの新月をまとっていらっしゃった。御神は仰った。
「お主の帰依は喜ばしい。それゆえ、願いを叶えてやろう。言うがよい」
それを聞いた若い王は御神の前で頭を垂れ、
「祝福されしお方よ、このまま御神の瞑想をさせてくださいませ。それで十分でございます」
と言上した。それをお聞きになると、マヘーシュヴァラが、
「さすがだ。とはいえ、我に対する願い事はないか」
と、お尋ねになった。すると、カマラミトラは答えた。
「そう仰るのでしたら、決断をくださねばなりません。では、私に妻を――ここの丘という丘のように、そしてこの空のように、御神の喉と御神の月の黒ずんだ輝きを両目に余すところなく宿す妻を授けてください。その目というのも、飽きることなく御神を見つめ、つかの間の鏡でなく御神の栄光に永遠に染まった絵にあたかも化したようなものです。この者には、私と御神の信心の絆をとりもつ存在になってほしいのです」
月の紋章をまとう御神は、その言葉にご欣快の至りであった。しかし、不思議な予知能力をもって、御神は未来をのぞきこみ、この先がどうなるかをお確かめになった。それから、ゆっくりとこう仰った。
「このような目は危険をもたらそう。それは他者に対してばかりでなく、その目を有するものにとっても同様だ。だが、願いを叶えてやった。ゆえに、お主の願ったものを得られよう」
そうお告げになった後、御神は姿を消された。カマラミトラは喜び勇んで住まいに帰った。御神の寵愛により、やつれた様子も、疲れた様子もすっかりなくなり、ビマのように強く、アルジュナのように麗しくなった。明くる日の夕暮れに自らの宮殿に着いたカマラミトラは、日輪が沈みゆくさなか、休息をとるべく庭園へと足をのばした。足を進めると、突如としてカマラミトラの目は一人の女の姿をとらえた。銀の櫂がついた白檀材の舟に乗った女は、白い蓮の花がたくさん見える小さな池を漂っていた。女の視線は、その雪白の蓮という蓮に注がれていた。伏したその目の色合いは青に変わった。横になった女は片手で頬杖をつくと、もう片方の手で血のごとく赤い蓮の花びらを一枚ずつ水面に落としていった。女の腰の、丸みをおびた曲線は砂州のごとく立ち上がり、しかも波立たぬ下方の水面に映し出されていた。女の唇は動いていた。花びらを落とす際、女はその枚数を数えていたのである。
一方、これを夢だと思ったカマラミトラは立ちつくしていた。息をひそめ、女をじっと見つめたまま、身じろぐこともできなかった。そのような中、女がいきなり視線を上げ、己の目で男の姿をとらえると、ほほえみかけた。男は、女の目が宿す色に包まれた。カマラミトラは、世界中のあらゆる青い蓮の真髄から形作られた色の海に立っているような心地だった。急に、カマラミトラは天をまとう御神からの恩恵のことを思い出し、大きな声でこう言った。
「貴方は契りを破ることのない御神によって遣われた者にちがいない。その上、まさしく私の妻であろう。再び日輪が昇りだす前に御神の栄光を見つめていた私が、今や貴方の両目を見つめている。どちらとも同じことだ。もしそうであれば、貴方を何と呼ぼうか」
そう聞かれると、女は言った。
「わたしはアヌシャイニーと申します。〈創造主〉は、どんな目的でこの目をこしらえたのでしょうか。その目をご創造なさった君主の姿を映すほかにあるのでしょうか」
カマラミトラはこうして御神から女を賜ると、かわいい愛妻を自らのものにした。それから女といっしょにカイラーサの周辺にとどまった。女の大きな双眸という御神のあの双鏡をたえずじっと見た若い王の気は動転し、有頂天になっていた。その目の成す海に飛びこみ、その中にどっぷりと浸かっていた。全世界が蓮の青でできているように、カマラミトラには思われた。やがて、水をなみなみと注がれ、それを容れきれなくなった器のごとく、女の美に対する王の喜びと、たぐいまれなる女の鑑を独り占めしているという誇りがあふれ出した。それゆえ、感情を抑えられなくなった王はその気持ちを和らげようと、足を運んだいたる場所で女のことを話した。そうすることで、世界じゅうの他の女たちがほかならぬ自分の妻と比べればまったくもって他愛ないと――これがカマラミトラの考えだった――全員に認めさせようとした。ああ、何と凄愴であろうか! 女と解脱は、まったくの別物である。
やがて、ある日のことだ。王は自らの友の一人とあの女のことを話し合っていた。が、その友は王の妻に対する、ありとある称賛の言葉をかたくなに認めようとしなかったため、王は友を罵った。すると、この者は出し抜けに笑い、強い口調でこう語った。
「何事に対しても、治療の薬がある。蛇に咬まれた傷にも、治療の薬がある。だが、女の美に咬まれてしまった者なら話は別だ。ああ、恋にのぼせあがった者よ、心に刻むとよい。我らにとっての〈片割れ〉であり、〈男〉を写しとった存在である〈女〉の優れた魅力とは、簡素な音楽の主旋律ではない。たとえるなら、幾万もの音をたずさえて、攪拌するための棒のごとく男の魂という大洋のなかに宿るすべての感情をかき立てる、限りなく多様な主旋律だ。お前の妻の目がどれほど麗しかろうと、目は目でしかない。だが、女は目だけの存在ではない。魅力は他にもある。滝のように、泡立つような音楽という嬌笑で男を魅了する女もいれば、森のなかの池のように、得体の知れない沈黙という静けさで男を忘我の境にさまよわせる女もいる。ヤマのように、自らの髪という甘露の香をただよわせる縄で男を絡めとる女もいる一方で、マノバヴァのように、毒を秘めた眼差しという弓矢の術で男の心を射貫く女もいる。日輪のように、病的な欲望という熱病のごとき火で男を燃やす女もいるが、月輪のように、露を思わせる口づけという樟脳の香りで男をなだめる女もいる。そして男は、女の邪悪さという痛烈な一刺しで牡牛のようにけしかけられ、別の女の純粋さという狡猾な呪文によって象のように懐柔される。加えて、男は乙女の両腕という木陰の魅力に鳥のごとくおびき寄せられ、別の乙女の唇という蜜の近くで蜜蜂のようにとどまってそれを少しずつ吸う。男は乙女の腰という華奢な茎に、蛇のようにぐるぐると巻きついて、挙句には別の乙女の胸という生ける枕に、疲れ果てた旅人のように頭をのせて眠りたがるのだ」
すると、カマラミトラはしびれを切らし、
「過去、現在、未来における三界のあらゆる女の魅力は忘れるがよい! その女たちが力を合わせ、ほかならぬ愛の神の肉体を形作ることができようか。しかし、アヌシャイニーの両目こそが、カウダルパに敵対する者の目がそうしたように、その存在を灰燼に帰すだろう。然り、抗いがたい青の誘惑の力を宿すあの両目であれば、メーナカー、ティローッタマーといった者たちが実現できなかった、聖仙の堕落を成し得るだろう」
と言って、友の話に割り込むのだった。
これを聞いた友は、嘲る調子で笑い声を上げ、こう言った。
「むなしい自慢だ。口でなら、男は誰でも何事をも成せ、女は誰もが第二のラムバーになる。あの女の美しさのことで無駄口をこれ以上たたいてならない。だが、お前の妻の鑑の力を試そうではないか。ここからそう遠くない、丘の中腹の森に、パーパナーシャナという聖仙がいる。この者の苦行には神々さえも慄いている。よどみのないお前の話の上では泡沫のごとく美しさを湛える、立派な妻の目がいかほどのものかを見事に見極めるだろう」
カマラミトラはその挑発に乗り、赫怒しながら強い調子で口にした。
「莫迦め! 琥珀が刈り株と草を引きよせるほど容易に、アヌシャイニーがあの者を苦行に専心するのを止められないのならば、まさにこの首を刎ねてガンジス川へと投げ入れようではないか」
これを聞いた友は再び笑い、
「無茶なことはするものではない。お前はダクシャではないのだから。斬首すれば、頭は決して取り戻せない」
と言った。ところが、カマラミトラはその場を匆々と去ってアヌシャイニーをさがした。その者を見つけたのは、蓮が浮かぶ池のそばの庭でのことだった。カマラミトラは自分が己の妻を自慢したことを明かすと、こう告げた。
「すぐに来てくれ。一刻も早く、その素敵な両目に貴方が宿す力を試して、力が実際にあると、そしてその力に対する我が信仰が真のものだと証明しよう。目に宿る力の実証を果たし、あの疑り深い愚か者に、自らの浅はかな過ちを悟らせずにはいられないのだ」
その言葉を聞いたアヌシャイニーは、落ち着いた口調で言った。
「旦那様。怒りに駆られ、そのせいで分別がつかなくなりましたね。悪行を働くことで、私たちに罰が当たるのではありませんか。オリオン座がローヒニーのすぐ後を追うのが確固たることであるように、罪滅ぼしをなした後には罪が生じます。このように軽率にことを試すとなれば、罪を犯して危機に直面します。あえて断崖のへりのような危殆に瀕するのは私たちのためになりません。危険を冒せば、取り返しのつかない災いへと真っ逆さまに落ちることでしょう」
そう話す一方、アヌシャイニーの目はカマラミトラに向けられていた。その視線で気が動転したカマラミトラに、女の言葉に宿る説得力は絶無になっていた。というのも、女の言ったことが何も耳に入らなかったが、分別が一切つかなくなって熱情に充たされ、アヌシャイニーの美しさに無限の力があると今まで以上に確信したためだった。そうして、夫の意志を変えられないと悟ると、アヌシャイニーは屈服し、自らの神であるように夫に従った。むしろ、夫の考えを変えられないと知った女は心の奥で喜んでいた。女自身が、自らの美がその苦行者に実際に打ち勝てるかどうか、興味津々であったのである。とはいえ、招きうる結果について懸念はあった。ああ、無念だ! 美、好奇心、若さ、頑固な思い、絶頂の歓喜が、狂える象のように組み合わさるのならば、自制という綿糸はいずこにあるであろうか。
やがて、慕い合う二人は情熱の口づけを交わした。引き離されて一年が経った旅人たちのようだった。それでも、彼らはそうしていられるのがこれで最後だとは知る由もなかった。二人はいっしょに森へと向かい、あの年老いた苦行者をさがした。手を取り合ってぶらりと歩いていたが、その様は人間の姿をとった〈愛〉の矢の一対を思わせ、そのような矢はその森のまさに中心まで到達していた。すると突如として、二人はその老齢の苦行者に遭遇した。直立の姿勢で瞑想に入って木のごとく動かぬ様子であった。この者のまわりでは、蟻が塚をいくつも築き上げていたが、苦行者の鬚と毛髪は頭から蔓のごとく伸び、地面に沿う形で流れ落ちるかのようで、地に触れた髪は葉という葉で覆われていた。男のか細い両腕じゅうを駆けまわるように、生ける翠玉を彷彿とさせる、つがいの蜥蜴が戯れていた。万物を鏡のごとく映す大きな双眸で、男はしっかりと眼前を見た。ところが、何も見えず、その目はありとある魚が眠っている山中の湖のように澄み、測れぬほど深く、穏やかな水面のようだった。
カマラミトラとアヌシャイニーは言葉を発さずにしばらく苦行者を目にした後、互いに目をやると、身震いした。己の魂を賭けているとの自覚があったのである。だが、カマラミトラの心が揺らぐなか、自らの友から虚仮にされたことが思い出された。そして、怒りが王を満たした。そこで、アヌシャイニーにこう言った。
「近くに寄って、この老いたムニに貴方の姿を見せよ。我はその結果をじっと見守ろう」
その命に従ったアヌシャイニーは前に歩み出て、葉よりも軽い足で葉を踏んだ。それから、女は聖仙の前に立った。男が動かないと認めると、男の両目を覗きこもうと、つま先立ちの格好になった。
「もしかすると、この方は息絶えているのでしょう」
と、女は自分に言い聞かせていた。両目を覗きこんだところ、「気をつけよ」と言いそうな、臆病の化身を思わせる自分の姿しかその双眼に映されていなかった。不安で心の揺れる女が身を震わせながらその場に立っていると、カマラミトラは女を恍惚としてまじまじと見て、独り笑いをして、自らにこう言い聞かせた。
「この年老いたムニは息絶えて久しいのだろう。そうでなければアヌシャイニーは、下界にあるこの男の両目の扉を抜けて、その魂に触れることになったであろう」
二人が待ちながらその場にとどまっていると、その老齢の聖仙の意識が徐々に戻ってきた。自らの瞑想が何者かに邪魔を入れられているという感覚を抱いていたのである。そうして男が目を向けたところ、見えたのは一日を締めくくる新月のようなアヌシャイニーが目前に立ちはだかるさまだった。妙なる美がとる、穢れない形であれば、天の色を帯びた傷のない水晶でもあった。即座に、苦行者は己の瞑想による神通力をもって、あらゆる真相とその正確な状態とを見抜いた。次に、心の揺れ動く麗人めがけて一瞥を投げた。その一瞥は、鹿のそれのように悲しげなものでありながらも、落雷のごとく恐ろしいものでもあった。たちまち、女の魂からは勇気が、膝からは強靭さが消え失せ、女は風で折れた蓮の花のように頭を垂れ、地にへたりこんだ。
カマラミトラは、女のもとに駆け寄り、腕のなかに抱き止めた。いっしょになった二人を見て、この老いた苦行者は口を開き、彼らに呪いをかけると、ゆっくりとした口調でこう言った。
「不敬にも恋に溺れた者どもめ、かような無礼を働いた佳人は相応の報いをすぐに受けるだろう。罪を負った者どもよ、不可避の死をともなった子宮に身を落とすがよい。そして、人間の悲しみの炎に焼かれる罪を清めきるまで下界で別離の苦痛に苦しむがよい」
別離という悲運を耳にすると、二人は悲嘆に暮れて苦行者に対して跪き、
「せめて、この呪いの期限を、私どもの苦痛の長さをお決めください」
と懇願した。すると、苦行者は再び口を開いて、
「お前らのいずれかが相手を殺めれば、呪いは終わるであろう」
と告げたのである。
不幸に見舞われたその恋人たちは一言も発せぬほどに絶望し、互いを見つめた。二人はその刹那、相思相愛という、色の濃い甘露の霊薬を互いの目から引き出した。あたかも別離という恐ろしい海を行脚する彼らを励ますかのようで、いわば互いに「自分を忘れることなかれ」と語っているようだったが、徒労に終わった。やがて突然、二人は姿を消し、雷の閃光のごとくどこかへ行ってしまった。
一方、カイラーサに鎮座していたマヘーシュヴァラは二人の行方を目にしていらっしゃった。運悪くも、御神はその方向をご覧になっていた。神秘の直感でことの真相をすべて悟ると、〈空の精〉に施された恵みのことを思い出され、ご自身にこう言い聞かせられた。
「予見した未来が現在のこととなり、アヌシャイニーの青い双眸が大いなる災いをもたらした。だが、この者の麗しい肉体には我が神威のかけらが宿っているゆえ、これを偶然の戯れに委ねるわけにはいかぬ。結局のところ、カマラミトラに大いに責めを負うべきでなかった。あの女の双眸に映った我が栄光に狼狽したのだから。ゆえに、責めを負うべきは我であり、この現状の原因は我にある。そして、恋の身にあるこの者らを見守らねばならぬ。さらに言えば、二人の冒険をもって大いに楽しみたい思いもある」
そのようにお思いになった〈瑜伽の匠〉は、しばらく考えを巡らせたのち、一輪の蓮の花を手にとり、僻地の海にお据えになった。すると、その花は島になった。御神は、天を思わせる存在をそっくり写し、ご自身にしか知られていない天性をもった地上の生物を、展開される未来のために、魔力によってその島に創造なさった。手筈を整えられると、御神は一連の出来事の成り行きにお任せになった。
一方、老齢の聖仙パーパナーシャナだが、恋仲の二人の姿が消えると、独りでその森にとどまった。二人の姿形はこの男の両目に映し出されなくなり、縹渺たる湖の水面の上を駆ける雲の影のように、男の心から消えていくと、やがて消散し、完全に忘れ去られた。
序章 完
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
