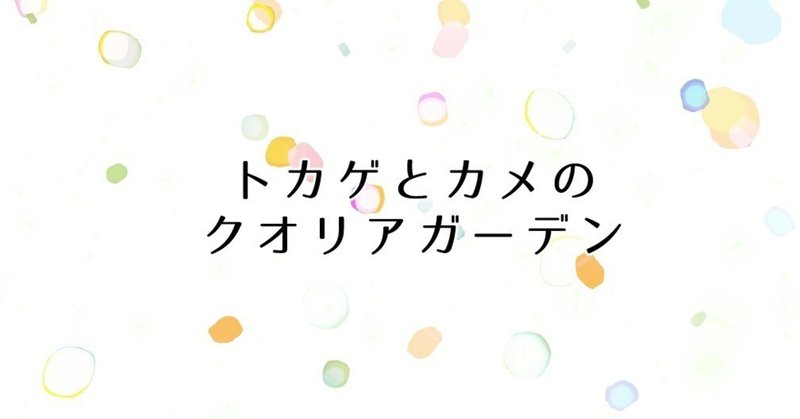
ハネモノ通り1
(目次に戻る)
保健室を出ると森石が廊下で立ち止まる。
見れば、壁にもたれるようにして岡村が立っていた。
俺たちに気づいて岡村が壁から離れる。その手には俺の鞄と森石のリュックを持っていた。
「森石、おはよう。というか、もうお昼だからこんにちはだよな」
無言のまま睨みつけてくる森石の視線を受けて、岡村が頬をかきながら苦笑する。
「岡村? なんでここに」
「花柴の使いっ走りだよ。二人が保健室にいるだろうから持って行ってくれってさ。怪我は平気なのか?」
渡された二人分の荷物を受け取ると、岡村が森石を気遣ったが好ましくは思われていないことがわかって、肩を竦めた。
これはフォローしなければ。
「平気ではなさそうだから、先に帰るよ。ありがとう」
「おっけー。今度でいいけど、事情は説明してくれるのか?」
「森石がさっき養護教諭に喋ってたから、そのうち情報が流れてくると思うよ」
「俺は森石か松毬からの説明が欲しいんだけどな」
これはなかなか難しいことを仰る。
しかしながら、そのやり方は嫌いじゃない。人から回ってくる情報はよくも悪くも補正が入っている。見えている景色も同じようでいて全く変わってしまうのだ。
「考えておくよ」
持っていたリュックを森石が軽く引っ張った。
井戸端会議でうんざりしている子どもが似たようなことをするなと思いながら、俺は眉尻を下げる。
岡村はそれだけで察してくれたらしい。「わかったよ」と頷いた。
「気をつけて帰れよ」
「そうする。できたら、教師に俺たちのことをうまく言っておいてくれると嬉しい」
「松毬の頼みだからな。任せろ」
本音としては事情を聞きたくて堪らないのだろうが、これで引き下がる辺り岡村は本当にいい奴だ。
何度か背後を振り返りながら森石が俺の隣を歩く。下駄箱についたところで、「自分で持つ」と再び森石がリュックの紐を引っ張った。
「怪我人に持たせるわけにはいかないよ」
「いや、曲解されると面倒だからだ」
森石が校門を示した。
わあ、嫌な予感しかしない。
学校の前に車が一台止まっていた。さすがに校門の前は難しかったらしく、右端に車体の後ろが見える程度だ。パステルピンクの丸みを帯びたリアに、やたらリアルなシロクマのステッカーが貼られていた。
「知り合いの車?」
「父の会社の人間に同じ車を持っている人間がいる」
「実家の方で何かあったとかじゃないの?」
「そうだとしたら、僕との約束を破ってでも学校に乗り込んで来るのが羽衣だ」
森石から何度か聞いたことある名前に記憶を探る。
二人の関係性は森石から言わせるとよくわからないとのことだったが、一応、森石の父親に雇われている人間だそうだ。
「避けたいなら裏門使うけど?」
「避けたいわけではない。ただ、松毬と会わせていいのかどうかがわからない」
「それなら、一人で帰るけど」
「嫌だ」
俺が言い終わらない内に、森石が言い放つ。
「お、おう」
今日の森石さん、いつもより意志が強いね。
俺の隣で考え込んでいた森石は、仕方がないと頷いた。
「タクシー代わりにしよう」
「それ大丈夫なの?」
「僕は早く帰りたい」
お腹が空いたと定番の一言を森石が付け加える。
校門の前まで来ると車がゆっくりとバックして、森石の前で止まる。車はウサギの名を持つ軽自動車だった。女性向けでは人気の車体である。
傷やへこみはあるものの塗装だけはしっかりをしているのを見ると、持ち主は随分と大事にしているようだ。
「松毬はそのまま後ろに乗って欲しい。話はしてあるが、もしも余計なことをされそうだったら、先に手を出してくれても構わない」
「そんな危険人物なの?」
「僕以外はどうなっても構わないと公言する人間だ」
「それは危険だね」
乗り込んだ森石の少し後に中に乗り込む。
「お疲れのようですが、そろそろ私の出番ですか?」
開口一番そんなことを言ったのは、運転席に座る女だ。布を一枚身体に巻き付けただけの服装に、インドの民族衣装を思い出した。
見覚えのある顔だと思ったら、いつだったか俺を尾行してきたおばさんだった。その時はスーツ姿で化粧も薄かったが、今回は口紅も含めてハッキリした色を使っているせいか前より色気がある。
「頼みたいことはあるが、君の求めるものではない」羽衣おばさんの見た目に何も触れずにシートベルトを締めた森石は、シートにもたれかかりながら気怠げに答えた。「あと、松毬を無視するな」
「無視ではありません。つい睨みつけてしまいそうになるのを耐えるために、あえて見ないだけです」
「つまり挨拶もできないということか?」
バックミラー越しに視線が絡む。羽衣おばさんは薄らと赤みを帯びた目の色をしていた。
最初に会った時には繋がれた猛獣のような苛烈さを向けられたが、今はすっかり大人しい。手綱の持ち主が隣に座っているからだろう。
忠犬みたいだな。
「ごきげんよう。松毬さん。気分はどうですか?」
忠犬かと思ったら駄犬だな、これ。
ロボットの方がまだうまく話せると思える棒読みである。駄犬相手に怒るのはよくない。俺は寛大な心で微笑んだ。
「意外なところで再会できて嬉しいよ」
「そうですか。私も嬉しいです」
一切笑いもせずにそこまでいうと、羽衣おばさんは森石を見た。
「どうですか?」
「僕が悪かった」
「謝らないでください。すべては後ろの席に座るトカゲが悪いのです」
トカゲというのは俺が地元で好んで使っていた通り名である。わかっていて口にしているんだろうと思うと、頭を抱えたい気分だった。
怒りよりも恥ずかしさが強いのは、かのティラノサウルスが爬虫類だと勘違いしていたからこそ使っていた名前だからである。あの見た目で遺伝子学上はニワトリに近いと聞いて、そうなんだーと言える訳がない。
「松毬は人間だ」
その切り返しを聞く限り、俺がその通り名を使っていたことを森石は知らないようである。
黒歴史としか思えないので知らないのならよかった。
「失礼しました。しかしながら、トカゲの方が私にとっては好感が持てますので、ご容赦いただければと思います」
「動物園でも経営するつもりなのか?」
「そうですね。私の周りの動物どもは閉じ込めておく方が平和だと思います」
腹の辺りで手を組んだ森石が薄く笑った。
俺はそれと同じものを別の場所で見た気がした。少し考えて、去年のファミリーレストランだったことを思い出す。父親にそっくりだ。
「君は全く情の向けられない相手に、動物名はつけないだろう」
どう考えても動物呼ばわりは格下相手に使う気がするのだが、羽衣おばさんは随分とひねくれているようである。
「誤解です」
誤解です。少なくとも俺に関してはそうなので、心の中で羽衣おばさんに同意しておいた。
「それなら、優しさであることを僕は願う」
羽衣おばさんの真意はわからないが、森石の言い方がずるいことはわかった。
そんな風に言われてしまえば、実際はどうであれ迂闊に悪いことはできない。俺が夜道で後ろから刺される危険が減ったのは嬉しいが、羽衣おばさんとしてはあまりいい気分ではないだろう。
「私への頼みというのはそれですか?」
「いや。このまま家まで送って欲しい」
「もっと大きな事を願ってもいいんですよ?」
慣れた様子で車を発進させる羽衣おばさんを横目に、森石が目を閉じた。
「それはすでに叶えてもらった。君は僕がガラスを割ったから駆けつけ、それでも僕との約束を守って学校に乗り込むことはしなかった。松毬を攻撃することもせず、それだけ譲歩することが君にとってどれだけ難しいか、僕は知っている」
「褒め殺すつもりですか?」
「君は褒めて伸びるタイプだろう?」
「このまま誘拐しても構いませんか?」
「その正当性を説明して、僕を納得させることができたなら好きにすればいい」
物騒な単語が出てきたが、森石は慣れた様子で切り返した。
「誘拐?」
思わず反復すれば、森石が視線だけ投げた。
「羽衣の仕事は僕を誘拐することらしい」
いやいやいや。誘拐が仕事っていうのはいいとして、なんでそんな人間が森石のところで雇われているのかわからない。これが障害を取り除くための行為ならまだしも、誘拐対象が雇い主側の森石というのはおかしい。
「いいえ、これは仕事ではありません。私の生きがいです。貴方をより安全かつ幸福な場所に連れて行くためなら、私はいかなるものを利用しても構わないと思っています。今やっている仕事は、生きるための手段の一つであり、貴方の近くにいるための口実にしか過ぎません」
こいつ、さてはヤンデレだな。この手のタイプは一歩間違えると虐殺者待ったなしである。
「あくまで僕限定だから、これでも誘拐の前科はない」
「それ、森石は誘拐されたことがあるってこと?」
「誘拐そのものは何度もされたことがあるが、わかっていて抵抗しなかったのは羽衣が初めてだ」
「それだけ私のことを信頼してくれたということですね」
隠そうとしたが堪えきれなかったような笑みを零しながら、羽衣おばさんが頷いている。
隣で森石が肩を竦めた。
「数ヶ月ぶりに登校しようとしたものの、学校に入れず、かといって一人で大丈夫だと大見得切ったせいで家に帰ることもできなかったところに、羽衣が現れた。その時に家に誘われたんだが、どう見てもまともな状態ではないのはわかっていた。その時の僕もまともではなかった。最終的に僕は自分の我が儘のために羽衣を利用した」
「利害の一致に関しては否定しませんが、それだけではないでしょうに」
交差点で羽衣おばさんが左にハンドルを切った。帰り道を考えるなら右に曲がった方が近いはずだ。
ただ、それを指摘すると話が終わってしまう気がしたので、俺は黙ることにする。
「君は僕に対して盲目的すぎる」
「そうでしょうか? 貴方のやり方が間違っていたとして、それを貴方のいう我が儘という表現で覆ったところで、その願いが濁ることはありません」
狂信者さながらの語り方ではあったが、森石がいうほど盲目的には思えなかった。
信者は神を間違っているとは言わない。利用したといわれて、羽衣おばさんは利害の一致だと認めた。そのうえでの発言だ。
だから、これは、盲目とは違う。全部わかった上で、それでも構わないと言っているだけだ。
「そういうことをいうから、お父さんに社会では野放しにできないって言われるのだと思う」
「おかげでいい会社に雇われたので感謝はしていますよ。お父様は私のことが嫌いなようですが」
残念そうな顔で羽衣は息を吐いた。
対する森石は呆れたように肩を竦める。
「ビール瓶で自分を殴ってきた相手を好きになれるわけないだろう」
誘拐だけでも不穏だというのに、さらに危険なエピソードが飛び出してきやがった。
森石の父親とは対面したからこそわかるが、そう簡単に手を出してはいけない雰囲気を持っている人だ。よくそんなことができたものである。
「あれは私から貴方を奪おうとしたので仕方なかった行為です。そもそも貴方をあの状態で学校に行かせる精神を考えると、当然の行動ですよ」
「そうやって君が謝罪しないのが問題だ」
「お父様だって貴方を私から奪ったうえに、私を拘束したことに対して謝罪しませんでした」
「あの人は僕の父親だ。それは謝罪する行為じゃない」
「いいえ。相手が父親であろうとなんだろうと関係がありません。家族だけが貴方を幸せにできるとは限りません。あの時、貴方に必要だったのは」
「それ以上は言わないでくれ」
口を挟むというにはか細い声だったが、羽衣おばさんは素早く言葉を止めた。
ミラー越しに見た森石は俯いていたせいで、表情がよく見えなかった。
羽衣おばさんのいうことは、俺には同意できないものである。他人は裏切るが家族は裏切らない。その不安がないだけでも幸せなことではないだろうか。
あくまでこれは俺の意見であって、森石の反応を見る限り別の何かがあるのだろう。
「僕が悪かった」
さっきとは明らかに違う響きのそれは、謝罪というより懺悔のようだった。
羽衣おばさんが口角を下げた。一度、親指の爪を囓ってから俺を見る。
「誰ですか?」
それは誰が森石をこんな状態にしたのか、ということでいいのだろうか。
相手がわかった瞬間に殺しにいきそうな目つきだが、第三者としてこの場にいた俺の答えは一つだ。
「羽衣おばさん」
「私が彼にこんな顔をさせるわけがありません」
その自信はどこから来るのかわからないが、完全に間違ってもいないのだろう。
謝罪の先が羽衣おばさんなら、犯人は駄犬だ。けれども森石のそれはもっと別の何かに向けてである。
誘拐が生きがいなだけあって、誘発するのも得意なんじゃないか。
>続き
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
