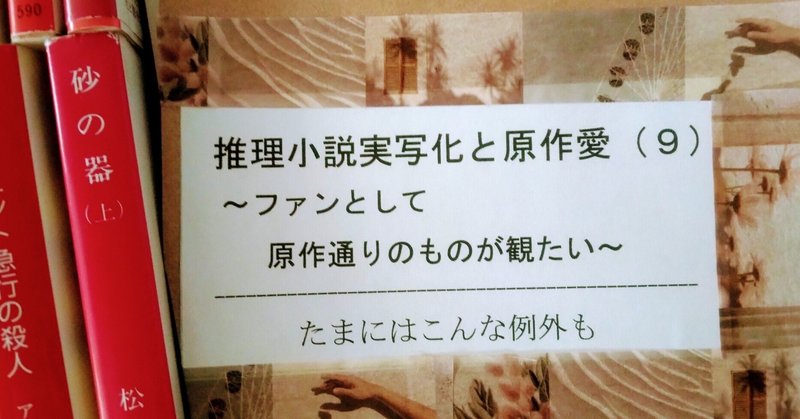
まさに奇跡の別物! 映画『砂の器』が邦画屈指の音楽映画でもある訳~ただ音楽が凄いとかそんな理由じゃない~
推理小説の実写化についてあれこれ綴る、つづきです。
前回はこちら。
映画『罪の声』は原作の行間を的確に映像化した傑作~こんな人生があったかもしれないと思うこと~|涼原永美 (note.com)
(以下、作家や俳優名等は敬称略とさせていただきます)
実写化されるなら、原作が好きでたまらないか、原作の良さを最大限生かせる方に手掛けてほしい。ファンとしての切実なお願いだ。
そんなことを改めて思うのも、綾辻行人による傑作ミステリー『十角館の殺人』(講談社文庫/税別695円)実写化のニュースを聞いたから。そこで、どうしても今このタイミングで・・・と思い、あれこれ書いているのだが、今回は松本清張『砂の器』(新潮文庫/上巻552円・下巻590円/各税別)の映画化についてである。
ーーさて、これに関しては、「どう考えても原作とは別物」なのだが、凄まじいほどの傑作となっている、と言わざるを得ない。
(1)音楽表現でこの映画が突出している理由と、すごい製作陣
1974年の映画『砂の器』。
原作・松本清張。監督・野村芳太郎。脚本・橋本忍と山田洋次。
この名前を見ただけでも戦後の邦画界にとってどれほど重要人達が関わっているか、わかる人にはわかると思う。
松本清張が残した作品群は令和の今なお映像化され続けているし、野村芳太郎、橋本忍、山田洋次は「戦後邦画界の〝神セブン〟」みたいなものがあったら悠々とランクインする人達だ(黒澤明や小津安二郎や市川崑も入ると思う)。
映画『砂の器』は、邦画史に残る社会派ミステリーであると同時に、私には「世界遺産級の音楽映画」に思えてならない。
それはもちろんクライマックスで約40分間(!)かけて演奏される『宿命』という楽曲(正式には「ピアノと管弦楽のための組曲『宿命』」というらしい)が素晴らしいからなのだが、それだけなら「ほかにも音楽がすごい映画は数え切れない程あるだろう」・・・ということになる。
そうではなく、「音楽」の扱いに関してこの映画が抜きんでていると感じるのは、こういうことだ。
劇中にはさまざまな登場人物がいるが、最も〝激しく複雑な感情〟を抱いている人は事件を起こした「犯人」である。
この人物の「感情と事情」こそが映画の大筋であり、重要なテーマでもあるのだが、この人物は劇中でそのことについては一言もしゃべらない。
もちろん、社会生活をおくるための会話はするし、人とも関わるが、いたって冷静、時には冷徹で、内面をうかがい知ることはできない。
それを映画では、代わりにすべて音楽と映像によって表現しているのだ。
ーーもっと言えば、映画で用意された映像は観客に対してのものであり、犯人にとって「想いのすべて」は楽曲、音楽に込められている。
だからこの映画、映像作品が音楽でできることの「ひとつの極み」を提示しているように思えるのだ。前述した通り、音楽が素晴らしい映画はたくさんあるが、ここまでストイックに「本題を音楽で表現」している映画を、私はほかに知らない。
しかもこれ、ちょっと言い方は悪いが、どうも「原作をよい映画にしようと作り手が試行錯誤したら、ある意味、結果的にこうなった」もののようなのだ・・・。そこがすごい(もちろん、作り手が凄腕なのが大前提)。
こねくりまわすのは、どちらかというと失敗しそうなベクトルだが、この映像化の場合は「不要と思える部分は潔く捨てた」という言い方が正しそうだ。
――今からその話をしたいと思う。
(2)誰がなぜ殺した? 「カメダ」って何? 面白すぎる映画『砂の器』あらすじ
映画『砂の器』は、まずこんな内容である。松本清張がこの原作小説を書いたのは1960年代だということをイメージしてほしい。
〈映画『砂の器』ざっくり ~といっても短くするのは無理な~ 内容〉
【1】
東京の蒲田駅操車場で男性の死体が発見される。何者かに撲殺され、顔は判別不能な状態となっていた。前日深夜、近所のバーで被害者と連れの客が話し込んでいた様子が目撃され、何度か「カメダ」の名を話題にしていたという。
人名かどうかもわからないまま「カメダ」を手掛かりに捜査を始める警視庁捜査一課のベテラン今西刑事(丹波哲郎)と、相棒をつとめる若手の吉村刑事(森田健作)。やがて被害者が、かつて島根県で巡査を務めていた三木謙一(緒方拳)であることがわかるが、調べれば調べるほど、三木が「善良で人助けをいとわない神様のような人物だった」ことがわかり、怨恨の線の捜査は行き詰まる。
【2】
一方、世間では天才ピアニスト兼作曲家として和賀英良(加藤剛)という人物が称賛と注目を集めていた。大物政治家の令嬢と婚約し、新曲である「ピアノと管弦楽のための組曲『宿命』」初演を目前に控えている。華やかで非の打ちどころのない人生をおくるかに見える和賀英良と、蒲田駅の殺人事件はどう結びつくのだろうか。
【3】
地道な捜査を続ける今西刑事はやがて、被害者三木謙一が見たであろう「ある物」から、会いに行った人物を特定し、事件の意外な真相にたどりつく。そして捜査会議の日、今西の口から被害者の人物像とその動機、秘められていた悲しい「父子の物語」が語られる。
おりしもその日は、和賀英良のコンサートの日であった――。
・・・という感じである。いちおう、わかりやすいよう【1】【2】【3】に分けてみた。
ちなみに、音楽の話は別として、刑事が被害者・三木謙一の足跡を丹念に追い、「彼はなぜ殺されなければならなかったのか」という真相を暴く過程は社会派ミステリーの真骨頂でもあり、初見の人は謎解きの面でもかなり楽しめるだろう。
(3)映画143分中、演奏会シーン40分! 名曲『宿命』が綴るのは父子の悲劇・・・
映画『砂の器』は、突き詰めれば「ある父子の情愛と別れ」に行き着く物語だ。同時に「宿命」の物語でもある。運命は、ある程度自分の力で切り拓く余地があるかもしれないが、宿命はどうにもならないーーというニュアンスがそこにあり、劇中のある人物は、宿命とは「生まれてきたこと、生きているということかもしれない」と話す。
この宿命が、父子の情愛と別れが、映画では後半の40分間をかけて音楽と映像とともに綴られる。
ーーある事情から故郷を追われた父親が6歳の息子を連れて、お遍路のごとく日本各地を放浪する。
それは四季折々の厳しくも美しい風景とともにあり、衣食住もままならない極限の旅ながら、親子が強い絆で結ばれている様子が伝わる。
ところがある土地で、ある人物に助けられたことから、親子の運命は大きく変わっていくのだったーー。
コンサートホールで『宿命』の演奏が始まると同時に、今西刑事が語りはじめる事件の「解決編」。
その内容に私は最初、ひたすら衝撃を受けたが、冷静に分析するとこの40分は、とても巧くできた三重構造になっている。
(1)今西刑事が事件の真相を語る捜査会議(ずらりと並んだ大勢の刑事が今西の話に聞き入る)
(2)和賀英良のコンサート(全身全霊でオーケストラを指揮、自身もピアノ演奏をする和賀)
(3)美しくも悲しい音楽と映像に乗せて展開する「父子の旅と別れ」
・・・という感じだ。これらが交互に浮上しながら、絶妙に絡み合い、観る者の胸を揺さぶり続けるのが、この映画の最も感動的な点である。
――これがもう、観ていて感情のコントロールができなくなってくるのだ。初見の時はもう、完全に心をもっていかれた。
自分が、予想もしなかった真相に驚いているのか、父子の情愛に感動しているのか、犯人の過去に同情しているのか、いやでも殺人はダメでしょうと思っているのか・・・整理が追い付かない。ただひたすら、互いを想い合う父子の姿が胸に焼き付く。
それでも、観る者以上に感情が「ぐちゃぐちゃ」なのは、ほかならぬ犯人だろう。そうなのだ。
(いまから犯人が誰なのかをはっきり書きます)
ここで言ってしまうが、犯人とは和賀英良のことである。
もちろんネタバレではあるが、映画では初見の人でも中盤から犯人が誰なのか予想がつくと思う。この映画の本筋は「犯人あて」ではないのだ。
話を戻すが、感情が「ぐちゃぐちゃ」であろう和賀英良は、『宿命』の演奏が終わるころには、なんだろう・・・すべての感情を音楽に込めて表現できたであろう一種の喜び、感慨、カタルシスを得たような表情へ収束する。人によっては、観ていて同じ感覚を得ることができるかもしれない。どんなに苦しい過程を経たとしても、表現とはやはり喜びなのだ。
私はこの映画を何度も観ているが、3回目位からようやく「父子放浪の映像」と「音楽」に圧倒されることなく、構成部分やその他の要素に目がいくようになった。
それは今西刑事の人間性だったり、原作にもある「ハンセン病」の苦難の歴史であったりするのだが、強く感じたのはやはり和賀英良の感情表現が「すべて音楽に集約されていく」構成面だ。
演奏中にはじつにいろんな表情を見せる和賀英良。日頃いかに仮面をかぶっているかがわかる。本当は秀夫、こういう人なんだろうな。演じた加藤剛の名演だ。
(4)小説『砂の器』は映像化難易度の高い原作?・・・その真相とは
ーーさて、話を原作の小説に戻してみよう。
書かれたのは1960年代、映画化は1970年代だから、いまとは当然、時代が違う。
もとは読売新聞で連載されたようだが、当時どのくらい人気があったのか、読者がどのくらい「映画化するなら原作に忠実に」と願っていたのかはわからない。ただ、インターネットはもちろんレンタルビデオ店もなく(録画という発想すら一般人にはない)、映画が今よりもっと大きな娯楽だったことは間違いない。
(ちなみに『砂の器』公開は1974年。前年の1973年は『日本沈没』、2年後の1976年は『犬神家の一族』が公開され、一大旋風を巻き起こしている。そういう時代だ)
ただこの時、松本清張たっての希望で「映画化を」と依頼された脚本家の橋本忍と監督の野村芳太郎は、原作を読んで困ったらしい。その後ロケハンをしたり、脚本を共同執筆する山田洋次と相談した結果、「小説に書かれてない、親子にしかわからない場面」をポイントに書いていく方向になったという。
また、そこから橋本忍が後日、山田洋次に「和賀英良のコンサートの日、刑事が事件について語りはじめる」という構成を提案したらしい。人形浄瑠璃を意識した、とウィキペディアや、各インタビュー等に書かれている。
映画化に際したこのあたりのエピソードは、『砂の器』ウィキペディアに詳しいので、興味のある人にはぜひ読んでほしいが、少しだけ引用させてもらう。
本映画の脚本を橋本と担当した山田洋次は、シナリオの着想に関して、以下のように回想している。「最初にあの膨大な原作を橋本さんから「これ、ちょっと研究してみろよ」と渡されて、ぼくはとっても無理だと思ったんです。(中略)「ここのところ、小説に書かれてない、親子にしかわからない場面がイメージをそそらないか」と橋本さんは言うんですよ。「親子の浮浪者が日本中をあちこち遍路する。そこをポイントに出来ないか。無理なエピソードは省いていいんだよ」ということで、それから構成を練って、書き出したのかな」。
砂の器 - Wikipedia
ウィキペディアの情報はけっこうな文章量だが、読んでいて思わず唸った。「『砂の器』が映画化されるまで」をドラマ化したら面白いんじゃないか・・・というくらいのエピソードの濃さ、登場人物の豪華さである。
そこには「こうすればとりあえず仕上がるし、大衆ウケするんじゃない?」というムードは微塵もなく、戦後の日本映画界を支えた、いや文字通りつくってきた神のような人達が、「絶対にこの『砂の器』をいい映画にしてみせる!」という情熱をもってやり切った仕事がこの作品だということがわかるのだ。名作は空から降ってくるものではない。決して。
そしてまた当初、父子の放浪シーンにはセリフがあったらしい。が、結局編集の段階でカットしたとのこと。英断だと思う。
(5)原作ラストはコンサート会場ではなく、意外な場所!
ところで橋本忍、山田洋次がなぜ原作を読んで当初「むずかしい」と感じたかという話なのだが、じつはこの原作、長くて複雑というだけでなく、結果論にはなるが今からするとちょっと「トンデモ」な内容だったりするのだ(清張先生ごめんなさい)。個人の感想です。
ちょっとここで、原作だけの設定や展開を挙げてみたい。
(1)じつはこの犯人、三木謙一だけなく小説のなかでは第二、第三の殺人を犯してるのである。しかも、たいした理由とも思えず・・・(すみません)。ワルい奴だなぁと言わざるを得ない。
(2)しかも犯人、三木謙一は扼殺(映画では撲殺)だが、他の2人に関しては電子音楽機器を用いた超音波(!)を殺人の道具に使用している。えぇっ(ちょっとコナンっぽい)。
(3)犯人は若手文化人・芸術家の集まりである「ヌーボー・グループ」に所属していて、若手芸術家が数人登場する。犯人候補が少なくとも2人いるので、小説では真犯人が下巻の後半になるまでわからない。つまり犯人あての物語でもある(それに対して映画は、犯人が中盤でなんとなくわかり、「動機」「過去の解明」が本筋となっている)
(4)今西刑事の家庭が何度も登場し、過酷な捜査を妻が支えている様子が伝わってくる。また、今西家の近所で、事件と関わりのある出来事がちょくちょく起こるのが面白い。
(5)原作では父子放浪の旅は、今西刑事による数行の説明で終わっており、詳細は書かれていない。
(6)原作では、和賀英良は電子機器を使った前衛音楽の作曲家。
(7)和賀英良の父親・本浦千代吉は、原作では既に死去している。
(8)原作ではラストにコンサートはなく、和賀がアメリカに旅立とうとする空港のシーンで終わる。栄光からの転落として、小説では印象的だが、映画のように盛り上がる場面はない。
・・・いかがだろうか。
映画を一度でも観たことがある人なら「ええ、そうなの?」と驚くかもしれない。私も、映画公開時は生まれておらず、20代の時に初めてDVDで視聴、その後数年経って「そうだ原作読んでみよう」と手に取ったのだが、「・・・こんなに違うの?」とひっくりかえった。
――あらためて、映画の構成をつくりあげた橋本忍と山田洋次の才能と情熱、仕上げた野村芳太郎監督の手腕を感じずにはいられない。
完成した映画を観た作者の松本清張も「この表現は小説では絶対にできない」「原作を超えた」と評価したそうだ。――言うまでもないことだが、松本清張は日本に社会派ミステリーの一時代を築いた偉大な作家である。たまたまこの映画が、「その通りつくらなかったけど、名作になった」ということなので、それだけはここに書いておきたい。
(6)こんなにあるの⁉ 映画オリジナルの名シーン
さて続いて、映画版をこよなく愛する人の大半が「これがなければ『砂の器』じゃない!」と思っているだろうけど、じつは原作にはないシーンを挙げてみたい。
(1) クライマックスの「父子放浪の旅」ほぼすべて
原作では、今西刑事が捜査会議で語る、以下のたった数行である。
本浦千代吉は、発病以後、流浪の旅をつづけておりましたが、おそらく、これは自己の業病をなおすために、信仰をかねて遍路姿で放浪していたことと考えられます。
本浦千代吉は、昭和十三年に、当時七歳であった長男秀夫をつれ、島根県仁多郡仁多町字亀嵩付近に到達したのでありました。
(2)今西刑事が和賀英良の写真を持ち、存命していた本浦千代吉を訪ねるシーン
千代吉は写真を見て「こんなひと知らねえ!」と絶叫する。本当は死ぬほど会いたいはずなのに、何かを察したに違いない・・・。千代吉を演じた加藤嘉の歴史に残る名演である。
本当は、互いを想い合う親子が会えない理由なんて、あってはいけないのだ。もとはと言えば病気に対する偏見、社会の無理解が本浦親子の悲劇をつくったのだと思うと、かなり胸が苦しい。
(3) 三木謙一が和賀英良に対し、父親に会うべきだと説得するシーン
「秀夫・・・なぜだ、どげんしてなんだ、(中略)わしにはわからん(中略)わしはお前の首に縄・・・縄つけてでもひっぱっていくから」と詰め寄る。
原作では千代吉は死亡しているので、三木はただ懐かさのあまり和賀を訪ねて行ったという設定。過去を明かされたくない心情はわかるものの、殺人の動機としては薄いという点が原作にあったのだが、ここを映画では改変し物語に深みをもたせている。
ちなみに映画の前半で、殺された三木謙一のかつての同僚が、三木の正義感について「こちらが根をあげるほど強引な三木さんの励まし」「これが正しいと思ったらどこまでも曲げずに押してくる」と話していたのだが、まさかこれが伏線だったとは・・・。
(4)「ピアノと管弦楽のための組曲『宿命』」初演、和賀英良のコンサートシーンは、繰り返すが原作にはない。
(5) 和賀の逮捕直前に交わされる、今西刑事と吉村刑事の会話
原作でも、ある種の「世代交代」を思わせる印象的な会話が交わされるのだが、映画では和賀の心情に寄り添う言葉になっている。
そして最後の「音楽のなかでしか・・・」という今西刑事の言葉こそが映画の本質をついており、犯人が決して口に出来なかった本心であると伝わってくる。いやぁ、こんなセリフを書ける脚本家はすごいな。
(7)神様のような三木と人間的な今西・・・そして宿命に支配される和賀
今から約50年前に公開された『砂の器』。
古いけど、決して古くならない。それは観るたびにそれぞれの人が、普遍的な人間の業に打たれるからだと思う。
私が40代になって再鑑賞した時、強く感じたのは、被害者三木謙一という人間の業についてだ。
三木謙一は、正義感に溢れた神様のような人だった。それはまちがいない。
映画では、仕事を引退し、念願の「伊勢神宮参り」を思い立って出かけたことが事件の発端となっている。そこで、かつて自身が保護したものの行方不明になった「本浦秀夫」の現在の姿を発見し、会いに行く。父親とは会えないと話す犯人に対し、「首に縄つけてでも・・」とせまり、殺されてしまう。
三木は正しいことをしようとした。けれど、相手にとっては受け入れがたいものだった。相手は、正しくはないかもしれないが必死で生きていた。
ーーまた、三木にとっては残酷だが、どうしても考えてしまうことがある。
父親はともかく、息子とって三木は果たして「恩人」だったのだろうか?
三木にとっては衣食住もままならぬ親子の保護と、病気の父親の援助ではあったが、子にとって三木は「父を奪った人物」ではなかったか?
別れの時、父親のもとへ必死で走ってくる少年の瞳を見て、子どもの幸せとは何か・・・と考えずにはいられなかった(子役の名演技)。
三木は生涯「旅」に縁のない人だったのかもしれない。理屈じゃない感情、事情を、どう説明したらわかってもらえたのだろう・・・と再鑑賞のたびに考えてしまう。もちろん和賀がしたことは許されないが、業が深すぎる和賀と、清廉潔白な三木は相容れない、人間として交わらない相性だったのではないだろうか。
その点、地道な捜査を通して心を巡る旅を追随した今西刑事は、千代吉と秀夫の気持ちに寄り添うことができたのかもしれない。職務を超え、捜査会議で流す涙が胸を打つ。
また、和賀は原作でも最後まで心のうちを他者に明かすことなく、表面上は冷静で冷淡な人物として描かれている。
ただ、映画では一度、婚約者から「宿命」について問われ、「生まれてきたこと、生きているということかもしれない」と話すシーンが印象的だ。これは映画オリジナルの秀逸なセリフ。ーーそれでも、身近な人間でも彼の本質はわからないだろう。
そしてそれは、ただただ演奏シーンに委ねられている。
音楽のなかに込められた宿命。そう考えるとやはり映画『砂の器』後半40分は、「犯人の激情のすべてをセリフなしで表現した、稀にみる映像体験であり、音楽体験である」と言えると思うのだ。
私は、人生でこんなすごい映画に出会えたこと、この作品が生まれるにあたって関わった人達すべてに、心から感謝を伝えたい。
(8)どっちが原作? 映画が後のドラマ版に与えた影響と、「原作とは何か」の問い
さて、最後にこのすごい映画『砂の器』が後のテレビドラマ版に与えた影響についてなのだが、これがちょっとした珍現象と言えなくもない。
結論から言うと、「どれもほぼ・・・映画のほうを原作にしているよね?」という構成なのだ。
私がリアルタイムで観ることができたものに限って挙げると・・・
・2004年TBSの連続ドラマ版(主演・中居正広)
・2011年テレビ朝日の二夜連続スペシャルドラマ版(主演・玉木宏)
・2019年フジテレビ開局60周年特別企画スペシャルドラマ版(主演・東山紀之)
・・・それぞれにオリジナリティがあって興味深かったし、映画版では登場しなかった「ヌーボー・グループ」あるいはそれに類する人達が出てきたり、こなかったりしているが、いずれも和賀英良はクラシックの作曲家(ピアニスト)だし、クライマックスは抒情的な音楽にのせた「父子放浪の旅」で盛り上がる。
たまには1作くらい、原作通りに空港で終わるドラマ版があってもいいのかなぁ、とも思うが、つくり手からすると「ラストのコンサートがないなんて『砂の器』じゃない!」という視聴者の声が怖いだろう。やはり無理か。
そのくらい、後の映像に携わる人達にとって(観る人にとっても)映画は大きなインパクトだったろうし、古典的名作となっているのだろう。
もちろん、ドラマでは「原作:松本清張」に加えて「構成」や「潤色」として橋本忍・山田洋次の名をのせており、敬意が感じられる。
ーーただ、私は思う。
このところ推理小説の原作と映像化についていろいろ書いてきたし、最後には〝別物だけど傑作〟として映画『砂の器』に思いを巡らせた。
そして、ちょっとわからなくもなった。
ーー原作とは、いったいなんだろうか。
それは、著者やファンにとって「絶対にそのまま映像化してほしいもの」かもしれないし、「少しなら改変していいもの」かもしれないし、時と場合や作品の特長にもよる。「これだ」という確たる答えはないものかもしれない。
でも、ひとつだけ確かだと思うのは、
「それがあるからこれがある」ということ。絶対的な順序だ。
そして重要なのは
「この物語の〝何〟を」「〝誰〟が伝えたがっているのか」
ということだ。
『砂の器』は、映画版にしてもドラマ版にしても、ベースは松本清張の小説で、作家には伝えたいことがあった。栄光を手にした者と、過去の因縁の物語、2人にしかわからない旅。そして映画の脚本を書いた橋本忍、山田洋次に「そのなかで、この物語の〝何を〟いちばん伝えたいと考えたのか」と問うたら、「こういうことだ」と明確な答えがあったことだろう。
どんなに時代が変わっても、「自分の言葉」をもつ人間が感動的な作品を生み出すのだと私は信じている。
原作とは尊厳――そんなふうに思ったりもする。
(9)早世した作曲家が遺した名曲『宿命』は永遠に
ーーさて、最後に今いちど音楽について。
映画で演奏された「ピアノと管弦楽のための組曲『宿命』」は、作曲家でジャズピアニストの菅野光亮によって作曲された。劇中の素晴らしいピアノ演奏も彼が担当している。
菅野光亮は1939年生まれとのことなので、宿命を作曲した時は30代前半(!)だったことになる。なんという才能だろう。もうひとつのドラマを感じてしまう。その後も活躍を続けるが、44歳で亡くなったようだ。すごく惜しい・・・。
この楽曲が映画の「もうひとつの主役」であることは間違いない。いや、もしかしたらこの映画そのものなのではないだろうか。
今なお、シネマ・コンサートなどの企画で、プロの楽団と指揮者によって演奏され続けているという。改めて音楽だけを聴いてみたが、日本が世界に誇る組曲のひとつなのではないかと感じた。
――語りつくせない。どれだけすごい映画なんだろう。
このシリーズ、終わります。またいつか書きます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

