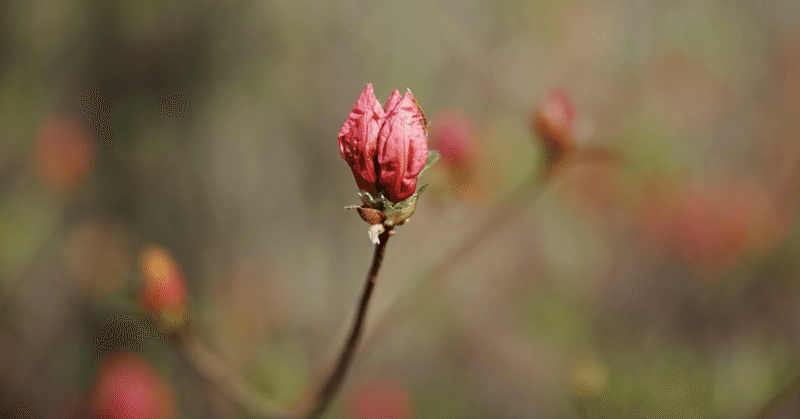
「褒める」雑感
昨日、私はこんな記事を書いた。
この記事では「褒める」ことの意味と重要性を語ったんだけど、これは、師弟関係・親子関係においてだけでなく、友人や同僚など、身近な人間関係でも大切なことだと思う。
「褒める」とは、自分の中にポジティブな観点をしっかり持ち、常に相手に対して愛とリスペクトをもちながら丁寧に観察しないと、適正にできないことだからだ。
ちなみに、ポジティブな観点が欠如していると(=自分の意識がネガティブに傾いていると)、どんなに良いことを言っても、相手には「嫌味を言っている」としか受け取ってもらえない。
また、相手に対して愛とリスペクトがないと(=相手を尊重する意識がなく、相手のことを粗雑に扱っていると)、どんなに素晴らしい言葉を並べても、相手には「私のことを見下して馬鹿にしている」としか感じてもらえない。
これらは、まさに日頃の「自分の心の在り方」がにじみ出てくるものであり、褒めたことが相手にちゃんと伝わるには、相手の受け止め方云々の問題ではなく、それ以前に、まずは「自分に人徳が備わっているか否か」が大事なんだと思う。
人徳=人間性なんだけど、もしも人間的に未熟な人が、目の前にいる人を急に思いついて褒めた場合、相手に自分の好意が伝わらないどころか、かえって相手に不快感を与える場合がある。
例えば「褒める」とは、「自分の価値観の物差し」を使って相手の言動を評価することだから、歪んだ価値観の人が安易に他人を褒めたりすると、ひょっとしたらハラスメントになってしまう。
だとすると、褒め下手の人は、無理して他者を褒めない方がいいのかもしれない。
こういうタイプの人は、おそらく普段から人間関係の失敗が多く、摩擦やストレスを抱えていると思うので、まずは自分自身が生きやすくなるよう、自分の心の持ち方や価値観を一度見つめ直すと良いと思う。
◇
ここで、ふと思い出すのは孔子さまの言葉だ。
【漢文】
子曰、吾十有五而志乎學、三十而立、四十而不惑、五十而知天命、六十而耳順、七十而從心所欲、不踰矩。
【書き下し文】
子曰わく、吾十有五にして学に志す。三十にして立つ。四十にして惑わず。五十にして天命を知る。六十にして耳順(した)がう。七十にして心の欲する所に従って矩(のり)を踰(こ)えず。
【現代語訳】
孔子はおっしゃった。「私は15歳の時に学問を志した。30歳の時に身を立てる事が出来た。40歳で迷いがなくなり、50歳の時に自らの天命を知った。60歳の時に人の言葉を聴く事が出来るようになり、70歳になって自分の心のままに行動しても人の道を踏み外すことが無くなった。」
孔子さまの言葉の「70歳」の部分。
この「矩をこえず」(=自分の心のままに行動しても、人の道を外すことが一切ない自分へと成長した)という箇所が、まさに人として目指すべき姿なんじゃないかな…と、しみじみ感じるのだ。
ここでいう「人の道を外す」とは、悪乗りして失敗するとか、調子に乗って言い過ぎるとか、そういう失態がない…という状態。自然にふるまっても、コミュニケーション上の失敗は1ミリもなく、素のままでいても誰からも信頼され愛される…だと、私は解釈している。
これは、いつも失敗をやらかす私には、まさに「こうなりたい」と思う理想の姿だ。
自分の口からポロっと出てきた言葉が、相手にとって最も必要な言葉となり、相手に喜びや感動を与えたり、あるいは、元気と励ましを与えたり、心を落ち着かせたり、安心させたり…等々。
自然に出てくる言葉、ふと思いついたこと、相手にシェアしたアイディア…云々。それらが全て、相手にポジティブに伝わっていったとしたら、これほど幸せなことはない。
自分の心が、この「矩をこえず」の境地に至れば、失敗を気にせず、いつでも自由に「褒める」が自然とできる。「褒めの達人」になれる。
上記の「論語」為政の文中、十五から始まって最後の七十へと続く配列から予想するに、「矩をこえず」は人生の終末期ににようやく到達できる境地なのだろう。つまり簡単じゃないってことだ。
しかし、なかなか遠い道のりではあるけど、私は今世では是非ここを目指したいと思っている。
よろしければサポートお願いします!いただいたサポートは旅の資金にさせていただきます✨
