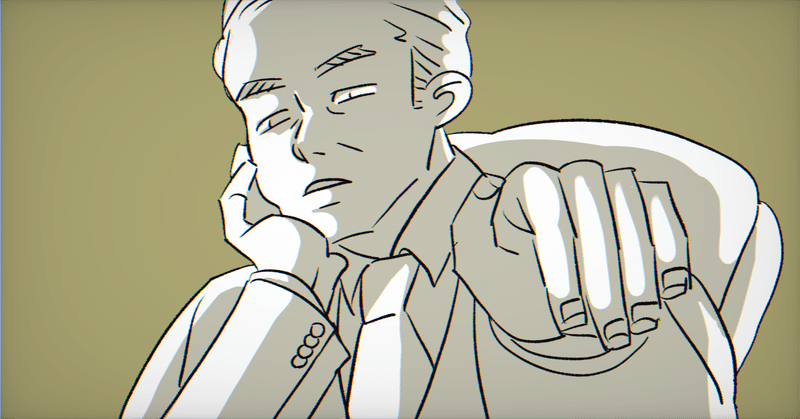
ルポ・通信社記者~朝起きると、家の前にヤクザが立っていたんです~
夜討ち朝駆けを繰り返す、刺激的な日々
通信社記者の日常は、想像を絶するほどにハードだ。
朝4時に起床、会社が手配してくれるハイヤーに乗り込み、警察・検察の要職の自宅へと向かう。彼らが出勤のために自宅を出る瞬間を待ち構えて話を聞くのだ。
運が良ければ、出勤のお供を許される。オフィスに到着するまでの限られた時間のなかで、口が固い官僚たちからどれだけ有益な情報が入手できるかが勝負だ。
その後、新聞各社に配信する記事を書き上げる。夕刊に間に合わせるには、13時がデッドラインだ。記事の作成と並行して、午後の取材のアポ取りを行なう。取材と執筆を繰り返して日が暮れる。深夜でも事件が起きれば現場に駆けつける。
今回話を聞かせてくれたMさんは通信社で記者職に従事している。
通信社は、自社のメディアを持たず、新聞社やテレビ局などに記事や写真を提供する企業だ。全国紙のように広大な取材網を持つことのできない地方紙は、通信社から多くの記事の提供を受け、自社媒体の紙面に掲載している。
Mさんは、都内の国立大学を卒業したのちに大手通信社に入社、現在6年目の28歳。
入社後は転勤を繰り返しつつも、一貫して警察や司法関連の取材を担当してきた。
名刺一枚で誰にでも取材ができ、一般市民が立ち入ることのできない現場にも赴き、見聞きしたことを言葉にして社会に届ける。
激務に追われながらも、非日常的で刺激的な毎日を心の底から楽しんでいるという。
ヤクザにだって突撃取材
ただ、記者の仕事にはそれ相応のリスクがついてまわる。
Mさんには、自らの仕事の危険性を思い知らされた経験を語って頂いた。
それは、ある地方都市に赴任していた時の話だという。
「反社会勢力との繋がりが噂されている地元企業が、市内の広大な土地を購入する計画があるという情報を入手しました。これは記事になると思い、裏を取るために社長に話を聞いてみることにしました」
社長宅をアポなしで訪れたMさん、ヤクザがらみと思わしき社長の家はコンクリート打ちっぱなしの大豪邸だった。インターフォンを鳴らしたが応答はない。
ここで怖気づいてはならぬと、勢いでインターフォンを連打するMさん。しかし何度鳴らしても返答はなかった。
しかたなく社長への裏どりは諦め、会社の代表番号に電話をかけることにした。
広報担当者に取り次いでもらい、Mさんが入手している情報の真偽を問い、記事にする予定である旨を伝えた。
「公表前の情報を記事にする場合、利害関係者には必ず事前通告をしています。余計な軋轢を生まないようにという意図もありますが、そこで交渉を行うことでより大きな情報を引き出す事も可能になります」
しかし今回、広報担当者からの返事はただ一言「ノーコメント」のみだった。
こうしてMさんは当初入手していた情報を元に記事を執筆した。
他社に抜け駆けされることもなく無事に記事は掲載され、ほっと一息ついたのも束の間、Mさんは思わぬかたちで報復を受けることになる。
これ以上、首を突っ込まないでね
「その日は休みで昼ごろまで寝ていたところ、インターフォンの音で目が覚めました。起きるのも億劫で無視していたのですが、何度も鳴らしてくるので仕方なく玄関に向かいました。すると見るからにカタギではない、スキンヘッドの大男がインターフォン画面からこちらを覗き込んでいたんです」
鳴り止まないチャイムの音、Mさんは恐怖に震えながら、物音を立てずに留守を装うしかなかった。
男はそのうち諦めたのか、立ち去っていった。
「記事には自分の署名もなく、住所が漏れるような心当たりもなかったのですが、今思えば社長宅を訪れた帰りに誰かにつけられていたのかもしれませんね」
Mさんは、自らの浅はかさを笑うかのように語った。
警察に相談した甲斐もあったのか、その後は特に危険な目に遭うこともなかったMさん。ある日、付き合いのあった地元財界の有力者から突然、話がしたいと連絡が来た。喫茶店の席に着くなり、件の記事について「よく書けている」と絶賛されたという。ひとしきり記事についての話をしたのちにお開きとなったので、Mさんは何のために呼び出されたのか訝しんだ。
帰り際、「続報は出さないでね。これ以上首を突っ込まないほうがいい」
と不気味な忠告を受け、呼び出しの目的を悟ったという。
時刻は24時、ここまで話を聞いたところで、Mさんの携帯電話が鳴る。
上司からの着信、会社へ戻るように指示があったようだ。
「どんなに忙しくても、恐ろしい目にあっても、こんなに魅力的な仕事はないですよ」
そう言い残し、我々の元から去っていった。(四)
四ツ谷:1996年生まれ。学術書編集者。出版社3社を経験。YMOを心から崇拝しているので、最近は傷心気味。生粋のシティボーイ。署名は(四)。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
