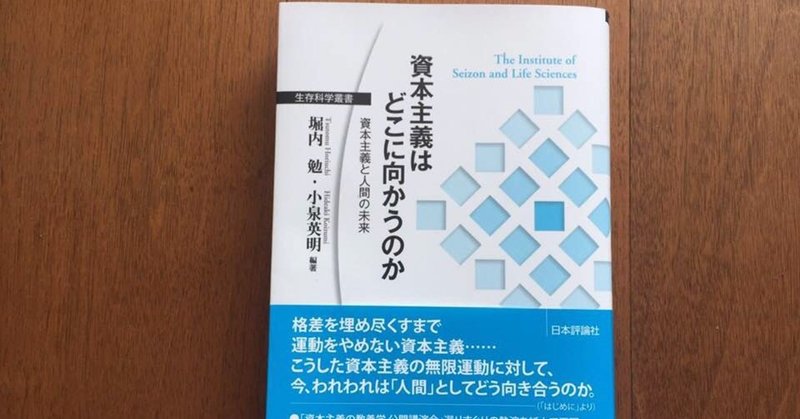
経済の課題を問い直すカギは何か ――書評『資本主義はどこに向かうのか』
「資本主義は、果たして人を幸せにするのか」。経済メディアの仕事をしていた頃から、ずっとこんな問いを掲げつつ、答えを探る切り口も問いを深める糸口も一向に見つけられずにいる。そんないまの僕にとって放って置かないタイトルの本が出た。『資本主義はどこに向かうのか』である。
本書は、資本主義研究会が5年前から開催している公開講演会の一部をまとめたものである。
研究会を主宰する堀内勉さんは、日本興業銀行、ゴールドマン・サックス証券、森ビル・インベストメントマネジメントなど、一貫して金融界から経済を見つめてきた人だ。その堀内さんは、そのキャリアを通し常に金融とは何か、資本主義とは何か、そして資本主義とは人間の存在にとってどのような意味があるのかを問い続けてこられた。その問題意識がこの研究会の背景であり、本書は、研究会の開催した講演会から、とりわけ「科学」と「人間」にフォーカスしたものを収録したものである。
こう書くと相当難解な本だと思われるだろうが、実際、読んでみると手強かった。正直「読みこなせた」と胸を張れないのだが、読み応えがあったことが確かにある。
何より、寄稿者(登壇者)の顔ぶれが、凄まじく魅力的である。
総勢12名の方々なのだが、それらは大澤真幸氏(社会学博士)、太田博樹氏(東京大学大学院理学系研究科教授)、岡本裕一郎氏(玉川大学名誉教授)、小野塚知二氏(東京大学大学院経済研究科教授)、小泉英明氏(公益財団法人日本工学アカデミー上級副会長)、渋沢健氏(コモンズ投信取締役会長)、中島隆博氏(東京大学東洋文化研究所教授)、広井良典氏(京都大学こころの未来研究センター教授)、堀内勉氏(多摩大学社会的投資研究所教授)、松尾豊氏(東京大学大学院工学系研究科教授)、水野和夫氏(法政大学法学部教授)、安田洋祐氏(大阪大学大学院経済研究科准教授)である。
資本主義を「科学」と「人間」から考察するというだけあって、これらの方々の専門分野は、金融論やゲーム理論、経済史はもちろん、AI、実験物理学、脳科学、ゲノム人類学、さらに社会学、哲学、思想史まで及ぶ。これらのジャンルを超えた専門家が資本主義を語るのだが、例えば脳科学者やゲノム人類学者が、このテーマでどのように語れるのかという見当がつかなかったのだが、それこそが本書の魅力になっている。
ゲノム人類学者の太田博樹氏は、「経済学の話は、突き詰めると結局、人類史の理解の話になる」と語る。そして、チンパンジーと人間との違いは時間の感覚だという。そして投資する発想がチンパンジーにはないことから、「ヒトが資本主義というシステムをつくったのも、共産主義(というか計画経済)という夢を追いかけたのも、チンパンジーにはないヒト特有の時間感覚をもっていたから」ではないかと推察する。その上で「『未来への不安』に駆り立てられた行動が、個人の利益の追求や、一つの国の内向きな利益の保守に向けられたとき、人類全体は滅亡へ向かう」と見立てる。
社会学者の大澤真幸氏は、サッカーを例に出して、ある意味で人間の本性にかなわないものが社会に普遍的な存在になりやすいという。手を使えないサッカーに対して、資本主義に内包されているのは富の無限性である。人の命は有限であるのに対し、資本という無限に利潤を生み出す仕組みが、「人間的と言えない」というパラドックスを提示する。さらに言えば、利子を禁止していたキリスト教から資本主義が生まれたということはそれ自体が「キリスト教の否定になっている」という矛盾も指摘している。
経済史家の小野塚知二氏は、人間の本性を「たとえ苦しくても過剰に欲望を充足しようとする傾向がある」と規定し、「欲望」を鍵に経済史を語る。さらに「人はしばしば他者の欲望を欲望します。他人の持っているものを欲しがるとか、他人に取られる前に自分で取ってしまおうとするとか、他者が存在することによって、欲望がよりかき立てられるという面があります」とし、ヒトの欲望には社会的な欲望もあるという。そして「続いてきた社会には、欲望を制御する機構がビルトインされていた」ことを例証する。ここで制御するものとして、小野塚氏は、「格好いい」などの「小さくて弱い規範」をつくることで破滅というディストピアを回避できるのではと締めくくる。
ここでは3人の方の論しか紹介できなかったが、これだけでも資本主義が人間の性にあっているのか否かがわからなくなる。本書は、まさに簡単に答えが見つからない問いに果敢に挑んでいるのであり、「どこに向かうのか」への結論があるわけではなく、むしろ、この問いを掲げて読んだ自分は、答えを探す荒野はますます広がってしまった。手強いのは本書の中身というより、人間社会が作り出した仕組みそのものかもしれない。
それでも、問いの入り口となる視点に発見があった。それは資本主義というものがあたかも、大きな制度の中に固定されたものとしてどしんと鎮座していたイメージが変わったことだ。資本主義は制度として確立されているわけではなく、宗教のように経典があるわけではない。市場経済を効率化させる法体系はあるが、それとて社会を動かしている全てではない。
近年のクラウドファンディングやソーシャルファイナンスの動きなどを見ても、それらは自主的に誰かが動き出し、それらに賛同者が集まってお金が動き、社会をつくる一因となっている。ブロックチェーンなどの新しいテクノロジーも、経済的価値以外のものが、人と人の交易を実現させる可能性がある。
経済学者も黙認しているわけではない。安田洋祐氏は、保守的とも言われる主流派経済学に身を置く立場でありながら、「主流派の殻を破る」糸口を探している学者のひとりである。ポスト資本主義を提唱する広井良典氏は、市場経済とコミュニティや自然との乖離を、つなげる方向へと政策提言をされている。実務家でコモンズ投信の渋沢健氏は「共感」への投資を掲げ、「昨日よりもよい明日のために」投資をするという。
資本主義に欠けているものを埋めようとする動きは、さまざまなところで始まっている。そして、それは本書に登場するような影響力のある人に限られない。持続可能な社会を作りたいなら、その意思を市場経済の中で、購買や投資という行動で票を投じることもできる。同様に、社会に幸福につながらないと思われる生産活動に寄与しないことから始めることだ。
小野塚氏が提唱される「小さな規範」とはまさに、社会や市場を構成する一人一人の美学から生まれるものだ。小さな動きのどこからか、あるいは重なり合った時、資本主義の閉塞感に風穴が開くのではないか。一人ひとりがどういう社会を作りたいか、その意思や思いの集合が社会システムを形作る。本書は、読む人の問題意識に応じて、それぞれの洞察が得られる無数の言葉が盛り込まれている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
