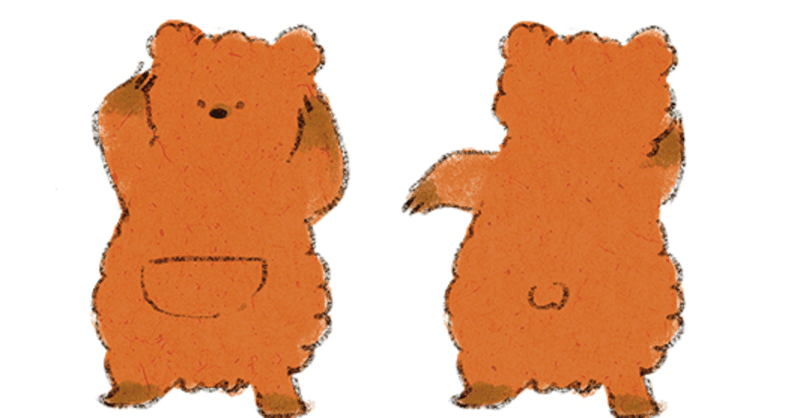
5分小説 『そのままの、きみがすき』
初めて会ったときから笑顔がかわいい人だな、と思っていた。その印象は今でもずっと変わらない。
ボクは誰にも顔を見られない仕事をしている。というか、見られては困る。子どもたちの夢を壊しかねないからだ。
そして仕事中はとにかく暑い。夏でも冬でもずっと汗だくだ。あとは全身の筋肉痛。これはもう職業病だと思って諦めている。
「わあ! くまさんだあ!」
それに子どもたちの笑顔を間近で見ることができる。だから、ボクはこの仕事に誇りを持っている。
「くまさん、ありがとう!」
くまさんに成りきったボクは喋らない。
基本的には風船を渡すだけだが、喋らないなりに滑稽な動きやジェスチャーを交えて、子どもたちと意思の疎通を図る。
「くまさん、あくしゅして!」
最近の子はもう着ぐるみの中に人がいると気づいていると聞く。でも、うちの遊園地に来る子どもたちはまだ無邪気な方だ。
それでいいと思う。
子どもでいる間くらい、着ぐるみを本物の動物だと思い、クリスマスプレゼントを届けてくれるのはサンタさんだと信じていた方がきっといい。
大人になっていろんなことを疑いながら生きているよりずっと幸せだ。
「くまさん、こんにちは!」
毎週木曜日になるとやってくる、くるみさんは毎回律儀にボクに挨拶をしてくれる。
声を出せないボクは、ぺこんと頭を下げて応えた。
彼女がどんな仕事をしている人なのか、何歳なのか、ボクは何も知らない。唯一知ってる名前は、くるみさん自身が教えてくれた。
「今日もいいお天気ですね」
そう言って笑うくるみさんは、子どもたちと同じくらいあどけない。
だけど近頃、彼女の笑顔を目の当たりにする度に、ボクの胸に邪な想いが沸き上がる。
ボクのことを知ってもらいたい。
本当のボクを見てもらいたい。
そんなことを考えてしまうボクは、着ぐるみを装う者として失格なんじゃないかと思ってしまう。
「風船もらってもいいですか?」
ボクはこくこくと頷いて、膨らんだ状態で結びつけていた風船をひとつとり、差し出す。
でもうまく手渡すことができず、ボクの手から離れた風船はあっという間に空高く舞いあがってしまった。
「……あ、」
慌てふためくボクとは裏腹に、彼女は切なそうに空を見上げた。
「すみません、私が悪いんです。うまく受け取れなくて、ごめんなさい……」
いつになく元気がなさそうだ。
何かあったんだろうか?
かつて、くるみさんはボクを助けてくれた。なのに、今のボクには何もできないのが焦れったい……
着ぐるみは子どもたちに喜ばれる反面、時として乱暴に扱われることもある。その日、ボクは少しやんちゃな男の子たちに、軽くパンチやキックをされていた。
「こら!」
そんなときに現れたのが彼女だった。
「そんな風に叩いたり蹴ったりしたら、くまさんが可哀想でしょ!」
「ちがうもん! オレたちはくまと遊んでるだけ!」
「自分たちはそう思ってても、くまさんは痛いかもしれないでしょ?」
「痛いはずないよ! だって、この中には人が入ってるんだから」
男の子のその発言に、ボクは一瞬ひやっとする。
「そんなことないよ! ちゃんとしたくまだよ!」
「おねえさん着ぐるみのこと知らないの?」
「このくまさんはそんなんじゃないよ」
「ふーん、へんなのーあっち行こうぜー!」
男の子たちはつまらなそうに言い返すと、走り去ってしまった。
「くまさん! 大丈夫でしたか?」
ボクはありがとうの気持ちを込めて、ぺこぺこと頭を下げる。
「本当に失礼ですよね。くまさんはくまさんなのに!」
まるで自分のことのように怒る彼女がかわいらしい。
「私、くるみって言います。またくまさんに会いに来てもいいですか?」
その言葉があまりにもうれしくて、ボクは着ぐるみの中で顔を綻ばせた。
出会った日のことを思い出していると、目の前にいる、くるみさんがこんなことを聞いてきた。
「くまさん……くまさんの中にはやっぱり、ほんとに、その、人が入ってるんですか?」
ボクの仕事は子どもたちに夢を与える仕事だ。
でも、大人の女性に対してもボクは夢を与えないといけないんだろうか?
「私、変に思われるかもしれないけど、くまさんが好きです。友達に話したら、笑われちゃったんですけど……」
突然の告白にボクは戸惑う。返事をすることさえできない自分が、もどかしくてたまらない。
「でも、くまさんは、くまさんだけはどうしても本物なんじゃないかって思ってて……」
一度でも期待したボクの胸は空気の抜けた風船のように、しゅうぅ~とあっけなくしぼんでいく。
何を自惚れてるんだ。くるみさんが好きなのは中にいるボクじゃない。
あくまでも、くまの格好をしたボクなのに…
「……ううん、本当は私だってわかってるんです。くまさんの中に人がいるってことくらい」
そう呟くと、くるみさんは悲しそうに睫毛を伏せた。
「でも、自分でもわかんないんです。くまさんのことが好きなのか、それともくまさんの中の人が好きなのか……」
気がついたら身体が勝手に動いていた。
「くま、さん……?」
ボクの腕の中におさまったくるみさんが不思議そうに見つめていて、我に返る。
すぐさま、くるみさんから距離をとると、ボクは待ってて、とジェスチャーで伝える。
もし伝わらなくて、その場を立ち去ってたなら、それでいい。
ボクはバックヤードを目指して、できる限り全速力で走る。
休憩室に飛び込むと、もこもこの手で自分の鞄を漁り、手帳とペンを引っ掴む。
急いで彼女の元に戻ると、ぽかんとしたままその場で立ち尽くしていた。
……よかった。
『へいえんじかんまでまってて』
覚束ない手つきで手帳に書いた文字を見たくるみさんは、一瞬驚いたあと、いつものやさしい笑みを浮かべた。
期待しても、いいんだろうか……?
もし閉園時間まで彼女が待っていてくれたなら、本当のボクのことを知ってもらおう。
そして今まで話せなかったことをたくさん話そう。
きっとくるみさんなら、くまじゃなくなったボクのことも受け入れてくれるだろうから。
(20151014)
バレンタイン週間として、たまには恋愛短編小説も更新してみたよ~!
最後まで読んでくださり、誠にありがとうございます。よろしければ、サポートいただけますと大変うれしいです。いただいたサポートは今後の創作活動に使わせていただきます!
