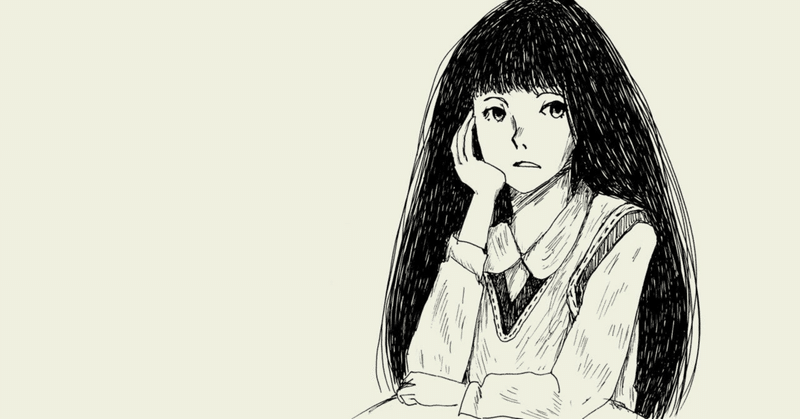
この平凡なる日常
ご近所の梅の花芽が一夜にしてすっかり綻んで、ポップコーンを散らしたように見えるのでした。
わたくしは見てハッと驚いた。梅一輪、一輪ほどのなんとやら、と古句が口をついて出て、はて、誰の作だったかと思い巡らしていると、目の前の家の門扉が勢いよく開いて、
「こんちは」
こう明るく元気に挨拶するのは、高遠家の長女の凛ちゃんで、
「これはこれは、おはよう。今日はまたずいぶんゆっくりですね」
「うん、遅刻確定だよ、ヤバしだよ」
走り出したかと思うとひらりとこちらを振り返り、
「わからないとこあるから、学校から帰ったら、寄るね」
そういって手を振るのでした。
「いつもあいすみません」
天から年増の声がして見上げると、二階のベランダで洗濯物を干すこの家の奥方で、あられもなくスカートのなかを覗かせる。
散歩から戻ると、自宅の玄関先には例のごとく野良猫たちの群れ。家のなかへ招き入れますとね、板張りの広い式台に上がってあの仔もこの仔もゴロンゴロンともんどり打って前脚を胸元に縮こまらせ肉球を軽く握って腹をあからさまにしてうずうずするわけですから、わたくしは手がいくつあっても足りません、もうこうなってはひとつまとめてえいやっと抱え込みましてね、ひとしきりもみくちゃにして存分に狂いましてから、パッと放り上げますと、無数の綿ヒラとなって舞い散って、わたくしはといえば、くしゃみがもう止まらない。
そうこうするうちお昼になります。朝も夜も胃に何も入れないわたくしは、昼はたっぷりいただく。先夜から昆布締めしたヒラメの柵を薄切りにしましてね、こちらを炊き立てのご飯の上に敷き詰めて、牡蠣醤油をさっと垂らし、昆布茶の素を少々まぶしましたら、渋茶を注ぐ。これを掻き込みながら、野菜は決まって香の物、塩分が気になりますゆえ、食後は手製の干果物をもって〆となす。
午後は心ゆくまで庭を見る。
今年も紅梅より白梅のほうが早いが、うちのはポップコーンとはまだいかない。昨年いち早く開いたのは庭の隅に植ったボケの花だったが、隣家が夏に目隠しの塀を建てたものだから、これがどうやら陰となるらしく、花芽のふくらみ自体がすこぶる遅い。フウセンカズラの枯れ蔦が、梅の幹や梢に絡まるのを昨日は風情よしと見たのに、なぜかいまは取り払いたい衝動に駆られて、ひょいと片手につかんで引っ張ったが最後、もう仇かなにかのようなやっつけぶり。パラパラと音を立てて敷石に散るフウセンカズラの黒い種。種は丸くて硬くてハート型のヘタが模様のように張り付いて、猿の尻のように見える。
「こんちは」
玄関のほうで黄色い声がして、庭から回れば、凛ちゃんと連れがお二人。
「おや、今日は早いんですね」
「早くなんかないよ。いつもと同じ四時半ですよ」
そういって案内もされないうちに、ズカズカと娘らは家のなかへ入っていく。
わたくしも庭履きのまま続き、玄関の戸を閉め、三和土に散乱する娘らの靴をそろえ、床に投げ出されたカバンを拾って壁際に並べ、そうしておもむろに居間に顔を覗かせると、わたくしの寝床を兼ねる掘り炬燵にはや包まって、娘三人ぬくといぬくといいってはしゃいでいる。真四角の座卓の空いた一辺にわたくしは脚をもぐらすと、さっそく誰彼の脚に当たって絡まりあう。
娘たちは、ひとしきり三十分ほど話柄を転じながら、おしゃべりに興じる。わたくしなどその場にいないかのような、あけすけな話題、そして振る舞い。見目は三様でも、おぐしは皆ひっつめで、前髪だけ簾のように垂らしておでこを隠す。このような髪型の成人女性をついぞ見ない、と観察するたび、わたくしは不思議に思うのである。
「なんか、喉乾いたよね」
気がつかない星人のわたくしは、遠回しにいわれてようやく席を立つ。コカコーラの瓶を三本と、茶菓子を山と盛った木鉢とを盆にのせ、座卓の中央へ盆ごと音を立てぬように置く。三人は顔を見あわせてから、わたくしを見る。それら悲しげな表情を見てようやく気がついて、いやいやごめんなさいごめんなさいと、立って栓抜きを取ってくる。またもや顔を見あわせる三人だが、ま、いっか、となって三人して慣れぬ手つきで瓶の王冠を抜くと、乾杯してからいっせいにラッパ飲みする。その白くて長い首筋の、前へ弓なりになって張る薄皮に、コクコクと嚥下するたび喉仏の上下しないのを、これまたわたくしは不思議に思いながらしげしげと眺めるのでした。
「おじさん、警察官なの」
凛ちゃんにいわれて、え? となってわたくしは顔を上げる。
「なんで、そう思ったのですか」
「だって、あれ」
そういって凛ちゃんが指差した先に、いかにも警察官のかぶる帽子が壁にかかっていたのでした。
「ああ、あれですか。よく観察してますね。その通り、おじさんは警察官だったんですよ」
「そっか。じゃあ、やっぱ、変な人じゃないよね。安心だね」
そのときでした、家のなかのどこかでかすかに猫が鳴いたのは。
「あれ? ひょっとして、猫いるんじゃね?」
しまった、午前中に始末しそびれたのが一匹家にいる模様なのでした。
「おじさん、猫飼ってるの」
「飼ってますとも」
平然とわたくしはいってのけ、口笛を吹いた。すると、冷蔵庫の上に隠れていたと思しきそれは、音もなく床に降りてくると、そろりそろり炬燵のほうへ近づいてきた。
「やべ、めっちゃ、可愛いんだけど」
「名前、なんていうんですか」
猫はわたくしのほうを見ないようにしながらも、抗いようもなく娘らの呼びかけに引かれていくようでした。凛ちゃんにさっと抱きかかえられた猫は、いわゆる猫撫で声を立て続けに三度発した。
「すごーい。おとなしいし、マジ人懐っこいんですけど」
そりゃま、人でしたからな、と聞こえないように独りごちてから、娘の手から手へと抱かれ継がれた猫を最後にわたくしが抱き取ると、猫からすれば油断したのが後の祭り、牙を剥いて爪を立てたものですが、わたくしは可愛い可愛いともみくちゃにすると、パッと宙に放って、するとたちまち辺り舞い散る無数の綿ヒラ。
「え、なに、いま、なにが起こった?」
「手品です」
「こわっ!」
「だって、ほら、猫に関わってる暇はあなた方にはありませんでしょ。勉強しないと」
いいながら、炬燵を立って床に落ちた綿ヒラを逐一拾い上げ、炬燵布団のファスナーを開けるとなかへそれらを詰めていくわたくしの所作の一部始終を、娘三人呆気に取られて眺めている。
……でもさ、たしかに、そろそろやらないと、うちら、ヤバいよね、と誰からともなくいいだして、炬燵から立って玄関までカバンを取りに行くと、なかから勉強道具一式取り出して、銘々また炬燵に包まってようやく勉強に取りかかる。見守るばかりのわたくしは、紙面を走るシャープペンシルの先の音やら消しゴムで文字を消す音やら消しカスを手で払う音やらに眠気を誘われる。
「ここ、わかんないんだけど」
いわれて覗き込む。悲しいかな、老眼で細かい字が見えないので顔を近づけようとすると、娘のほうが気遣ってぴたりと軀を寄せてきて問題集をすぐ横に開いてくれる。礼を言い、ひと通り問題文を読んでから、ああ、これはね……とわたくしは教えてやるのです。娘らはわたくしの説明を神妙に聞いて、あ、わかったかも、と独りごちて破顔する。礼をいわれ、そのたびに恐縮するわたくし。すると今度はうちのひとりが消しゴムがないないいいだして、掘り炬燵のなかへ落としたのではないかとなって、いうだけいって三人してわたくしを見るから、しょうがないですねと潜り込むと、果たして消しゴムは堀の底にあって、それを拾いがてら四方を見渡して、炬燵のなかなのをいいことに、娘らがあられもなく脚を開いているのを見つけて、各々の膝をつかんで閉じさせながら、「脚を易々と開くんじゃありません」と注意していくと、口々に「はーい」と上で生返事。わたくしは呆れて炬燵のなかで大きく息を吸うと、残念至極とばかりに聞こえよがしのため息を吐く。
凛ちゃんは、ある程度ヒントを聞いてから「あ、わかった」となって自走するタイプの子ではなく、要するに答えは? と結論を急ぐタイプ。人が説明しているあいだも両腕をぶらんとさせ、相槌も打たず、ただ聞いている。
「さ、じゃあ、ここからは自分で解いてごらん」
「いや、おじさん、答え出してよ」
「それじゃあ、あなたのためになりませんよ」
「うっざ」
聞こえるか聞こえないかの声で悪態ついてから、問題集に並べられたノートに渋々屈んでシャープペンシルを走らせる。凛ちゃんの左の耳介がすぐ目の前にあって、折しも窓から差し込む西陽を受けて、耳朶のまわりの産毛が虹色の光を纏った。これに霧吹きで水を噴いたなら、さぞかし微細な水玉がつくものだろうと想像するだに恍惚となりかかる。
娘たちの集中力は、続いてせいぜい二時間が限界。七時前には帰路につく。
「おじさん、今日もありがとう」
「寂しいからって泣くなよ」
「また来るからね」
三人を見送ってからしばらくもしないで、玄関のインターフォンが鳴る。
「どちらさまでしょう」
「ちょっといいですか。警察なんですが」
わたくしは玄関の戸を開けに立つ。玄関先に控えるのは若い制服の警察官のお二人。
「これはこれは。どういったご用件で……」
「いえね、ちょっと通報がありましてね。その確認で。どうもここ最近、女生徒らがお宅に連れ込まれているとの情報が寄せられたものですから。念のためこうしてうかがった次第で」
「それはそれはご苦労様で。立ち話もなんですから、どうぞお上がりください」
「それでは失礼して」
掘り炬燵に案内すると、警官らは立ったままでいいという。
「あれは」
壁にかかった警察官の帽子を目ざとく認めてひとりが問う。
「ああ、あれですか。精巧なレプリカですよ。警察官に憧れがございまして」
若いほうが年嵩のほうへなにやら耳打ちし、途端に二人の顔から血の気が引いていった。
わたくしはこの機を見逃さない。果たして次のように畳み掛けるのです。
「お二人とも猫はお好きですか。お好きなら、どんな柄の猫がお好みでしょう。キジトラですか、ハチワレですか、それとも舶来猫ですか。……犬派だったり特にお好みがなかったりでしたれば、わたくし男性は三毛猫にして差し上げておりますゆえ、そこは悪しからず」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
