
王は神殿ではなく獄舎に住んでいる
男性の修道士と女性の受刑者。いずれも修道院と刑務所という社会から隔絶された空間で暮らす人びとである。1950年代、写真家の奈良原一高は、彼らの世界に入り込み、その内実を内側からとらえた。
《壁の中》の撮影地は、和歌山県の女性刑務所。タイトルから察すると、自己完結した小社会の生態を連想しがちだが、奈良原の焦点は、むしろ「壁」に当てられている。高い壁が直接的に写り込んでいるだけではない。鉄格子の向こうの監房で佇んだり、覗き窓から外を伺ったり、受刑者たちの存在はつねに閉塞感を伴っているのだ。彼女たちと私たちのあいだには、必ず何らかの障壁が介在していると言ってもいい。
一方、《沈黙の園》は北海道のトラピス修道院で撮影された。羊とともに野原を歩き、農作物を収穫し、そして神に祈りを捧げる。奈良原の写真は、たしかに超俗の静寂に包まれている。けれども、その静けさは決して自然環境に由来しているわけではない。それは、やはり「沈黙」という主体的な意志の現われなのだ。
カメラの前で両目をつむる修道士。親指と人差し指で両目を押さえる身ぶりは、宗教的な儀礼行為なのかもしれない。だがその一方で、カメラの向こうにある世俗的な世界を見ることを拒否する意志の表明のように見えなくもない。奈良原の写真をとおして私たちは彼らを見るが、写真の中の彼らは私たちを見ることを拒んでいる。ここでもやはり、目に見えない「壁」が、彼らと私たちを遠く隔てているのである。
興味深いのは、奈良原が《壁の中》と《沈黙の園》あわせて《王国》と名づけている点だ。私たちの視線が及ばない「壁」の向こうに、はたしてどんな「王」がいるのだろうか。
建築史家で建築評論家の長谷川堯は、名著『神殿か獄舎か』において、明治建築と昭和建築の狭間に埋もれていた大正建築の実態を解明した。そこでとりわけ浮き彫りにされるのは分離派のような表現主義建築だが、長谷川はその前提として、大正建築の始点が後藤慶二による「豊多摩監獄」であり、終点は蒲原重雄による「小菅刑務所」であるという。つまり、大正建築とは獄舎にはじまり獄舎に終わるのだ。ここから長谷川は獄舎の思想を鮮やかな手並みで練り上げていく。
長谷川によれば、都市とは本来的に獄舎であり、人間ですら意識を肉体という物質によって閉じ込めてはじめて人間となったのだという。重要なのは、都市であれ人間であれ、獄舎として自閉することによって身体性を確立するという点である。長谷川が大正建築に見出したのは、身体の延長としての建築、内部空間に確実に身体感覚が及ぶ建築だった。それは、経済的合理性という名の下、構造を重視した反面、表現を軽視した明治や昭和の建築には到底望めない、大正建築ならではの特質である。
さて、長谷川はサン・テグジュペリの『城砦』を引用しながら、次のように言う。
「王は豪奢な神殿的住いの中にいるからして王として認められ崇拝されるのではなく、まさに自らを獄舎のうちに閉じ込めて成った最初の人間として、王となりえたのだ」。
そう、奈良原一高がとらえた修道士や受刑者らは、いわば「最初の人間」なのだ。だからこそ「王国」なのだ。動機こそ異なるとはいえ、両者はともに「自らを獄舎のうちに閉じ込め」ることで、自分の身体性を十全に確保した。私たちの視線が彼/彼女らに到達しえないのは、「王国」に体現された身体性が、私たち一人ひとりの身体より、文字どおり大きいからだ。その圧倒的な差に、私たちの視線は怯むのである。
芸術が生まれるのは、その「王国」にほかならない。
初出:「Forbes Japan」(2015年2月号)
奈良原一高 王国
会期:2014年11月18日〜2015年3月1日
会場:東京国立近代美術館
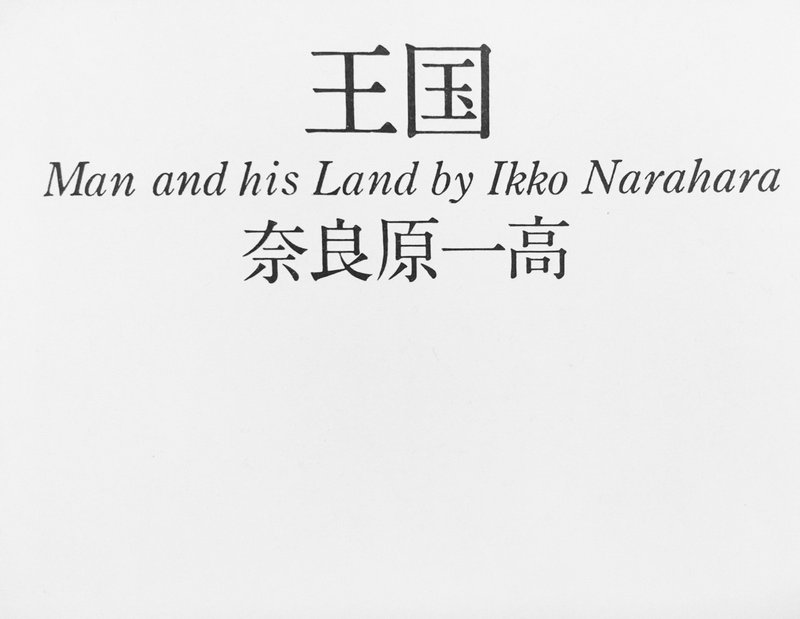
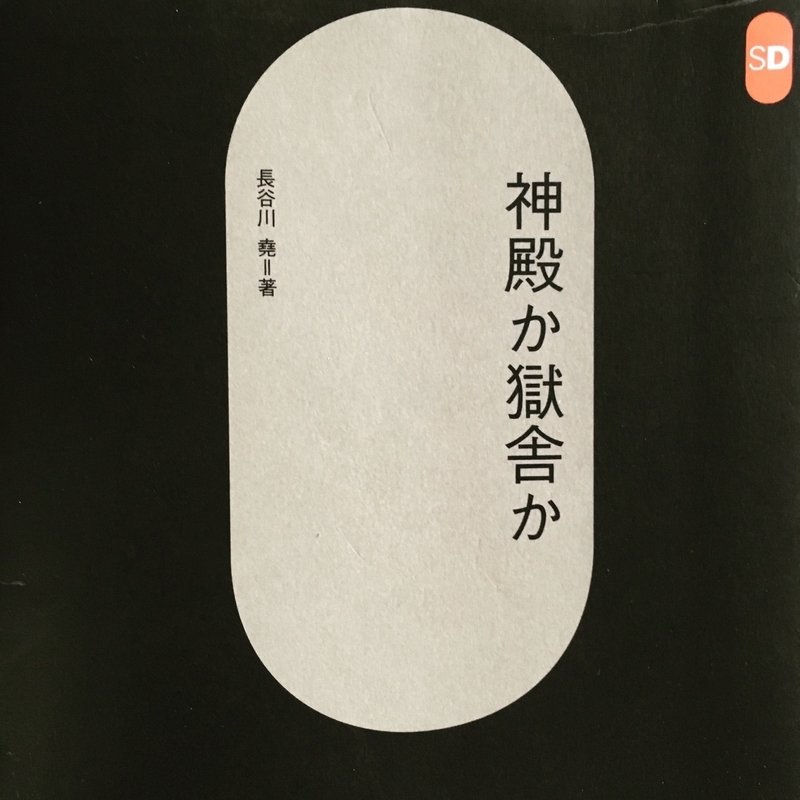
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
