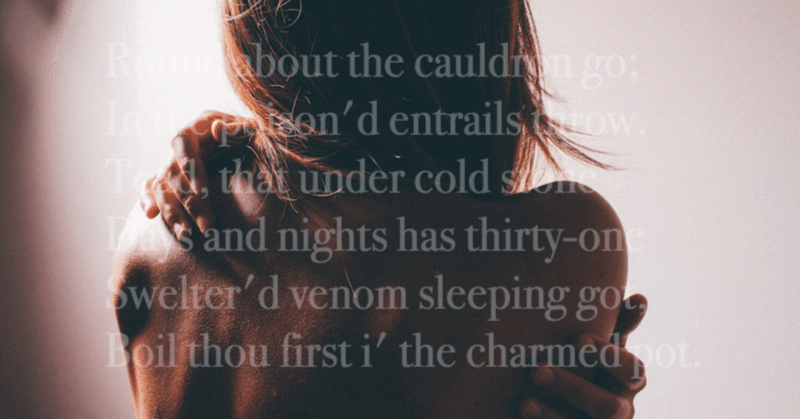
ショートショート 『夏おじ』
車のエンジンをとめると、雑木林を抜ける風の音だけが耳についた。
僕は枯れ葉の積もった庭に立ち、山裾にたつ家を見あげた。
人が住まなくなった家屋は急速に荒れ果てると聞いたことがある。古家はその言葉のままの姿であるように思えた。人に見捨てられたがらんどうだ。
「………居ないな、こりゃあ」
僕はつぶやいた。
窓はすべて閉まっている。中のカーテンは引かれていない。軒先の物干し竿に洗い物はない。振り返ると、所々がひび割れた農道の向こうに田園地帯が広がっていた。遠くの幹線道路を軽トラが走っていく。隣家まで数百メートルあるような田舎町なのだ。
「何だって、こんな場所に」
夏おじのことだ。
田原夏樹。それが彼の名前で、父の末弟にあたる。うちの家系には珍しい楽天家で、大学を卒業しても定職に就かず、関東のメディア関係の周辺で細々とした仕事をこなしていた。良く言えばフリーランスのライターというやつだった。
夏おじがフィリピンに行った、と聞いたのは、8年くらい前だ。
………今からは海外ノマドの時代だとさ。
父が苦笑していたのを覚えている。
それからしばらく、夏おじの暮らしぶりは耳に入らなかった。あきらめ半分の親戚たちの中、あえて彼の話をしようとする者がいなかったというところだ。
夏おじが帰国したと聞いたのは、去年の初夏だった。
GWを利用して帰省していた僕に、
「東南アジアって言うの? あの周辺でフラフラしていたみたいだけど………」
母が言った。「詐欺かなにかに引っかかって、警察沙汰になったみたいなのよ」
「引っかかった? 捕まったの?」
僕は聞いた。被害者が捕まるなんて聞いたことがない。夏おじには悪いが、あの性格だ。犯罪という意識まではなくても、何かの詐欺の片棒をかついで捕まったという筋のほうがしっくり来る気がした。
「分からないのよ、詳しいことは。でも向こうにはいられなくなったみたい」
母は手を振った。「あ、これ、お父さんに聞かせちゃあ駄目よ。ぜったい気にするから」
その頃、父は肝臓癌で県立病院に入院していた。長男とは言え、成人した弟の素行などどうにもできるはずもないのだが、父はそうしたドライな割り切りができない人だった。
そして一昨日、母から電話があった。
N市の郊外で古家を借りて住んでいた夏おじに連絡がつかないというのだ。
もう放っておこう、などと言ってはいたが、母も義姉として夏おじを見放すわけにはいかず、彼が県の空き家バンクの制度に申し込む際の保証人になっていたらしい。
「しばらくは野菜を作って自給自足する、これからは地方の時代だなんて言ってたけど」
電話越しに母は言った。
滞納している家賃はわずかなものだが、町役場のほうから連絡を取るように依頼されたらしい。しかし退院しても本調子ではない父の耳には入れたくないと。
そして、僕の出番となったわけだ。
僕は家の周囲を歩いてみた。
百坪ほどの敷地で、裏山との間に畑と物置小屋がある。畑には雑草が生い茂っているだけで、野菜らしきものを育てた様子はなかった。自給自足できるような状態ではない。
「駄目だな」
僕はつぶやいた。
母にも言ったが、やはり夏おじは駄目な人なんだろう。やる事なす事すべてが中途半端で、これからは何々の時代だなどと、目の前の現実から逃げる言い訳ばかり繰り返しているだけの人なんだ。帰ったら、もう関わり合いにならないように、母に言うべきだろう。
僕は玄関のほうにまわった。一応、チャイムを押した。家の奥でベルが鳴っているのが聞こえたが、もちろん誰も出てきはしない。
僕はあきらめ、途中で寄った町役場から借りた鍵で、ガラスの引き戸を開けた。
家の中にはカビ臭い空気が淀んでいた。
黒く色の変わった板敷きの廊下が奥に続いている。
「夏おじさん、居ます?」
僕は形ばかり声をかけた。
返事はない。
僕は少し躊躇した後、スニーカーを脱いだ。靴下が汚れるだろうが、さすがに土足であがることはできない。
もちろん夏おじはいなかった。毛羽立った畳の部屋が二間、台所にトイレ、風呂場だけの家だ。押入れまで確認したが、彼の姿はなかった。
「夜逃げ、かな?」
空気を入れ換えようと庭に面した居間の窓を開け、僕は首をかしげた。
モノが少ないということはあるが、家の中はおおむね片付いている。流しの横には洗った食器が整然と並べられていた。それにしてはブレーカーは落とされていず、何も入っていない冷蔵庫が空気だけを冷やしていた。
「中途半端なんだよな、やることが」
僕は文句を言いいながら玄関から庭に出た。
最低限の光熱費にタダ同然の家賃、それも払えなくて夏おじは逃げ出したのかもしれない。甥としては不遜な言い方だが、40歳を過ぎた大人のやることとも思えなかった。
裏の雑木林を覗き、戻ってきたときに、物置小屋の戸が少しだけ開いているのに気づいた。
ドキン、としなかったと言えば嘘になる。
嫌なイメージが頭の中を過ぎった。小屋の中で首を吊っている夏おじ………。
縊死体は、ずいぶんひどい状態になると聞いたことがある。それを見ることになるんだろうか?
僕は助けを求め周囲を見渡したが、遠くの県道をトラックが走っていくだけだった。
「ないよ、そんな極端なこと」
僕は口に出して言い、物置小屋に近づいた。
おそらく腰が引けていた。
小屋の戸を半分ほど開けた。
薄暗い空間に、下がっている人の姿はなかった。腐敗臭もない。ほら、見ろ。
僕は安心し、小屋の戸を大きく開いた。そして奇妙なものを発見した。
それは立方体だった。一辺が1メートルほどの物体が、小屋の中央、土間の上に置かれていた。
「何だ? これ」
僕は小屋の中に入った。
近づくと、その立方体がひどく正確な形をしていることが分かった。灰色の表面、きちんと立ったエッジ。触れると、ひんやりとした感触があった。たぶんコンクリートだ。最近の家の洒落た内装で使われるようにきめ細かく研磨されている。
指で弾くと、コンと跳ね返された。立方体の周囲を歩いて確かめ、今度は両手で押してみた。びくともしない。圧倒的な重量をそれは持っていた。
つまりは、何かを中に入れるような口もないコンクリート製の正確な立方体なのだ。
「何に使うんだ?」
僕は小屋の戸まで戻り、中を見渡した。
板壁にはごついシャベルや鍬といった農作業の道具が下がっている。前の持ち主のものだろう。夏おじはたぶん一度も使ったことがないはずだ。
そうした古くからの道具に囲まれた空間にある立方体は、ARの立体モデルのようにも見えた。
「アートだったりして………」
夏おじにその手の趣味があった記憶はないが、目的の分からない立方体は、いかにも現代アートっぽくはあった。こいつに水玉でもつければ良かったのに。
僕は家の戸締まりをして車を出した。
途中、町役場に寄って鍵を返さなければならない。苦情のひとつも言われるだろうと思うと、気が重かった。
県道に合流する信号で車をとめた。むこうの田舎屋の庭で柿の実が色づきはじめている。
信号が変わったが、僕はブレーキを踏んだままだった。
………夏おじは逃げていたんじゃないのか?
母が言っていた、詐欺か何かに巻き込まれ警察沙汰になった件から。だから、彼の性格に合うとも思えない、過疎の町に引きこもっていた。それが見つかったのだとしたら?
「箱」
僕は言った。
カラスの群れが畑の上を飛んでいく。
やはりあれは箱だったんじゃないのか? 中に何か、誰かを詰めた。
ハンドルに置いた指が震えていた。
僕は自分の指を見続けていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
