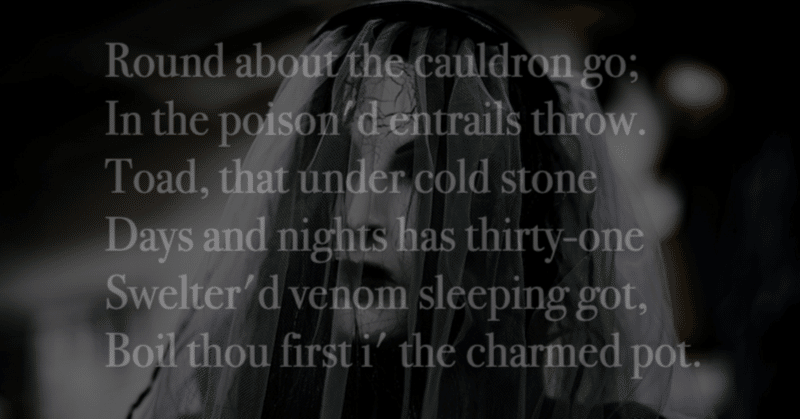
ショートショート 『彼の食卓』
「確かに、あの記事は舌足らずだったと思っている」
亀本は言った。「暇を持て余す奴らが切り取って面白おかしく騒ぎ立てるには格好の言葉も含んでいた」
「先生の作家としてのご高名もあってのことですね」
早乙女は如才なく微笑んだ。「このインタビューでは、その説明不足だった部分を補足するお手伝いをさせていただきたいと考えています」
「スポンサーからもきちんと説明するように言われているよ。僕も人気商売ではあるしね。ただ文章だけで食っていけるほどの原稿料をもらっているわけではない。あそこのCMがなくなると、家計的にもかなり痛い」
「正直ですね」
早乙女は嫌味にならない程度に笑い、スカートの下で長い足を組んだ。
亀本は一瞬、女性記者のストッキングに包まれた脚に目を走らせ、それをホテルの窓に逸らした。
仕事場代わりに出版社が提供してくれている部屋だ。鎮守の森の向こうに小さくタワーが見える。ビジネスホテルに毛が生えた程度だが、中の下レベルの作家への待遇としては良いほうだろう。人には根っから殺人への指向性がセットされているという話をネット記事に書き、目下、各方面からバッシングを受けている者としても。
「殺人の場面がある小説を書くのに、作家が人を殺す体験をする必要はない」
亀本は言った。「法にも触れるし、効率も悪い」
早乙女はうなずき、ノートにペンを走らせる。低いテーブルにはボイスレコーダーが置かれている。
「僕はこれでも研究熱心なほうでね」
亀本は言った。「あの小説を構想する段階で、殺人衝動に関する様々な文献を大量に集め、咀嚼した。古典から心理学、病理学、人類学の最新論文まで含めて。そしてある結論に達した」
「それは、あの小説に書かれていますか?」
亀本は首をふった。
「僕は論文を書いているわけじゃあない。あのストーリーの中に僕なりの理解をダイレクトに記すには建て付けに無理があった。下手な作家の中には、自分のハマっているトンデモ話を登場人物に滔々と語らせる間抜けもいるが。………口が悪すぎるかな?」
「言葉遣いは、記事にする際に調整させていただきますから」
早乙女は言った。「どうぞお気になさらずに」
亀本はうなずいた。
有能な記者だ。加えて美人だ。年齢は三十代前半といったところか? 栗毛色の髪が肩のあたりでウェーブし、ブラウスから出た喉は白く柔らかそうだ。
「乗り越える力だ」
亀本は唐突に言った。
早乙女は形の良い眉で疑問をあらわした。
「僕はひどく落ち着きのない子供だった。家でも学校でもね。今なら多動性なんとかなんて名前をつけられ、治療の対象になったかもしれない。ハンター・バーサス・ファーマー仮説って知ってるかな?」
その言葉を口の中で繰り返し、
「知りません」
早乙女は頭をふった。
「長い長い人類史においては、狩猟採集社会がその期間のほとんどを占めている。農耕なんてつい昨日始まったばかりの社会様式に過ぎない。君なら分かると思うが………」
亀本はアイスコーヒーのグラスを持ち上げ、喉を潤した。氷が溶けコーヒーは薄まっていたが、それで良かった。カフェインの興奮作用は仕事を雑にする可能性がある。見落としてはならないものを見落としたり。
「狩猟採集社会と農耕や工業、情報処理社会などでは、求められる意識の有りようが異なる」
「その片方の極がハンターの意識ということですね」
早乙女が言った。
「その通り。全方位的な、ある意味、落ち着きのない意識の状態だ。複雑かつ危険で変動する世界を処理する能力に長けている。そんな意識の持ち主が狭い教室に押し込められ、愚鈍な教師やクラスメイトに囲まれ、無意味な教科書に顔を埋める生活に耐えられるかな?」
「無理でしょうね」
「彼、もしくは彼女は徹底した破壊者になる。その破壊衝動の向かう先は何だろう?」
「ヒト、ですか?」
亀本は小さく手を叩いた。乾いた音がした。緊張はしていない。自分を制御できている。
「ハンター型の意識の持ち主にとっての邪魔者、言い換えれば牢獄は、同種のヒトでしかないからね」
「それが殺人への指向につながる?」
早乙女は微笑んだ。その微笑みの意味は分からなかった。
「我々は皆、キラーエイプだ。殺人への指向性が集合的にセットされている。もちろん程度の差はあり、その原種に近い者は根っからの殺人者と言えるだろう」
………オオカミは言いました、お前を食べるためだよ。ここは僕の食卓だ。
女性記者はドアを背にしている。その斜め後ろに安っぽいアンティーク調の棚。二番目の引き出しには使い慣れた道具がある。無骨で重い。ちょっとこの資料を見てくれないか? さりげなく棚を開け、振り返りざまに打ち下ろす。優雅に、遅滞なく。練習済みの動作だ。
「先生、三月に旅行に行かれましたね?」
聞かれ、亀本は眼を瞬いた。
「………それが?」
「攻撃性に関係する神経伝達物質は、視床下部の受容体を能動化させます。常態的に。平たく言えば、癖になっちゃうということです。そうですよね、先生」
早乙女は言った。「彼の地で撲殺は楽しめましたか? ハンマーは人類最古の道具らしいですね。さすがに先生は趣味が良くていらっしゃる。でも………」
赤い口紅が喋るのを、亀本は見ていた。
「そんなことまでセッティングする業者がいるんですね。それで狩りをしただなんて、ちょっと甘えすぎなんじゃないでしょうか」
早乙女は胸の前で手を組んだ。ネイルも赤い。「ここの後片付けも、業者任せのつもりだったんでしょう?」
亀本は黙っていた。状況が理解できない。滑りやすい氷の上に立っている気がする。スケートは苦手だ。
「我々はすべてを自分で処理します」
早乙女は言った。「先生のお好きな狩猟民族のやり方で。その分、時間はかかりますが、食べ物を捨てたりはしない。肉にも魂にも敬意を払います」
ドアの開く音がした。
同時に、遠心力が乗った早乙女の腕が亀本の喉首を叩き潰した。亀本の丸みを帯びたメガネが部屋の隅に吹っ飛んだ。トラウザーズの脚がちぐはぐに踊り、床に倒れ込む。
ここが彼の食卓になる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
