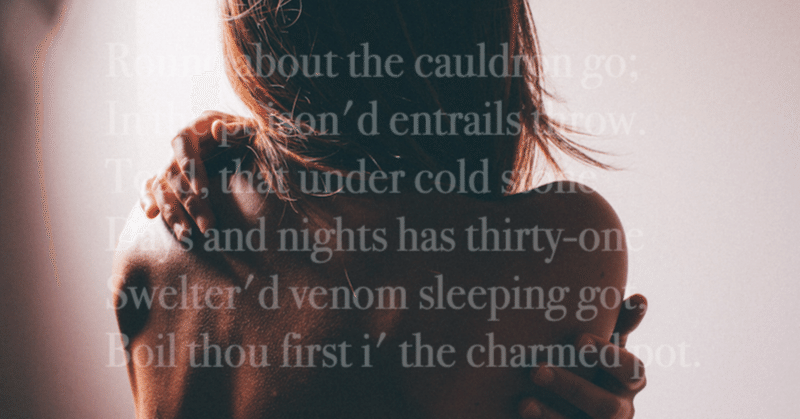
ショートショート 『招く猫』
その客が来たのは、午後の八時近くだった。
書生の速水が来客を告げ、彼は客を庭に面した応接間に通させた。
客の名刺には、「田中一郎」とのみ記されていた。所属も肩書きもない、名前だけだ。
彼は書斎の椅子にもたれかかり、
………こんな夜更けに、初対面の男が何の用だと言うのか?
首をひねった。
彼も書生もすべての用事を終え、各々の居室ですごしている時刻だった。
………いっそ、明日出直すよう、速水に言わせれば良かったか。
彼はそんなことを思いすらした。
突然の夜中の客に応対することが億劫で仕方なかった。
しかし、と彼は思った。
幾つかの方面に渡した彼の論文に興味を惹かれ訪れた客ではないか、とも。
そうであれば、無下に追い返すわけにもいかない。
もちろん金が欲しいわけではない。
彼と書生、そして通いの老女中からなる日々の暮らしは、資産家の出であった妻が遺した金でじゅうぶんまかなえている。ただそれは彼の友人が評するように高等遊民の暮らしでしかなかった。
彼が欲しいのは要請だった。
勤めに出る必要もない今の暮らしは世間との関わりが薄い。いや、身動きならぬほどに関わりたいわけではない。彼の論文に驚倒し、是非出版を、我が研究室に、といった要請が欲しいのだ。
そのような依頼に対し、彼は微笑み世間的なことには興味が持てない、と断る。そこまで含めた体験を、彼は欲していた。だからこそただの高等遊民でしかないのだが………。
彼はため息をつき、椅子から立ちあがった。
色の白い男だ。
客と向かい合う形で座敷机に座り、彼はまずそう思った。男の前には速水が出した湯呑みが置かれ、茶の香りが漂っていた。天井の電灯がときおり、じじ、と音を立てる。
白茶色の麻スーツを着た田中は、彼に一礼した。
「夜分に失礼いたします。なにしろ、思い立ったら我慢のできない性格でして」
「どこかでお会いしましたか?」
彼は聞いた。
「いえいえ」
田中は手を振った。顔の艶は良いが、頭髪はまるきり白髪だ。この男、アルビノなのかもしれない。
シロという名前が頭に浮かび、彼は眉をひそめた。あれは妻が残した白猫だった。
「偶然、先生の書かれたものを読ませていただきまして」
田中が言ったのは、果たして彼が知り合いの大学人に送った論文だった。東西の憑き物に関する研究をまとめたものだ。
「いや、驚きました。縦横無尽とはあのことですね。膨大な資料を調べあげ、あのような結論に至る、まるで手品を披露されているような、いえ、これは褒め言葉です」
彼はもぞもぞと尻を動かした。
「私は先生なぞと言われる者ではありません。どこに属しているわけでもなく、ただ市井の研究者としてアレを発表しただけです」
「それは違いますな」
田中は否定した。「どこの大学に属している、研究所で働いているなど、些末な話です。そんな俗な卑下は、あの論文を書かれた先生には似合いません」
「卑下している気などありませんが」
彼は少し気分を害して答えた。まるで田中が判定の権利を持っているようではないか。
田中はにやりと笑った。そうすると整った顔の向こうに、粗野な何かが垣間見えるようだ。
田中は湯呑みを取り上げ、丹念すぎるほど息を吹きかけ冷まし、茶を飲んだ。
田中の右手の甲には、二寸ほどの白い毛が生えふわふわと動いていた。福毛だ。手入れの行き届いた姿形の田中にしては、その一点、均衡を欠いているように見えた。
彼が目を戻すと、田中の顔相が変わっていた。
猫にである。
彼が玄関脇の書生部屋のドアをノックすると、速水が顔を出した。
「お客様がお帰りでしょうか?」
「いや………」
彼は茶のお代わりと、何がしかの菓子を速水に頼んだ。「どうやら、あの論文を読んで、教えを請いに来たようだ。長い話になるかもしれない。こんな時刻に申し訳ないが………」
「それはようございました」
速水は顔を上気させた。論文を書くにあたって様々な資料を集め整理する手助けをした身としては当然だろう。「やはり届くべき方には、届くのですね」
「ああ、そのようだ」
彼は落ち着かない気持ちで答えた。
応接間に戻り、田中がまだ猫、あのシロの顔をしていたら、どうすれば良い?
今すぐに速水を連れ、田中の顔相を検分させたい。
しかし恐れもあった。
速水が客の顔を猫と認めなかったら? それは彼の精神の異常を証明することにならないか? 狂気の根元には、もちろん妻とシロに対する罪悪感がある。
「すぐにお持ちします」
速水は微笑み、そこに突っ立っている彼の意図を誤解したか、顎を伸ばし、素早く彼の唇を吸った。
応接間のドアを開けると、田中はまだシロの顔をしていた。先ほどよりいっそう猫らしく、顔全体が白毛にびっしりと覆われている。部屋にただよう生臭い臭いは、獣特有の体臭だった。
妻の死後、シロは近所の悪童にくれてやった。野良猫を池に放り込むような子供だった。
彼は元来、猫が嫌いだった。妻が実家から連れてきた猫だから我慢をしていたのだ。妻がいなくなれば、シロを飼い続ける義理などどこにもなかった。
「女性の書生とは珍しいですね」
不意に、田中が言った。
彼はうろたえ、さっき速水に吸われた唇に指をやった。
「あれは亡妻の在所から来た娘で、学問の面で大変見込みがあって………」
弁解じみた口調で言うのに、
「おまけに、大層美しい」
田中は言った。
「そうでしょうか?」
「いっそ後添えになどと、お考えなのでは?」
田中はひどく不躾なことを言った。吊り上がった目の底が金色に光り、瞳孔は細くすぼまっている。
彼は唾を呑み、
「まさか。ご冗談を」
力なく答えた。
田中が声もなく笑った。
速水とのどっちつかずの関係は、妻が病に伏ししばらくした頃に始まった。
………アレは疑っていた。
衰弱するに従い、速水への妻の態度が邪険になっていったのは、彼女の嫉妬だったに違いない。
妻は二人に対する恨みを抱いたまま死んだ。
その考えが呪縛になり、彼は速水に向かって一歩を踏み出すことができずにいる。
話の最中に速水が茶と桃色の干菓子を持ち、応接間に入ってきた。
………どうだ、この客の顔は? 猫だろう、猫に見えないか?
彼は速水が悲鳴をあげて湯呑みを取り落とすことさえ期待した。しかし速水は目を伏せたまま茶を換え部屋を出ていった。田中の顔を見たのか見ないのか、彼には分からなかった。
夜が更け、庭はすっかり闇に呑まれていた。
「もう一人、客がありそうですね」
音を立て、赤い口を見せ菓子を砕いた田中が言った。
「あなたが呼んだのですか?」
彼は聞いた。だとしたら不躾な話である。
「いえ、呼んだ覚えはありません。どうやらついてきてしまったようですね」
田中は面白がるように言った。「私も迷惑をしているんですよ。ああいった者たちは、自分で自分の家に戻ることさえできない。盲のようなもので、飼い猫の後を追い、ようやく辿り着く」
「自分の家?」
彼は言った。「………誰です、それは」
「しっ」
田中は長く白い人差し指を口の前に立てた。「聞けば分かります。ほら」
彼は耳を澄ました。微かに、………シロ、シロ、と呼ぶ女の声がある。誰かが家の中にいる。速水は気づかないのか?
「分かりましたか」
シロは彼を見て言った。
廊下を近づいてきた足音が、部屋の前でとまった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
