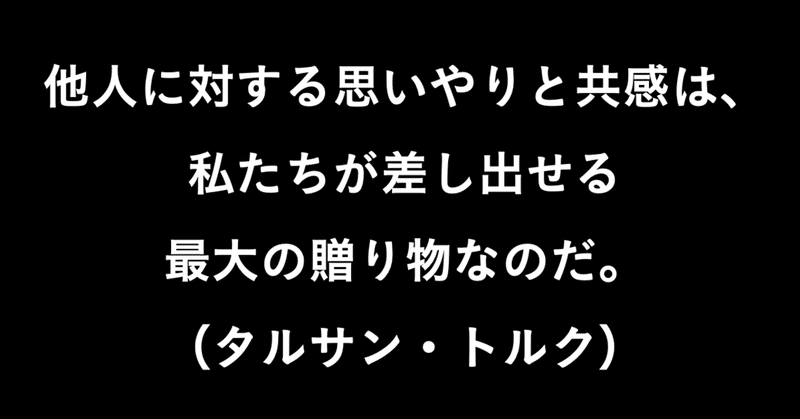
「鶴の恩返し」で部屋を覗いてはならない理由は「贈与」の仕組みにあった
【超訳】贈与は合理的であってはならない。非合理なものだけが、受取人の目に贈与として映る。贈与の正体とは本質的に偶然で、不合理なものであることが、贈与を差し出す人間に必要な資質だ

もし1年後に死ぬことになると言われたら、この本を読み直すかもしれない。一生というあまりに短い人生で、だれに何を残すことができるのか、ということを深く、哲学的に考えさせてくれる秀逸な一冊。人類とは進化の歴史であり、進化とは「贈与」の歴史である。贈与、施し、偽善。人に何かを与える、そして与えられることを前提として生きてゆく、生きてゆかざるを得ないことを運命付けられていることを改めて痛感させられる一冊だ。
「自分へのご褒美」は空虚
贈与とはモノを「モノではないもの」へと変換させる創造的行為に他ならない。誰から贈られた瞬間に、この世界にたった一つしかない特別な存在に変貌する。つまり、他社から贈与されることでしか、本当に大切なものを手にすることはできない。
確かにその通りかもしれない。ゆえに、自分へのご褒美に対する何となくの虚しさというのは感覚的に捨象できない。マーケティング、経済学の合理主義的な観点からすれば一見、非効率に映るこの贈与という行為の本質はどこにあるのだろうか?
「贈与の受取拒否」は関係性の拒否
なぜ贈与がつながりを生むかといういと、贈与には必ず返礼が後続するからだ。つまり、贈与というのものは、単にモノではなく、つながりを持つことを受け入れることそのものである。こちらの好意や善意は必ずしもうまく伝わったり、相手が気持ちよく受け取ってくれるとは限らない。だからこそ、プレゼントといった贈与を受け取るという行為を、嬉しく感じるのだ。
”無償の愛”の正体とは「孫の顔がみたい」
”無償の愛”とは、贈与の宛先である子供からの見返りを期待しない、という点では正しい。だが、贈与というのは、無から生まれるものはではなく、そのまた親からの無償の愛という、プレヒストリー(贈与以前の贈与という歴史)が必ず存在する。「不当に愛されてしまった」という被贈与感と負い目を感じることこそが、無償の愛の正体なのだ。
だから、この無償の愛には不安がつきまとう。そして、その不安は、「子がふたたび他者を愛することのできる主体によって」自分の愛の正当性を確認できる。「孫の顔がみたい」と切に願うのは、ここにつながってくる。
計算可能な贈与。人はそれを偽善と呼ぶ
誰かに与えることを計算したとたん、それは贈与ではなく、金銭的ではない形の「交換」となる。自己利益を見込んでの行為なのにもかかわらず、本人の主観的には純粋な善意による一方的な贈与であることを装うことを、僕らは「偽善」と呼ぶのだ。
・贈与は受け取ることなく開始することはできない。
・贈与は返礼としては始まる
・贈与は必ずプレヒストリーが存在する
これこそが贈与の力学なのだ。
ビジネスパートナーとは友人関係になりにくい理由
結論、互いを手段として扱うからだ。「助けてあげる。で、あなたは何をしてくれるの?」これこそがギブ&テイクの論理を生きる人間のドグマだ。ギブン&テイクやWin-Winの論理は「交換するものを持たないとき、あるいは交換できなくなったとき、そのつながりを解消する」という非常に公平かつ平等であるが冷徹なものともいえる。
つまり、贈与のない世界に信頼関係は存在しない。裏を返せば、信頼は贈与の中からしか生じない。合理主義が嫌う「ムダ」「非合理」なやりとりこそが信頼関係を構築する手段ともいえる。こういう論理でみると、なぜプレゼントを送り合うのか?飲み会という場が存在するのか?日常的な疑問も解消されてくるのではないだろうか?
ギブアンドテイクについては、過去の記事で『GIVE & TAKE「与える人」こそ成功する時代(アダム・グラント)』を考察しているのでぜひ、以下のリンク先から読んでほしい(渾身のレビューです!)
驚愕の真実。最も成功するのはギバーだが、最も失敗するのもギバーだった
仕事のやりがいも贈与論で説明できる
人はインセンティブ(報酬)によって行動し、サンクション(制裁)によって行動を抑制する考えがちがそれは異なる。倫理、義務感、誇り、プロ意識といった内的動機が、金銭というもので交換できるとなった瞬間、その価値は瓦解し、頽落してしまう。仕事のやりがいとは、責任であり、使命である。天職とは、自分にとって効率的に稼げる職業ではなく、誰から呼ばれること「使命感」によって支えられるものだ。自分のできることと自分のやりたいことが一致しただけでは天職とは言えない。「自分がやらなければならないと気づく」、すなわち使命の自覚が発生しなければならない。
事実、成功者というのは使命感が強い。ただ、個人的に勘違いしてはいけないと思うのが、使命感=MMV(ミッション・ビジョン・バリュー)・パーパスの策定すれば良いと安易に企業理念の策定に結びつけないことだ。それらはあくまで手段であっても、そもそもの原動力がないものは決して天職にはなりえないのだろう。
鶴の恩返しで部屋を覗いてはならない理由
「これは贈与だ、受け取ってくれ」と明示的に語られる贈与は呪いへと転じ、その受取人の自由を奪う(例えば年賀状。なんとなく返さないと気分が悪くなる感覚に近い)。手渡される瞬間に、それが贈与であることが明らかにされてしまうと、それは直ちに返礼の義務を生み出してしまい、「交換」へと変貌する。そして交換するものを持たない場合、その負い目に押しつぶされてしまう。
鶴が「部屋を覗いてはならない」という禁止は、男に知られないようにすることで純粋贈与を完遂しようとしていた。もし、覗かれてしまうと恩を返すという「交換」に成り下がってしまうためだ。私たちにできることは何があるのか?それは「あれは贈与だった」といつかどこかで気付き、贈与を連鎖させること、受取人としての想像力を発揮することだけである。
贈与はだれにつなぐべきか?
贈与は使命感である。つまり、誰かという宛先が存在する。しかし、よく考えてみると宛先を持つというのは奇跡であり偶然だ。宛先がなければ手紙を書くことはできない。そして宛先を持つというのは、その存在自体が贈与の差出人に生命力を与えることになる。
これも日常でよく目にする光景として、アーティストが「ファンのおかげです」と謝辞を述べるのもこの一例だろう。自分が元気づけているようで、差出人(アーティスト自身)が元気をもらっているということでも説明できる気がするがどうだろうか?この世に生まれてきた意味は、与えることによって与えられる。与えることによって、こちらが与えられてしまう。
贈与は市場経済の隙間に存在する
資本主義はあらゆるものを「商品」へと変貌させ、等価交換を前提とした市場経済で成り立っている。だからこそ、一見不合理な「商品でないもの(贈与という行為)」にふと気付いたり、心を奪われたりする。
そして、この日常も社会も不安定なつり合いの上に置かれた文明がこれまでに安定して、昨日と変わらない今日がやってくること自体、これ以上ない不合理であり、アノマリー(常識に照らし合わせても説明がつかないこと)であるということに気づけるものだけが贈与を受け取り、差し出す資格を持てるのだ。私たちが贈与に気づいていないだけで、この社会には語られることなく連綿と受け継がれる贈与が歴史を紡いでいるのだ。まるでサンタクロースのように。
教養ある人間とは「贈与に気づけるひと」
贈与はすべて「受け取ること」から始まる。そしてその贈与の受け取りにどうやって気づけるようになるのか?それは、歴史を学ぶことだ。歴史を学びながら、もしその世界に自分が生まれ落ちたらこの目に何が映るか、どう行動するか、何を考えるのかを意識的に考えることに尽きる。
この世界の壊れやすさ、この文明の偶然性、これらに気づくには、意識しない限りは決してみえてこない。想像力を働かせ、世界が贈与に満ちているかを悟ることができる人間が、教養があるといえるのだ。ボランティアブームは起きても献血は人気がないという矛盾。目の前に誰に何を贈与しているのかを実感できないことにも、どれだけ真摯に想像力を働かせることができるか、それが教養人なのだ。
ハラスメントゼロの社会へ!サポートは財団活動費として大切に活用させていただきます。
