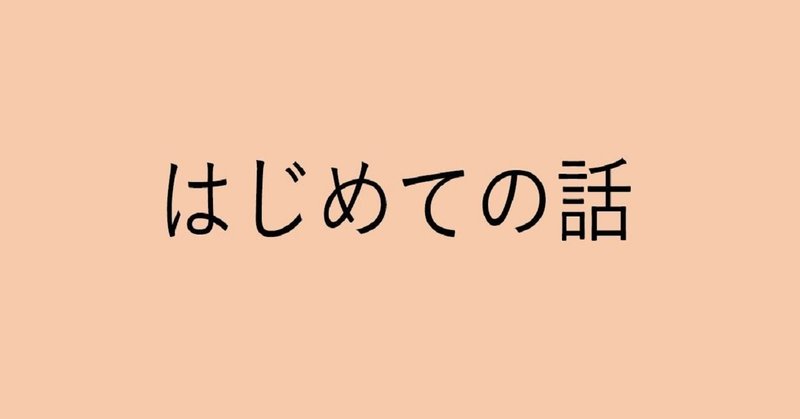
はじめての葬式
私が中学生の頃、同居していたおじいちゃんが亡くなった。
ある日の授業中、突然教室のドアを開けて校長先生が私を呼んだ。
何事かとざわつくクラスの中を横切り、廊下に出ると校長先生は小さな声で言った。
「お家の方から連絡があって、おじいさんが亡くなられたそうです。今日はもう早退して帰宅しなさい」
もちろんその言葉の意味は分かった。
私は教室に戻って「えっ、なになに?」と袖を引っ張るクラスメイトを無視して鞄を肩にかけ、学校を出た。
家までは徒歩で30分近くかかる。道路をあと一本分離れていれば自転車通学が許可されていたのに、と何度も思ったものだ。
歩きながら何度となく校長先生の言葉を反芻したが、まるで国語の時間に興味のない文章をなぞっているだけのような空々しい感じがするだけで、おじいちゃんの思い出とかそういうものは全く浮かんで来なかった。
家に帰って、もし両親やおばあちゃんが泣き崩れているとか、文字通りのお葬式ムードだったなら、私もそこに加われたかもしれない。しかし現実にはまるで急遽大売り出しが決まったかのような大騒ぎだった。葬儀の手配やらなにやら忙しかったのだろう。
玄関で立ち尽くす私に気付いた母が足を止めて、一瞬言葉を飲んでから「居間におじいちゃんいるから、手を合わせてきて。それから部屋にいなさい」と言った。私は言われたとおりにした。
それからは、はじめての連続だった。
おじいちゃんは私にとって初めて見る人間の遺体だったし、鼻や耳に綿を詰めることや、化粧することや、一晩誰かが同じ部屋に寝ることや、棺の釘を順番に石みたいなので打つことや、葬式と焼香にすごくたくさんの人が来るような人だったことや、火葬場では時間がかかることや――何もかも初めてだった。
葬式には親族として参列していたが、母と姉は泣いていたし、父と兄はフラフラしてモゴモゴ返事していた。私は直立したまま機械のようにただ、挨拶されたらそれに返し続けた。
ここは泣くべき場面だ、と心のどこかで思ってはいたものの、涙は出なかった。頭の中に石が詰まっているような感じで、ただ決められた事をする以外に何もできなかった。
全てが終わって親戚だけになり、「浩くんは偉い。一番しっかりしていた」と褒められた。兄はそれが気に入らなかったらしく、「あいつは心がない。冷たい」とか何とか言い、姉は「本当は悲しいけど我慢してるんだ」と私を擁護した。実際はそのどちらでもなかったのだが。
そうして親戚も去り、嵐が去った静けさだけが残った。
父はさっさとネクタイを外して喪服を脱ぎ、ビールを飲み始め、母と姉は残った料理をタッパーや皿に移して冷蔵庫にしまう作業に入り、兄はテレビを見始めた。私は一人、自室に戻った。
そして、部屋に入った瞬間だった。
突然、胸の奥から感情が溢れ出してきて私はその場に泣き崩れた。
泣き崩れる、というのはこういうことだと知ったのも、それがはじめてだ。立ち上がれず、その場に座り込んでわんわん泣いた。やがて喪服代わりの制服もそのままにベッドへ飛び込んで、ぐずぐずと泣き続けた。
喧嘩して「クソじじい!」と怒鳴ったら顔を真っ赤にして怒った事や、毎日飲む色とりどりの錠剤がキレイで欲しがって困らせた事や、絶対に興味ないであろう変なキーホルダーを修学旅行のお土産に買って帰ったらものすごく喜んだ事など、次から次へと思い出が再生された。そのまま私は眠ってしまい、翌日の朝まで目を覚まさなかった。
ちなみに、祖父の最後の言葉は「ああ、いいお湯だった」だそうである。
少しでもお心に触れましたら「スキ」して頂けると励みになります。
