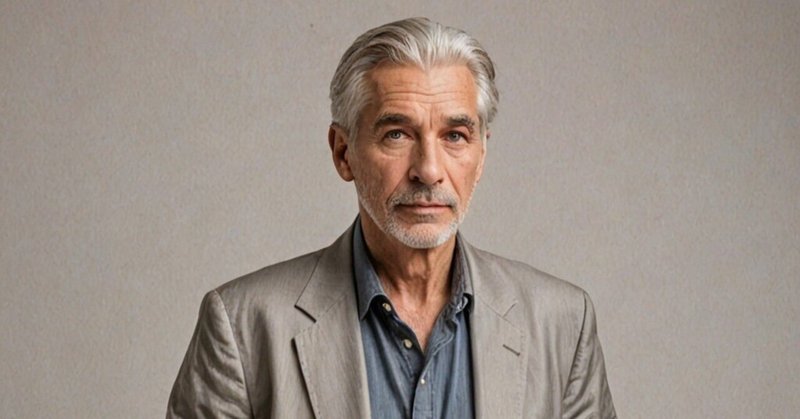
父への手紙 最期に贈る言葉
この執筆を終えた時には、父は、もう読むこともできない状態でもあるし、この世を去っているかもしれない。
家庭を顧みずというのはよく言われることではあるけれど、父の生まれた世代では、それが当たり前な立ち振る舞いで、がむしゃらに前進しなければならない世の中であったことも今では理解できます。
日本は、ハイコンテクストな社会と言われ、「言わなくても言いたいこと分かるでしょ」の社会かもしれない。
しかし、それは日本だけの話。
そんな日本においても、言わなければ分からないことはたくさんあり、うちの家庭には、そういう事例は多く存在していた。
恐らくうちの家庭だけでもなく、他にも多くの家庭がそうだと思う。
家族、家庭、会社において、上手くいかないことの原因の最たるものは、コミュニケーションの欠如で、ちょっとした共感、話し言葉の選択だけで、全ての不協和音は取り除かれる。
きっと、なんとなくは父も分かっていたのだと思うけれど、アルツハイマーになって喋れなくなった後、伝えきれなかった様々な言葉や感謝が溢れかえってきたのではないだろうか。
それが涙になって表れたのだと思う。
あの涙に込められた気持ちや言葉を伝えられることができたら、父の人生も悪くない、興味深い人生で幕を閉じることができたのではないかと切に思う。
父とは、一緒に過ごす時間は殆ど持てず、一緒にいた時でも多くを語る人ではなかったけれども、一対一で話す時は、家庭にあまり関心のない父親ではなく、非常にプロフェッショナルな意見をくれる人だった。
平社員から経営者にまで昇った背景には、頑固でありながら間違ったことは許せないという会社人としての真摯な態度に他ならない。
真摯な一面を家族には見せられなかったが、ストレスや無駄の多い伝統的な日系企業での就労の毎日を過ごした日々、帰宅後や週末は、誰にも邪魔されず自分時間を満喫したかった一心であったと思うが、そのミスコミュニケーションもあり、家庭での父親という役割を全うしにくかったのかもしれない。
私に留学という機会をくれた父は、一緒に過ごす時間を過ごせなくとも、父親としての責任は全うしてくれたんだと思う。
アルツハイマーになる前、「俺は、家族に迷惑かける死に方はしない」と言っていたような気もするが、人間は基本的に他人に迷惑をかけなければ生きていけない生き物である。
アルツハイマーになって本人は迷惑をかけるつもりはなかったとしても、結果的に人の力を借りなければ最期は迎えられないし、迷惑をかけてくれて構わない。
それが会社と家族の違いであり、そういう生き方こそ、人間的な生き方と言えると思う。
年齢的にはまだ早い時期にアルツハイマーになってしまい、コミュニケーションは取れなくなったが、妹達は父のことを心から頼りにしていたし、慕っていたことを忘れないで欲しい。
皆、歳を重ねて名古屋という土地から見舞いに来るまで、老体に鞭を売ってでも来てくれた。
それだけ愛されていたということを胸に、最期を迎えてくれると信じている。
人生で一度も涙を見せなかった父が、アルツハイマーになって初めて涙を見せた。
母や兄の見舞いに対しても涙を見せた。
それが父の本当の姿であり、家庭に関心を見せることがあまりなかった父の姿は、正直な自分を見せるのが恥ずかしかった昭和の男にはよくある姿だったと皆思っている。
長い間、家族を陰で支えてくれてありがとう。家族を代表してお礼をいいます。
2024年4月7日、父はその生涯に幕を閉じた。
夜中の3時頃に息を引き取り、死亡診断書に記載された確認時刻は、午前8時34分。
家族の誰も、死に目に会うことは叶わなかった。
兄は、施設から連絡を受けた夜中に、私にラインで知らせたが、私のスマホが睡眠中のミュート状態になっており、気が付かなかった。
父が亡くなった知らせを聞いたのは、朝の7時くらいだ。
葬儀は、亡くなってから九日後に執り行った。
一日で行う家族葬という形態で行った。
「九日後って遅くない?」
恐らく誰もがそう思うだろう。
葬儀当日、その日が、父の死後、私が初めて父の顔を見た日である。
広角は上がっていた。
笑っている口の形だった。
息を引き取る時も、静かに口を開けて逝ったようである。
まるで、口から魂が抜けていったようにも思える。
話を戻して、葬儀屋さんに、死亡から葬儀まで時間が空いているのはなぜかと尋ねると、今は、火葬場の予約がなかなか取れないからとのこと。
団塊の世代が、次々に亡くなる時期に来ており、お通夜や告別式を色々なところで執り行うことができたとしても、火葬場に持っていくまで、遺体を保管しておかなければならないのは同じ事なので、火葬場の予約が入る日に合わせて葬儀を行ったという流れだ。
勿論、市外の火葬場に依頼することも可能だが、市内だと六千円で依頼できる火葬が、市外の火葬場に依頼することで、20万弱になるところもある。
お金を持っている家庭であれば、市外に頼むかもしれないが、市内の予約が取れないということは、それだけ財政的に余裕のある家庭は多くはないのが現状かもしれない。
特に、葬儀に親族全員を呼ぶとなれば、火葬場以外の費用もかなり掛かる。
そうであれば、待ってでも予算を抑えたいと思うのは、理解できる。
父の遺体は、九日間保存されていたわけだが、指が赤く壊死し始めていた。
遺体としても、ギリギリの状態だったのがうかがえる。
お通夜と告別式を一回で済ませるわけだが、4歳と6歳の娘も、お焼香というスキルをここでラーニングした。
妻は外国籍でカトリック教徒なので、勿論お焼香も初めて行ったが、見よう見まねでよくできたと思う。
いよいよ火葬の段階に入る。
火葬を始めてから2時間程待つわけだが、この間に昼食を済ませる。
久しぶりに、日本的なお上品なお弁当を頂いた。
亡くなった父の遺影にビールを注いで一緒に昼食を取るわけだが、落ち着きのない長女は、父のテーブルに行き、
「どうしてビールは減らないの?」
と質問をする。
「逆に減ったら、怖いだろ」と答える。すると長女は
「あっ、でも少し減ってる」と続ける。
ビール減らす前に、口数を減らした方がいい。
と言うのも、長女が父から最後に聞いた言葉は、
「うるさい!、うるさい!」
だったからだ。
父は、母以外には怒る人ではなかったが、アルツハイマーになると、優しかった人が怒りっぽくなり、怒りっぽかった人が優しくなるという話を聞いたことがある。
まさにそれだった。
長女と次女が実家を訪問した時にはしゃいでいて、特に長女の騒ぎ方が激しい。
父は、私たちが語りかけても、まともに話せなくなっていた時期だった。
その認識で長女が騒いでいると、今に座っていた父が突然、野太い声で
「うるさい!うるさい!」と二回はっきりと言ったのである。
怒ることがなかった父が怒ったので、その場にいた全員が、父を驚いたように見た。
一瞬、場が凍るという感じ。
そこにいた皆が「ていうか、話せるじゃん」と思ったのは言うまでもない。
長女や次女も驚き、舞台袖へと姿を消した。
葬儀の日、長女に
「おじいちゃんから最後に言われた言葉、覚えてる?」
と尋ねると、
「うるさい!、うるさい!」
と再現V並みの模範解答を答えてくれた。
個人的に、小学校の低学年の作文で「おじいちゃんからの最期の言葉」という題で、記録に残してくれると、父も浮かばれると思う。
この「父への手紙」に書かれてある言葉をかいつまんでいくと、「家族に関心がない」「漬物がないとキレる」「駅伝バカ」「競馬に夢中」「孫への最期の言葉がうるさい!」となり印象が悪くなってしまう。
どうか、かいつまむことのないようにお願い申し上げる。
この手紙を父の臨終までに書き上げることが叶わず、棺に一緒に入れることが出来なかったのは、残念でならない。
しかし、父がアルツハイマーになり、私に執筆をさせているんだと思う。
父に編集者がいれば、間違いなく売れない小説を書き続けていたと思うし、書き上げた後、毎回「これ、読んでみ」と私に渡して読ませることを止めなかっただろう。
当時、私には、小説の良し悪しが分からなかった。
ましてや、父が受講しているクラスで書いた短編の表現が、よくかけているのかどうかも分からなかった。
しかし、父は毎回「読んで感想聞かせて」と半笑いで私に強制してきた。
本人は相当自信があったのだと思う。
生まれながらにして、根拠のない自信家だった。
朝日新聞の受講を止めてからは、書くことを止めたのだが、書いた作品を承認してもらう講師がいなくなったから止まってしまったのだと思う。
だから、作家として、鳴かず飛ばずを実現でいていたら、アルツハイマーにも早期にはかからなかったかもしれない。
その父の見えない力が、私に書かせているのだと考えるようにしている。
父の遺伝子を受け継ぐ以上、鳴かず飛ばずも続けなければならないと思うと、自分の宿命が許せない。
人生、一度でいいから、鳴いたり飛んだりしてみたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
