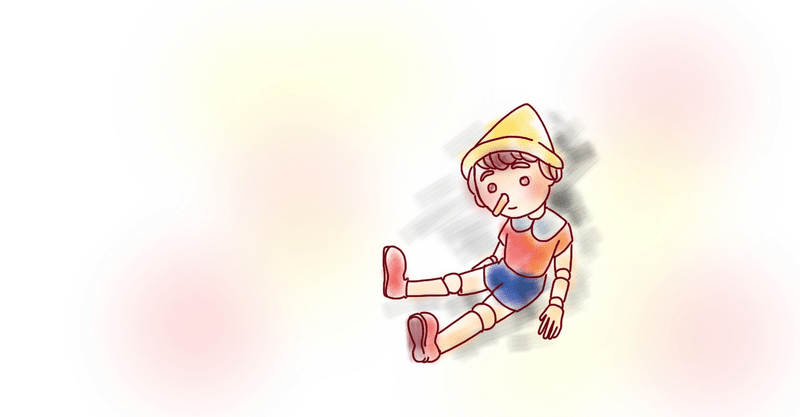
続・なぜ、小さな「ずる」をしてしまうのか。
大学時代にアルバイトさせてもらっていた焼肉屋の「店長被害者の会」で会食中、
「この前、店長がJUN先輩を怒ったとき、本当は私のミスだったんです。でも、JUN先輩はかばってくれて・・・。」
という、男前エピソードを後輩が話始めたとき、心の底から思い当たる節がなくて、「人違いじゃね?」と思いながらも、「おっ、おぅ。」と、受け入れてしまったJUNです。
本当に神に誓ってそんな神エピソードなかったんです。すみません。
先日、ちょっとした「ずる」について書きましたが、本日はその続編。
「安心できる集団ほど、『ずる』が増えるよ!」という話題です。
何かしらに取り組む際、グループ活動というのは選択肢の1つとなりますよね。ぜひとも、本記事を読んでグループ活動を見直していただけたらと思います。
▶グループ活動のメリット。
学校では、集団での学び合いを基本としていますが、あまりにも大集団だと学習効果が下がることは請け合いです。だからこそ、少人数グループでの学び合いを授業に取り入れていくのは当然の選択でしょう。しかし、難しいのが「気心知れたメンバーで集まると、逆に『ずる』を生じさせて、学習効果を下げてしまう。」というような事実を発見しました。
#「ずる」嘘とごまかしの行動経済学
とはいっても、もちろん、グループ学習でのメリットはあるのです。一人で取り組んでいてもらちが明かないときは協働で進めた方が双方にメリットがあるでしょう。
話し合い活動に関しても、大人数で話すよりは自分の主役が回ってきやすい少人数グループで取り組んだ方が、自分事として参加できる可能性も高まります。
このようにメリットはあるのですが、ちょっとした葛藤場面が訪れると、気心知れたメンバーが集まっている集団ほど、残念な結果となることもあるのです。
▶気心知れた集団だからこその「ずる」。
前回にも同じような実験を紹介しましたが、おもしろいのでもう一度紹介させたください。ざっくり結論を書くと、
「テストの採点場面。他者に採点されるよりも、自己採点をさせると若干ずるをして得点を高めてしまう。」
という特性が人間にはあるという結果でした。
さて、この実験に「監視者」をつけたらどうなると思いますか?
そうです。あなたが、テストの採点をしている様子を背後からじっと見ている監視者。なんとその影響は絶大で、
「得点の水増しが0になった!」
ということなのです。やはり、「見られている。」という意識は強いということですね。しかし、ここで実験は終わりません。
その「監視者」を気心知れた友達にした場合はどうなるか分かりますか。本記事の内容から推測すると、結果は分かってしまいますね。そうです、
「得点の水増しが起きた。」
ということなのです!!
あらら・・・。の結果ですよね。この実験から分かることは、
「だれに監視されているかにより、誤魔化し具合が変わる。」
ということなのです! やはり人間っておもしろいですね。
さらに、おもしろい結果もどうぞ。
次の実験では、初対面の監視者とテスト前に「簡単な関わり場面」を設定するとどうなるか分かりますか。簡単にいうと、監視者と
「少しだけ打ち解けた状態になる。」
ということです。なかなか、絶妙な実験ですよね。その結果がおもしろくて、
「得点の水増しが予定通り実行された。」
人間の大胆さ!! 監視者に対して少しでも心を許していると、監視の意味はなくなっていまうのですね。
▶グループでの学び合い。
さて、学校場面に照らし合わせてみましょう。
この結果から使えるのは、学校での「グループ編成」場面でしょう。グループ編成で意識しておくことは、
「仲の良い友達同士でグループを組むと、気心知れているだけに話し合いが盛り上がる反面、些細なところで誤魔化しがうまれ、学習効果を阻害してしまうこともある。」
ということが言えるでしょう。
気心しれたグループメンバーでの教え合いを期待してグループ編成をしたのにもかかわらず、
「これ? ちょっと違うけど・・・。まぁ、ほぼ正解だからいっか。」
というような甘めの採点をしてしまう可能性が考えられますね。理解できてないのに、「大丈夫大丈夫!」と先に進んでしまうということが起きているかもしれません。
▶まとめ。
本記事では、「友達だからこそ厳しくしてあげて!」という話題をまとめました。僕もグループ学習を取り入れると「なんだか、楽しそうに話し合っているな。」なんて平和ボケしたみとりをしてしまうこともありました。
しかし、「楽しさ!」と「しっかり学んでいるか!」は、分けて考えないといけないということですね。あまりにも仲良しグループ学習を乱用すると、「あんなに楽しそうに勉強していたのになんでこんなに点数が取れていないんだ?」という結果になってしまうでしょう。
教師としては、グループ学習後の振り返りも重視していく必要があります。
また、グループ学習の目的、
「グループで教え合い、全員が完璧に問題を解けるようにしよう!」
など、「結果」を問うのではなく「理解度」を問うような目的を明確にしてスタートすることも効果的でしょう。
グループ学習はメリットがたくさんありますし、仲良しメンバーであるという利点もあります。だからこそ、その良さを十分に生かせるよう支援してあげてくださいね!
正直に録音しました。
いただいたサポートは、地域の「居場所」へ寄付させていただきます!
