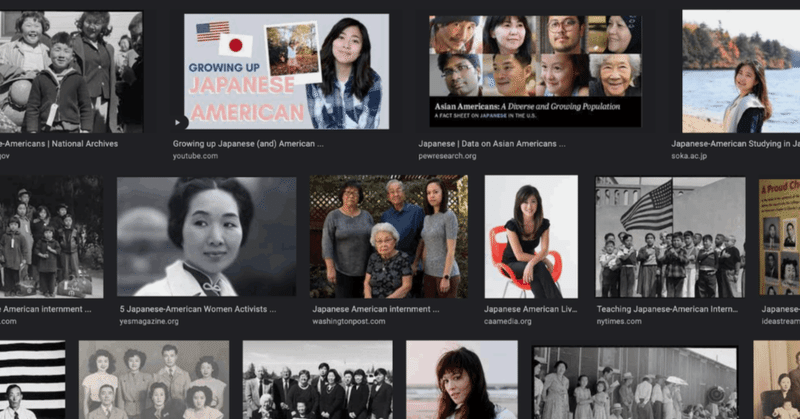
日系アメリカ人2世の視線と視野 その2(映画製作者)
最近、2人の日系アメリカ人の作品を見る機会があり、日系人という立ち位置の人のものの見方に触れ、興味をもちました。
この記事は、その1「真崎嶺さんの『サラリーマンはなぜサーフボードを抱えるのか』」のつづきです。
*タイトル写真はGoogleイメージ検索で「Japanese American」の結果より
ミキ・デザキさんの映画『主戦場』
先月noteを閲覧しているときに、映画『主戦場』がネットで配信されることが決まったという記事を読みました。映画のことも、制作のデザキさんのことも、まったく知らなかったのですが、この映画が日系アメリカ人監督による従軍慰安婦問題を扱ったものだと知り、見てみようかという気になりました。実際には見るまでに少し時間がかかりました(時間が取れなかったのと、有料コンテンツ/税込1100円だったこともあり見ようかどうか迷っていた)。そして判断するためもあって、本編を見る前に、デザキさんを取材した映画にまつわるインタビュー動画を見てみました。(「池田香代子の世界を変える100人の働き人」シリーズ)
ミキ・デザキさんのプロフィールをこの動画から引用すると:1986年、フロリダ州生まれの日系アメリカ人2世。ミネソタ大学で生理学の学位を取得後、2007年に来日。英語補助教員として山梨、沖縄で2012年まで中学高校で英語を教える。YouTubeでコメディビデオや日本、アメリカの差別問題をテーマにした映像作品を制作、発表。2018年、上智大学で修士課程を修了。同年、修士論文に代わる映像作品『主戦場』により、山形国際映画祭のドキュメンタリー・コンペティション部門の招待を受ける。
このインタビューをデザキさんは日本語通訳付きで受けています。日本語は聞く方は問題ないけれど、しゃべる方は正確に丁寧に伝えるために母語の英語で答えたい、ということでした(通訳者の質は高かったです)。実際のところ、デザキさんは日本人両親のもとで育っているので、日本語はかなりうまいですし、英語なまりがそれほどあるわけではありません。ただやはり母語である英語の方が、ずっと考えていることをスムーズに話せるのは、インタビューを聞いていてわかりました。
さて映画『主戦場』ですが、扱っているテーマがcontroversialな(論議、論争を呼ぶ)ものだったことが、購入→視聴の最終的な引き金になりました。
この映画の主題である慰安婦問題に詳しいわけでもなく、これまでにそれほど関心があったとは言えないのですが、韓国と日本の活動家、政治家の間で、あるいは一般社会的にも、慰安婦少女像設置の問題を中心に、物議をかもすアブナイ話題(この問題に触れたことで誹謗中傷を受けるといった)であることは知っていました。
インタビュー動画を見て、この映画を見てもいいかなと思ったのは、一方に肩入れするプロパガンダ映画ではなさそうだったことがあります。この問題をできる限りフェアな形で、多くの、両サイド(人権主張派と「ナショナリスト」または「否定論派」)の識者や論客に率直な考えを話してもらい、それを並べ、比較し、そこで話された事柄を一つ一つファクトチェックにかけ、視聴者自身がそれをどう見るか、どう考えるかの材料としてほしい、という態度で制作したことが見えました。
デザキさん自身、人権や差別問題には関心があったものの、慰安婦問題に詳しかったわけではないそうで、この問題が大きな議論を呼んでいることに興味をもった、それが映画制作のきっかけとなったと語っていました。
『主戦場』では、たくさんの人(日米の両サイドの歴史学者、憲法学者、活動家、政治家、元慰安婦の人、その家族、元日本兵などの関係者)が、次々に、交互に目まぐるしく登場し、発言します。一つの事実についての発言を両者の対比として素早い切り替えで見せたり(一方がAと言うのに対し、もう一方がBと言って切り返すなど)、発言を裏付ける(または否定する)テキストや図、グラフなどの資料、図書をパッパッと画面上でハイライトを付けて示すなど、息つく暇もないような展開です。デザキさんによるナレーション(日本語字幕付き)も2倍速くらいのスピードで、1回見ただけですべてを頭に入れ、理解するのはなかなか難しいかもしれません。4時間分の内容を2時間にまとめたような印象です。
ここで、この映画の内容について詳しく触れることはしません。見終わっていくつか印象に残ったことを記してみます。
日砂恵・ケネディさんという、元ナショナリストで元「歴史修正主義者」だったという人のインタビューが目にとまりました。ケネディさんはナショナリストとして活動していた頃は、「次期櫻井よしこ」と称されるくらいの右派の論客だったそうです。当時自分の考えていたことについて、次のように語っていました。
日本が糾弾されることで、自分自身が攻撃を受けている、名誉を傷つけられていると感じていた。自分自身のために、自尊心を守るために、擁護しなければと思った。
日砂恵・ケネディさんは日本で生まれ育ち、アメリカ人と結婚してアメリカに住むようになった日系人で、その点が真崎・デザキ両氏とは違います。「アメリカに住むようになった日本人」として、日本のことを非難されると自分が攻撃を受けているように感じてしまった、ということでしょう。
ただ、これは多くの一般の日本人の中にもある心理ではないかと思います。日本のことを悪く言われる、海外から非難されると、それを国家に対する申し立てではなく、自分への攻撃と感じてしまうという。それで深く考えることなく反発するようなことを口にしてしまう。
ここには日本の人が抱えてる心理的な落とし穴、アイデンティティの問題(自分と日本という国家を同一視してしまう)が関係しているように思います。自分という存在を国家から分離して考えられない、考えることが難しいということです。自分とは何か、日本とは何か、自分と日本との関係はどうあるのか、どうありたいのか。外部から日本について問題を指摘されたとき、本当にそうなのか、という冷静な疑問をもつより先に、瞬間的に反発心が湧いてしまうということが起きます。このことと、日本における個人に認められている社会的権利の低さ、人権に対する軽視傾向とは関係があるように見えます。
この映画を見て、もう一つ気づいたことは、教科書問題のことの起こりについてです。日本政府が慰安婦問題について韓国に正式に謝罪し、河野談話と呼ばれるものを発表したのが1993年(外務省サイト)、その後、中学高校の歴史教科書が「慰安婦」という言葉を明示して、この問題を記述するようになりました。その直後に、結成されたのが「つくる会」(新しい歴史教科書をつくる会:慰安婦問題があることを否定している)だったとのこと。つくる会については多少知っていましたが、この問題が創設のきっかけの一つだったとは知りませんでした。
やはり慰安婦問題というのは、日本にとって喉にささったトゲのようなものなのでしょうか。
作品内の言葉の定義という点を見てみると、「奴隷(性奴隷)」「強制連行」などの用語で、人権派、否定論派の理解に大きな違いが見られました。つまり議論の際に使用されている言葉が、共有されていないということです。
「強制連行」は、否定論派側では、夜中に眠ている人の家に押し入って引きずり出す、とか、縄で縛って連行するなどのことを指しているようでした。人権派の方は、強制とは、自由意志ではないことを指し、甘言によってだまされた場合もそこに含まれると考えているようでした。
また「奴隷」については、否定論派側は、人間が鎖に繋がれているような状態のことで、何の自由もない人間以下の扱いという理解のようでした(よって慰安婦は性奴隷ではない)。一方人権派の理解では、人がもののように扱われ、生きることを他者に全的支配されること、としていました(たとえ報酬を得ていたとしても、慰安婦が性奴隷であることに変わりはない)。
どうでしょう。このように言葉の定義が違っていれば、議論がうまく噛み合わないことは容易に想像できます。
言葉の定義以外にある問題として、議論を有利に進めるために、どちらの側も事実を盛って話す、つまり誇張表現をすることが多く見られるようでした(その一部は、映画内のファクトチェックにより否定された)。慰安婦問題を糾弾する韓国の活動家集団には、一貫して発言に決めつけが多かったように思います。日本の人権派の学者や活動家は、数字の扱い(慰安婦の数など)に慎重な態度が見えました。
この映画を見てよかったと思うのは、考えの異なる者が互いの考えを交換し合うときに、どのような基本態度が必要かということを知ったことです。相手の言い分を理解し、自分の主張を相手に理解してもらおうとすることは、対立する2者にとって簡単なことではありません。それほど自分の考えや立ち場を変えることは難しいことです。また個人として、相手の言うことを理解した場合も、それを率直に口することは自分の仲間、あるいは所属する集団から非難を受け、排斥されることも考えられます。
そんなことを考えていたとき、書棚にあった朴裕河(パク・ユハ)の『和解のために:教科書・慰安婦・靖国・独島』(2006年、平凡社)に目がとまりました。朴裕河さんは『主戦場』にも登場している韓国の日本文学者です。慰安婦問題を糾弾する韓国の活動家からは、この問題に関する彼女の著書が「読むに耐えられなかった…」と非難を受けていました。しかし朴裕河さんは、日本の否定論者のような立ち場をとっている人ではありません。
一方「慰安婦」問題自体を否認する「新しい歴史教科書をつくる会」は、性奴隷としての「慰安婦は存在しなかった」と語る。「慰安婦」とは「自発的に」金を稼ぎに行った者であり、強制的、奴隷的な搾取をこうむったのではなく、きちんとした金銭的収入を得ていた「公娼」だったというのである。
(中略)
しかし女性がその性を売ることは、一見したところ本人の自由意志によることのようにみえるが、決してそうではない。それは、女性は国家と男性に奉仕すべきものとされる、家父長制構造の内でのことだ。慰安所が「公認された」場所であり「合法的」だったとする彼らの主張は、その「法」が国家と軍のつくった男性のための「法」だったという事実を淫靡している。その「合法性」は、問題がないがために合法的なのではなく、男性中心の国家が自身のためにもうけたルールであったがゆえに、合法的だったのである。
….勤労隊としての「挺身隊」とみるのさえ困難なその少女が「慰安婦」と紹介されていることに対する疑念を妨げるのは、韓国の内にある強固な、単一化された被害者意識だ。この資料集(注:吉見義明による『資料集従軍慰安婦』)にはまた、明るい表情で微笑みながら河を渡る「慰安婦」の写真が載せられている。彼女の微笑をそのまま「慰安婦が満足に暮らしていた」証拠としてみようとする日本の右派の試みは、もとよりそれが「責任」を否認する発言であるからには、断固として拒まれるべきである。
どちらの側からも都合の悪いこと、認めたくないことを朴裕河さんは書いています。八方嫌われ者とでも言いましょうか。それは盛った話の裏にある真実に近いことを見つめようとしているから。
この本の「はじめに」のところで、著者は「韓国のなかでも日本のなかでも、右でもない左でもない『あいだ』に立たねばならなくなったことだ。(中略)….五年前を上回る孤独が待ち受けているかもしれないが、それも仕方のないことだろう」このように書いています。「あいだ」に立つことの困難さがひしひしと伝わってきます。
朴裕河さんは韓国人、そして『主戦場』のミキ・デザキさんはアメリカ人。日本社会の外で生まれながらも、日本に関心をもって生きてきた研究者、クリエーターだから、両サイドそれぞれの真実に迫ることができるのか。その意味で、前回の真崎嶺さんも同じ立ち場にいる人です。
日本で生まれ育った人間にとって、日本人や日本社会を客観的に見ることは簡単ではありません。そのようなとき、日系アメリカ人をはじめとする、違う出自をもつ「日本人に近い人」の考えを聞くことは、意味あることに思えます。今後、デザキさんや真崎さんのような人の発言や作品が、もっと表に出てきたらいいと感じています。
*
日系アメリカ人2世の視線と視野 その1(グラフィックデザイナー)
真崎嶺さんの『サラリーマンはなぜサーフボードを抱えるのか』
『サラリーマンはなぜサーフボードを抱えるのか』は、真崎嶺さんが去年(2021年)、個人で出版した本のタイトルです。小部数発行でアマゾンでは扱いがなく、わたしはネット(ABC)で買いました。……….
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
