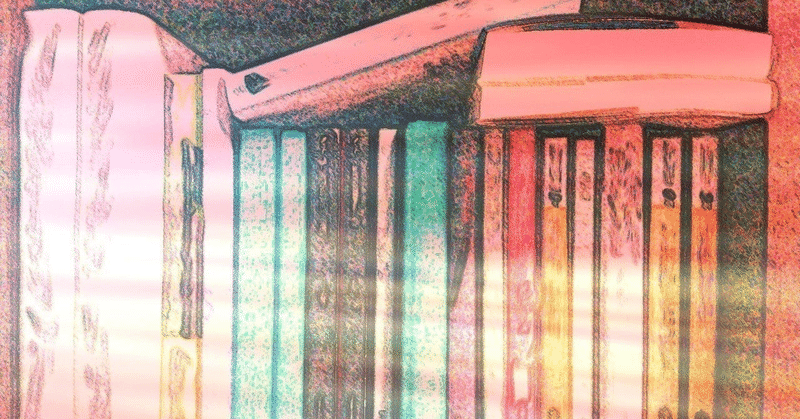
掌編小説「人柄」
「ようこそ、春木君。何もない家だけど、ゆっくりしていってね」
小学生のころ、仲良くなったユミちゃんの家に遊びに行ったときに、彼女の母親に最初にそう言われた。
彼女の家は、確かに何もなかった。言ってしまえば、貧乏だったのだろう。確かによくよく考えると、ユミちゃんの服は少し古くて解れていたし、体型は痩せていた。
家には物は多かったけど、高価なものや流行の物などはほとんどなかった。唯一、ユミちゃんの部屋にだけ、小説や図鑑などの書籍だけがたくさんあった。
「これは斉藤のおばさんから、こっちは従姉妹から、こっちは――」
ユミちゃんは、僕がこれだけの本をどうやって手に入れたのかを聞くと、「もらったの」と答えた。そして、感謝とともにくれた人の名前を言っていった。
ユミちゃんは何か物をくれた人の名前を決して忘れず、会うたびに感謝しているようだった。
そのため、あげる人も嬉しくなり、どんどんくれるそうだ。そうして彼女の部屋だけ、価値のあるものが多くなっていた。
「そんなにいっぱいの本を全部読めるの?」
僕がそう聞くと、彼女は少し自慢げに「もう半分は読んだわ」と答えた。
ユミちゃんは小学生にしては非常に賢かったし、美人さんで、コミュニケーション能力もあった。神が彼女に与えなかったのは唯一経済的な力だけだったが、そこが致命的でもあった。
ユミちゃんは一人でに、そのことを理解しているようだった。自分のやりたいことをやるには、もっとお金が必要なのだ。
ユミちゃんはとても本が好きだったので、よく内容を説明してくれた。彼女の話を聞いても、何が何だかわかっていない僕が落ち込んでいると、ユミちゃんはこういった。
「春木君はすごく優れていると思うの。とても論理的で、だけど機械みたいじゃないのよ」
彼女は僕が人の心を理解することが得意であること、そして論理的であることを見抜いていて、そこを褒めた。
僕はよくわからないまま照れていたが、彼女の真剣な表情を見て固まった。
「春木君にお願いがあるの」
そう言って彼女はとある展望を話し始めた。僕はそれを驚きで受け止め、彼女の行動力に惹かれて受け入れた。
数日後、僕らは市民会館に集まっていた。ユミちゃんの持っている本を展示し、彼女がその本について話すという中々挑戦的な試みだった。
手伝いにはユミちゃんのお母さんと、僕の父親、そして斉藤のおばさんと、眼鏡を掛けた若いお兄さんが来てくれた。若いお兄さんは斉藤さんの親戚だという。
本の展示を準備しているとき、持ってきた本が入っている段ボールからお兄さんが一冊の本を見つけた。
「これもユミちゃんの本かい?」
出てきたのは純粋理性批判という本だった。僕はなんか小難しいタイトルが出てきたぞと目を擦った。
頷いたユミちゃんに対して「読んだのかい?」とお兄さんは聞いた。すると、ユミちゃんは首を振った。
「難しくて途中で諦めたの」
お兄さんは少し驚いているようだった。読もうとすること自体が驚きだったのだろう。少し興味深げな表情でお兄さんは口を開いた。
「ユミちゃんは将来勉強したいこととかあるかい?」
お兄さんの目は何かを期待しているように見えた。
「うーんとね、経済学をやりたい!」
お兄さんは吹き出して笑った。ユミちゃんはぽかーんとしていたが、僕は何となく理由が分かった。
お兄さんは哲学をやりたいと言うのを期待していたのだろう。しかし、ユミちゃんが言ったのは全く別のジャンルだったのだ。
「ふふっ、そっか。理由を聞いてもいいかい?」
「えっとね。うちにはお金が無いから、一番役に立ちそうなものをやろうと思って」
「あ~、そっか~」
お兄さんはそれを聞いて少し表情を硬くしていた。そして少し首を傾げた後、斉藤のおばさんと話し始めた。斉藤のおばさんはそれを聞いて笑って頷いていた。
話し終わったお兄さんがユミちゃんに話しかけた。
「本当は何がしたい?」
ユミちゃんは少し考え込んで言った。
「……文学がやりたい!」
ユミちゃんの目はそのとき一番輝いているように見えた。お兄さんはそれを見て頷いた。
「それなら、その夢を手伝おうかな」
お兄さんはそう言って笑った。それからしばらくお兄さんとユミちゃんは話し込んでいて、最後には彼女の親と斉藤のおばさんも加わった。ここまではずいぶん前のことだ。
そして時間が経った今、僕は大学生になった。入学式の翌日、驚くことに僕の横にはユミちゃんがいて、彼女の服はピカピカだった。化粧までして小綺麗に身を飾っていた。
「ユミちゃんは文学部だもんね。ここでお別れかな」
「ええ、春木君は経済学部ね。お互いに頑張りましょう」
彼女はそういっていたずらげに微笑んだ。僕もごく最近知ったのだ。ずっと近くにいたのに、同じ大学に来るとは知らなかったし、教えてくれなかった。
もちろん経済的な理由で大学になんか来られないと思っていたのだ。
入学式の少し前に突然聞かされて、僕が「ど、どうして大学に入れたんだい?」と聞くと、彼女はこう答えた。
「もらったのよ。斉藤のお兄さんに」
笑みを浮かべた彼女を見て思った。これは彼女の人柄が成せる技だな、と。
彼女は自らの人柄によって、障壁を乗り越えた。一つ、与えるのをケチった神もこれには悔しがるに違いない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
