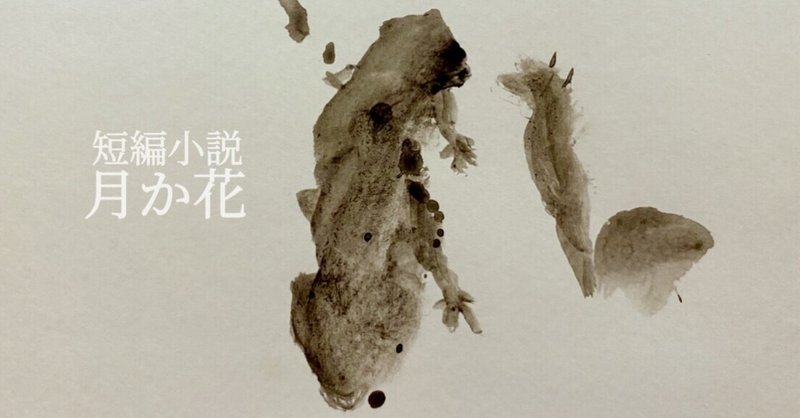
短編小説 | 月か花 #1
気持ちのよい夜であった。
一日分の熱に夜気が注いで、街は足し水のようにほんわりとしている。
居酒屋のエアコンに凍えた体は、生ぬるい夜の風に浸かって生き返ったところ。
火照ったり冷えたりを繰り返した夜に、脳はぼんやりとした夢心地に緩んだまま。
酔心もほどほど駅の前を通ると、ちょうど最終電車が着いたらしい。改札からは人が潮のように溢れ出てきた。が、それもしばらく歩いて駅の灯りが薄れゆくと、そこらでとんと人は消え、それをちょっと不気味にも感じながら、ふらふらと交番の前を通った。
交番では赤ちょうちんに似たランプが、ぽっと暗闇に浮かび、また青黄色い室内も同様に、エドワードホッパーの絵画のように黒へ浮く。蜘蛛の巣にまみれた観音開きの扉には、「巡回中」との白い掛け看板が、夏の虫にたかられ垂れ下がっていた。
小林は、巡回という文字に、今朝の朝礼を思い出した。
副校長がいつものように連絡事項を挙げる。
それに加え、このところ校区内では窃盗事件が流行っているとのことだった。
犯行はいつも深夜。いやしくも寝静まった住家に忍び込む手口。
幸い傷害の被害はなく、金品目的であることは明瞭だから、登下校の警戒を強める段階ではない。しかし物騒は物騒。念のため注意しておけとのことだった。
若い体育教師である小林はこの手の臨時業務によく駆り出される。
通学路や繁華街へ見回りの必要が起これば、必ず小林の名がまず挙がる。街で問題を起こした生徒の保護も、よく小林が命じられた。
それは小林にとって決して不平ではなかった。
少なからず肉体を使うことには自信がある。学生時分は陸上と柔道をやっていた。現役よりはずいぶん細った体であるが、不良や悪漢に対応できる術は体に染みついている。それにまだ、街を走り回る体力も十分。日頃から、周囲が喜んでくれるならば、自分の体で良ければいくらでも差しだす気概でいた。
だから巡回中という文字を見ると、むしろちょっとくすぐられるものがある。もとより就職は警察官か教師かを悩んだ程だ。地域を守るのと、子供たちを守るのと。悩んだ末に後者を選んだ。過去によって熟成されきった大人よりも、未来ある、未熟な子供を守る方が世のためになる。どうせ人生を社会に摩耗される身であるなら、できればその身を美しい未来に寄与したい。小林の生活の動機はそこにあった。何より純粋な子供たちが愛おしい。愛おしさを還元すれば、子供たちは小林を慕った。そこに生きる喜びすらも感じた。
加えて吹くのは気持ちの良い夜の風。ちょっと酔い醒ましのかたわら、散歩を兼ねて校区内の見回りをしても良いような気持になった。
いわんや本当に泥棒と出会おうとは思っていない。しかし気持ちよく酒を飲んだ後、多くの者が気の大きくなるにまかせて、食欲や性欲でその日を締めるように、小林にも肉体を使って地域に奉仕したという自己満足を、この夜の締めに置きたい気持ちがあった。
それは一面では教育者たる者の鑑であると言えるかもしれない。私欲におぼれず、奉仕によって一切の悦びを得る。そんな修行僧のような清廉さが、小林の自負でもあった。
また、小林のそんな清廉な性質は住処からもうかがえる。彼は赴任先の学区内に賃貸を借りている。それはプライベートの確保より、むしろ自分の生活圏と生徒保護者のそれを重ねることに美徳を置いた結果である。そこには私生活すら教師であり続けたいという克己があった。
小林は胸を張るように伸びをすると、体を傾け、帰路とは異なる道に入った。
時間はすでに日を跨いでいる。生ぬるい夜風は彼の体をもう十分に暖め、汗ばみ始めたポロシャツをすり抜けていった。
夜の窃盗は、駅前の小汚い小店通りから駅から少し離れた目新しい開発住宅地、そして古くから土地に根付く屋敷が並ぶ集落と、学区内ならところ構わずあちこち起こった。捜査のかく乱のためだろうか。と、小林は自分に空想の刑事を重ねながら推理し、屋敷集落の方へと向かった。
集落は道が細く入り組み、屋敷同士が迫るように立ち並ぶ土地である。古い屋敷ばかりだから外塀も一様に高い。当然見通しも悪い。もし自分が泥棒であるならばそこを重点的に選ぶ、などと推理したのだ。そこなら目撃されても追われにくいし、集落は藪山と隣接する立地にある。そのため隠れやすいし逃げのびやすい。そんな場所だから、パトロールの巡査たちもどうかすれば見落とす点があるかもしれない。有事の際には少しでも手伝えればとも思った。
しかし当然、犯行が今夜起こるとは限らない。犯行が起こらないに越したこともない。とどのつまりどうせ夜道を歩くなら、多少風情があった方がよいと、そんな軽い気持ちもあった。そこなら山から下りる空気もみずみずしいだろう。酔体には涼しいぐらいが気持ちよいのだ。
十分と歩き、集落に着けばすぐ、屋敷群が立ち塞ぐように現れた。街灯も電柱も数少ない土地、思っていたよりもずいぶん暗い。集落自体が裏の藪山と闇とに融け、それはひとつ大きな城のようにも見える。また、空気に爽やかなみずみずしさを期待したものの、実際踏み入れば、ヒヤリとする悪寒じみた冷気の世界。草木の湿気の青い香りもする。整備され切っていない排水路の生臭い匂いもする。そこに水が流れているのか、遠くで水がちょろちょろ流れる音もする。
小林は暗闇にぶるっと身をひとつ震わすと、尿意が半身に染みるのを感じた。しかし教師たる身、幕末の風雲児のようにそこらの塀で用を足すわけにもいかない。ぐっと腹に力を込めて我慢した。
引き返したいとの誘惑も起こった。が、ともかく地域をひと回りするまでは生徒たちに顔向けできないと、ひとり勝手に自戒する。小林は腰に据えた太刀を握る心地、入り組んだ細い道、集落を奥へ進んだ。
静かな道を幾らか進んだ後、三又路に差し掛かった。
うっすらとした視界は月光のみ。左右分かれる道の中央には古く小さい祠が、門衛のように小林を見据えている。
雲の加減か、月光はその一方、一路だけを差し照らしていた。
小林は目を細めた。その道の先、ふとその奥で、ひとつ影の動くのが見える。おやと思う足も、自然と忍ぶようになる。(続)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
