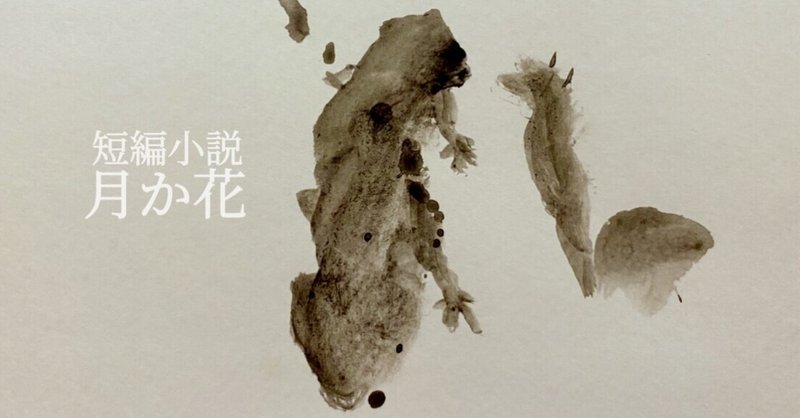
短編小説 | 月か花 #2
すると影は、ある一戸の塀の傍で体を伸び縮みし、屈伸するように動くのが分かった。と思うと、するするとまるで忍者のように塀を這い上り、そのままさっと翻ると、敷地の中へ、吸い込まれるようにして消えていった。
当たりだと思った。小林の脳裏には、瞬時に自分を囲む生徒や保護者などの敬慕の顔が踊った。自然と足は塀に向かって動いていく。
この時小林には通報するという頭はなかった。静かな通りである。いま通電すれば、話声で相手に自分を知らせることになるだろう。また、聞こえないところまで悠長に引き返していては、うかうか泥棒に逃げられることとなる。事態は喫緊だった。
忍び足のまま、屋敷の塀伝いに表門まで回った。インターフォンを押せば中の住人を起こせるだろう。しかし、すると泥棒にまで聞こえるかもしれない。
小林はそう勘定を働かせ、そのまま表門の木の引き戸に触れた。からりと動く。不用心にも鍵はされていない。これではまるで泥棒に入れと言っているようなものだ。
そう心で叱責しながら、表門をくぐった。その時水の音がまた聞こえた。藪山からの水源が近いのだろうか。それとも中に水場でも?
そんなことを過らせながら、正面の玄関には触れず、迂回し庭へ回った。影が塀を越えた位置に向かう。泥棒なら玄関から入らない。勝手口や窓を使うはずだと思った。そして侵入するためには窓を破るなり鍵を壊すなりの作業が必要になる。今なら鍵穴に集中しているはず。飛び掛かって抑え込むには十分な隙だろう。
小林は半ば息を止め、角からひっそりと庭を覗き込んだ。
月夜に浮かぶのは、小さいながら立派な庭園だった。寺庭をきゅっと縮小させた風情がある。夜を纏う石灯篭や松の木に泥棒の影を探した。しかし一見では見当たらない。
小林は慎重に足を動かした。玉砂利が鳴らないようゆっくりと。
歩みを進めれば掃き出し窓が庭に並行して並び、中に内縁が見える。目を凝らせばその窓のひとつが半身ほど開けられ、レースのカーテンがゆらゆら風に小さく揺れるのが見えた。
窓が破られた形跡はない。鍵は開いていたか。ならばもう中に?
小林はちらちらと庭にも注意を向けながら、慎重に窓に近づいた。ぬるい風が中から抜ける。ほんのりとお香の香りが通った。
もし泥棒がすでに中に入っているなら、これはこれで好機。袋の鼠だと思った。しかし迂闊に動けば中の住人に危害が及ぶ恐れもある。小林は焦る心を鎮めながら、音の出ぬようゆっくりと身を屈め、その窓から内縁へと頭を滑り込ませた。
気を抜けば闇討ちを受ける恐れもある。小林は狩りをする動物のように慎重に周囲を睨みながら、体をするりと縁側に内入れた。
と、縁側に接する襖が開かれていて、奥がぼんやりと明るいのが見える。そこは座敷で、覗く間も同時に、ぽっかりとした電気行灯の傍、ひとり女が力なく首を傾け、しな垂れ座っているのに出会った。
そこがひどく脱俗した雰囲気ではあったものの、ともかく今は構っていられない。小林は知らせねば、という使命感から、遠慮も無礼も忘れ、忍び声に女に叫んだ。
「あの。大変です。泥棒。泥棒が入りました」
挨拶や説明の猶予はない。小林は小鼻に汗を浮かべながら必死に声を絞った。と、女は眼を薄め、ぼんやりとしていたが、小林の声が届いたか、縁の方、襖の影で屈む小林へ顔を上げると、微かに頬を行灯に明るめた。
「え……、なに。泥棒?」
「ええ、たった今。気を付けて。どこかにいます」
すると女はぽかんとしたのち、うっとり微笑むと、次第に口をおさえ、肩を震わせて笑い始めた。
なぜ笑うのか。小林には瞬間分からず、今度は小林がぽかんとした。状況が飲めない。泥棒の危険、初対面の女、と、その嬌笑。ともかく今騒がれるのはまずかった。
「ちょっと、静かにしてください。気づかれます」
「だって。」
と女は言うと、なおも笑いながら続けた。
「御免なさい。だって、いきなり現れて。あまりに真剣に。……ふふ、でも、どう見たって、あなたの方が泥棒ですわ」
小林はちょっと面食らい、女を怪訝そうに睨んだ。女があまりにも悠長なのだ。
有事とはいえ身知らぬ男が入ってきたのだ。多少取り乱しても良い。この瞬間、小林にはそう思う暇はなくとも、直感に予見した住人の態度とは、それはあまりにもかけ離れている。女にはまるで女子学生のような能天気さがあった。いや、まだ女子学生のほうがしっかりとしている。
そして次第に憤りに似た非難の心も起こった。身の危険だぞと、叱りたくもなった。しかし泥棒に気付かれれば元も子もないものだから、
「ここの窓から入るのを見たんです」
と、女の理解を促すため、できるだけ神妙そうに声を落としてみせた。
「そこから?」
女は尚もくすくすと笑う。
「静かに」
「だって。私、ずっとここに居たんですよ。もしそこから誰か入ってきたなら、いまみたいにすぐ分かるものだろうけど。」
小林は口を丸くした。そうかもしれない。座敷と縁側はひとつづき。その位置、誰か通れば、嫌でも女に見つかるだろう。
「しかし確かに」
勢いづく小林へ、女はそれから、すぐに見知った親戚のように顔を緩めていた。
「もう。泥棒だってなんだって、特段代わりはしませんよ。ほら、いらっしゃい。折角来たんだから、ゆっくりされて」
女はそう言って重たそうに体を起こすと、脇の座布団を動かし、ちゃぶ台へと小林を促した。
女がそういう態度だから、加えて泥棒など見ていないと言うのだから、小林は自分の方が早とちりをしているのではとの懸念を抱いた。
見間違い? あるだろうか。自分はしかと塀から入る影を見た。
が、その影も、泥棒泥棒だと思って歩いていたのだから、月光に生まれた影か何かを見間違えたのかもしれない。猫かイタチの類か。加えて醒めているとはいえ自分は酒を飲んだ身。アルコールを入れたという隙は、小林の実見を簡単に揺るがせた。女のあっけらかんとした様子から、あれが空目だったという気も強くなる。
女は逡巡する小林の脇をするりと抜けると、微笑みをたたえたまま、縁側とは逆の、内の襖へ抜けていった。小林は女の後ろ姿とその隙に、彼女が和装であると気が付いた。黒か、灰の混ざった深緑の付け下げである。襖を閉めゆく女の座り姿を眺めながら、普段着にしては窮屈な、と、その奇妙なシチュエーションに、あんぐりと口を開けたまま、ついぞ言葉を続ける機会を逃してしまった。
席を外した女に、勝手に帰れば余計に不振で失礼だからと変に気を利かせ、小林はおとなしく、出された座布団の傍に立って腕を組み、女が戻るのを待った。
あの影は泥棒か、それとも月夜の見間違いか。かといって家中を勝手にうろうろ探し回るわけにもいかない。せめてこうやって人騒がしくしていれば、もし泥棒が居たとしても危機と察して帰るだろうか。もし女の叫び声がすればすぐ飛んでいこう。小林はそう決め、ぐっと耳を澄ませた。どこかでまた、水の流れる音が続いている。他には特段怪しげな物音は聞こえない。
しかしこんな夜半に着物とは、外から帰ったばかりなのだろうか。小林は腕時計を見た。それにしては遅い時間だ。それに自分が入った瞬間、女はくつろいでいたようにも見えた。くつろぐなら部屋着になってもよいものだが。など、くるくると思いを巡らしている。
女はすぐには戻らない。小林は手持無沙汰に座敷を見渡した。女が横座りにしな垂れていた行灯の足元には、色打掛だとか柄襦袢とかが円座を作っている。きっと今脱いだものではないのだろう。よく見ればあちこちに帯だとか麻の浴衣だとか小紋やらも散らばっている。が、不思議とそれらは不潔そうには見えず、むしろ畳に彩る艶やかな植物のようにも見えた。
行灯の後ろは床の間となっている。
その床板には細長い漆の花器に、菖蒲の花が一輪、活けてあった。小まめに替えているのか、葉や茎は今切ったようにピンとしてみずみずしい。そしてその上につく花は、行灯の灯りを吸うように色づき、利発そうに上向き凛としている。
小林は導かれるように、その上に掛かる掛け軸を眺めた。それは一幅の書であった。
「何て書いてある? 花?」
だろうか。小林は墨で描かれたそのひと文字を眺めた。(続)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
