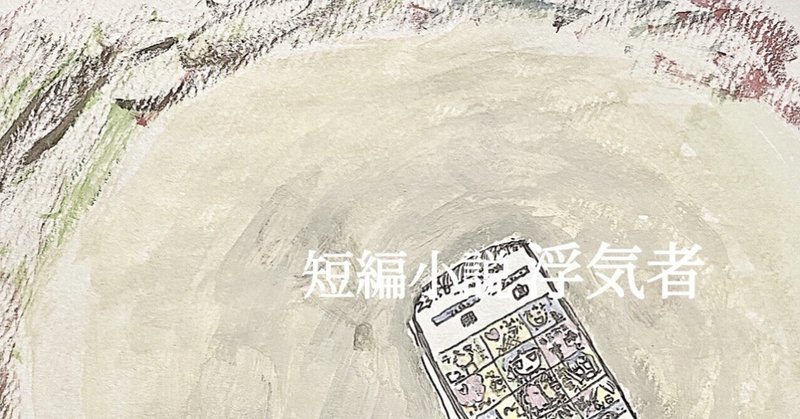
短編小説 | 浮気者 #1
金曜日は私も早引けになるのだから、一緒に夕飯でも作り1週間の労働を共に労い合いたい。
有里子はそんな風に苛立ちながら、冷えた夏野菜を叩き切っていた。
結婚して3年になる。夫の倖一は今日も外に遊びに出ていた。
しかしそれを特段悪いとは思わない。生き方は人それぞれ、ましてや彼は自由業だった。平日の5日間、8時間労働が社会人として当然だという、そんな枠に押し込めようとするのは、今の時代身勝手だと有里子は思う。
しかし鼻に付くのが、その遊びに行く相手が同世代の女たちということ。皆どうせ裕福な主婦で、きっと時間を持て余している。その退屈しのぎに夫が使われているのが気に食わない。
私の夫は、もとい、私の家庭は、そんな他人の暇つぶしにあるわけじゃない。
有里子はそうなおも苛立ちながら、乱暴にまな板の野菜を銀のボールへ流し入れた。
また何より不服なのが、倖一がそれを有里子に事前に報告しないことである。この日はあの場所であの人に会う。その連絡をうやむやに出かけてしまうのだ。だから有里子は自分と夫との予定を照らし合わせ、一家庭としての夜の予定を組むなどといった計画が立てづらい。しかしその不服を訴えるのは、夫の人格を束縛するようで、なんだが強く言い出せないでいた。
それでも倖一は酒など飲まず、もとより飲めないのだが、ともかく夜半まで飲み歩くことはなかった。そして憎たらしくも、いつも決まって夕飯までに帰ってきた。だから有里子の沸点はいつも微妙なラインで揺れ動く。これで朝帰りだとか浮気の露呈などすれば簡単に怒れるものの、至極健全なように白い顔で帰ってくるのだから、有里子はいつもちょっと不機嫌そうな中でも、
「おかえりやっしゃ」
と、おちゃっぴいに迎えるのだった。
倖一はそのようにして、誰それに会ってこんな話を聞いただとか、若奥様たちの派閥がどうだとかの話を仕入れてくる。そこでやっと有里子は、夫が今日どう過ごしたのかを把握する。会っていたのがいつも同世代の女性たちであることもそうやって分かる。
また、その活動が仕事のネタになるのだから真っ向からは否定もできない。倖一は個人のイラストレーターで、ソーシャルメディアに簡単な漫画を描いて生計を立てている。
正確にはそれが収入を生むわけではないが、浮気話や家庭の問題などを茶化す小話を描いて、それを客引き用に、最終的には真っ当なイラストの販売を成果としている。漫画の人気は良くも悪くも上々で、それを発端に企業からのイラスト依頼も度々入るらしい。
だから主婦方との退屈しのぎは、イラストの依頼に遠からず繋がっている。したがって今のところ収入の面でも、イラストレーターとして大成するという倖一の夢の面でも、平日の優雅なお茶会は必須であるのだ。
一方の有里子は京都の土産物会社で事務方のチーフをしている。入社当初は観光産業の土地柄、手堅く安泰な仕事だと思っていたものの、観光客の激減で社内は改革を迫られてしまった。今では各地の店舗を閉じて、代わりに入れるテナント業に舵を切り出した。事務もいろいろな変革があったものの、業務自体は簡略し、早帰りの実施なども取り入れられている。楽になったと思う一方で、仕事が減った不安も覚えないわけではない。いつかは自分も旧態の捨てられた業務のように、お払い箱となる恐れもおおいにあった。
安泰というものは存在しない。生き残るためには常に進化を強いられる。変化し続けることが生きるということだ。それは生き残ってきた生物の歴史を見たって明白だ。
有里子はそんな風に結論しながら、豚肉の小間切れを沸いた湯の中に放り込んだ。眼鏡が湯気に曇る。しかし放っておいても晴れるのだからと、その曇った視界のまま、有里子は鍋をじっと見届けた。
とはいえ、夫の行動を許し続けることも、夫婦関係の進歩であると言えるだろうか。
有里子の思案はぐつぐつと揺れた。
変化と寛厚は近くもあるが、しかし別物である。ましてや夫は家族である。この先も倖一の自由を許容できるだろうか。許容すべきとするのが私や時代の変化だろうか。
そんな風に問いながら、有里子は菜箸で鍋の中をぐるぐると掻きまわした。湯の中の肉の汚れも同じようにぐるぐる回った。
豚肉を鍋から引き上げた頃、倖一は帰ってきた。一年で日が一番長い時節である。午後7時前であるのにまだ外は明るく、キッチン窓の網戸からは夕方の匂いがした。が、それを台無しにするようなジャケットに染みた香水の匂い。有里子はそれでも笑顔を作った。
「おかえりやっしゃ」
「ただいま。おはようお帰りで」
倖一は飄々とジャケットを脱ぐと、肌着になってキッチンを覗いた。
「冷しゃぶかいな」
「そうどす」
こうした少々アクの強い二人の言葉は、いつしか現実から少し離れたものになっていた。芝居がかったような関西弁は、3年間の二人のやりとりが築き上げた、一種独特な空気だった。不満、不服、疑念、退屈。それらをすべて包み込んでしまう便利な道具が、その芝居じみた言葉であった。
「もうできるやろか」
「へえ。大人しゅうまっとくんなまし」
「へえへえ」
倖一はそう言って、食卓へ麦茶や食器を並べ始めた。
「せや、味噌汁つくろか」
「や、昨日のんがまだあるさかい」
「さいでっか」
さいでっか、などとは二人それぞれの現実では使わない。この、二人の家庭というものがある種の非日常を作る、劇場のようになっているのである。客はいない。そのため二人の茶番に終演はない。(続)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
