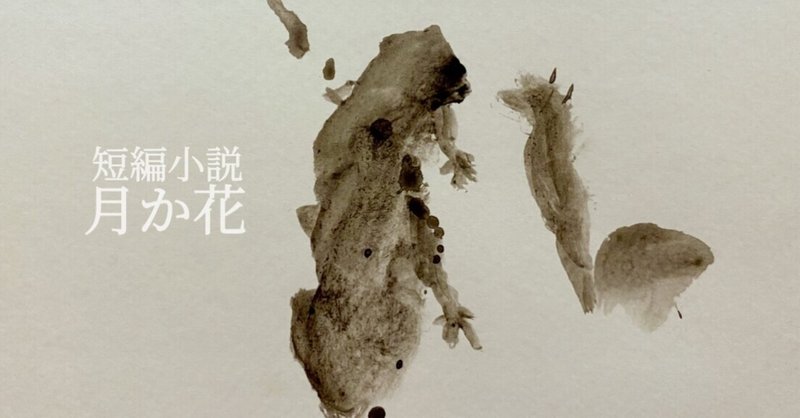
短編小説 | 月か花 #4
「ハア、私ねえ」
と、女はおもむろに、何故か焦れたようにため息を吐くと、小林の勘定を介せず口を割った。
「私ね。おなかに子供が居たの」
「……子供、ですか」
唐突な言葉だった。脈絡もない。何を今から聞かされるのだろうか。しかしともかく居た、という言葉尻に、小林はただ身構えた。
「でもねえ、生まれる前に行っちゃって」
つまりそれは流産だろうか。小林はその言葉を口に出せず、感慨深そうに頷いた。
「今日、四十九日を迎えてね。はっきりとした日は分からないんだけど、たぶん今日なの」
「それは、その。お悔み、申し上げます」
流産した日から、今日が四十九日目ということだろうか。女の話す意図が不確かなまま、小林がひねり出せたのはありきたりの言葉であった。
というのも、同時に小林の胸には響くものもあった。それは生徒たちのことである。
小林のように生徒の有事に駆り出される立場であれば、ただの非行の対処が多いが、ごくまれに悲惨な場面に立ち会うこともあるにはあった。子供の命の問題については、おそらく人より敏感だった。それゆえ、多少思うところもあって、小林から出るのは気遣いに満ちたゆえの、ありきたりな言葉であった。
しかし女は、そんな小林の言葉を聞いているのかいないのか、ともかく話を続けるのだった。
「それでね、今日はお参りに行ってきたの。」
「お参り、ですか」
「まだ形にもならなかったから、死産届なんかなくて。お医者様も自然にまかせましょうって。……位牌も、御骨も、何もなくて。だからあの子が居たという証が何もなくて。あの子が居たという時間が嘘になりそうで。だから私、お参りでもしないと忍びなくって」
それは小林にはまだ無理解な話であった。何週目からそうなるのか。医者とのやり取りは、行政の手続きは? これといった助言や提案もままならず、ともかく頷いて話を聞くしかなかった。
「きっとお地蔵様が導いてくださるって。……私ね、トイレの水に流しちゃったの。私から落ちた黒い血の塊。きっとあの子が居た小さな布団を。私、トイレの水に落としちゃって。でも私、どうすればいいのか分からなくって。何がなんだか分からなくって。それで、私動揺しちゃって、どうしようもなくて、流しちゃったの」
女の声が徐々に感情的になるのが分かった。それでも女は続ける。
「きっとあそこに居たんだわ。あの血の中に。それで冷たくて暗い水道管の中を、ひとり流されていったんだわ」
そういって女は両手を顔で覆い、言葉にならない声を震わした。小林はもう頷くことも忍びなく、空になった猪口を眺め、ただ神妙そうな顔をして黙っていた。
すると女は両手を顔から剥がすと、天を仰ぐように額を上げた。
小林は、その女の顔を見て息をのんだ。行灯に浮かぶ女の顔は、涙に濡れ、悲壮そのものである。が、しかし、頬は脈々と生きた血潮に色づき、瞳は涙と共に灰色の宝石のように輝いて見える。それはまるで美しい絵画を眺めるようだった。……絵画。いや、小林は今までこれほどの情動を見たことはない。それは色欲さえ及ばぬ、清廉なばかりの感情の隆起だった。
「……それでね、私、お地蔵様にお願いしたの。どんな姿でもいい。どんな形でもいい。だから、きっとあの子が戻って来られますようにって。あの子をお導きくださいって。あの子が寂しくないように。あなたの居場所はここにあるわよって。」
女は上向いたまま滑らかに話した。両手はいつの間にか、小さく腹の前で合わせられている。小林は女の話から、自然と、神々しい地蔵菩薩の偶像を頭の上に描いていた。それが女の天を見る視線と相まって、自分の後ろに何か立つような、生ぬるい気配を感じるような気がした。
「だから、今夜、お地蔵様は導かれたんだわ。ほら、だって、現にあなたがここに来て」
女はそれから顔をゆっくりと下げ、その灰色の瞳を小林の眼前に真っ直ぐと晒した。それは優し気で慈しみに満ちた清明な目であった。女の口は動く。
「でもね、あの子ずっと私のお腹に居たでしょう。きっとまだ目は見えませんでしょう。でも、音だけはきっと聞こえるでしょう? だから名前を呼んで、私、あの子をここに呼ばなきゃいけないの。」
女はそう言い終わると、少しの間口を閉ざして、小林を意味深に見つめた。小林は何か言葉を促されているような気がして、乾燥した口を開けたが、しかし何も言いようは無かった。口内に少なくなった唾液の音が、座敷に小さく鳴るだけだった。
女は心持、首を傾げた。
「あなたはきっと泥棒でしょう? じゃなきゃ入る理由がないじゃない。……お地蔵様に、あの子に、導かれてこの家に入ったんでしょう?」
いいえ、違います。僕は泥棒なんかじゃありません。答えは明白だった。が、それを口にするのは至難であった。
「……私、あの子を流したの。その償いよ。償いに、あなたみたいな悪い人を借りたんだわ。でも、それだっていいの。きっと、あの子が私に戻るためなら、どんな新しい体をお借りしたって。丈夫なら、きっと……ねえ、」
女はそう呟きながら、続いてはっと顔を崩した。
「そう、名前。名前を呼ばなければ分からないわよね。……名前ね、この書を見て、誰かがおっしゃったように、月か、花だろうと思っていたの。あなたならきっと名前をお分かりよね。ねえ、あなたはこれをなんとお読みになったの」
女はもはや、小林がそこに居るのかも知らぬように、実に嬉々と、空に話しかけていた。
「あなたは。月ちゃん? 花ちゃん? どっち?」
そう言って、女は熱の陰る瞳を、ゆっくりと小林の瞳に向けた。いつからか、内襦袢の胸元が緩み、膨らんだ胸元が晒されている。
ぞくっと走る熱気を感じた。女に何を求められているのか、小林は直感した。それはとてつもない甘みを予知させた。
しかしその熱気は、小林がはっと思い出す、不貞への忌避と共に、一度強く彼の体を後方へと押しやった。その力を借り、小林はさっと座布団から腰を上げ、早口に言った。
「あの、僕、そろそろ帰らせてもらいます」
しかし女はゆっくりと首を傾げ、真から不思議そうにつぶやいた。
「……なぜ?」
同時に女の背後で何かが動いた。それは掛け軸の書に見える。文字の一部がずるりと動いて、墨の一部が半紙の空白に躍り出る。小林は目を疑った。文字が動いた。が、その黒いものはすぐに知った形となった。
——家守だ。
それを口に出せたかどうか、小林には自分でも分からない。小さな家守はその黒灰の体を書の墨汁に重ね、息を潜めて待っていたのだ。そして今姿を見せた。名の呼ばれるのを、待ちわびたように。
小林は硬直した。そして家守と女とを交互に見遣った。
女はこちらを見つめている。家守はじっと耳を澄ませる。
二人から、強い渇望の渦を感じた。
同時に、渦に呑まれる恐怖を覚えた。
二人の奥に家族が見える。暖かく幸福な、三人の、家庭の影絵。
「ぼ、僕は、失礼し」
小林は即座にそう言い捨てると、座布団を後ろ足に蹴り、襖に肩をぶつけながら、雪崩れるようにして縁側から庭に転げ出た。そして尻もちを突きながら、その際再度、行灯に明るむ座敷を顧みた。
その時彼は、喉を絞められたようなか細い声を漏らした。
座敷の天井に、黒い大きな影が張り付くように映っていた。それは、塀を乗り越え、自分を中へと誘った、あの影に他ならない。
小林は玉砂利の音も気にせず、庭を駆けだした。その後ろ背に、尚も女の声が後に続いた。
「——ちゃん。また連れていらしてね」
その名前は聞き取れない。月だろうか花だろうか。しかし小林には端からどちらとも区別が付かない。
小林は門を抜けると、息の切れるのも忘れ、集落をただ力の続く限り走り抜けた。
もう小林には草木の青い香りも、排水路の生臭い匂いも感じられない。
ただ、耳には遠く音が聞こえる。ちょろちょろと流れる水の音。それはどこまで走っても、後からずっと着いてくる。
……彼が夜叉のごとく駆け抜けた後、三叉路は元の静けさを取り戻していた。
そこには月光が落ち、細道は白く染みている。
いつか戻る、彼の帰路を教えるように。(了)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
