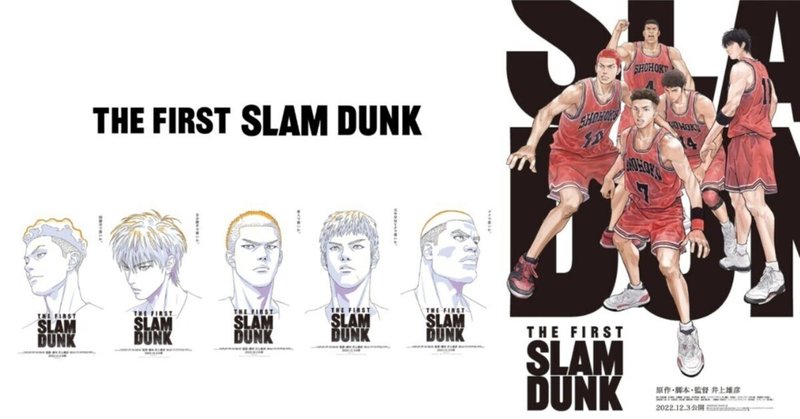
映画『THE FIRST SLAM DUNK』ネタバレあり感想
公開前に色々な不安や憶測が起こったのですが、やっぱり今年最後の映画として見ねばなるまいと見てきました。
結論から言えば今年見てきた映画の中で間違いなくトップクラスです、この構成ならば私のような原作至上主義のリアタイ勢も新規層も納得できる作りになっているでしょう。
原作完結から20年以上経った今の視点だからこそ作れる「SLAM DUNK」をきちんと見せてくれたという意味でいい裏切りを食らいましたね。
ただし、原作の山王戦をそのままアニメで再現してくれるだろうと思って見ると肩透かしを食う感じなっているので、そこは注意が必要です。
作風から言うと今回の映画は『SLAM DUNK』というよりは「リアル」「バガボンド」のような写実主義に寄せた作りになっていて、それは脚本と映像の双方において一貫しています。
声優を一新したのも公開前は不安の塊だったのですが、いざ完成したものを見るとそれも納得の出来栄えであり、確かに旧キャストの演技ではこの作風には沿わないだろうと思うのです。
原作をアニメ化したテレビアニメシリーズは90年代の「ドラゴンボール」に代表される東映アニメの手法で作られているので、演出的にも脚本的にもめちゃくちゃ誇張されているんですよね。
別にそれが悪いわけじゃなく、週刊少年ジャンプ自体がそもそも熱血スポ根ものからスタートしていますから、どうしてもそういうあざとい誇張やスーパーロボットアニメの手法にならざるを得ません。
「侍ジャイアンツ」「巨人の星」辺りのようなとんでもない魔球や大リーグボール養成ギブスのような現実ではありえない荒唐無稽なものが出てくる、そしてそれに合わせるように強敵が次々と出てくる。
ボクシングだと「リングにかけろ」なんかもそういうもので、それまでの「あしたのジョー」「がんばれ元気」なんかでは絶対やらなかった超人技としてのフィニッシュブローが出てきました。
そんな中で『SLAM DUNK』は意外とそういうスーパー系には頼っていないのですが、でもやはり後半になるにつれてどんどん強い敵が出てくるというジャンプ漫画の強さのインフレからは逃れらていません。
また主人公の桜木花道とライバルの流川楓の関係性もそれまでのジャンプ漫画の伝統から大きく外れるものではなく、原作はそういうジャンプ漫画黄金期のあり方に沿って作られたものです。
で、井上雄彦先生の中ではもう『SLAM DUNK』は原作の山王戦で完結を迎えていてあれ以上の物語は作れないということを語っていましたし、私たち原作リアタイ勢もそれで納得しています。
それを今更になって改変するのはとんでもない悪手であり、例えば新訳「Zガンダム」はその典型で富野監督が納得行かなかったからといって原作の「Zガンダム」の結末を捻じ曲げた改変をしているのです。
あれに関しては原作リアタイ勢からするととんでもない裏切りではないでしょうか、だって「Zガンダム」のあの結末に納得するしかなかった人たちからすればそれを根こそぎ否定されたわけですから。
また、だからといって原作者に無許可で作られたハリウッドの「ドラゴンボールGT」や関東大会の六角編以降アニメスタッフの暴走が酷かった「テニスの王子様」も今見直すと酷いものでした。
だからそんな風にならないよう今回はきちんと脚本から映像まで井上雄彦先生が監修としていながら、それに従って若手のキャスト・スタッフがきちんと映画化してくれて納得のいく出来栄えです。
舞台は山王戦で、確かに映画化するとしたら唯一アニメ化されていない全国大会の山王戦で作るしかないのですが、かといってそのまま原作再現したのではわざわざ令和の今に作る意味がありません。
それだったら今までいくらでもアニメ化する機会はあったわけですから、それを敢えてせずに20年以上も寝かせて映画を作るからにはそれなりのものを用意する必要があります。
その意味で本作は正に絶妙な作りだったというか、原作の本筋を決して壊さないようにしつつ足りなかった部分をしっかり補って完璧な1枚のパズルに仕上げてみせました。
前置きが長くなるので本格的な感想に入りますが、今回の主役は湘北の宮城リョータであり、宮城視点で語られる山王戦という一種のスピンオフになっているのです。
宮城リョータといえば原作で全くバックボーンが語られていないキャラで、以前にキャラ語りの記事を書いた時に「身体能力のハンデ」があり「それを言い訳にしない」と書きました。
しかし、それにしては上背ある牧に苦戦したり深津を相手に「俺がこいつとマッチアップすんのかよ!」と恐怖したりとちょくちょく上背がないコンプレクックスを見せていたのです。
だからこそ彼が沢北と深津のダブルポーチを食らった時に「ドリブルこそチビの生きる道なんだよ!」が出たわけですが、ただ個人的にはいまいちピンと来ない台詞でした。
確かにドリブルはバスケットの基礎であり大事ですが、それを宮城というキャラで象徴させるにはもう一歩土台の補強が足りていなかったのです、そもそもどういう経緯で湘北高校に入ったのかも不明瞭ですしね。
唯一描かれた動機らしい動機が彩子に認められたいという承認欲求と陵南戦で明らかになった「安西先生が好きだから」ですが、私の中ではこの2つの動機が全く繋がりませんでした。
桜木や三井はこの辺りがわかりやすく、桜木は晴子さんに認められたいという承認欲求があって、それが続けていく内に本当に「バスケ大好き」へと変質していって最後の「断固たる決意ができた」になるのです。
三井も三井で中学MVPを取った時の「最後まで希望を捨てちゃいかん、諦めたらそこで試合終了だよ」という安西先生に惚れ込むきっかけがあったのです。
また、赤木の場合も元々バスケが大好きで木暮と一緒に北中時代からやって来たけど、恵まれたバスケセンスがないから湘北に行くしかなかったという暗い過去がありました。
流川の場合は「近いから」で全部が片付いてしまいますが、でもそれだけではなく同じ富ヶ丘中出身の彩子姉さんがいるからといった部分も影響しているといえます。
その点宮城はキャラクターの核になる要素が絶妙にボカされた形でいつの間にか湘北の次期キャプテンになったわけですが、そこのミッシングリンクを埋めたのが本作です。
まさか宮城に兄がいて、その兄が流川や三井・沢北のような完璧超人タイプのバスケットの天才だったとは思わず、しかも負け続けていたというところまで語られていたとは誰が想像したでしょうか?
しかしその兄が亡くなってしまって家庭環境が悲惨になってからの宮城はずっとうだつの上がらない日々を過ごすことになったわけで、バスケを頑張っても認めてもらえず不良に絡まれる日々の連続でした。
だから宮城リョータという男は実は赤木剛憲と同じで報われない日々を過ごしていたわけであり、ある意味湘北の中で誰も対等な理解者のいない孤独を抱えて過ごしていたのかもしれません。
「SLAM DUNK」という作品にはそれぞれ山王戦で各キャラが自己肯定感を高める瞬間というか、ギアが上がってグンと大きく化ける瞬間が描かれています。
赤木は魚住に「お前は鰈だ、泥に塗れろよ」と言われた時、桜木は安西先生に「君が勝利の切り札になる」と言われた時、三井は「君は十分にあの頃を超えている」と言われた時、そして流川は沢北相手に笑った時。
4人は明確なバックボーンや心情が描かれた上で化けたのですが、宮城はその辺がボカされたまま急に確変したので、その辺をきちんと掘り起こして描いてくれたのがよかったです。
さらに言うなら宮城の家庭環境は「沢北のIF」でもあり、山王の沢北が優秀なバスケ街道を歩んで来たが故に自己肯定感高く育った成功者だとするなら、宮城は負け続けが当たり前の敗北者でした。
そして両者に共通しているのは「同期に競い合えるライバルがいない」ということであり、沢北のライバルが実は流川ではなく宮城であったというのは盲点でしたね。
また、宮城も宮城で同期に恵まれなかったわけであり、例えば桜木花道と流川楓、赤木剛憲と三井寿のように対等に高め合えるライバルがいなかったのです。
そんな宮城と沢北の視点で見直す山王戦は原作とはまた違った意味合いで見ることができました、負け続きだった宮城は勝つことで自己肯定感を高める必要がありました。
そして勝ち続きで脅かすものがいなかった沢北は「負ける悔しさ」を改めて湘北相手に思い知ることによってそこから先のバスケ人生に繋がっているのです。
どうしても桜木花道中心でしか描かれない原作の山王戦に唯一足りていなかったもの、それは宮城リョータという男が抱える苦悩と挫折の日々でした。
それを知った上で原作を「宮城リョータの物語」として読み直すと違った視点で面白く見直すことができるのであり、絶妙な塩梅で作られた傑作です。
また、今回の映画で良かったのはバスケのシーンを誇張なしのリアリズムというか実際のバスケに近い作りにしたことで、後半のゾーンプレスの恐ろしさが実感できました。
確かにあんなのやられて20点以上もの差をつけられてしまったらそりゃあ心折れるってものですよ、海南の牧だって深津相手にそれをやられて心折られてるのもわかります。
だからこそ安西先生の言う「断固たる決意が必要なんだ」の重みが増すわけであり、写実主義で原作を捉え直すことで原作をより深みのあるものにしてくれました。
こういう原作に足りない部分を補完してくれるのはとてもいいことですし、私も本作を見たことでまたちがった視点で「SLAM DUNK」という作品が見られそうです。
そのため、タイトルは「THE FIRST SLAM DAUNK」ですが、正確には「ANOTHER SLAM DUNK〜宮城リョータの挫折と栄光〜」ではないでしょうか。
確かにこれは少年漫画の領域を超えた範囲になってしまうし、コンプライアンスやら自称フェミによるポリコレが厳しくなってる昨今では中々やりにくい。
でもそれをきちんと描き切ってくれたことは大歓迎ですし、変にファンに媚びたり周りの目を気にしたりして作っていないので好感が持てます。
それと同時に私が『ドラゴンボール超 スーパーヒーロー』『シン・ウルトラマン』に求めていたものも正にこういうものだったのかもしれないと思いました。
ぶっちゃけ過去作品をお洒落にして作り直しただけのなんちゃってリブートものなんて要りません、何故ならば既にもう原作は原作で完結しているからです。
しかし、過去にあったもののミッシングリンクを絶妙に埋めて補完し、原作にあったものを深めてくれるという姿勢のものであれば私は構わないと思います。
今回の映画はその意味で「過去の名作を現代に掘り起こすならこうだよね」といういい見本になった傑作だったのではないでしょうか。
見た目が綺麗なだけの過去作の擦り倒しではなく原作ではまだやり切れていなかったことを突き詰めるというのを見事にやり切ってくれました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
